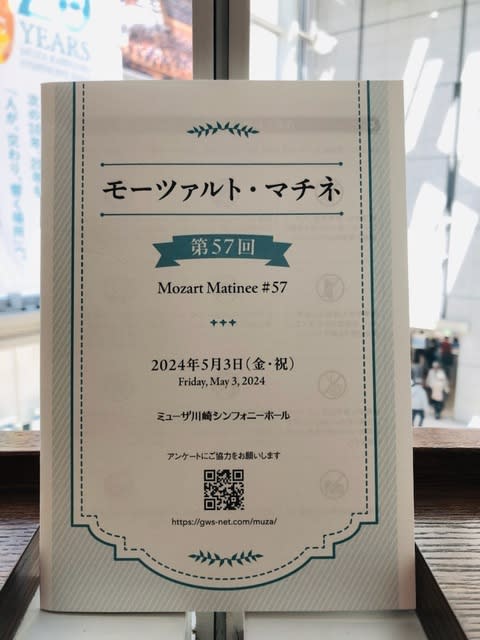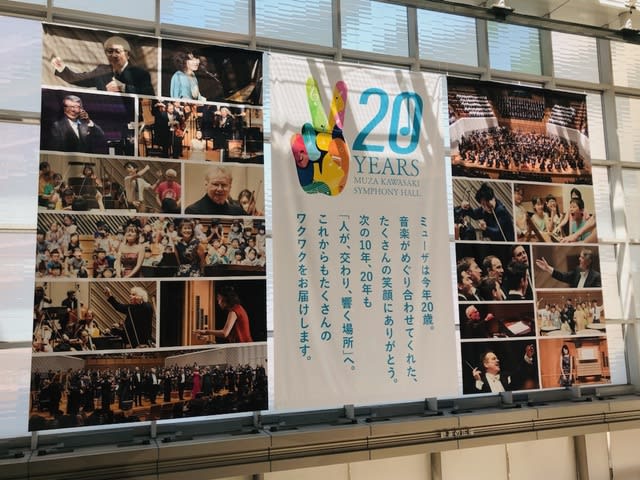4日(土・休)その2.昨日行われた東響「モーツアルト・マチネ」については「その1」で書きました モコタロはそちらに出演しています。是非ご訪問ください
モコタロはそちらに出演しています。是非ご訪問ください





今年も5月の連休に有楽町の東京国際フォーラムを中心に開かれる「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2024」が開幕しました 私は第1回「ベートーヴェン特集」とコロナ禍で中止となった年を除いて毎年LFJに通い続けてきましたが、「ORIGINES(オリジン)~すべてはここから始まった」をテーマとする今年は3日間で計6公演を聴きます
私は第1回「ベートーヴェン特集」とコロナ禍で中止となった年を除いて毎年LFJに通い続けてきましたが、「ORIGINES(オリジン)~すべてはここから始まった」をテーマとする今年は3日間で計6公演を聴きます

昨日は、最初に午後4時10分から東京国際フォーラム・ホールCで開かれる「ルネ・マルタンのル・ク・ド・クール ~ ハート直撃コンサート」を聴きました この公演はLFJ音楽祭の主宰者ルネ・マルタンが主催する「若手で初来日のアーティストによる公演」のエッセンスを紹介するコンサートです
この公演はLFJ音楽祭の主宰者ルネ・マルタンが主催する「若手で初来日のアーティストによる公演」のエッセンスを紹介するコンサートです 「プログラムは当日のお楽しみ
「プログラムは当日のお楽しみ 」ということで、事前には公開されていませんでした
」ということで、事前には公開されていませんでした 従って、聴衆は内容を全く知らないまま公演を聴くことになります
従って、聴衆は内容を全く知らないまま公演を聴くことになります 後で知ったのですが、ホール外側の案内ボードに本公演のプログラムが掲載されていました
後で知ったのですが、ホール外側の案内ボードに本公演のプログラムが掲載されていました
自席は2階14列34番、センターブロック右通路側です。会場はほぼ満席です
プログラムの最初は、ヴァイオリン=イリス・シャロム(女性)、チェロ=クシシュトフ・ミシャルスキ、ピアノ=アントナン・ポネによるラヴェル「ピアノ三重奏曲 イ短調」から第1、第2楽章です 3人ともパリ国立音楽院の出身者です
3人ともパリ国立音楽院の出身者です
3人は、ラヴェル特有の浮遊感のあるニュアンスに満ちた演奏を繰り広げました
2番手はサクソフォン=ヴァレンティ―ヌ・ミショー、パーカッション=ガブリエル・ミショーによる演奏で、①ピアソラ「失われた小鳥たち」、②ヒルポルイ「ザ・ピーコック・モーメント」、③ザ・ビートルズ(マ二エ編)「ブラックバード」です ヴァレンティーヌがローザンヌ音楽大学、ガブリエルがパリ国立音楽院の出身者です
ヴァレンティーヌがローザンヌ音楽大学、ガブリエルがパリ国立音楽院の出身者です
ヴァレンティ―ヌがソプラノ・サックスで演奏する間、ガブリエルは両手に2本ずつマレットを持ち、ステージの左右に設置されたシロフォンとビブラフォンの間を行き来しながら鮮やかに演奏しました ①「失われた小鳥たち」は映画音楽のような聴きやすい曲で、②「ザ・ピーコック・モーメント」はメシアン風だな、と思いました
①「失われた小鳥たち」は映画音楽のような聴きやすい曲で、②「ザ・ピーコック・モーメント」はメシアン風だな、と思いました
3番手は「レ・イティネラント」(ア・カペラトリオ)とパーカッションによる演奏です 「レ・イティネラント」とは「巡歴者たち」を意味します
「レ・イティネラント」とは「巡歴者たち」を意味します 歌はマノン・クザン、ポーリーヌ・ラングロワ・ド・スワルテ、エロディ・ポンの女性3人、パーカッションはティエリー・ゴマールです
歌はマノン・クザン、ポーリーヌ・ラングロワ・ド・スワルテ、エロディ・ポンの女性3人、パーカッションはティエリー・ゴマールです 歌うのは①伝統曲(スワルテ編)「ウォーキング・ソング」、②伝統曲(クザン編)「アデス・キリイ」、③ポン「水の月」、④ドビュッシー(スワルテ編)「亜麻色の髪の乙女」です
歌うのは①伝統曲(スワルテ編)「ウォーキング・ソング」、②伝統曲(クザン編)「アデス・キリイ」、③ポン「水の月」、④ドビュッシー(スワルテ編)「亜麻色の髪の乙女」です このうち、③「水の月」は明らかに滝廉太郎「荒城の月」をアレンジした曲です
このうち、③「水の月」は明らかに滝廉太郎「荒城の月」をアレンジした曲です いずれも透明感のある素晴らしい歌唱で、パーカッションもそれぞれの曲に応じた控えめな演奏で好感が持てました
いずれも透明感のある素晴らしい歌唱で、パーカッションもそれぞれの曲に応じた控えめな演奏で好感が持てました
最後を飾るのはエリプソス四重奏団(サックス四重奏)による演奏です 曲目はディ・バッコ「パリの4本のサックス」です
曲目はディ・バッコ「パリの4本のサックス」です 4人はパリ国立音楽院でメイエ、ル・サージュから指導を受けました
4人はパリ国立音楽院でメイエ、ル・サージュから指導を受けました 演奏を聴くと、明らかにガーシュイン「パリのアメリカ人」のパクリであることが分かります
演奏を聴くと、明らかにガーシュイン「パリのアメリカ人」のパクリであることが分かります 4人はサックスを演奏する傍ら、歌も披露しましたが、なかなかのものでした
4人はサックスを演奏する傍ら、歌も披露しましたが、なかなかのものでした
さて、この公演は予定では16:10から16:55までとなっていましたが、終演したのは17:15でした。予定時間を20分オーバーです 45分の公演で20分の超過は、ちょっとサービスし過ぎのような気がします
45分の公演で20分の超過は、ちょっとサービスし過ぎのような気がします 演奏途中に退席する人がちらほら見られましたが、次の公演に間に合わなくなってしまうのでしょう
演奏途中に退席する人がちらほら見られましたが、次の公演に間に合わなくなってしまうのでしょう 私も何回か経験がありますから気持ちは良く分かります
私も何回か経験がありますから気持ちは良く分かります

次に、午後6時15分からホールAで開かれる斎藤友香理指揮神奈川フィルによる「オール・ラヴェル・プログラム」を聴きました プログラムは①ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」、②同「ピアノ協奏曲 ト長調」、③同「ボレロ」です
プログラムは①ラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」、②同「ピアノ協奏曲 ト長調」、③同「ボレロ」です
指揮をとる齊藤友香理は桐朋学園大学卒。小澤征爾から指揮研修生に選ばれてサイトウ・キネンフェスティバル松本での「ヘンゼルとグレーテル」でデビュー、2013年からドレスデンで研鑽を積みました
自席は1階17列51番、センター右ブロック左通路側です ホールAは5000人収容できますが、結構埋まっていて驚きます
ホールAは5000人収容できますが、結構埋まっていて驚きます
オケは12型で、左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという並び 舞台下手にはハープが控えます。自席からステージが遠いのでコンマスが誰か確認できません
舞台下手にはハープが控えます。自席からステージが遠いのでコンマスが誰か確認できません その代わり、ヴィオラのトップは、その仕草から読響ソロ・ヴィオラの鈴木康治であると確信します
その代わり、ヴィオラのトップは、その仕草から読響ソロ・ヴィオラの鈴木康治であると確信します
1曲目はラヴェル「亡き王女のためのパヴァーヌ」です この曲はモーリス・ラヴェル(1875-1937)が1899年にピアノ独奏曲として作曲したものを1910年にオーケストラ用に編曲した作品です
この曲はモーリス・ラヴェル(1875-1937)が1899年にピアノ独奏曲として作曲したものを1910年にオーケストラ用に編曲した作品です
齊藤の指揮で演奏に入りますが、極めて遅いテンポで演奏が進みます。それでもオケは何とかペースを維持して演奏します オーボエ、フルート、ホルン、そしてハープの演奏が冴えています
オーボエ、フルート、ホルン、そしてハープの演奏が冴えています どっしり落ち着いたよい演奏でした
どっしり落ち着いたよい演奏でした
2曲目はラヴェル「ピアノ協奏曲 ト長調」です この曲は1929年から31年にかけて作曲、1932年にパリで初演されました
この曲は1929年から31年にかけて作曲、1932年にパリで初演されました 第1楽章「アレグラメンテ」、第2楽章「アダージョ・アッサイ」、第3楽章「プレスト」の3楽章から成ります
第1楽章「アレグラメンテ」、第2楽章「アダージョ・アッサイ」、第3楽章「プレスト」の3楽章から成ります
ピアノ独奏の萩原麻未は広島県出身。2010年の第65回ジュネーヴ国際コンクールで日本人として初めて優勝 パリ国立音楽院、モーツアルテウム音楽院を卒業。国内外のオーケストラと共演を重ねています
パリ国立音楽院、モーツアルテウム音楽院を卒業。国内外のオーケストラと共演を重ねています
萩原麻未がグリーンを基調とし白の帯模様を配したステージ衣装で登場、さっそく第1楽章の演奏に入ります
軽快に疾走する萩原のピアノが素晴らしい 白眉は第2楽章でした。弱音によるキラキラと輝く高音は萩原ならではの特質です
白眉は第2楽章でした。弱音によるキラキラと輝く高音は萩原ならではの特質です 独奏ピアノとコーラングレ(イングリッシュホルン)との対話は抒情に満ち、ロマンティシズムの極致を感じます
独奏ピアノとコーラングレ(イングリッシュホルン)との対話は抒情に満ち、ロマンティシズムの極致を感じます 第3楽章は一転、スピード感あふれる演奏が展開し、切れ味鋭い萩原のピアノとオケとの丁々発止のやり取りにより、輝かしいフィナーレに突入しました
第3楽章は一転、スピード感あふれる演奏が展開し、切れ味鋭い萩原のピアノとオケとの丁々発止のやり取りにより、輝かしいフィナーレに突入しました
今、この曲で一番素晴らしい演奏をするのは誰か?と問われれば、私は躊躇なく萩原麻未の名前を挙げます
最後の曲はラヴェル「ボレロ」です この曲は1928年にダンサーのイダ・ルビンシテインの委嘱により作曲、同年パリ・オペラ座で初演されました
この曲は1928年にダンサーのイダ・ルビンシテインの委嘱により作曲、同年パリ・オペラ座で初演されました
小太鼓がスペイン舞曲のボレロのリズムを刻む中、主題を演奏する楽器がフルートからクラリネットへ、そしてファゴットへと受け継がれていきます 各ソロ楽器の演奏の巧いこと
各ソロ楽器の演奏の巧いこと 神奈川フィルっていつの間にか名手揃いになったようです
神奈川フィルっていつの間にか名手揃いになったようです 斎藤の鮮やかな指揮によって、最後のどんでん返しで終結しました
斎藤の鮮やかな指揮によって、最後のどんでん返しで終結しました
満場の拍手にカーテンコールが繰り返され、ソロを担当した楽員が一人ひとり立たされて賞賛を浴びました ホールAはステージ左右の壁に大きなモニター・スクリーンが設置されていて、彼らの顔や姿がそこに映し出され、一躍脚光を浴びることになりました
ホールAはステージ左右の壁に大きなモニター・スクリーンが設置されていて、彼らの顔や姿がそこに映し出され、一躍脚光を浴びることになりました
この公演も、18:15から19:00の予定でしたが、終演は19:10分頃でした。10分の超過です LFJは原則として1公演45分を目途にしているようですが、実際には枠に収まり切れていないのが現状のようです
LFJは原則として1公演45分を目途にしているようですが、実際には枠に収まり切れていないのが現状のようです コンサートをハシゴする場合は、余裕をもってスケジュールを立てないと、演奏途中で抜け出すことになります。気を付けましょう
コンサートをハシゴする場合は、余裕をもってスケジュールを立てないと、演奏途中で抜け出すことになります。気を付けましょう