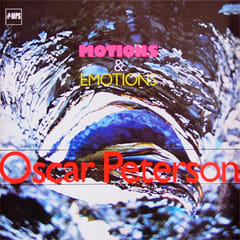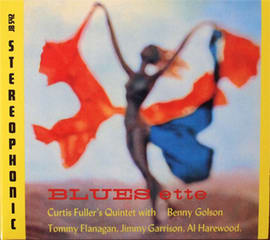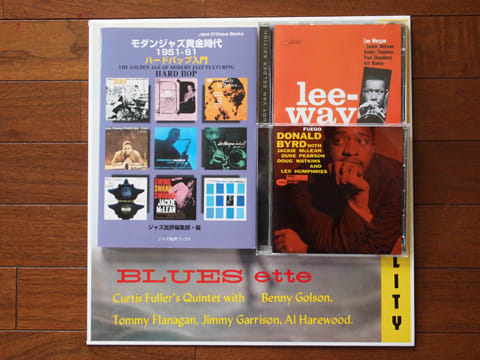横浜方面は依然梅雨入りしていませんが、本日は、少しだけ雨が降りました。明日からの天気もパっとしなさそうなので、そろそろ梅雨入りするかも知れません。今回は、ジャズのスタンダード「バードランドの子守唄」を取り上げます。有名な曲ですので、ジャズを聴かれる方ならお気に入りの音源があることと思います。作曲は英国のジャズ・ピアニスト、ジョージ・シアリングで1952年の作品です。元はインストルメンタルでしたが、歌詞がつけられ、多くの女性ヴォーカリストが取り上げてきました。
スペインの女性ヴォーカリスト兼トランぺッター、アンドレア・モティスのライブ盤です。Youtubeで音源を探索する中で彼女の存在を知りました。私の好きなスコット・ハミルトンが応援で参加していたことも、CD購入のきっかけとなりました。メジャーデビュー前の10代の頃のライブで、途上感いっぱいですが、周りの演奏陣が重しになっています。「バードランドの子守唄」でもそんな対比を楽しめます。Amazon Musicでメジャーデビュー前後の他の作品も聴きました。メインシステムでも聴きたくなりましたので、徐々にCDを集めることになりそうです。

大御所女性ヴォーカリストの作品で最も有名なのはサラ・ヴォーンでしょうか。クリフォード・ブラウンを招いたアルバムです。akahanamizukiさんのお宅でレコードを聴かせていただいたのは、ちょうど4年前の今頃になります。雨飾山の無念のリタイヤ、晴天の春日山城址が思い出されます。早、4年も経ちました。チューバホーンさん宅のオフ会でも、ハンコックさんの持ち込み音源にあったと記憶しています。それらの印象からすると、拙宅で聴くデジタル音源は今一つでした。システムのせいではなく、盤のせいであって欲しいと思います(苦笑)。

エラ・フィッツジェラルドの『LULLABIES OF BIRDLAND』はデッカ時代のアルバムです。45年~55年にかけて録音された音源が、スタンダード半分、スキャット半分の構成で収められています。オーディオ的には、この直後の時代の『Ella and Louis』となるのでしょうが、こちらではよりフレッシュなエラの歌声が楽しめます。「バードランドの子守唄」の出だしは、一瞬、エッという感じで始まりますが、歌が始まるとグッと引き込まれます。やはりスタンダードの「エンジェル・アイズ」と共に気に入っています。

クリス・コナーはのアルバムはこの『Sings Lullabys of Birdland』と『THIS IS CHRIS』を所有しています。本日挙げた5枚の中では、このアルバムの「バードランドの子守唄」がベストです。クリスコナーの声は意外に押し出しが強く、どっしりとセンターに定位します(ちなみに大御所の3枚は全てモノラルです)。メインシステムで聴き入り、白人ヴォーカルの中低域の魅力を再確認しました。クリス・コナーにも膨大な音源が残されています。次はガーシュインのソングブック当りを考えています。

最後は方向性を変えて、阿川泰子です。80年発売の『JOURNEY』に「バードランドの子守唄」が収められています。当時、中学生だった私は、洋楽/邦楽こそよく聴いていましたが、ジャズはテリトリー外でした。阿川泰子の存在を知ったのは、80年代後半になってからです。全体的に洗練されたアレンジでフュージョンの色合いを感じます。バックの演奏陣も素晴らしく、「バードランドの子守唄」では向井滋春のトロンボーンが阿川泰子の大人?の声といい対比になっています。この盤なら、中古レコード入手もありです。

前回、ジャズを話題にしたのは、2015年ですから、ずいぶんと間が空きました。