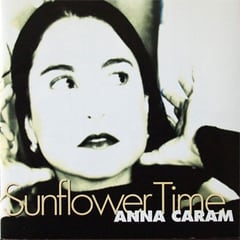連休明けに拙宅に来ていただいたKYLYN(キリン)さんを、昨日訪問しました。小金井界隈はちょうど夏祭りの日で、活気のある雰囲気になっていました。KYLYN(キリン)さんは、ワンルームマンションの角部屋でデジタル/アナログ/マルチチャンネルを楽しまれています。お言葉と音楽に甘えて6時間超の滞在となってしまいました。特に中盤以降は赤霧島(黒霧島ではありません)も入って、他愛のないオーディオ/音楽談義に付き合いいただきました。お酒が入ってしまうとどうしても聴き方は緩々になってしまいますが、それを差し引いても、実に整った雑味の無い音が印象的でした。
システムの要はB&Wの805Dです。6畳の部屋でいかに805Dを鳴らすかを追求されています。SPは長辺配置で、ニアフィールドリスニングです。805Dの下のウェルフロート・大理石のボードは、共にSPのサイズに合わせた特注品です。ウェルフロートの機能をより発揮させるために、硬い大理石を導入するに至ったとのことです。本来ならSPスタンドを使いたいところですが、ローボードは外せない理由があるようでした。与えられた環境でベストを尽くす・・・この姿勢が一貫していて、ボード以外にも電源環境整備、ケーブルの製作、ルームチューニングなど、ご自身が手が出せる個所は一通り手を加えていました。

コーナー部に施されたルームチューニング材です。同様の処置を4つのコーナー全てに行っていました。このチュニーング材は、吸音より反射がメインとのことです。残念ながらメーカーが無くなったので現在は購入することはできません。床はフローリングで、その上に絨毯を敷かれていました。その状況は拙宅も同じですが、会話する声に拙宅ほどのライブ感はなく、ルームチューニングの効果を感じました。

上流の機器は全てクアドラスパイアのラックに納められています。アナログプレーヤーは英国のRega P3、CD/SACDプレーヤーはDenonのDCD-1650SEです。プリメインアンプは独のトライゴンです。下の二つの段はマルチチャンネル用で、OppoのユニバーサルプレーヤーとSONYのAVアンプの組み合わせです。

聴かせていただいた音源(デジタル)の一部です。フュージョン系の音楽が多かったですが、クラシックや歌謡曲も混ぜていただきました。SPは内振りですから音場の広がりは抑え目ですが、SPの存在は消えていました。余計な音がしない、そこに音楽がそのままあるような聴こえ方です。雑味がなく、いわゆる「長時間聴ける音」だと思いました。どの帯域もしっかり音が出ていましたが、特に低音には拘っている様子。Christian Mcbrideでは、とても小型SPとは思えない量感のある低音が、きちんと制動されて出ていました。渡辺香津美(SACD)の空気感も見事でした。

アナログは80年代の懐かしい盤を沢山聴かせていただきました。レコードの詰まったローボードは、私にはちょっとしたタイムマシンのように思えました。アナログで聴くシンセサイザーは暖かみを含んでいますね。KYLYN(キリン)さんがアナログを再開されたのは10年以上も前の事です。アナログ2年生の私とは年季が異なります。どのレコード盤もコンディションが良く、ダストノイズがほとんど聴こえない点は感心しました。何か特別なクリーニングをやっているのか尋ねたところ、レーベルを保護して水道水(+微量の洗剤)でじゃぶじゃぶ洗っているとのこと。この方法だと埃の付き具合も簡単に確認できるようです。

訪問先でマルチチャンネルを体験するのは初めてでした。私の中では映像の優先度は依然低いままですが、オフ会では余計なバリアは不要です。センターSPは置かず、805Dを活かした4.1chシステムでした。確かにリアのBOSEのSPは音量は控えめで引き立て役に回っていました。映像は何と言っても演奏者の表情が見えることが、ピュアオーディオとの大きな違いです。写真はアメリカのトランぺッターChris Bottiのコンサートですが、ゲストのYo-Yo Maとの駆け引きは惹きこまれるものがありました。映像には映像の良さあります。二者択一で決めるものではなく、別のメディアと割り切って楽しむのもありですね。

オーディオには機器を変える楽しみもありますが、あらためて使いこなしの大切さを再認識するオフ会となりました。KYLYN(キリン)さん、どうもありがとうございました。
システムの要はB&Wの805Dです。6畳の部屋でいかに805Dを鳴らすかを追求されています。SPは長辺配置で、ニアフィールドリスニングです。805Dの下のウェルフロート・大理石のボードは、共にSPのサイズに合わせた特注品です。ウェルフロートの機能をより発揮させるために、硬い大理石を導入するに至ったとのことです。本来ならSPスタンドを使いたいところですが、ローボードは外せない理由があるようでした。与えられた環境でベストを尽くす・・・この姿勢が一貫していて、ボード以外にも電源環境整備、ケーブルの製作、ルームチューニングなど、ご自身が手が出せる個所は一通り手を加えていました。

コーナー部に施されたルームチューニング材です。同様の処置を4つのコーナー全てに行っていました。このチュニーング材は、吸音より反射がメインとのことです。残念ながらメーカーが無くなったので現在は購入することはできません。床はフローリングで、その上に絨毯を敷かれていました。その状況は拙宅も同じですが、会話する声に拙宅ほどのライブ感はなく、ルームチューニングの効果を感じました。

上流の機器は全てクアドラスパイアのラックに納められています。アナログプレーヤーは英国のRega P3、CD/SACDプレーヤーはDenonのDCD-1650SEです。プリメインアンプは独のトライゴンです。下の二つの段はマルチチャンネル用で、OppoのユニバーサルプレーヤーとSONYのAVアンプの組み合わせです。

聴かせていただいた音源(デジタル)の一部です。フュージョン系の音楽が多かったですが、クラシックや歌謡曲も混ぜていただきました。SPは内振りですから音場の広がりは抑え目ですが、SPの存在は消えていました。余計な音がしない、そこに音楽がそのままあるような聴こえ方です。雑味がなく、いわゆる「長時間聴ける音」だと思いました。どの帯域もしっかり音が出ていましたが、特に低音には拘っている様子。Christian Mcbrideでは、とても小型SPとは思えない量感のある低音が、きちんと制動されて出ていました。渡辺香津美(SACD)の空気感も見事でした。

アナログは80年代の懐かしい盤を沢山聴かせていただきました。レコードの詰まったローボードは、私にはちょっとしたタイムマシンのように思えました。アナログで聴くシンセサイザーは暖かみを含んでいますね。KYLYN(キリン)さんがアナログを再開されたのは10年以上も前の事です。アナログ2年生の私とは年季が異なります。どのレコード盤もコンディションが良く、ダストノイズがほとんど聴こえない点は感心しました。何か特別なクリーニングをやっているのか尋ねたところ、レーベルを保護して水道水(+微量の洗剤)でじゃぶじゃぶ洗っているとのこと。この方法だと埃の付き具合も簡単に確認できるようです。


訪問先でマルチチャンネルを体験するのは初めてでした。私の中では映像の優先度は依然低いままですが、オフ会では余計なバリアは不要です。センターSPは置かず、805Dを活かした4.1chシステムでした。確かにリアのBOSEのSPは音量は控えめで引き立て役に回っていました。映像は何と言っても演奏者の表情が見えることが、ピュアオーディオとの大きな違いです。写真はアメリカのトランぺッターChris Bottiのコンサートですが、ゲストのYo-Yo Maとの駆け引きは惹きこまれるものがありました。映像には映像の良さあります。二者択一で決めるものではなく、別のメディアと割り切って楽しむのもありですね。

オーディオには機器を変える楽しみもありますが、あらためて使いこなしの大切さを再認識するオフ会となりました。KYLYN(キリン)さん、どうもありがとうございました。