久々に音楽の話題です。ジャンル別の楽曲の紹介、9週目に入りました。中学後半になって聴くようになったRainbowの初期のアルバム3枚を取り上げます。高校受験の年、大きなニュースではJohn LennonやJohn Bonhamの訃報がありました。洋楽を聴く割合が邦楽を上回るようになった頃です。何だかんだ言って入試が迫ってもFM放送を中心に音楽からは離れませんでした。昔から、ながら聴きは好まないので、一応メリハリをつけてましたが・・・。Deep PurpleやLed Zepplinの威光はまだ健在でしたが、リアルで旬なバンドとしてRitchie Blackmore率いるRainbowへの関心が高まりました。
御大との相性やら音楽の志向の違いやらで、Rainbowは頻繁にメンバーが入れ替わりました。それに伴い楽曲の志向も変化したので、戸惑ったファンは多かったと思います。ベストメンバーは?と問われると、ヴォーカルにRonnie James Dio、ドラムにCozy Powellを迎えた第2期を挙げます。これは多くのファンも同様だろうと思います。ちょうどJohn Bonhamが亡くなったこともあり、Cozy Powellの注目度が高まっていた時期です。もっとも、そのCozy Powellも80年にはRainboiwを脱退、既にRonnie James Dioも辞めてましたから、もはや旬のではなかったのですが、2nd、3rdアルバムのインパクトは大きかったです。
取り分け惹きこまれた曲が2ndアルバム『Rainbow rising』に入っている「Stargazer」でした。8分半のドラマティックな展開に、中学生ながら痺れたのを思い出します。いわゆる3巨頭の個性がぶつかり合った作品で、Cozyの冒頭のドラムス、Ronnieの熱唱、インドめいたRitchieのソロ、エンディングのストリングス・・・スケールの大きさに、Purpleの名曲「Burn」超え、を感じたものです。レコードB面でこの曲に続くのが「A Light in the Black」です。やはり8分超の大作ですが、スピード感と様式美は「Stargazer」以上。結局のB面はこの2曲のみですが、もう十分お腹一杯です。
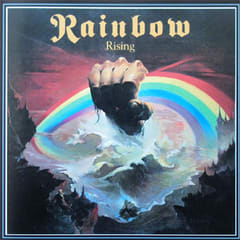
3rdアルバム『Long Live Rock 'n' Roll』(邦題はバビロンの城門)です。少し前に100%ピュアLP(透明な盤)でも復刻されました。代表作はやはり前作と同路線の「Kill the king」「Gates of Babylon」ですが、この後のRainbowの路線を感じさせる、米国志向の曲もちらほら。エンディングのバラード「Rainbow Eyes」はフルートが沁みる聴かせる曲です。アルバムのハイライトは何と言っても「Kill the king」でのギターソロでしょうね。凄味という点ではPurple時代を通じても一番ではないでしょうか。残念ながらRainbowの中世志向もここで曲がり角となり、方向性の違いからRonnieが去ることになります。
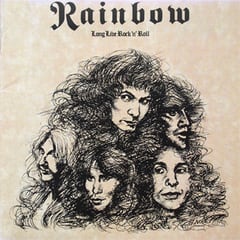
1stアルバムは私にとっては完全な後追いで、オーディオ熱が上がってからの購入です。ベスト盤に選ばれている曲は知っていましたが、全般に好曲が揃っています。元々はDeep Purple在籍中のRitchieが空いた時間を利用してレコーディングしたのがきっかけだそうです。バンドのロゴが定まってませんし、Ritchie Blackmore'sとありますね。ドラムがCozy Powellでない分、押し出し感は上記2枚ほどありません。何となくDeep Purple 3期の雰囲気も感じますが、「Sixteenth Century Greensleeves」や「The Temple of the King 」のように、その後の路線の芽生えもあります。

高校受験が終わった3月の春休み、新生Rainbowのシングル「I Surrender」をFM放送で聴く機会がありました。Ritchie節は部分部分で感じられましたが、あまりにPOPS化していて、これには大いに戸惑いました。結局、Rainbowを積極的に聴いていたのでは高校1年の終わりくらいまでで、私の中ではJudus PriestやScorpionsのウェイトが増していくこととなりました。
御大との相性やら音楽の志向の違いやらで、Rainbowは頻繁にメンバーが入れ替わりました。それに伴い楽曲の志向も変化したので、戸惑ったファンは多かったと思います。ベストメンバーは?と問われると、ヴォーカルにRonnie James Dio、ドラムにCozy Powellを迎えた第2期を挙げます。これは多くのファンも同様だろうと思います。ちょうどJohn Bonhamが亡くなったこともあり、Cozy Powellの注目度が高まっていた時期です。もっとも、そのCozy Powellも80年にはRainboiwを脱退、既にRonnie James Dioも辞めてましたから、もはや旬のではなかったのですが、2nd、3rdアルバムのインパクトは大きかったです。
取り分け惹きこまれた曲が2ndアルバム『Rainbow rising』に入っている「Stargazer」でした。8分半のドラマティックな展開に、中学生ながら痺れたのを思い出します。いわゆる3巨頭の個性がぶつかり合った作品で、Cozyの冒頭のドラムス、Ronnieの熱唱、インドめいたRitchieのソロ、エンディングのストリングス・・・スケールの大きさに、Purpleの名曲「Burn」超え、を感じたものです。レコードB面でこの曲に続くのが「A Light in the Black」です。やはり8分超の大作ですが、スピード感と様式美は「Stargazer」以上。結局のB面はこの2曲のみですが、もう十分お腹一杯です。
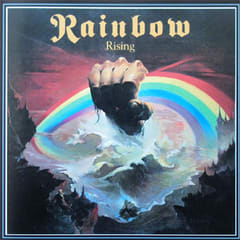
3rdアルバム『Long Live Rock 'n' Roll』(邦題はバビロンの城門)です。少し前に100%ピュアLP(透明な盤)でも復刻されました。代表作はやはり前作と同路線の「Kill the king」「Gates of Babylon」ですが、この後のRainbowの路線を感じさせる、米国志向の曲もちらほら。エンディングのバラード「Rainbow Eyes」はフルートが沁みる聴かせる曲です。アルバムのハイライトは何と言っても「Kill the king」でのギターソロでしょうね。凄味という点ではPurple時代を通じても一番ではないでしょうか。残念ながらRainbowの中世志向もここで曲がり角となり、方向性の違いからRonnieが去ることになります。
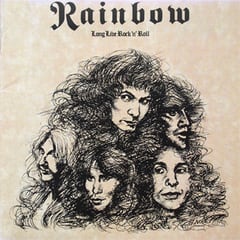
1stアルバムは私にとっては完全な後追いで、オーディオ熱が上がってからの購入です。ベスト盤に選ばれている曲は知っていましたが、全般に好曲が揃っています。元々はDeep Purple在籍中のRitchieが空いた時間を利用してレコーディングしたのがきっかけだそうです。バンドのロゴが定まってませんし、Ritchie Blackmore'sとありますね。ドラムがCozy Powellでない分、押し出し感は上記2枚ほどありません。何となくDeep Purple 3期の雰囲気も感じますが、「Sixteenth Century Greensleeves」や「The Temple of the King 」のように、その後の路線の芽生えもあります。

高校受験が終わった3月の春休み、新生Rainbowのシングル「I Surrender」をFM放送で聴く機会がありました。Ritchie節は部分部分で感じられましたが、あまりにPOPS化していて、これには大いに戸惑いました。結局、Rainbowを積極的に聴いていたのでは高校1年の終わりくらいまでで、私の中ではJudus PriestやScorpionsのウェイトが増していくこととなりました。



























