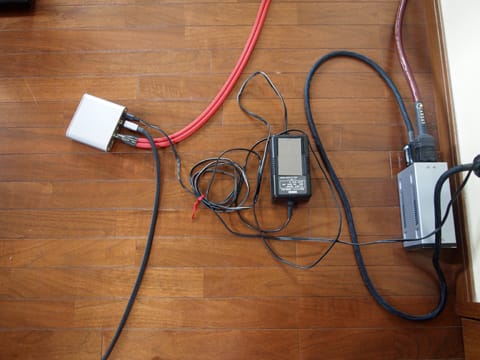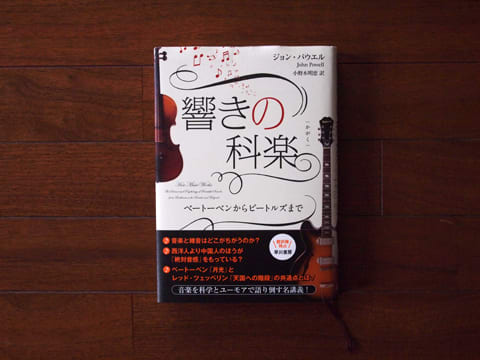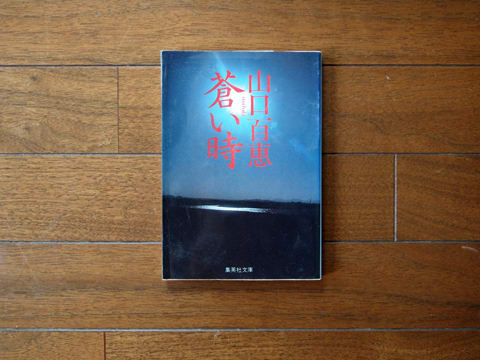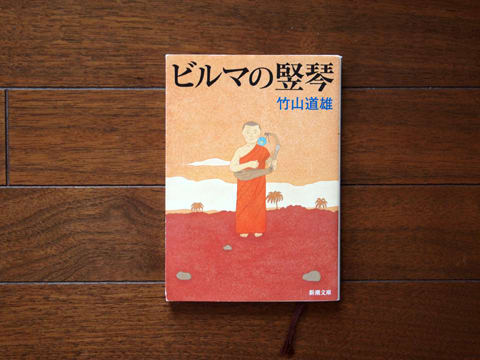猛暑続きで真空管アンプの出番は減っています。ロンドン五輪も始りましたし、オーディオは少し控えめにといった状況です。でもオーディオ欲をかきたてるニュースもあります。e-onkyoからワーナーミュージックのハイレゾ音源がDRM(デジタル著作権管理)フリーで販売されるようになりました。これまで聴きたいアーティストの作品が少なく、おまけにDRM付きで再生環境にも制限があったので関心は低かったです。個人的にはトリガーになる出来事かもしれません。
さて、アナログ導入も落ち着き、次は何をと考えていたわけですが、一つは2ndシステムのVoyage MPD化でこれまでに何度か紹介してきました。もう一つは、ルームアコースティックの調整です。今年後半のテーマと言えます。といっても、あまりゴツゴツとその手のアクセサリーを林の如く立てるのは、自分の好みに合いません。それ以前の、ごく基本的なところで取り組んでいることを、何回かに分けて紹介します。
当ブログをご覧の方ならご存じかと思いますが、メインシステムのある部屋はフローリングの部屋です。何もしないと、いわゆる”ライブ”となり、素のままではオーディオ用には向かないとされています。実際、
・会話が妙に響いて不自然
・手を叩くと、パンではなくビンと鳴る
・本のページをめくる音も気になる
といった状況でしたから、何とかしなければと思っていました。
実は5月の連休に、対策としてラグを敷いています。普段はこちら側の写真は掲載していませんが、こんな雰囲気になっています。これまでは音楽を聴くときに大きめの毛布を持ち出して床に広げていましたが、面積が不足していたこと、そして敷く手間がかかることから、恒久的に置けるラグがあればいいと思っていました。装置側で過度に吸音するのは避けたいので、ラグはあくまでリスニング側に配置します。平行法においては反射音の扱いは大切です。

素材は化学繊維ではなく、天然ウールにしました。吸音効果に優れるようです。比較して試したわけではありませんが。

ラグの効果をまとめます。
・会話の不自然さはかなり解消されましたが、まだライブ感が残っています。
・少なくともリスニングポイント付近で手を叩く分には、ビンからパンになりました。
・本のページをめくる音も違和感が無くなりました。
まだライブさが優っている印象ですが、追い込む余地が残っていると思って、取りあえず一段落です。次回は、左右の非対称性対策について、ご紹介します。
さて、アナログ導入も落ち着き、次は何をと考えていたわけですが、一つは2ndシステムのVoyage MPD化でこれまでに何度か紹介してきました。もう一つは、ルームアコースティックの調整です。今年後半のテーマと言えます。といっても、あまりゴツゴツとその手のアクセサリーを林の如く立てるのは、自分の好みに合いません。それ以前の、ごく基本的なところで取り組んでいることを、何回かに分けて紹介します。
当ブログをご覧の方ならご存じかと思いますが、メインシステムのある部屋はフローリングの部屋です。何もしないと、いわゆる”ライブ”となり、素のままではオーディオ用には向かないとされています。実際、
・会話が妙に響いて不自然
・手を叩くと、パンではなくビンと鳴る
・本のページをめくる音も気になる
といった状況でしたから、何とかしなければと思っていました。
実は5月の連休に、対策としてラグを敷いています。普段はこちら側の写真は掲載していませんが、こんな雰囲気になっています。これまでは音楽を聴くときに大きめの毛布を持ち出して床に広げていましたが、面積が不足していたこと、そして敷く手間がかかることから、恒久的に置けるラグがあればいいと思っていました。装置側で過度に吸音するのは避けたいので、ラグはあくまでリスニング側に配置します。平行法においては反射音の扱いは大切です。

素材は化学繊維ではなく、天然ウールにしました。吸音効果に優れるようです。比較して試したわけではありませんが。

ラグの効果をまとめます。
・会話の不自然さはかなり解消されましたが、まだライブ感が残っています。
・少なくともリスニングポイント付近で手を叩く分には、ビンからパンになりました。
・本のページをめくる音も違和感が無くなりました。
まだライブさが優っている印象ですが、追い込む余地が残っていると思って、取りあえず一段落です。次回は、左右の非対称性対策について、ご紹介します。