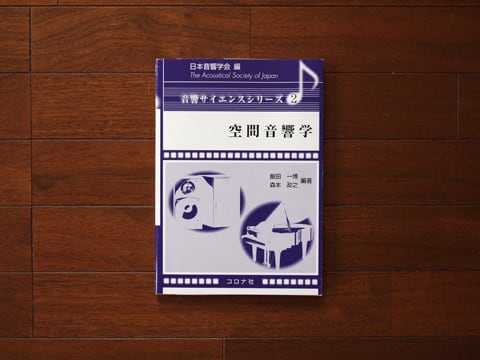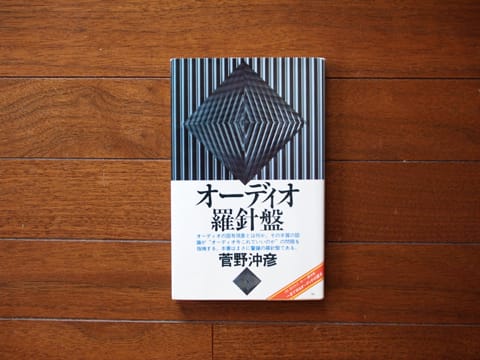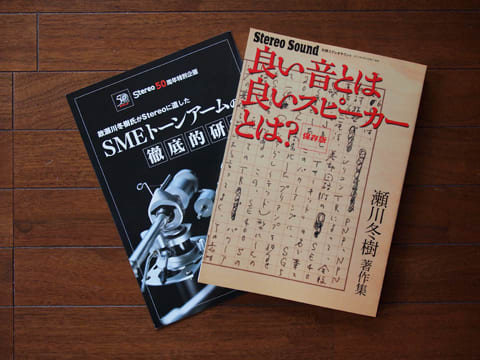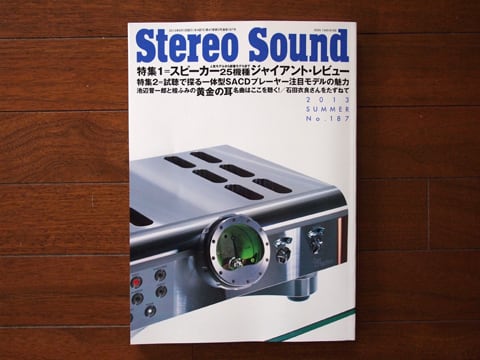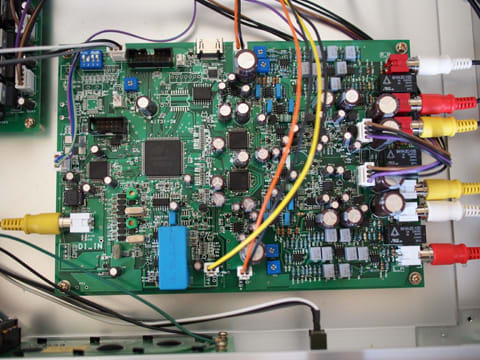先週の記事でも触れましたが、台湾に忘れてきたカメラが無事戻ってきました。お手数かけた方々にまずは感謝です。ありがとうございました。
学生時代の格安旅行から海外出張まで、これまでは全て成田からの移動でしたが、今回初めて羽田からの搭乗となりました。成田エクスプレスの雰囲気も好きなのですが、羽田となるともう通勤感覚というか、国内出張の感覚でした。便利さを実感します。今回は一週間もない出張でしたので荷物は全て機内持ち込みで済みました。

往復ともJALを使いました。JALの騒動があったのは、もう何年前でしょう?月日が経つと関心は薄れてしまうものです。もちろん当事者の方は大変な苦労をされたのでしょうが、客側は気楽なものです。ただ、東電といい、シャープといい、一寸先は何が起こるかわからない時代であることは言えます。

台湾の空港というと桃園のイメージがありますが、今回は松山(ショウザン)空港が玄関口です。入国手続きを終えて、1万円分を元に替えました。物価は特に安いという感じはしませんでしたが、生活費+足裏マッサージ+お土産はこれで十分でした。飛行場を出ると南国の暑さが待っていました。この出張の段階では既に沖縄は梅雨明けでしたから、更に南方の台湾はとっくに明けています。素直に考えると5月頃が梅雨なんでしょうかね。写真の左端に映っているビルが、500m超えの台北101です。この時はタワーは意識していなかったのですが、帰り際に撮ろうとしてカメラの忘れ物に気付いた次第です。

滞在したのは台中より更に南下した雲林県の斗六という街です。

日本との時差は1時間です。ですから目が覚めるのは現地で早朝ということになります。朝食の調達がてら散歩してみました。ここはちょっとした街の広場で、朝から熱心にヨガをやっている人々がいました。動きが揃っているのでびっくりです。ホテルの食事が今一つとの話を聞いていましたので、近くのセブンイレブンを利用しました。サンドイッチは違和感ありませんでしたが、おにぎりは具の甘さにちょっと閉口です。台湾の食事は油がきつくて駄目という方もいます。小龍包や魯肉飯などは抜群に美味しかったですが、長期滞在だと苦労があるのかも知れません。

最後に携帯した本です。吉田修一さんの「路」という小説です。台湾新幹線の建設プロジェクトを題材に、それに関わる人々のちょっとした成長物語です。同時並行的に進む日本人、台湾人の物語がプロジェクトを介して一つにつながっていく展開が面白く、駆け足で読んでしまいました。今回は車での移動でしたが、プライベートで行く機会があれば新幹線に乗りたいところです。吉田修一さんは、ANAの「翼の王国」で連載されていたエッセイを機内で読んだことで知りました。iPodも持っていきましたが、殆ど出番は無し。敢えて音楽を絶つのもいいのでは思います。自宅に戻って最初に聴く音楽が活きます。
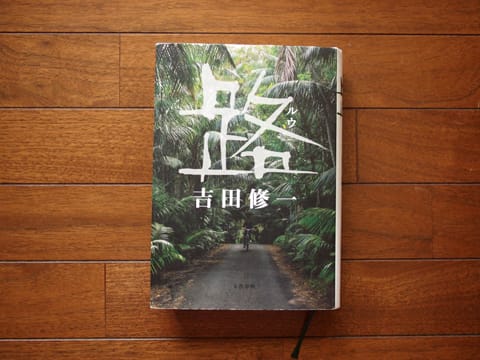
麦わら帽子に、路上のスクーターラッシュ、薄味のビール、それに熱気・・・アジアを感じますね。蝉かどうかわかりませんが、日本ではあまり馴染みの無い鳴き声でした。一足早い夏を先取りしてきました。
学生時代の格安旅行から海外出張まで、これまでは全て成田からの移動でしたが、今回初めて羽田からの搭乗となりました。成田エクスプレスの雰囲気も好きなのですが、羽田となるともう通勤感覚というか、国内出張の感覚でした。便利さを実感します。今回は一週間もない出張でしたので荷物は全て機内持ち込みで済みました。

往復ともJALを使いました。JALの騒動があったのは、もう何年前でしょう?月日が経つと関心は薄れてしまうものです。もちろん当事者の方は大変な苦労をされたのでしょうが、客側は気楽なものです。ただ、東電といい、シャープといい、一寸先は何が起こるかわからない時代であることは言えます。

台湾の空港というと桃園のイメージがありますが、今回は松山(ショウザン)空港が玄関口です。入国手続きを終えて、1万円分を元に替えました。物価は特に安いという感じはしませんでしたが、生活費+足裏マッサージ+お土産はこれで十分でした。飛行場を出ると南国の暑さが待っていました。この出張の段階では既に沖縄は梅雨明けでしたから、更に南方の台湾はとっくに明けています。素直に考えると5月頃が梅雨なんでしょうかね。写真の左端に映っているビルが、500m超えの台北101です。この時はタワーは意識していなかったのですが、帰り際に撮ろうとしてカメラの忘れ物に気付いた次第です。

滞在したのは台中より更に南下した雲林県の斗六という街です。

日本との時差は1時間です。ですから目が覚めるのは現地で早朝ということになります。朝食の調達がてら散歩してみました。ここはちょっとした街の広場で、朝から熱心にヨガをやっている人々がいました。動きが揃っているのでびっくりです。ホテルの食事が今一つとの話を聞いていましたので、近くのセブンイレブンを利用しました。サンドイッチは違和感ありませんでしたが、おにぎりは具の甘さにちょっと閉口です。台湾の食事は油がきつくて駄目という方もいます。小龍包や魯肉飯などは抜群に美味しかったですが、長期滞在だと苦労があるのかも知れません。

最後に携帯した本です。吉田修一さんの「路」という小説です。台湾新幹線の建設プロジェクトを題材に、それに関わる人々のちょっとした成長物語です。同時並行的に進む日本人、台湾人の物語がプロジェクトを介して一つにつながっていく展開が面白く、駆け足で読んでしまいました。今回は車での移動でしたが、プライベートで行く機会があれば新幹線に乗りたいところです。吉田修一さんは、ANAの「翼の王国」で連載されていたエッセイを機内で読んだことで知りました。iPodも持っていきましたが、殆ど出番は無し。敢えて音楽を絶つのもいいのでは思います。自宅に戻って最初に聴く音楽が活きます。
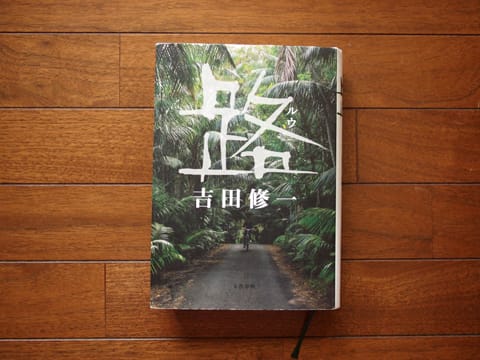
麦わら帽子に、路上のスクーターラッシュ、薄味のビール、それに熱気・・・アジアを感じますね。蝉かどうかわかりませんが、日本ではあまり馴染みの無い鳴き声でした。一足早い夏を先取りしてきました。