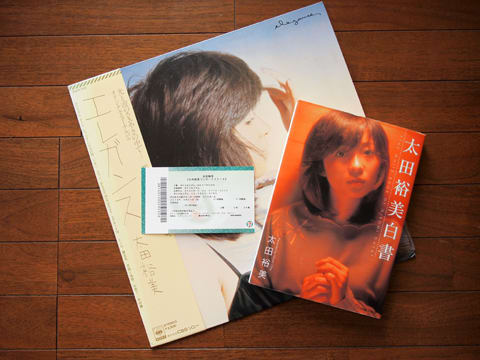横浜地方は、四月下旬の陽気で桜の開花も一気に進みました。拙宅の庭木もいよいよ開幕です。定番のレンギョウとユキヤナギが揃って咲きました。他に、クリスマスローズやムスカリなど、新しい面々も加わってSpring has come! を演出しています。先週より交換したロシア製のEL34も今のところ問題ありません。途切れずに音楽が聴けるのはありがたいことです。もう少し様子を見て、オフ会を延期していた方には案内を出そうと思います。前回から間が開きましたが、音楽の話題です。ドイツの作曲家Bruchのヴァイオリン協奏曲を取り上げてみます。

華のある協奏曲と言えば、ピアノ協奏曲とヴァイオリン協奏曲が双璧でしょうか。以前、ピアノ協奏曲について記事にしましたが、同じようにヴァイオリン協奏曲を聴く機会が増えました。ピアノと違ってヴァイオリンはオーケストラの音色に近いですから、却って空間的なコントラストが強調されます。オーディオの表現力が上がると、クラシックが楽しくなると、漠然と聞いたり読んだりしましたが、私の場合は協奏曲でそれを実感したように思います。その後、室内楽なども面白なってきました。交響曲は案外、私の中では優先順位が低いままです。
話をヴァイオリン協奏曲に戻します。三大ヴァイオリン協奏曲というのがあるそうです。Mendelssohnが有名ですが、他にBeethoven、Brahmsがあります。ただし、これらの協奏曲よりも、Bruchのヴァイオリン協奏曲を聴く頻度がずっと多いです。少し前までは、曲どころか、Bruchの存在自体を知らなかったのですから、これもオーディオの恩恵の一つです。比較的短い曲で、クラシック初心者でも組し易かった点もありますが、やはり曲自体の魅力が大きかったように思います。旋律の美しさがベースにあり、特に第一楽章の後半部の重厚感、第二楽章の叙情性に惹かれます。
最初にこの協奏曲を知ったきっかけは、チョンキョンファのBOXセットです。もう購入から2年が経過し、その間、私自身のシステムも変化しました。以前はヴァイオリンが煩くなる傾向を感じていたのですが、Cubox、AIT DAC、DEQ2496、HUB交換・・・これらの積み重ねで少しはマシにはなったようです。オーディオ評論家の小原さんが、72年のこの演奏を女豹と表現されてましたが、女豹の尻尾くらいは見えたでしょうか。研ぎ澄まされたヴァイオリンと雄大なオーケストラの対比は、システムのバロメータになります。96/24のハイレゾもありますが、いつの日にか英国プレスのオリジナル盤で、たじろいでみたいものです。

Bruchのヴァイオリン協奏曲は、他に3枚のCDを所有しています。こちらはチョンキョンファの再録で1990年録音です。EMI移籍後の作品は都度1枚ずつ購入していますが、四季やアンコールピース集など、どちらかというとリラックスして聴く傾向です。Burchも72年よりは落ち着き、円熟といった印象を受けます。3大・・・の方のBeethovenの協奏曲は、まだ聴き込みが足りていません。

新しいところでは、2012年録音のJulia Fischer盤を持っています。このブログを始めたころから聴いているヴァイオリニストです。日本公演が中止になったり、産休もあったりとしましたが、嬉しいことにここにきてコンスタントに新作が出ています。今年も2月にSarasateが出ました。Bruchは伸びやかで素直な印象です。日本での演奏の機会を心待ちにしています。

最後はHeifetzの62年録音です。私の数少ないSACDの一枚です。と言ってもSACDプレイヤーが無いので、CD層をリッピングして聴かざるを得ないのですが。私が生まれる前の録音ですが、こうして並べて聴いても古さを感じません。太い筆で描いたような力感溢れるヴァイオリンですが、この方は演奏の正確性でも群を抜いていたようですね。Bruchの曲調と弾き手の個性のマッチングの良さを感じます。

演奏者の個性、オーケストラの個性、録音の良し悪し、盤の良し悪し・・・今後もいろんな視点でBruchの協奏曲を聴くことになるでしょう。オーディオに深入りする前には知らなかった作曲家、知らなかった曲をリファレンスにしていることになります。少々不思議な気もしますが、いい曲に巡り合えました。

華のある協奏曲と言えば、ピアノ協奏曲とヴァイオリン協奏曲が双璧でしょうか。以前、ピアノ協奏曲について記事にしましたが、同じようにヴァイオリン協奏曲を聴く機会が増えました。ピアノと違ってヴァイオリンはオーケストラの音色に近いですから、却って空間的なコントラストが強調されます。オーディオの表現力が上がると、クラシックが楽しくなると、漠然と聞いたり読んだりしましたが、私の場合は協奏曲でそれを実感したように思います。その後、室内楽なども面白なってきました。交響曲は案外、私の中では優先順位が低いままです。
話をヴァイオリン協奏曲に戻します。三大ヴァイオリン協奏曲というのがあるそうです。Mendelssohnが有名ですが、他にBeethoven、Brahmsがあります。ただし、これらの協奏曲よりも、Bruchのヴァイオリン協奏曲を聴く頻度がずっと多いです。少し前までは、曲どころか、Bruchの存在自体を知らなかったのですから、これもオーディオの恩恵の一つです。比較的短い曲で、クラシック初心者でも組し易かった点もありますが、やはり曲自体の魅力が大きかったように思います。旋律の美しさがベースにあり、特に第一楽章の後半部の重厚感、第二楽章の叙情性に惹かれます。
最初にこの協奏曲を知ったきっかけは、チョンキョンファのBOXセットです。もう購入から2年が経過し、その間、私自身のシステムも変化しました。以前はヴァイオリンが煩くなる傾向を感じていたのですが、Cubox、AIT DAC、DEQ2496、HUB交換・・・これらの積み重ねで少しはマシにはなったようです。オーディオ評論家の小原さんが、72年のこの演奏を女豹と表現されてましたが、女豹の尻尾くらいは見えたでしょうか。研ぎ澄まされたヴァイオリンと雄大なオーケストラの対比は、システムのバロメータになります。96/24のハイレゾもありますが、いつの日にか英国プレスのオリジナル盤で、たじろいでみたいものです。

Bruchのヴァイオリン協奏曲は、他に3枚のCDを所有しています。こちらはチョンキョンファの再録で1990年録音です。EMI移籍後の作品は都度1枚ずつ購入していますが、四季やアンコールピース集など、どちらかというとリラックスして聴く傾向です。Burchも72年よりは落ち着き、円熟といった印象を受けます。3大・・・の方のBeethovenの協奏曲は、まだ聴き込みが足りていません。

新しいところでは、2012年録音のJulia Fischer盤を持っています。このブログを始めたころから聴いているヴァイオリニストです。日本公演が中止になったり、産休もあったりとしましたが、嬉しいことにここにきてコンスタントに新作が出ています。今年も2月にSarasateが出ました。Bruchは伸びやかで素直な印象です。日本での演奏の機会を心待ちにしています。

最後はHeifetzの62年録音です。私の数少ないSACDの一枚です。と言ってもSACDプレイヤーが無いので、CD層をリッピングして聴かざるを得ないのですが。私が生まれる前の録音ですが、こうして並べて聴いても古さを感じません。太い筆で描いたような力感溢れるヴァイオリンですが、この方は演奏の正確性でも群を抜いていたようですね。Bruchの曲調と弾き手の個性のマッチングの良さを感じます。

演奏者の個性、オーケストラの個性、録音の良し悪し、盤の良し悪し・・・今後もいろんな視点でBruchの協奏曲を聴くことになるでしょう。オーディオに深入りする前には知らなかった作曲家、知らなかった曲をリファレンスにしていることになります。少々不思議な気もしますが、いい曲に巡り合えました。