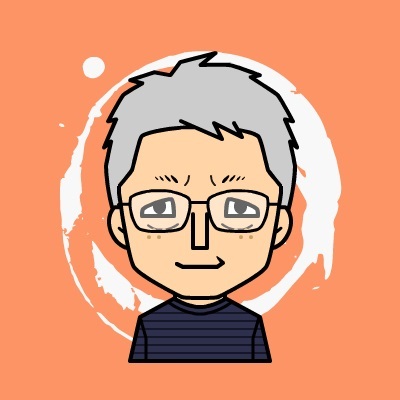ブラっと、大阪城公園に立ち寄った際です。
観光バスに大阪の観光場所が詰め込まれています。

近辺の高層ビルに映った雲です。

生国魂神社お旅所跡地です。

説明書きです。


生国魂神社の歴史を文献資料でたどると、「日本書紀」孝徳天皇即位前紀(645年))に「生国魂神社の樹をきりたまふ」とあるのが初出になります。
これは難波宮造営のためだと考えられています。
また、「天文日記」(1436年〜1454年)の記載からも大坂(石山)本願寺に接して生国魂神社のあったことがわかります。
難波宮や大坂本願寺は、この大阪城の近くにあったことがわかっており、生国魂神社が古くよりこのあたりに祀られていたことがわかります。
その後、豊臣秀吉は大坂城の築城に際して、天王寺区生玉町の現在地に移築させました。
豊臣大坂城の大手門は、生玉門と呼ばれていたそうです。
この「お旅所」は1932年(昭和7年)に新築され、夏祭りの渡御祭に用いられました
と言う事です。
生き物です。


サルノコシカケとイチモンジセセリです。
イチモンジセセリは、卵をくっ付けている様です。
観光バスに大阪の観光場所が詰め込まれています。

近辺の高層ビルに映った雲です。

生国魂神社お旅所跡地です。

説明書きです。


生国魂神社の歴史を文献資料でたどると、「日本書紀」孝徳天皇即位前紀(645年))に「生国魂神社の樹をきりたまふ」とあるのが初出になります。
これは難波宮造営のためだと考えられています。
また、「天文日記」(1436年〜1454年)の記載からも大坂(石山)本願寺に接して生国魂神社のあったことがわかります。
難波宮や大坂本願寺は、この大阪城の近くにあったことがわかっており、生国魂神社が古くよりこのあたりに祀られていたことがわかります。
その後、豊臣秀吉は大坂城の築城に際して、天王寺区生玉町の現在地に移築させました。
豊臣大坂城の大手門は、生玉門と呼ばれていたそうです。
この「お旅所」は1932年(昭和7年)に新築され、夏祭りの渡御祭に用いられました
と言う事です。
生き物です。


サルノコシカケとイチモンジセセリです。
イチモンジセセリは、卵をくっ付けている様です。