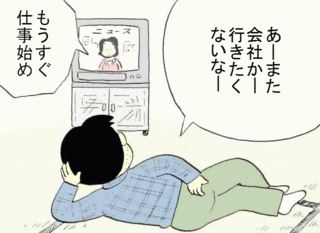さあ、今日もいくぞっ!




と、緑豊かな八王子のいなかの家(マンションですが)を出てから都心の会社まで、door to doorでほぼ2時間かけて通ってます。座席を確保するためホームで5分ほど並んで始発電車を待つのですが、自分の座席の位置と周囲の着席関係が確定するまでの攻防に毎朝かなり神経を使います。
座席の快適さの要因としては、まずは座席の方位(南側/北側)があり、当然冬は南側、夏は北側が快適です。車内は空調が必ずしも快適とは言えませんので。方位に次いで、いやそれ以上に重要とも言えるのが左右に座る方々。座席の端は大抵最初に確保されるのでそれ以外のところに座ることになるのですが、隣に座るとちょっと困る人達もいろいろいて、避けたい順位としては、①タバコ臭のきつい人、②口臭のきつい人、③オヤジ臭のきつい人、④イヤホンからシャカシャ音漏れの激しい人、⑤おしゃべりの声が大きい人、などです。
常連さん達の特性はすべて頭に入っているのですが、そうでない方々の場合は座る前に見た目で判断せざるを得ません。電車がホームに入ってきてドアが開いて、他の乗客とともにドドッと車内に押し込まれると、各人の動きと視線からそれぞれが目指している座席を推定し、自分の座るべき座席を瞬時に判断してすばやく確保しなければなりません。このお姉さんはタバコは吸いそうもないな、と思うと服がタバコで煮しめたような臭いだったり、座る直前に微妙に席をずらす人がいたり、金田一耕介並の推理力と星飛遊馬の大リーグボール1号並みの行動予測力が求められます。
前に立つ人は左右に比べれば影響度は低いのですが、それでも新聞を人の頭の上まで広げて読む人、口を押さえないで派手にくしゃみをする人、立ちながら居眠りして人の目の前まで倒れかかってくる人、等々いろいろいますので、座席を確保した後も気が抜けません。この人ちょっとあぶないなー、と思った時はさりげなく靴の紐を結ぶふりをして前に立たないように誘導するなど、タイミングを逃さない臨機応変の対応が必要です。しかし判断に狂いがなくすべてがぴったりとはまった朝は、ポカポカと背中を暖めるやわらかな日差しの中、都心まで快適に読書三昧の至福の時を味わえます。
毎朝鍛えたこの高度な?判断力が仕事に生かせればいいのですが、なかなか成果にはつながりませんねー。
追記(1/27夜):
読んだ方もいらっしゃるかと思いますが、1/3から1/19まで読売新聞に12回シリーズで”男ごごろ「らしさ」を超えて”という記事が連載されていました。今日の同紙朝刊の17面に同シリーズへの読者からの反響、というまとめ記事が出ていたのですが、第一回の”「おばおじさん」自然な姿”という記事の「おばおじさん」について私が命名者のマーケティング戦略プロデューサー塚田祐子さんのブログに入れたコメント(親近感を感じます)も引用されていました。
「おばおじさん」を検索してみるとあちこちで話題になっており、流行語としての地位を確立しつつあるようです。いわゆる世間一般のオジサン達の世界に違和感を感じ、「酒もタバコもやらんのか?」などと上役に言われても、「酒やタバコがそんなにエライのか!」と反論したいのをぐっとこらえて、「ええ」と微笑むしか術のない私としては、おばおじさん達がどんどん増殖し、隠れおばおじさんはカミングアウトして勢力拡大してくれるのを期待しています。