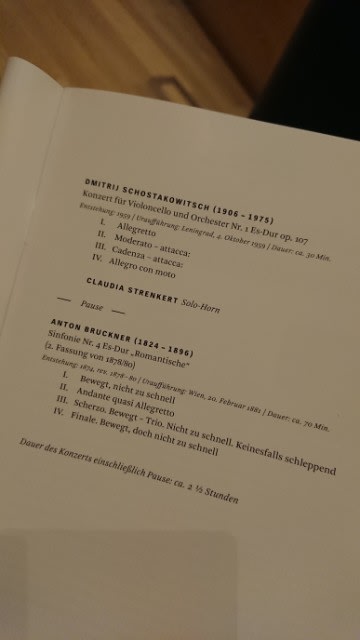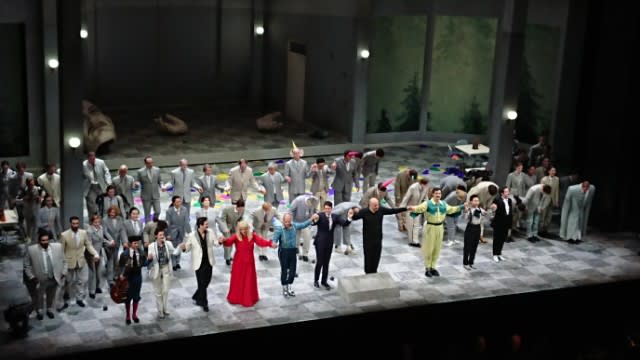エッシェンバッハ&エルプフィルの終演が13時半頃。ケント・ナガノ&ハンブルク・フィル開演まで2時間半、何をしよう?

まずは運河沿いのベンチに座ってノンビリ釣人を眺める。風が気持ちよく、このまま15時くらいまでノンビリ過ごしても良かったのだが、ハンブルク響終演後、タクシー乗り場に行列が出来ていたときのため、バス停まで下見に行くことにした。Googleマップによると950メートル、徒歩14分とある。もし道に迷ったりしたら命取りだ。


しかし、これが心楽しい散歩だった。運河そのものも美しいし、こんな橋を渡るのだって嬉しい。


ひとりの幸せ。もし誰か知人に声を掛けられ、現実に引き戻されたら台無しだ。万一、知ってる顔を見掛けたら、物影に隠れて過ぎるのを待つか、急いで人混みに紛れることにしよう。


バス停までは普通に歩いて10分、急げば1~2分詰められるかな? 途中、ニコライ教会にも挨拶できて良かった。
さて、エルプフィルハーモニーに戻ると、入口からホールロビーまで、スマホで動画撮影。このblogには動画が直に貼れない仕組みになっているので、興味のある方はFacebookを覗いて欲しい。



小腹が空いていたので、エルプフィル内のカフェで地元のケーキから林檎ケーキを選んで食べる。余分な味付けのないシンプルさを舌が喜び、十分に昼食変わりになるサイズでお腹も満足。

と、前置きを長々と書いているのには理由がある。
演奏が良くなかったのだ。
否、前半のメシアン「世の終わりのための四重奏曲」(ヴァイオリン、チェロ、クラリネット、ピアノのための)は、瞑想的な美に貫かれ、素晴らしかった。チェロがヴィブラートに頼り過ぎなければなお良かったけど、60分弱という長丁場、4人の奏者は時間と空間を完全に支配、まったく緊張の糸の切れる瞬間はなかったのである。ただ、クラリネットの最弱音によるモノローグの最中に、平戸間客のスマホの呼び出し音の鳴ってしまったのは残念だったが・・。

なお、わたしの座席はサントリーホールで言えば、RAブロックのかなりP席寄りであったが、特に内田光子が選定したというスタインウェイが玉のように美しく響いてきた。サントリーホールのこの位置では考えられないほど、明晰で、生命力があったのである。ここで、誰かのピアノリサイタルを聴いてみたいと思わせたものである。

休憩後、目を付けていた平戸間後方の空席に移り、ケント・ナガノの登場を待った。
聴く前には、「ブルックナーはいくら聴いても疲れない」と豪語していたわたしも、ケント・ナガノのブルックナーにはお手上げだった。
まず、その音楽づくり、というかケント・ナガノの指揮が神経質なこと。さらには、オケの自発性を尊重するよりは従わせるタイプの指揮で音楽が生きていないこと。テューバやティンパニを筆頭にフォルテが下品なほどにうるさい。さらに、ブルックナーの命であるゲネラル・パウゼで何も感じないまま、先を急いでしまう、等々。
指揮そのものにも疑問があった。第1楽章後半、2つ振りか、4つ振りか、迷った場面でアンサンブルが崩壊しかけたことなど、それはただの事故だからよいけれど、フォルテのたびに見せるケント・ナガノの尋常でない力みが、オーケストラに悪影響を与えてしまっているのは根源的な問題だ。
大好きなブルックナーなのに、最初から最後まで、ただの1小節も美しいと感じる場面がなかったのだから恐れ入る。エッシェンバッハの思い出で終わりにしておけばよかった、と言っても後の祭。それも実際に聴いてみなければ、分からなかったことだと自らを慰めているところ。

最後のホルンの響きが消えるや否や、拍手は省略してタクシー乗り場に直行。果たして、ハンブルク響の開演に間に合うのか?

まずは運河沿いのベンチに座ってノンビリ釣人を眺める。風が気持ちよく、このまま15時くらいまでノンビリ過ごしても良かったのだが、ハンブルク響終演後、タクシー乗り場に行列が出来ていたときのため、バス停まで下見に行くことにした。Googleマップによると950メートル、徒歩14分とある。もし道に迷ったりしたら命取りだ。


しかし、これが心楽しい散歩だった。運河そのものも美しいし、こんな橋を渡るのだって嬉しい。


ひとりの幸せ。もし誰か知人に声を掛けられ、現実に引き戻されたら台無しだ。万一、知ってる顔を見掛けたら、物影に隠れて過ぎるのを待つか、急いで人混みに紛れることにしよう。


バス停までは普通に歩いて10分、急げば1~2分詰められるかな? 途中、ニコライ教会にも挨拶できて良かった。
さて、エルプフィルハーモニーに戻ると、入口からホールロビーまで、スマホで動画撮影。このblogには動画が直に貼れない仕組みになっているので、興味のある方はFacebookを覗いて欲しい。



小腹が空いていたので、エルプフィル内のカフェで地元のケーキから林檎ケーキを選んで食べる。余分な味付けのないシンプルさを舌が喜び、十分に昼食変わりになるサイズでお腹も満足。

と、前置きを長々と書いているのには理由がある。
演奏が良くなかったのだ。
否、前半のメシアン「世の終わりのための四重奏曲」(ヴァイオリン、チェロ、クラリネット、ピアノのための)は、瞑想的な美に貫かれ、素晴らしかった。チェロがヴィブラートに頼り過ぎなければなお良かったけど、60分弱という長丁場、4人の奏者は時間と空間を完全に支配、まったく緊張の糸の切れる瞬間はなかったのである。ただ、クラリネットの最弱音によるモノローグの最中に、平戸間客のスマホの呼び出し音の鳴ってしまったのは残念だったが・・。

なお、わたしの座席はサントリーホールで言えば、RAブロックのかなりP席寄りであったが、特に内田光子が選定したというスタインウェイが玉のように美しく響いてきた。サントリーホールのこの位置では考えられないほど、明晰で、生命力があったのである。ここで、誰かのピアノリサイタルを聴いてみたいと思わせたものである。

休憩後、目を付けていた平戸間後方の空席に移り、ケント・ナガノの登場を待った。
聴く前には、「ブルックナーはいくら聴いても疲れない」と豪語していたわたしも、ケント・ナガノのブルックナーにはお手上げだった。
まず、その音楽づくり、というかケント・ナガノの指揮が神経質なこと。さらには、オケの自発性を尊重するよりは従わせるタイプの指揮で音楽が生きていないこと。テューバやティンパニを筆頭にフォルテが下品なほどにうるさい。さらに、ブルックナーの命であるゲネラル・パウゼで何も感じないまま、先を急いでしまう、等々。
指揮そのものにも疑問があった。第1楽章後半、2つ振りか、4つ振りか、迷った場面でアンサンブルが崩壊しかけたことなど、それはただの事故だからよいけれど、フォルテのたびに見せるケント・ナガノの尋常でない力みが、オーケストラに悪影響を与えてしまっているのは根源的な問題だ。
大好きなブルックナーなのに、最初から最後まで、ただの1小節も美しいと感じる場面がなかったのだから恐れ入る。エッシェンバッハの思い出で終わりにしておけばよかった、と言っても後の祭。それも実際に聴いてみなければ、分からなかったことだと自らを慰めているところ。

最後のホルンの響きが消えるや否や、拍手は省略してタクシー乗り場に直行。果たして、ハンブルク響の開演に間に合うのか?