ニコラム・スロニムスキー編 :『名曲悪口事典』(伊藤制子ら訳) 音楽之友社 2008
以下は本誌に掲載された19世紀の音楽評論である。

ショパンについて
『多くの人はもっと悪く言うかもしれないが、比類なく馬鹿げて大げさな贅沢品の卸売業者である。(中略)ショパンの作品はどれも、大言壮語と耐えがたい不協和音のごちゃごちゃした外観である。彼が「このように」風変わりなことをしないときは、シュトラウスや他のワルツ作曲家以上のものではない。(中略)ショパンの怠慢には目下のところひとつの理由がある。あの恋多き魅惑的な女のなかの女ジョルジュ・サンドの抗い難い束縛に妨げられているのだ。同じく不思議なのは、かつて崇高で恐ろしく敬虔な民主主義者ラムネーの心を奪ったほどの彼女が、夢のような生活を手放してまでショパンという芸術的にも取るに足らない者と戯れることに、どうして満足できるのかということだ。』(ミュージカル・ワールド(ロンドン)1841年10月28日)
ベートーベンについて
『《交響曲第九番》のオーケストラ部分全体が、実際とても退屈だった。幾度か寝入りそうになってしまった。(中略)非常に期待していた合唱部分に到達したときには、ずいぷんとほっとした。《ヤンキー・ドゥードル》のような八小節の陳腐な主題で始まった(中略)。有名な交響曲のこの部分に関しては、ほとんど互いに混ざり合わない奇妙で滑稽、たどたどしく捧猛でキーキー響く素材と、ただひとつのわかりやすい旋律からできあがっているようだ、と残念だがいわなくてはならない。プログラムに印刷されている歌詞に関していえば、まったくお話にならず、しかも一切の騒音がなにを意図しているのか、まったくわからなかった。総体的な印象としては、インディアンの雄叫びと荒れ狂った野良猫たちから成り立ったコンサートだった』(「The Orchestra」 1868年6月20日)
ワグナーについて
『ワーグナーという男には、いささかの才能も備わっていない。彼の旋律は、といっても旋律がみつかる場面にかぎっての話だが、ヴェルディやフロトーよりもさらにまずいし、気の抜けたメンデルスゾーンよりも捻くれている。こうしたことはすべて、厚い堕落の壁に覆われている。彼のオーケストレーーションは装飾的だが下品だ。ヅァイオリンが最高音域で悲鳴を上げ、聴き手を極度の緊張状態に陥れる。私は演奏会が終わる前に席を立った。請け合ってもいいが、もし、あと少しそこにとどまっていたら、私も妻もヒステリーの発作を起こしていただろう。ああした神経症は、ワーグナー白身の持病だろうか?』(セザール・キュイがリムスキー・コルサコフRimsky,Korsakovへ宛てた手紙、1863年3月9日)
チャイコフスキーについて
『《悲憤交響曲》は、汚いドブに人間の絶望の吐き溜を編み込んだ作品で、音楽がなしうるかぎりの醜態である。第一楽章は、ゾラの『クロードの告白』の音楽版と言ってよい。なんともいいがたい第二主題は、いわばハイネがいう「もうろくして思い出す幼な恋」〔訳注‥『新詩集』〕だ。それにしても幼な恋とは!風刺画家ホガースの書いた放蕩息子の恋だろうか,明らかにこの楽章には力がこもっている。野蛮で品のない楽想を、チャイコフスキー以外の誰が力あるものにできようか?斜に構えたリズムの第二楽章は、卑しいとしか言いようかないし、第三楽章は薄っぺらな悪態だ。最終楽章では、目のかすんだ脳梅毒に直面させられ、トロンボーンの荘厳な碑文が、締めくくりの言葉を述べる。「かくして堕落が続きます」(後略)。』(W.F. アブトーブ 「ボストン・イヴニング・トランスクリプト1898年10月31日」
なんともどれも凄まじい。音楽評論というものは少しほめて、沢山けなすというのが正道かと思っていたが、この著が紹介する評論は、どれも頭から100%否定に徹している。しかも罵詈雑言に近いものが多い。それも相手はベートーベン、ショパン、シューマン、ワグナー、ブラームス、チャイコフスキーなどの大家ばかりである。読んでいて、頭がくらくらしてくる。どうしてこんな音楽評がはやったのか? 著者スロニムスキーの説では、この手のものでないと読者が読まないということらしい。あるいは、これを読んで、どんなにひどいか確かめるめるために、音楽会に聴衆があつまったのかもしれない。

















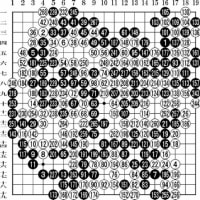








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます