2009年3月21日(土曜日)
孫と健さんと3人で朝から福井へでかけました。
(優先順位は孫のほうが上になってる!)
福井県立美術館で開催されている
『川喜田半泥子と人間国宝たち』
~桃山ルネッサンス陶芸の近代化~
を見るために・・
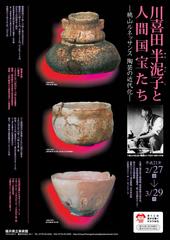
30年以上も茶道とは無縁の暮らしを続けている
わたしですが、結婚するまでは
お茶のある暮らしに結構なじんでいました。
いまでも陶芸や茶花、書画骨董の世界には
心惹かれております。
このあたりの趣味の世界のことになると
なぜか、健さんと話が合うんですね・・・
で、わたしの3月議会が終わるのを待って
ふたりで美術館へ行こう! となったのです。
とっても都合よく(?)、孫の面倒もみることになって
3人でお出かけが実現しました。
今年5歳になる孫は、これはなあに?
なにをいれるの?
あっ、このお茶わん、デンバアのとこにもあるで。
ごはんのとき、つことるなぁ・・・
(ちなみにそれは粉引茶碗です)
これはなんて名前がついとるの?
こっちのはお花をいれるんでしょ・・・
と、ひとつひとつの作品をわたしといっしょに
じっくりと鑑賞してくれたので、大助かり!
彼女がいちばん気に入ったのは、なんと!
北大路魯山人の綾部の大鉢・・・
へ~、結構見る目があるじゃないかと
内心ほくそ笑むわたし・・・
心ゆくまで陶芸の世界にひたることができて
至福のひとときを過ごすことができました。
かえりに今庄の「おばちゃんの店」で
おろしそばを食べて帰ってきました。
ここのお薦めは、そばはもちろんのこと
ワサビの葉の漬物やフキノトウの味噌が
とってもおいしくて、立ち寄ったときには
いつもおみやげに買って帰ります。
家に帰り着いたとたん、わたしは布団にかけこんで
夕方、タミヨさんの電話で起こされるまで
ぐっすり・・・
思ったより、疲れたみたいです。
「おばちゃんの店 ほっと今庄」のホームページから
http://www.hotimajo.jp/index.html
南越前町今庄は、
【そば】を核とした町興しに取り組んでおり、
そば文化を後世に伝えて いこうとしていました。
町内の女性グループが、平成4年から
農協の加工施設を借り受け、 町特産の【そば】をテーマに
いろいろな料理や加工品の開発に取り組んでおりました。
平成12年7月に、12名の女性メンバーで、
そばを提供する 有限会社ほっと今庄を設立し、
手づくりをモットーとした今庄そばの
加工販売活動を開始したました。
**************************
福井県立美術館ホームページ
http://info.pref.fukui.jp/bunka/bijutukan/bunka1.html
こちらが公式ホームページ
http://info.pref.fukui.jp/bunka/bijutukan/h20_yotei.html#handeisi
「東の魯山人、西の半泥子」と称された
川喜田半泥子(かわきた・はんでいし)は、
財界人として活躍する一方、桃山時代の陶芸の
近代的復興を目指した偉大なる趣味人。
志を一つにする荒川豊蔵、金重陶陽、三輪休和ら、
後の人間国宝たちとともに近代陶芸の新たな時代の
幕開けのため奔走しました。
本展では彼らの作品を中心に、親交があった中里無庵、
北大路魯山人らの陶芸、書、絵画、書簡など約170点から、
研ぎ澄まされた美意識と溢れんばかりの遊び心が交錯する
陶芸家たちの技と、そのおおらかな交遊を紹介します。
こちらは美術館だより
http://info.pref.fukui.jp/bunka/bijutukan/dayori_vol122.pdf
川喜田半泥子(かわきた はんでいし)は
明治11年(1878年)、三重県の歴代富豪の名門に生まれ、
百五銀行の頭取を務めるなど実業界で成功を
みた人でしたが、その傍らで陶芸、茶道、書画、
俳句などにも才能を発揮しました。
特に「しろうと」と自称しながら作る何にもとらわれない
自由な茶陶は、数寄風流人半泥子にしか
到達できない境地といえます。
また、昭和初期に再評価の機運が高まった
桃山茶陶に対しては、単なる模倣や再現にとどまらずに、
むしろ学ぶべきはその表現の自由さや独自の表現であり、
それを超えるものを作り出さねばならないことを指摘します。
そしてその志を共有する荒川豊蔵(あらかわ とよぞう)、
金重陶陽(かねしげ とうよう)、
三輪休和〈十代休雪〉(みわ きゅうわ)、
中里無庵(なかざと むあん)など多くの陶工たちと
おおらかな交友が結ばれて、技術的には彼らに学びながらも
精神的には牽引する役目を担いました。
本展では半泥子という多才で遊び心に富んだ
魅力的な人物とその作品を紹介するとともに、
半泥子と親交があった北大路魯山人らを含む
陶芸家たちの陶芸、書画、書簡など172点から、
昭和初期の桃山ルネッサンスとそれに伴う
陶芸の近代化を展観します。
















