先週土曜日、「理事長講話」に行って参りました
保護者会主催の「講演会」が毎年この時期に行われるのですが、今年はそれが「理事長講話」となったのです。
理事長ご自身が教員時代にハンドボール部の顧問をなさっていたそうで、その時の経験から学んだことをお話されました。
・技術は「ゆっくり」「確実に」身に付けるほうが良い(体力作りは後でも良い)
・子どもは環境によって変わるもの
・子ども1人ひとりの個性を伸ばすことでチーム全体も伸びる
・子どもによって「伸びる」時期は異なる
・あせらない!あきらめない!ことが大事
・好きなことを伸ばそう!
講演の要旨は以上のようなことでした。
さて、そのお話に先立って、これから先「開智」の何が変わるのか…など、いろいろ興味深いお話がありました
…が、その中で私が最も驚いたこと
それは…
「総合部と中高一貫との中3での初合流後、1学期期末テストにおける全教科平均点比較の結果……総合部の方が高かった」
「教科別においても、英・数・国全てにおいて総合部が上だった」
「中でも数学は総合部の方がかなり高く、英語は2番目に上で、国語は少し上くらいだった」
へぇへぇへぇへぇへぇ~・…
「金」の脳ミソ~~~(古っ )
)
開智中学と言えば、3大模試偏差値で…
四谷大塚合不合80%ライン=男子58 女子60
日能研R4=男子55 女子56
首都圏統一模試80%ライン=男子63 女子63
相当偏差値高いです
中学から入学してくる子たちは、ハッキリ言ってガンガンに受験勉強して合格した子どもたち
特に開智の入試算数は「難問かつ良問」も多いので、勉強も相当の「質」と「量」をこなして来ている
その子たちより「かなり」上 ~~~
~~~
 マジで~~~
マジで~~~
「かなり」上なのは、てっきり英語の方かと思っていました
だって、総合部の子どもたちは小5から「中学英語」をやっているんですから…
これについて理事長はこうおっしゃっていました。
「小学生からやっている総合部の子どもたちはリスニングやディクテーションについてはスゴイ でもテストはペーパー中心ですから…」
でもテストはペーパー中心ですから…」
まあ、確かにね~~~
とにかく私のイメージでは…
「中入生」(中学から入学した生徒)の方が「内進生」(内部から上がってきた生徒)より上位を占めることが多い
…それが「小学校 中学校」進学における普通の構図だとばかり思っていました。
中学校」進学における普通の構図だとばかり思っていました。
他の埼玉県内私立、たとえば、さとえ小→栄東中も然りではないかと…
良い意味で、軽くカルチャーショックです
理由について理事長見解は…
「総合部の、特に算数の授業などは教え方を相当工夫している。講義中心ではなく、考えさせる授業をしている。その成果では…」
その考え方から生まれたのが来年創設される中高一貫の 「先端創造クラス」
「先端創造クラス」 だそうです。
だそうです。
なるほどね…
優秀な生徒を集めるための「策」だけじゃなかったのね…
それなら、スゴイ
(でも、教える先生は相当の力量がいるし、大変そう~~~ )
)
「考えさせる授業」とはちょっと違うかもしれませんが…
娘が今やっている1年生の算数…
足し算(繰り上がりあり)を教えるなら、一桁も二桁も三桁も一緒。
どうして間をあけて何年もかけて教える必要があるのか…
(現行の学習指導要領では、1位数=1年、2位数=2年、3位数=3年)
これが開智の考え方。
全く同感です
以上は1つの例ですが、たとえばそんなところが算数が伸びる要因なのかな、と思います。
受験国語を永年指導していた私としては、国語についてはもうちょっとがんばって欲しいな~と、正直思います。
さて、他にも「学内宿泊施設建設予定」など、興味深いお話はたくさんありました。
折に触れてご紹介したいと思います。
それよりも、例の 「入試方法変更の方向性」
「入試方法変更の方向性」
期待していた通り、その件についても在校生保護者にはいち早くお話をして下さいました
が、「方向性」というだけあって、現時点ではあくまで「予定」。
したがって、12月5日に行われる「学校説明会」までは、一般公開は一応控えさせて頂きます。
ご興味のある方は、ぜひご自分の目と耳でお確かめください。

保護者会主催の「講演会」が毎年この時期に行われるのですが、今年はそれが「理事長講話」となったのです。
理事長ご自身が教員時代にハンドボール部の顧問をなさっていたそうで、その時の経験から学んだことをお話されました。
・技術は「ゆっくり」「確実に」身に付けるほうが良い(体力作りは後でも良い)
・子どもは環境によって変わるもの
・子ども1人ひとりの個性を伸ばすことでチーム全体も伸びる
・子どもによって「伸びる」時期は異なる
・あせらない!あきらめない!ことが大事
・好きなことを伸ばそう!
講演の要旨は以上のようなことでした。
さて、そのお話に先立って、これから先「開智」の何が変わるのか…など、いろいろ興味深いお話がありました

…が、その中で私が最も驚いたこと

それは…
「総合部と中高一貫との中3での初合流後、1学期期末テストにおける全教科平均点比較の結果……総合部の方が高かった」
「教科別においても、英・数・国全てにおいて総合部が上だった」
「中でも数学は総合部の方がかなり高く、英語は2番目に上で、国語は少し上くらいだった」
へぇへぇへぇへぇへぇ~・…
「金」の脳ミソ~~~(古っ
 )
)開智中学と言えば、3大模試偏差値で…
四谷大塚合不合80%ライン=男子58 女子60
日能研R4=男子55 女子56
首都圏統一模試80%ライン=男子63 女子63
相当偏差値高いです

中学から入学してくる子たちは、ハッキリ言ってガンガンに受験勉強して合格した子どもたち

特に開智の入試算数は「難問かつ良問」も多いので、勉強も相当の「質」と「量」をこなして来ている

その子たちより「かなり」上
 ~~~
~~~
 マジで~~~
マジで~~~
「かなり」上なのは、てっきり英語の方かと思っていました

だって、総合部の子どもたちは小5から「中学英語」をやっているんですから…
これについて理事長はこうおっしゃっていました。
「小学生からやっている総合部の子どもたちはリスニングやディクテーションについてはスゴイ
 でもテストはペーパー中心ですから…」
でもテストはペーパー中心ですから…」まあ、確かにね~~~
とにかく私のイメージでは…
「中入生」(中学から入学した生徒)の方が「内進生」(内部から上がってきた生徒)より上位を占めることが多い

…それが「小学校
 中学校」進学における普通の構図だとばかり思っていました。
中学校」進学における普通の構図だとばかり思っていました。他の埼玉県内私立、たとえば、さとえ小→栄東中も然りではないかと…
良い意味で、軽くカルチャーショックです

理由について理事長見解は…
「総合部の、特に算数の授業などは教え方を相当工夫している。講義中心ではなく、考えさせる授業をしている。その成果では…」
その考え方から生まれたのが来年創設される中高一貫の
 「先端創造クラス」
「先端創造クラス」 だそうです。
だそうです。なるほどね…
優秀な生徒を集めるための「策」だけじゃなかったのね…
それなら、スゴイ

(でも、教える先生は相当の力量がいるし、大変そう~~~
 )
)「考えさせる授業」とはちょっと違うかもしれませんが…
娘が今やっている1年生の算数…
足し算(繰り上がりあり)を教えるなら、一桁も二桁も三桁も一緒。
どうして間をあけて何年もかけて教える必要があるのか…
(現行の学習指導要領では、1位数=1年、2位数=2年、3位数=3年)
これが開智の考え方。
全く同感です

以上は1つの例ですが、たとえばそんなところが算数が伸びる要因なのかな、と思います。
受験国語を永年指導していた私としては、国語についてはもうちょっとがんばって欲しいな~と、正直思います。
さて、他にも「学内宿泊施設建設予定」など、興味深いお話はたくさんありました。
折に触れてご紹介したいと思います。
それよりも、例の
 「入試方法変更の方向性」
「入試方法変更の方向性」
期待していた通り、その件についても在校生保護者にはいち早くお話をして下さいました

が、「方向性」というだけあって、現時点ではあくまで「予定」。
したがって、12月5日に行われる「学校説明会」までは、一般公開は一応控えさせて頂きます。
ご興味のある方は、ぜひご自分の目と耳でお確かめください。










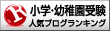

















開智でどう教えているかは存じ上げないのですが、例えば、算数・数学で”=”(等号)を
・計算式の終わりに書く記号 とするか
・右側と左側が”等しい”意味とするか
で随分違います。等号の概念が最初から判っていれば、方程式に進むのは容易ですよね。
等しいものの両方に同じ数を足したり、掛けたり、引いたり、割ったりしても同じだよ、ということは直ぐに理解できます。そこさえ理解すれば方程式を解くのは容易ですが、”=”を計算の答のしるしと考えている事によって、ここでつまづく友達が多かった記憶があります。
そういうことなのかな、、?
貴重な記事、有難うございました。