ほとんどの学校では先週末までに入学式が終わり、いよいよ今日から本格的な授業開始ですね~

ウチの娘の教科の先生は、それぞれ誰になるのかしら…

実は、ウチの娘、この春休みに「春期講習」を受けました。
私の教室で、同じ開智の新2年生たち3人と一緒に。
ここのところ、もう、私と2人きりの授業は限界…

すぐケンカ

になってしまう

やっぱり親子は難しいわ~~~

…というのもあり、お友だちも是非一緒に、となった次第。
内容は開智1年生の算数・国語の復習。
一応これだけやっておけば問題なく2年生に進級できるであろう内容を、5日間で厳選して学習させました。

算数

計算問題
・1ケタ~3ケタまでの加減(繰り上がり・繰り下がり)
・2ケタ~3ケタの筆算(繰り上がり・繰り下がり)
A4オモテウラのプリントで、早く正確に解く練習をしました

相当な量でしたが、30枚近くこなすことができました

娘は、スピードも速く、ほぼノーミス


既習内容
・時計(何時何分)
・虫食い(2ケタ~3ケタの筆算)
・1000までの数
時計は全く問題なし

娘は虫食いが苦手だったのですが、今回の復習で「わかった

」らしく、逆に好きになったみたい

謎解きのようにクイズ感覚で解かせたのが面白かったみたいです

1000までの数もOK

「100が10コでいくつ

」ではなく、「100円が10枚でいくら

」などと、お金

に置き換えると、とたんにデキル…

ホント、お金の計算は、チョー早い…


文章題
・加減
・かくれた数
・3つの数の計算
・なんばん目
どの子も皆、苦手な文章題。
1年生からしっかりできるようにさせたいですね

ウチの娘も得意なほうではありませんでした

そこで、まずは文章を正確に読み取り、簡単な「絵」や「図」にする練習です。
「絵」や「図」が描けさえすれば、式は簡単に立てられます。
ところが、「どんぐり倶楽部」式に「絵」を描かせてじっくり考えさせるのは、時間がたっぷりある時ならとても良いことだと思いますが、あまり実践的ではありません。
テストの時にいちいち絵を描いていたら時間もかかるし、絵を描くことのほうに集中して肝心な立式まで行かない怖れがあります。
そこで、私は「テープ図」を描かせるようにしています。
「テープ図」は、子どもたちも学校で習っています。
でも、独力ではなかなか描けない。
そこで、今回は「テープ図」を徹底演習。
最初はトンチンカンな図を描いていましたが、演習していくうちにだんだん描けるようになり、最終日にはほぼ全問正解できるようになりました。
「なんばん目」の問題では、図だけでなく式も立てられるように練習しました。
問題例)
コンサートのかんきゃくが1れつにならんでいます。
ひなたくんはまえから175ばん目、うしろから45ばん目です。
コンサートのかんきゃくはぜんぶでなん人いますか。
しき
175+45-1=219
こたえ
219人
この問題では、「ひなたくん」をダブって数えているので、「1」引かなければならない。
他にもいろいろなパターンをこなし、「1」足すのか、それとも「1」引くのか、じっくり考えさせながら練習。
それを小さい数からだんだん大きい数にしていって、図を描かなくても解けるくらいまで練習させました。
娘のお友だちで、公文をやっている子、やはり多いです。
低学年のうちの計算基礎演習は大切ですし、そのための公文プリントは私も良いと思います。
でも公文だけだと、計算問題は条件反射的に強いけれど、じっくり思考しなければならない文章題や図形問題などについては、太刀打ちできません。
それに、開智に入ったら計算問題などあっという間に追い越されてしまいます。
一般的に、算数の文章題は読むのさえイヤ

という子ども、多いですね。
でも、絵や図を描かせ、よーく考えさせながら解かせると、子どもたちはクイズ感覚でとても楽しそうに取り組みます。
それに、解けたときの達成感や満足感

は、計算問題が解けたときよりも数倍大きいようです。
それを今回、改めて痛感しました

次に…

国語

漢字テスト
1年生の漢字の復習です。
ただし、発展的な学習として、習ってはいるけれども読みの難しい漢字の「書き取り」も行いました。
「三日月」「山村」「水田」「千人力」「(早おきは)三文(のとく)」「(ビルが)林立(する)」「本音」「名手」「十中八九」「天(の)川」「竹林」「足(す)」…etc
子どもたちは最初…
「えー、習ってない~~~

」
と怒ります

そこで、シメシメ…

「でもさ、全部1年生の漢字だよ。だからみんな書けるはず。文をよく読んで意味をよーく考えてごらん」
すると、みんな一生懸命考えて…
「わかった

」
なんと、正解してしまうのです

できたら、褒めまくる

すると、「下手」「上手」「七夕」「二十日」などの難しい「熟字訓」まで考えて書けちゃったりするのです

子どもって、すごいなー


文章読解
開智では、プライマリーまでは「光村図書」の教科書に準拠して授業が進みますが、小学3年生の中間・期末試験では、早くも初見の文章読解問題が出題されるようになります。
さらに、セカンダリー(小学5年生)からは教科書を使わず、完全にプリントでの読解演習になります。
しかも、結構すごいレベルの高い文章で

カリキュラムに載っている出題文など、いわゆる「中学受験」のレベル

そのため、というわけではありませんが、娘にも1年生から文章読解がしっかりできる子になって欲しいと、私は思っています。
そこで今回は、文章読解の基礎を徹底的に演習しました。
「おおきなかぶ」「くじらぐも」「しまうまの赤ちゃん」「たぬきの糸車」
難しい文章ではなく既に習った教科書の文章を題材に、文章読解問題を解くコツをつかませました。
最終日、初見の文章読解をさせてみましたが、練習の成果か、娘は問題なく正解できていました

国語の力はなかなか一朝一夕にはつきません。
1年生からこういう読解演習を積み重ねておくと、高学年になって初見の文章ばかりになっても苦手意識を持つことなく解けるようになると思います。
いずれは記述力もつけさせたいと思っているところです。

語句の知識
これも、1年生既習内容の確認。
・拗音、長音、撥音、促音
・紛らわしいかなづかい
・「は・を・へ」
・主語+述語の文
・カタカナ
こちらは、難なくクリア

ここでひっかかっていると、2年以降ヤバイです

今回、初めて、生徒の1人として開智の子どもたちと一緒に娘の勉強をみました。
結果、とても良かった

娘もワガママを言わず良い子だったし、お互いにケジメがつけられて良い感じでした

それに、開智の子どもたちと授業するのは、ナント楽しいこと

ポンっと、投げたら、パッと、返ってくる

時間がとれたら、夏期講習もやろうかな~~~

…とか
時間ないか



 」とせがまれても、無理なのだ
」とせがまれても、無理なのだ



 「目玉白玉」
「目玉白玉」



 を企画してくれていて、娘は今からとても楽しみにしています
を企画してくれていて、娘は今からとても楽しみにしています

 「洗濯」
「洗濯」 「掃除」
「掃除」 「ゴミ出し」
「ゴミ出し」 …
…


 「散らかる」
「散らかる」




 」とせがまれても、無理なのだ
」とせがまれても、無理なのだ



 「目玉白玉」
「目玉白玉」



 を企画してくれていて、娘は今からとても楽しみにしています
を企画してくれていて、娘は今からとても楽しみにしています

 「洗濯」
「洗濯」 「掃除」
「掃除」 「ゴミ出し」
「ゴミ出し」 …
…


 「散らかる」
「散らかる」













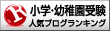








 ふってる
ふってる 授業中だぞっ
授業中だぞっ



 に始まって、保護者会
に始まって、保護者会 、懇親会
、懇親会 、打ち合わせ
、打ち合わせ …
…







 算数
算数 計算問題
計算問題



 」らしく、逆に好きになったみたい
」らしく、逆に好きになったみたい
 に置き換えると、とたんにデキル…
に置き換えると、とたんにデキル…
 は、計算問題が解けたときよりも数倍大きいようです。
は、計算問題が解けたときよりも数倍大きいようです。 漢字テスト
漢字テスト






 「入学式」
「入学式」


 頭の働き。理解し判断する力。知恵。
頭の働き。理解し判断する力。知恵。 さとり。
さとり。 物事をよく知り、わきまえている。賢い。さとい。
物事をよく知り、わきまえている。賢い。さとい。 知恵がある人。賢い人。
知恵がある人。賢い人。 はかりごと。謀略。
はかりごと。謀略。 「人の話を注意深く最後まで聞く力」
「人の話を注意深く最後まで聞く力」


