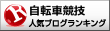(風張峠より)
先週、風張峠から武蔵五日市方面に下っていると、武蔵五日市から登ってくる人が多く楽しそうだったので、今日は武蔵五日市から風張峠まで登ってみた。
毎週、同じことをしているのだけど、サドルを少し高くして走り出してみた。すると、シッティングもダンシングに近い感覚で体重をかけられ、走り出しのトルクが出しやすいのであるが、ペダルが回しにくく、すぐ疲れてしまう。それに、つま先に体重がかかって痛くなってしまう。そんなわけで、結局もとの位置に。体の構造上、膝の曲がり角度が少ないサドルが高い方が力が入りやすいはずだが、ペダリングは複雑な運動なのである。
10時半頃、武蔵五日市から登りがはじまるが、最初の方は軽め。走っていると下ってくる人が多く、速い人はもっと早くきて帰り始めているようである。
武蔵五日市から都民の森に向かう道は、アップダウンが多く、うまく速く走るのは結構大変である。ちょっとした急坂がいくつもある。上野原に向かう道との三叉路を通り過ぎたあとはなおさらで、地味にきつい坂が多くなってくる。しかも、同じような道が延々と続く。あまり走り慣れていないような人も多く走っているが、よくぞ来たなという感じ。たまに自転車から降りて歩いている人もいる。走って走って、奥多摩周遊道路までくると、かえって一安心。ここも、9%の標識があるが、勾配が安定している分走りやすい。都民の森で一休みし、風張峠まで登り、Uターンして降りてくる。やはり、奥多摩周遊道路は奥多摩湖側から登る方が好きかな。
あとはひたすら下り。下ることの方が多い道なので慣れたものだが、バイクが多くちょっと怖い。カーブでも平気で抜いてくる。僕も大型二輪免許をもっているしバイクは好きだが、追い抜き上等みたいな乗り方をされるとさすがに怖いのである。まあ、バイクはトロトロ走っている方が疲れるものではあるけれど。
そんなこんなで、途中ハンガーノックになりながらも、とことこと走り帰宅。先週よりも走った距離も獲得高度も少ないが、それでも相当疲れた。武蔵五日市~都民の森ルートはしばしばプロ選手を見かけるだけあって良いトレーニング・ルートだが、覚悟して走らないと痛い目に合うのである。
走行距離:152.8km
獲得高度、4,052m
推定消費カロリー5,211kcal
平均速度26.2km/h