最後にこの寺の見どころもう一つが、
境内にある「もみじ観音」だ。
その姿がこれ。
でもねえ、あれおかしいですよ。
古い写真を見ると、
このもみじ観音はもみじの木の中の
空洞に立ってるはずなんですが、
ここではこの観音だけが立っていますねえ。
あの空洞のあったもみじは
枯れてしまったのかなあ。
過去の写真では不老の大木の中に
立つ観音といわれていたのですが、
今はそんなことはありません。
不老長寿といわれていた木の中に・・・
といういわれは変わっていくのですねえ。
さて、こうして西教寺の見どころは
全て押さえました。
また道を歩いていきましょう。
この辺りは里山の中腹を歩いていきます。
そういえばここから3キロほど
北の仰木地区には昆虫写真家の
今森光彦が住んでいますねえ。
滋賀県の里山のすばらしさを
よく言ってる写真家ですねえ。
まあ雰囲気が似ているんでしょう。
この辺りも人里としての歴史も古く、
一方で自然も意外に深く
いい感じで風が漂っているところです。
車が時々走って行く道を歩いていきますと、
あ、前方に千体地蔵尊の看板が
上がっている道がありますよ。
これを入っていく道を何というか。
実はこの道の名前は
「山の辺の道」
というのです。
あの奈良の天理や桜井を通る
有名な散歩道と同じ名前なんですねえ。
確かに道の自然環境からみて、
山の辺を歩く道という意味では
普通なんですけどね。
でもこういう道に出会って
散歩も急に楽しくなったりします。
こんな道が続きます。
山手からは小さな川が流れてきたりして、
自然も豊かな感じです。
ここが八講堂の千対地蔵尊です。
これは歩き始めの頃に見た
多くの地蔵尊と同じですね。
山から地元のお寺にかけて
無数の地蔵尊が散在しておりました。
比叡山が修行の山で
一般の人のお参りには
制限があったので、こうして
各地に地蔵を作ったのだそうです。
う~ン、やはり、酒飲みの足を
洗わせるための地蔵じゃなかったんですね。
この辺りも開発に伴って、
ひと鍬入れるごとに地蔵が出てきたので、
それを誰いうことなく
ここに集めたのが、
八講堂の千体物と
いわれているそうです。
ざっと数えてみますと
1000体はなさそうでしたがね(^^)。
田植えの始まった田んぼ、
散在するヘビイチゴ、
土手には夫婦像のような石像。
いいところですねえ。
草深い土手や竹林の中を通ったりします。
やがて石の階段を降り、
鉄橋のある所にさしかかったところで
ランニングをしている人が
抜かしていきました。
ああ、こんなところを
走ったりしてるんやなあ
と思いつつ見てたら、
そのランナーが鉄橋のところで
「ウヒャー」といって
立ち止まっています。
どうしたのかなと思って
見に行きますと、
鉄橋の上に大きな蛇がいてました。
ヤマカガシかなあ。
最近は毒のある蛇といわれています。
結局橋のすみっこから
逃げていきましたね。
その逃げる姿のしっぽの部分が
これでした。
この道、あちこちで
こんな蛇の死体も見つけました。
まあ、それだけ生き物も
多いということなんでしょうか。
よく探したらツチノコとか
見つかるかもねえ。
しかしそれにしても
この辺りの谷は深い。
こうして写真を撮ると、
まあなんて静かな自然の中に
doironは似合わん格好やねえ。
ここから先に行くと
道は結構な山の中に
入っていくなあと思ったら、
いつの間にか日吉大社の
中に入っていきます。
こんな道標が建っており、
そこに「逢のみち湖のみち山歩みち」
と書かれています。
山の辺の道とかいろんな
名前を付けていますねえ。
それにしても「山歩みち」
というのはいいですねえ。
軽い山をてくてく歩くコースを、
これからは山歩みちといいますかねえ。
続く
この阿波羅屋地蔵の周りには
小さな地蔵尊がいくつもあります。
昔はこの辺りが大きな寺だったようで、
その名残がここから
山の方に向かっていくと、
ほんとにいくつもの地蔵尊に出会います。



まあ、いわゆる地域の地蔵道ですねえ。
酔っぱらって帰ってきたら
たくさんの地蔵さんに
にらまれるかもしれませんねえ。
うう~そう考えたら
ちょっと怖いですねえ。
坂道をくねくね登っていくことも
しないといけないので、
なんか酔いもさめてしまいそうです。
こういう地蔵のいる道は
一本の川に接しており、
この川の名前を「足洗川」というのは、
ぼちぼちそんな酔っ払い人生とは
「足を洗いなさいよ」という意味で
つけられた名前なんだそうです。
え~それはうそですが。
本当はもっと怖い理由で、
昔は比叡山なんかで合戦があって、
戦いに勝った人間が足を洗って、
血でまっかな水が流れていた
という説があるそうです。
ヒャー、これの方がこわいですねえ。
川に沿った道を上がっていきます。
今日は比叡山麓あたりを
ウロウロするので
アップダウンは覚悟してきていますが、
この辺りはかなりの傾斜で登っていきます。
はあ、はあと登ってきたぞ
と思った頃に、古墳が現れます。
「袋古墳群」」です。
どうも出土したものから見ると、
当時渡来した人か
もしくはそれに近い人の墓か
といわれています。
それにしても古墳て本当に
どこにでもありますねえ。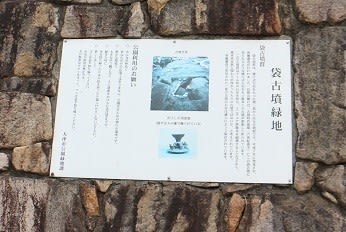
堺の百舌鳥古墳群だけでなく、
これまで豊中、五條などの
古墳も見て回りましたねえ。
最近は泉南の古墳の方も
見に行くつもりをしていますしね。
この辺の古墳は規模は
あまり大きくありませんが。
こんな形でていねいに
保存されているようです。
さあ、では次の目標地である
「西教寺」を目指しましょう。
ここは聖徳太子が創建したお寺で、
今は天台真盛宗の総本山であります。
住宅地を登っていきますと、
こんな石碑が立っています。
この先の日吉神宮から大榊が
大津の天孫神社に渡らされる神事があり、
この広道芝松というところに
榊が下ろされ神事を行った上で
移し返されたという神事があることを
説明しています。
よくわからない神事ですが、
まあいろんな神社がありますから
想像もできないような神事も
あったりするんでしょうねえ。
さあて、いよいよ前面に濃い緑が
見えてきましたよ。
緑に覆われたこんな道標を
見ながら進んでいきますと、
そこにあるのが「西教寺」です。
このお寺でチェックしておきたいことは
3つあります。
ひとつは護猿(まもりざる)です。
昔、このお寺の法難が押し寄せたときに、
手の白い猿が鐘をうち、
証人の代わりにお経をあげた
といういわれがあり、
お寺の建物に猿の瓦がのってる
というのでそれを見に行かねばなりません。
中に入って屋根を見上げてみると、
いました。
全部で何匹いるのかわかりませんが、
この寺ではこの猿を
お守り代わりにしています。
そしてこの寺のもう一つの見どころは、
明智光秀の墓です。
本殿の隅っこにそれはありました。
後ろは穴太衆の石段かな。
織田信長の比叡山焼き討ちのあと、
この寺はここに坂本城を築いた
明智光秀の菩提寺となっていたそうです。
ここに、光秀の辞世の句
といわれるものが掲示されています。
漢字ばかりでややこしいですねえ。
自刃の前に藩士に託した
といわれています。
大意は、修行の道には順縁と逆縁の
二つがあるといわれていますが、
実は二つとも同じもので、
人間の心の源に達するものだ。
自分の人生五十五年も夢が覚めれば
一つだったという意味だそうです。
いやあ、彼の人生そのものを
振り返って考えれば、
なかなか味のある言葉ですねえ。
彼の深い人生哲学がわかる言葉
といわれています。
続く
たまあにジダンと情報交換などで
松ノ浜周辺で飲んだりする。
まあ無理をしてこちらの体の
動きなんかを気にしながら、
それなりの遊びに誘って
くれたりするので
ありがたいものである。
また、それと同時に酒のみの
地元範囲が同じなので
ウヒウヒいいながら
飲んだりもしているのだ。
今月もエイに行ったんだよね。
歩いたり山の情報の話をしているときに、
doironが最近行きたいな
と思っているのは
比叡山当たりかなあと話をしたことがあった。
まあまだあまり近寄っていないエリアである。
で、そんな話をしたものだから、
こちらとしてもああやっぱり
あのあたりには是非行って
みなくてはという気持ちが強くなり、
飲み会の翌々日に滋賀県の坂本へと
一人でひょっこり出かけて
いくことにしたのでした。
場所的には遠いが、
高速道路の発展で大津までは
とても近くなったので、
そのあたりまで車で
行けるようになったのは便利やねえ。
大津の駅に車で到着し、
安いPに車を止めて
さあ坂本まで行く湖西線に乗るぞ~
と思ったら、もうその時点で
大きな勘違いをしていました。
湖西線に乗るには、山科まで
戻らなくてはならないのです。
ああ、大津で湖西線と東海道線に
分かれてるんやと思っていたのに、
手前の駅で分かれている
というそんな経路になっていたんですねえ。
で、慌てて山科まで行きました。
あとで気が付いたのですが、
ここからJRではなくて
京阪で向かっていけば
よかったのかもしれません。
いやいやそれよりも車で
坂本まで行くのが
一番正解だったかもねえ。
でもまあそんなんは
行ってみないとわかりませんから、
ここはまあ最初に決めた
JRでの移動を中心に
とにかく進んでいきました。
まずは山科です。
先日疏水巡りで降りた駅ですねえ。
駅舎は新しいようでしたが、
ホームのあたりは昔からの様子ですねえ。
ここから東海道線と湖西線に
乗り換えるのですが、
酔っぱらったり、気を抜いて
電車に飛び乗ってしまうと
経路を大きく間違えてしまいそうです。
doironもまた大津に
戻ってしまわないようにちゃんと
電車を待ち湖西線にのりこみましたよ。
で、そうして、結局目的の坂本に
ついたのは午前11時過ぎでした。
場所的に言いますと、
雄琴温泉の一つ手前という感じです。
そこでナビを入れ、
さあではここから山の方へと
向かって進んでいきましょう。
あ、駅前にこんな施設がありますよ。

ここは穴太衆の案内です。
この坂本あたりは野面積みの
石垣を作る集団の本拠です。
これらは穴太衆とよばれ、
安土城を手掛けたりしたあと、
各地の城づくりで活躍したそうです。
坂本を歩きながら、
これは穴太衆の石垣とかわかるのかな。
その辺も見ていくことにしましょう。
そしてここには坂本の概略が
書かれていました。
比叡山の延暦寺、西教寺、日吉大社などの
ある門前町だそうです。
最澄が中国から持ち帰った天台宗は、
空海の真言宗とともに
日本の仏教を作っていった宗派です。
その最澄が作った比叡山の
延暦寺の聖地の門前町ですから、
さぞやかつてはにぎやかだったんでしょうねえ。
ここからコースは、
多くの人が駅前の道を
まっすぐ上がっていくのが
よさそうですが、
doironは線路沿いに少し北上し、
大きなスーパーの方に向かって
行くことにします。
線路沿いに緑の整備された道を
進んでいきますと、

そこにこの地蔵尊があるからです。
伝教大使が刻まれた地蔵尊で、
山手の日吉大社にあったものが
ここに移され、悪行消滅、子孫繁栄、
家運隆昌、幼児のかんの虫にも
ご利益があるという阿波羅屋地蔵様です。
いやあ、7月に生まれる孫のために
お祈りしておきましょう。
続く
高野街道をまっすぐ行ったら
九度山橋に出るのですが、
途中で小田井用水上の道が
直角に交わっています。
ああ、これをたどっていけば
取水口に出るはずですね。
高野街道を離れて左折して
進んでいきましょう。
途中のマンふたを見ると、
おおやっぱりここは用水の上に
作られた道に間違いありません。
異様に広い道がまるで
川のようにくねくねと続いて行きます。
この日は天気も良くて、
気候もさわやかな日でしたねえ。
でも平日昼間のこんな田舎道って、
ほとんど人を見かけることは
少ないですねえ。
やがて道は公園のような
ところに突き当たります。
その向こうにもう川の施設が
見えかくれしていますよ。
あれが小田井用水の取水口のようですね。
おお~そのようです。
吉野川から取水した水が
ドド~っと流れています。
ああ、ここは怖いですねえ。
もし何かの事故等でここにながされたら、
一キロ以上高架下を
流されることになるんですねえ。
フェンスにも「あぶない」
と書かれていました。
ここに置かれてある案内板を読むと、
小田井用水のことがしっかりと
書かれていました。
この取水施設のことは正式名は
「頭首口」といわれているんですね。
ここから小田井用水は約30キロの
水路となって流れて行ってます。
河川の傾斜は、ゆるいところでは
なんと3000分の1から5000分の1
といわれるような精密さで作られています。
学文路の大畑才蔵氏が作った
精密な器具が役に立ったそうです。
そんな彼の「彰功之碑」が
粉河寺に立っており、
知らず知らずのうちに
その写真を以前とっていたのは
驚きでした。
これがそれです。
しかしまあ300年以上も前に
作られた水路が、
各地で改修を重ねられながらも
今まで続いているのは
本当にすごいことですねえ。
この小田井水路の他に
もっと古い藤崎井水路
というのも粉河から流れているそうで、
いかにこの地方の人たちが、
水を大切にしてきたかが
よくわかります。
この小田井水路は大和街道を
歩いているときも各地で見かけました。
そして最後は船戸の山手の方で
根来川にそそいでいるそうで、
いつかまたその地点も
見に行かなくてはと思っています。
さあ、これで今回の目的のひとつだった
小田井の取水口を見ました。
少し河川を下って
その河川上の姿を撮影しておきましょう。
それがこれ。
何度も大水で流されたりした
施設だからか、今はとっても
堅牢な姿をしていますねえ。
まあ、カヌーイストにとっては
悲しい姿かもしれませんがね。
さらに遠くから
はい、では九度山橋まで
河川敷を進んでいきましょう。
途中の河川敷のすぐ横には
こんな神子稲荷神社
なんてのもありましたね。
はえている木も立派な古木でしたねえ。
やがて前方に九度山橋が見えてきました。
大きな橋ですねえ。
これを右に回って高野口の
駅の方に向かいましょう。
途中の店々にはこんな

「真田幸村応援隊」の提灯が
ぶら下がってましたよ。
NHKの大河ドラマで
ブレイクしたようですねえ。
そんな田舎の商店街を抜け、
国道もわたり、高野道の交差点も
過ぎると駅の方に到着です。

今日はこんな感じで約7キロを歩きました。
中飯降の駐車場へと戻る電車も、
時間を見ると15分くらいで
来そうです。
駅前のチェックだけしておこうと、
無人駅を出ると駅前にこんな施設が。
「葛城館」という名前の宿泊施設で、
昔から高野山参りの人を
とめていたそうです。
風情のある建物ですねえ。
そして駅の中には昔の駅舎の
古い鉄骨柱のようなものも
残されていましたね。
ああ、これもまた歴史を感じさせますねえ。
さあ、これで高野口あたりの
大和街道は終了です。
次回はここから橋本の方に
向かって行くことになるでしょう。
高野口のあたりは駐車場が
見つからなかったので、
次回は橋本に車を止めて
歩くことになるかなあとおもいつつ、
おしまいです。
道の下にもぐった小田井用水なんです。
でもところどころは
この用水の上を広い道にしていますし、
歩いていて用水の上を
歩いているとよくわかります。
だってマンふたがこんな感じなんです。
さすがにきっちりこんな
マンふたも設けてやってるんやねえ。
この辺りはかつては
高野口町だったのですが、
2006年に合併して
橋本市になっています。
なので本来のマンふたも、
橋本市のこんなふたの他、
高野口町の名前の入った
これや
こういうのが散在しています。

道標も割と熱心に立てられていますねえ。
道は途中でこんな川を
こえますが、用水のあった
あたりを見ても渡井とか
配管とかは見つかりませんねえ。
ここでも川をくぐるように
水路がつけられているんですかねえ。
そういえばこの辺は道が
異常に広いですから、
今渡った橋の下に
配管とかが通っているのかも
しれませんね。
こんな道の下をコースが
くぐっていきます。
へ~植物と昆虫の絵が
割と上手に書かれていますねえ。
これは落書きではないですねえ。
自治体または道路管理者の方で
描かれているんでしょう。
カキや道標、
水準点なんかを
見ながらdoironおじさんは
進んでいきます。
用水が交わったりはなれたりしながら、
そのうち道は旧道となっていきます。
ああ、この辺ももうすぐ
高野口の駅に近いのかなあ。
ぼちぼち時間もお昼ですから、
コンビニか食堂を探していきますと、
おおこんな食堂がありましたので
入っていきましょう。
ちょっと健康そうなランチが
ありそうですよ。
それがこれ。
う~ん、ご飯も五穀米かなあ。
どうしようかなあとか思いましたが、
ここは優しく午後の静かなひと時ですので、
ビールは置いときましょう。
帰りは車やしなあ。
11時45分くらいに店に入ったのですが、
12時を過ぎたくらいから
客がどんどん入ってきます。
まあ地元じゃ結構人気店なんですかねえ。
さあ、おなかもふくれたので
また歩き始めましょう。
しばらく行くと、小さなお堂に出ます。
「名倉市場蛭子神社」で、
高野街道の交差点と書かれています。
どうやら大和街道を来た人にとって、
ここは高野山へ行く経路と
交わっているんですねえ。
大阪からの高野街道は
もう少し先のところで
吉野川を渡っているよなあ。
そういえば、以前堺市から
西高野街道を河内長野まで
昔の同僚と歩き、
さあ続きにまた行こうと
思っていたのだが、
これが止まったままである。
また懐かしい人たちと
歩きたいなあと
ずっと考えているのだが、
なかなか連絡等の踏ん切りが
つかないでいる。
ねえ、のんさんまた歩きませんかあ、
とまた声をかけてみようかな。
階段じゃないけど
足は大丈夫かなあ。
本来ここから大和街道は左折して
高野口の八幡神社を経て
紀伊山田の方に向かって行くのだが、
今回はぜひとも小田井用水が
吉野川から水を取り入れている
取水口を見たいので
右折してしばらく高野山の方を
向いて歩いていくことにした。
道はこのまま九度山橋を目指している。
昔のこんな古い道を歩いていく。
途中に垣花大使といわれる
大師堂がありましたよ。
この御廟に参拝して
高野山参りの人たちは
進んでいったそうです。
道のずっと向こうに川の堤防が
見えていそうですね。
でもねえ、小田井用水の取水口が
この橋の下流なのか上流なのか
どっちにあるのか知らないのです。
でもまあとりあえず川まで
出ればわかるだろうと思い
歩き続けました。
ここは昔からの街道ですから、
道標とかあるかなあ
と思いながらキョロキョロと
歩いていますと、
あここになんか石がありますよ。
まるで橋のように二本立っている石には
「小田井」と書かれてあるじゃないですか。
それを眺めるとこんな広い道が
高野街道を横切っています。
どうもこれが小田井用水の道です。
続く
さあて、また大和街道に行くかあ
と計画を立ててみた。
だいたい、この沿線辺りは
電車まで遠いところの人が多いので
駅に駐車場なんかあって
電車に乗る人が多いやろうから
と思って、車で行くと
これがなかなかないんだよねえ。
南海本線の樽井や箱作の方に行くと
いっぱいあるのになあ。
この辺の人はどんな移動手段を
使っているのだろう。
だいたいこの辺は土地も安いだろうから、
会社に駐車場とか整備されているのかなあ。
なので、こちらも車で遊びに行くと
コインパーキングがほとんどなく、
駐車にとても苦労するのだ。
今回の大和街道は中飯降の
駅からの歩きとなるのだが、
さあ果たしてあの駅周辺に
駐車場はあっただろうか。
とにかくはまあ電車で行くには
遠い距離だから車で行くに限るから、
なんとか駐車場を探すほかはないか
と決めて出発することにした。
まあ最悪は前に駐めた道の駅から
ちょっと歩いて、笠田から
電車を乗り継いで行くという方法はある。
何とかなるんちゃうかあ、
といういつものようなお気楽な感じで、
鍋谷トンネルをこえて
向かって行ったdoironなのでした。
とりあえずは道の駅をこえて
中飯降の方へと向かいましょう。
駅まで行くと横の広場で
朝市をやってましたな。
その横の方に入っていきますと、
おおっ、突き当りです。
うーん、あきませんなあ。
もう少しこの辺を走ってみましょうと思い
ぐるぐると移動しました。
車をとめれそうな空き地は
いっぱいあるんやけど、
パーキングという位置づけには
なっていません。
う~ん、しかたないか。
では道の駅に戻ってみようかと
国道へ戻っていき、少し走ったところで
小さなコインパーキングを発見。
やれやれです。
ここからだと駅まで歩いていくのも
かなり近いです。
よしよしと駐車し、
歩き始めたのでした。
ここからだと先日行った
小田井用水の水門に近い
ところなので立ち寄っていきましょう。
なにせこの日の予定では
歩きの後半に小田井用水の
水取り入れ口に向かうのですから、
ちょっと復習しときましょう。
道が川のそばに出た時に、
一字一石墳の石のある
地蔵さんに出ます。
そしてこれが一字一石塔。
もうこれらの塔のそばを流れる
近くの小田井用水はもう満水です。
あふれ出るんじゃないか
というくらい、満々と
水が流れています。
ああ、そうかあこの頃は
田植え等もあって
たくさんの水が必要なんですねえ。
天満宮の橋の下も、
以前はこんな感じだったのが
いまはこんな感じです。
小田井用水自慢の水路も、
以前はこんなのも
今はこんな感じで満タン状態。
ああ、これだと水路の入り口では
水の取水が大変でしょうねえ。
でも楽しみにそこへ向かって行きましょう。
こういう道標のところから、
道は山の方へと上がっていきます。
そしてこの道標に沿って右折し、
山と並行に歩いていきます。
この辺りは果樹園も盛んですねえ。
梅の実がいっぱいなっているよ。
ああ~春ももう真っ盛りですねえ、
ヘビイチゴも実っています。
そうして道が山近くの
JRのそばになっていくと、
ごご~と水の音が流れてきます。
おおこの辺も小田井用水が
水満タンで流れているではないですか。
百姓さんたちには
とても頼もしい水路なんでしょうねえ。
かなりの勢いで流れているから、
ごみなんかあったら大変ですねえ。
水路をふさいだらあふれるもんねえ。
周辺の人はほんとに流れを
大切にしているんでしょう。
この辺りは標高も高いです。
向こうのほうには町石道で
登っていく山方向も
よく見えています。
あの鉄塔のところは
本当にきれいな景色だったなあ。
また一度上りに行ってみようかなあ。
そんな景色も見ながら歩いていくと、
おお小田井用水が
ここから道の下にもぐっていきます。
続く
泉南市にある農業公園は
「花咲きファーム」
といいますね。
泉南の高速道路からおりてすぐの
山の中の高台がエリアです。
その花畑エリアが、
今はイングリッシュローズガーデン
としてリニューアルされ、
本格的な英国風のバラ園となっています。
ミセスが見たいというので行ってきました。
実は以前ミセスはナビを入れて
ここに向かったことが
あったのだそうですが、
気がついたら泉南市役所の前に
来たことがあるそうなんです。
電話番号か何かを入れて
間違ったんでしょうねえ。
到着しましたという合図が
「泉南市役所」のところに
出たそうなんです。
え~っと、バラ園はどこやろ
と車を止めて歩き回ったそうですが、
見つかるわけがありません。
すごすごと帰ってきたそうなんです。
まあ、全く何の知識もなく
来ているわけだから
仕方ないといえば
そうなのかもしれません。
今回doironの運転で現場に向かうと、
へ~こんな山の中やったんやあ
と驚いてはりましたね。
ここはイギリスのバラ園を
意識して作られています。
デビッド・オースチンイン
グリッシュローズガーデンと
名付けられています。
いやあ、格調高い名前ですなあ。
来ているこてこてのおっちゃんおばちゃん
にはちょっと似合わない名前です。
まあ、地元の泉南の言葉で言ったら
「バラバラ園」やなあっ
て感じでしょうか。
3000本以上のバラが
置かれているそうです。


doironはここに来るのは2回目です。
以前来たのは、退職した後
しばらく働いていた高齢者施設の
リクレーションで来たんでしたねえ。
車いすのおばちゃんを押したり、
無表情な高齢者を散歩させたりと
あの時は大変でしたねえ。
でもあの時は高齢者も一緒だったので、
公園の周りの近そうなところに
車を止めることができたので
よかったです。
今は、ローズガーデンから
ずーっと下の駐車場に止めて、
てくてく歩いて入って
いかなくてはなりません。
かつては高齢者の車いすを押しながら、
合間にうまくバラを写真に撮ったり
していたのですが、
ビックリしたのはそのときでした。
ファインダーの中に見慣れた顔が・・・
親父でした。6年前かなあ。
年の頃なら80歳代後半くらいでしたね。
年齢的には連れてきている人と
よく似たものだったのですが、
施設の利用者から見れば
一線を画すように
元気度が違ってましたねえ。
公園の中を友達と歩き回ってはりました。
まあ、以前はそんなバラ園だったんですが、
それでは少し今年のバラを
写真に撮っていくことにしましょう。
あ、ちなみにここは無料ですからね。
ピンク、赤、黄色、白のバラたちが
とてもきれいでした。







あずま屋に座って、
持参してきたホットコーヒーを
飲みつつじっくり眺めていると、
どうも高齢者初心者のような
夫婦がやってきて、
お弁当を広げて食べ始めはりました。
な、なんと男性はビールまで
持ってきているじゃあ~りませんか。
ああ、高齢者生活を
味わっているんでしょうねえ。
うらやまちかったです。
ゲートのところでこんな写真を
撮ったりしながら、
我々はぼちぼち退出です。
帰りは急ぎましょう。
この日は月曜日でしたので
ジムも休みですから、
お家に帰ったdoironは、
二階のベランダにこっそり腰かけて、
ビールを飲みながら
雑誌の読書なんかしながら
ゆったりとしました。
そんな高齢者にふさわしい
一日を何とかすごしたのでありました。
中央エリアに入って
すぐに東側へ行くと、
ネモフィラや白い紫蘭に包まれ、

やがて菖蒲園に出てきます。
ああ、この辺もつぼみを
いっぱいつけているから
咲いたらきれいなんでしょうねえ。
そして乙女山古墳の方への
道を進んでいきます。

名前が名前だけに惹かれる古墳ですねえ。
草の上に作られた木の道を進んでいくと、
ああ、ここが乙女山古墳です。
この古墳の特徴は「帆立貝式古墳」で、
古墳の南西部の造り出しから
円筒埴輪が出てきたそうです。
乙女山はこの地方の名前が
「乙女山」だからそんな名前の
古墳になりました。
乙女山とはきれいな名前ですが、
もともとは「御留」「御禁止」から
来ているという説もあるようです。
ここはよくわかりませんでしたけどね。
ここから池のふちを歩き、
公園のずっと東側の道を
ぐるっと回っていきましょう。
「ケンケーン」。
あ、雉が鳴いていますよ。
ここにいるようです。
え?雉ってどんな鶏?
ああちょっと前なら
「一万円札見てね」となるのですが、
もう今の紙幣は火の鳥で
デザインが違いますねえ。
でもねえ、大体雉ってわかりますよねえ。
ここでは写真にこんなに不鮮明にしか
写せていませんでした。
鳴き声から「けんもほろろ」という
言葉ができたんだと辞書に
書かれてありましたな。
あ、ここには「クロヤツシロラン」が
生えているそうです。
うわー見たいなあ。
でも立ち入り禁止なんですよねえ。
ネットで調べた写真がこれ。
葉緑素を持たず菌だけに生える
ランの一種です。
うん。
でも本当によく見つけたものです。
これは、ここにあった古墳の中身を
再現しているようです。
石棺がぽつんと置かれている
シンプルな展示ですねえ。
無理矢理こんなにシンプルな
古墳を作る人のことを
「古墳症」と呼びましょう。
向こうのほうの道の下にも
古墳があるみたいですが、
草深くて近寄りがたい感じでした。
古墳症のおじさん、ごめんなさい。
ああ、このあたりは
キツネアザミなんかがきれいに
咲いていますねえ。
きっと池の周りなんかだったら、
カワセミなんかも多いかもしれません。
さあてこうして公園を
ぐるりんと往復してきました。
最初ここに来ようと思った時よりは
歩く距離も長く、古墳や植物が多い
いい公園でしたね。
これからはこの公園の周りの歩きコースを、
以前の「もっともっと田原本」を
活用して作って足していけばいいかもね。
そしてこの後どこかで行く
予定の温泉の情報も加えて、
いいドジ旅ができそうなら
作っていくことにしましょう。
今日歩いたのは、こんな感じで、
距離は約9キロ。
奈良で二番目に大きい都市公園で、
気候のいい時に、のんびりしに行くには
ちょうど良いところかもしれません。
馬見丘陵は公園はうまい公園でしたとさ。
おしまい。
河合町の温泉が、
緑道エリアの横にあります。
これですねえ。
河合町の温泉で
「豆山の郷」という名前だそうです。
料金は500円で、中身はというと
これはまだチェックしていませんし
この時は遠目に見ただけでした。
でもねえ、この公園を歩いているときに
ふと思ったんです。
もし温泉がいいところで、
食事等も気軽に出来そうなら、
もう少し先の方のドジ旅で
使えるかもしれないからチェックしないとね。
なので、ここはまた雨降りの時にでも
温泉チェックにやってきましょう。
ここが緑道からの出入り口のようですねえ。
覚えておきましょう。
さらに歩いていきますと、
展望台と書かれたところに出てきますが、
登ってみてもこの通り。
ちょっと展望には遠いですねえ。
そしてついに緑道は終わり、
こういう交差点に出ました。
馬見丘陵公園は終わりですが、
せっかくここまで来たので、
駅をチェックしに行きましょう。
近鉄田原本線池部駅です。
こんな役場の前を通り、
しばらく行くと「駅」にやってきます。
うんうん、田舎の静かな駅です。
で、ふと駅の横にある
古い建屋を見てみますと、
こんなところにお寺でもあるのかあ
と思ったら、
な、な、なんと
この門屋は「河合町役場」の
入り口じゃないですか。
調べてみると、この土地はもとは
「近鉄田原本線」を建設した
森本千吉という人の家でしたが、
そのうちに河合町に売られ
ここに役場が経ったという経緯があります。
入り口のこの重層な門屋は
その時の名残です。
いやあ、doironも歩きだけでなく
仕事をやってた時もあちこち回りましたが、
こんな入り口を持つ役場は初めてですなあ。
駅前で目立つイベントとかも
できるかもねえ。
ではここで今日の歩きは片道終わりです。
さっそく公園の方へと向かって行き、
緑道を逆に歩いていきましょう。
このとき時刻は12時20分くらいです。
散歩に歩きに出ている人も
役場の人のような気がします。
あ、走っている人もいるぞ。
あれはどうも保険年金担当者のようやなあ。
ストレス発散!みたいな顔をして
走っていますよ。
ああ、これは子育て担当者のようです。
「そ、そんなスピードで走ってたら
帰ってこれませんよ~」なんて
勝手に職務まで想像しながら眺めています。
そういえばdoironも若い頃は
昼休みに近所の公園で
3kmのスピード走をしましたねえ。
調子のいい時で10分30秒。
午後からの仕事がハードな時は
12分と仕事を頭に置いて、
はあはあと練習してましたねえ。
実業団駅伝の3.4キロを、
大会では一度も12分を
切ったことがなかったのに、
ここでは練習で11分55秒で
走ったのが最高でした。
練習で自己ベストだなんて、
ぜんぜんバカみたいな兄ちゃんでした。
でも若い時はそんなん平気で
真夏も仕事してたもんねえ。
走って職場に戻って着替えたら、
クーラーで汗が一気に引いたもんなあ。
そんな時代もあったんですねえ。
今は、ここの公園の走る人も
そんな想像で眺めてしまいました。
猫だって、うるさいおっさんやなあ
ときっと眺めていたに違いありません。
「昔はネズミを捕まえるときは、
あれくらい走ったのになあ」
なんて考えていたかもね。
行きは西側の道路を中心に
歩いて行ったので、
帰りは東側の道路の方へ回って帰りましょう。
相変わらず道はきれいに整備され、
お、こんなところには
「スイカズラ」なんかも咲いているようです。
また公園内にはちょうど
ラベンダーも咲いていますねえ。
この写真の背後の方に移っている山は、
地図によると池上古墳かもしれません。
さあ、ではまたトンネルをくぐって
中央エリアのほう入っていきましょう。
ここも東側を歩いていきます。
続く
公園館を出たら、北エリアの方へと
向かって行きましょう。
途中で菖蒲園の横を通っていきますねえ。
ここで高齢女性5人組が
前を歩いています。
「え~っと、菖蒲園やけど
全然花が咲いていないねえ」
「何を言うてんのあんた、
菖蒲の花は今終わったところやで」
と偉そうにしゃべる人がいます。
「ああ、そうかあ」
で終わったんですが、
よく花園を見てくださいよ。
あんなに大きなつぼみが
いっぱいついているじゃないですか。
偉そうに僕もあんな風に
人に偉そうに話すのはやめましょう、
と再認識してしまいましたな。
「菖蒲はこれからですからねえ。」
と心の中でつぶやいて歩きます。
しばらく歩くと大きな花壇の中に
ベンチがいっぱい
置かれているところがあります。
パッと見てみると、
座ってるよ、たくさんの高齢者。
中にはビールを飲んでるおっさんも。
これはもうdoironも
ここで昼食ですねえ。
今日の昼食はこれ。
焼き明太にシラスだって。
う~んなんでこんなに
痛風に悪そうなんが
好きなんかなあ。
あかんよなあ、
なんて反省をしながらも
買ってきてしまいます。
本能的に人間てこんなんが
好きなんでしょう。
尿酸値さん、あんまり
頑張らないでねえ。
それにしてもここは
ネモフィラが多いですねえ。
中に埋もれてしまいそうですわあ。
あ、道で絵を描いている人たちが
おおぜいいますねえ。
どこかのお絵かきクラブの
遠足ですかねえ。
多くが水彩画で、
ちょっと絞れば水が出てくる
という便利な筆で描いてはりましたなあ。
doironもその筆を持っているので、
頑張って練習しなきゃなあ。
でもこんなにぎやかな花壇とかを
描いていると、色がたくさんいるよなあ。
どんな感じやろね。
僕はまだこんな感じで
人前で絵を描いたりしたことはありません。
いつかそんなことも
するようになるのかなあ
なんて考えつつ歩いていきます。
まもなく前方のトンネルを
こえていきますと
北エリアに入っていきます。
一般道とクロスしているような公園ですから、
こんなトンネルや高架道路の
多いところですねえ。
公園の地図の下には、
公園内でしてはいけないこととか
書かれています。
器物を損壊すること、
立ち入り禁止に入ること、
ボールを投げた後のQBに
不意にタックルをかますこと
なんかが書かれてあります。
まあ、どれも普通にしては
いけないことが
書かれてあるのが多いのですが、
一つだけ、ん?と思うことがあります。
それは
「犬を連れて公園内に入らないこと
(盲導犬のぞく)」と書かれてあります。
う~ん、今の年寄りなんかは
犬を我が子のようにかわいがって、
散歩させたりしている人も多いよ。
ちょっとご近所の
犬スキの人にはかわいそうですねえ。
でもまあ何か理由があるのでしょうねえ。
企画者がかんがえたのかなあ。
ここは大きな芝生広場の周りに、
花々が植えられている
ようなところですねえ。

こういった団体が作っているような
花壇も並んでいました。
この模型電車の後ろに
並んでいるでっかい
ノビルのような植物が面白かったですねえ。
今のコースは帰りもまた
別のルートで通りますので、
サラーっと過ぎていきましょう。
そして花見橋を渡って、
ここから近鉄の駅まで続く
細長い緑道エリアに入っていきます。
緑が多く、ごみも落ちていない
こんな気持ちのいい道を

通勤とかで歩いて行けたらいいよなあ。
地面にはこんな歴史的事項の
書かれたタイルなんかも
埋め込まれていますよ。
でもねえ、地図を見てて
気になることが一つあります。
それは、この緑道を歩いていくと
途中にでかい風呂屋さんがあることです。
そこはどんな風呂なんでしょうか。
続く









