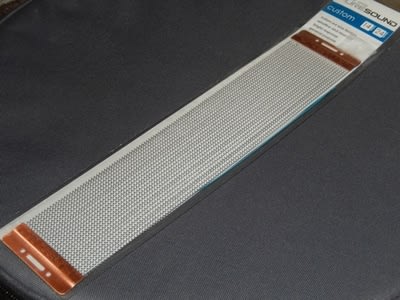昨日はスタジオに個人練習で入ってきたが、その時顔を合わせた知り合いはこっちの変化に気付いた。
髪を切ったからな。
言ってもこの6年間ほぼ長いままで、そこからうなじが見えるほどまで短くした。
現状、未だ希望の働き口への再就職の見込みはなく、時季的にどうしても鬱蒼となりがちなのは否めない。
で、髪が長いってのが今はどうしても妨げになっていると感じたので、思い切ってバッサリ行った。
こんな気分である時にしか出来なかったのも皮肉ではあったが、実際に短くはせずとも、色の着いた箇所を切り落としたいという気はあった。
去年に、LUNA SEAのカヴァーバンドをやった際に髪の色を変えたのだが、そのライヴ以降なるべく早く地毛の色に戻したかった。
ぶっちゃけ、もう髪の色に対して執着がなくなっているし、元の黒髪の方が今は寧ろ良いと感じている。
昔は色々とやっていたモンだケドね。
ホント、若い時期のノリってやつだったんだろうな、と今は思うよ(笑)。
髪の色変えるってのに対して、だからといって今非難をするつもりはないし、若気の至りなどという一時的な行為に当て嵌めるつもりもない。
オレはもうやるつもりは無い、ってだけ。
長かった頃は、黒髪の方が手入れは楽だったし。
色があった時は、何とも負のエネルギーがつきまとっていた感覚だったし、そしてこの状況である。
いっそ短くしてしまった方が開き直れる。
今後の事を考えれば、外観としては受け入れやすい雰囲気になる。伸ばして良いのであれば、また伸ばせば良いだけの事。
正直、短くなければいけないのであれば、それなりの髪型にしていこうかとも思っている。
実のところ今でもおかしな髪型には変わりない(笑)。
今後会う人間は驚くだろうね。
今居る場所でオレの事を知っている人の中で、オレが短い髪の頃を知っているやつが寧ろ少ないと思う。
ま、しかしその所為で家の床に髪がかなり散らばっちまったがな(笑)。
もう他人に髪切ってもらわんよ。
自分でどうすりゃいいのかは、自分である程度出来るから。
短くやり過ぎたとしても、伸びてきた時にまた調整かければ良いだけ。
もう余程でなければ、外観なんて問題にならん。
ここもまた、齢を経たって事なんろうね。
ま、そんなこんなで昨日のスタジオでは、今後のライヴに向けても含めて、以下のメニューに取り組んでみた。
「BLACKMAIL THE UNIVERSE」(MEGADETH)
「99 WAYS TO DIE」(MEGADETH)
「TORNADO OF SOULS」(MEGADETH)
「RECKONING DAY」(MEGADETH)
「MADNESS」(OUTRAGE)
「FANGS」(OUTRAGE)
「LOST」(OUTRAGE)
「RISE」(OUTRAGE)
「MEGALOMANIA」(OUTRAGE)
「REIGN FOREVER WORLD」(VADER)
「PIECE BY PIECE」(SLAYER)
「SELF BIAS RESISTOR」(FEAR FACTORY)
「REPLICA」(FEAR FACTORY)
やっぱりやってる曲/やりたい曲ってのが、スラッシュ/デスメタルばかりだね(笑)。
ま、今後もやれる範囲で曲のレパートリー増やせるようにしていきたいが、肝心なのはオリジナルバンドのWRECKONで、曲構成力をどれだけ反映させられるか、だ。
既に長尺の曲として考えている一曲に関しては、もう少し中盤部分を練る必要性がある。
あとは持久力を保たせる為の展開も置いておく必要がまだある。
個人的に、ツーバスプレイに於ける長時間持続を落としたくはない。
音量、左右のバランスと共に、スピードという三点を基本に、どれだけキックプレイの基準値を上げていけるか。
先達は未だに現役で怪物プレイをしているし、少なくとも今よりも落とさない様にはしていきたい。
髪を切ったからな。
言ってもこの6年間ほぼ長いままで、そこからうなじが見えるほどまで短くした。
現状、未だ希望の働き口への再就職の見込みはなく、時季的にどうしても鬱蒼となりがちなのは否めない。
で、髪が長いってのが今はどうしても妨げになっていると感じたので、思い切ってバッサリ行った。
こんな気分である時にしか出来なかったのも皮肉ではあったが、実際に短くはせずとも、色の着いた箇所を切り落としたいという気はあった。
去年に、LUNA SEAのカヴァーバンドをやった際に髪の色を変えたのだが、そのライヴ以降なるべく早く地毛の色に戻したかった。
ぶっちゃけ、もう髪の色に対して執着がなくなっているし、元の黒髪の方が今は寧ろ良いと感じている。
昔は色々とやっていたモンだケドね。
ホント、若い時期のノリってやつだったんだろうな、と今は思うよ(笑)。
髪の色変えるってのに対して、だからといって今非難をするつもりはないし、若気の至りなどという一時的な行為に当て嵌めるつもりもない。
オレはもうやるつもりは無い、ってだけ。
長かった頃は、黒髪の方が手入れは楽だったし。
色があった時は、何とも負のエネルギーがつきまとっていた感覚だったし、そしてこの状況である。
いっそ短くしてしまった方が開き直れる。
今後の事を考えれば、外観としては受け入れやすい雰囲気になる。伸ばして良いのであれば、また伸ばせば良いだけの事。
正直、短くなければいけないのであれば、それなりの髪型にしていこうかとも思っている。
実のところ今でもおかしな髪型には変わりない(笑)。
今後会う人間は驚くだろうね。
今居る場所でオレの事を知っている人の中で、オレが短い髪の頃を知っているやつが寧ろ少ないと思う。
ま、しかしその所為で家の床に髪がかなり散らばっちまったがな(笑)。
もう他人に髪切ってもらわんよ。
自分でどうすりゃいいのかは、自分である程度出来るから。
短くやり過ぎたとしても、伸びてきた時にまた調整かければ良いだけ。
もう余程でなければ、外観なんて問題にならん。
ここもまた、齢を経たって事なんろうね。
ま、そんなこんなで昨日のスタジオでは、今後のライヴに向けても含めて、以下のメニューに取り組んでみた。
「BLACKMAIL THE UNIVERSE」(MEGADETH)
「99 WAYS TO DIE」(MEGADETH)
「TORNADO OF SOULS」(MEGADETH)
「RECKONING DAY」(MEGADETH)
「MADNESS」(OUTRAGE)
「FANGS」(OUTRAGE)
「LOST」(OUTRAGE)
「RISE」(OUTRAGE)
「MEGALOMANIA」(OUTRAGE)
「REIGN FOREVER WORLD」(VADER)
「PIECE BY PIECE」(SLAYER)
「SELF BIAS RESISTOR」(FEAR FACTORY)
「REPLICA」(FEAR FACTORY)
やっぱりやってる曲/やりたい曲ってのが、スラッシュ/デスメタルばかりだね(笑)。
ま、今後もやれる範囲で曲のレパートリー増やせるようにしていきたいが、肝心なのはオリジナルバンドのWRECKONで、曲構成力をどれだけ反映させられるか、だ。
既に長尺の曲として考えている一曲に関しては、もう少し中盤部分を練る必要性がある。
あとは持久力を保たせる為の展開も置いておく必要がまだある。
個人的に、ツーバスプレイに於ける長時間持続を落としたくはない。
音量、左右のバランスと共に、スピードという三点を基本に、どれだけキックプレイの基準値を上げていけるか。
先達は未だに現役で怪物プレイをしているし、少なくとも今よりも落とさない様にはしていきたい。