へうげものがコミックス25巻(第25服)で完結した。
いやぁ、面白かった。いいエンディングだ。思わず一巻から一気読みしてしまった。
へうげものは、2005年からモーニング誌で連載されてた、戦国武将であり茶人の古田織部を山田芳裕さんが独自の解釈で描いた漫画。
この漫画のおかげで(せいで)俺は、それまで興味のなかった日本建築や数寄に興味が出て、和食器に凝りだして骨董市とか陶器市とかに出かけるようになってしまい、お茶とかにもこだわり始めてしまった。ちょうど寺とか仏像に凝り始めた時だったから、シンクロしてやたら和の美と歴史が好きになってしまった。

古田織部は、織田信長、秀吉、家康と仕えた武将でありながら茶や陶器に凝り、千利休に師事して利休亡き後は筆頭茶頭として大名クラスまで出世している。戦国武将は出世するたびに名前変わるから古田重然なんだけど、黒田官兵衛(黒田孝高/如水)とか竹中半兵衛(竹中重治)と同じく、重然より織部の方が一般的だからこのブログでもそう書く。
この漫画は戦国時代ファンが読んでも面白いと思う。
織田信長、明智光秀、羽柴秀吉、徳川家康、細川幽斎・忠興、高山右近、伊達政宗、蒲生氏郷、佐竹義宣、中川清秀、加藤清正、福島政則、石田三成、大谷吉継、柳生宗矩、真田幸村など誰もが知ってる戦国武将がガンガン出てくる。
しかし戦国時代といえばドラマ・小説・漫画でも戦国武将の武の方が重視して描かれるが、このへうげものは茶道・茶器・建築などの美や数奇からこの時代を描く。
土蜘蛛とともに自爆した松永久秀、地下道逃亡の際に茶器を大事に抱えてた荒木村重を始め、上田宗箇、小堀遠州、金森宗和、大久保長安・・・、武家でありながら数寄や茶の世界に入り込んでしまった奴らも描かれてる。
もちろん武将だけでなく、千利休、今井宗久、山上宗二、織田有楽斎、加藤景延、長谷川等伯、岩佐又兵衛、俵屋宗達・・・。のちに日本の美を語る際に出てくる先駆者たちも描かれてる。
大筋は歴史に忠実でありながら、時にフィクションを交え、大胆なレイアウトと大袈裟な描写が真骨頂の山田芳裕さんによって描かれるこの作品は、名作だ。
南蛮の粋と華やかさを武家の世界に取り入れ、茶器や茶会を報酬・恩賞に取り入れた織田信長。奇天烈な鎧兜や服装もこの漫画では、なるほど!って頷いてしまう。
この漫画では本能寺で殺されたのは秀吉の陰謀と描かれ、秀吉に切られた信長は胴体が真っ二つになりながら、そのまま秀吉に茶を振舞ったりする描写があったりする。
その秀吉を動かしたのは独自が極めた侘びの世界を否定し、華美なものを好む信長に反発した千利休。秀吉にはめられ謀反人になってしまった明智光秀もまた独自の美を持った人であったと描かれる。
秀吉の下で侘びの世界を広めた千利休だが、秀吉が豊臣になり箔を欲するようになると対立、切腹させられる。
弟子でもあった古田織部は利休切腹の介錯をし、その後秀吉の筆頭茶頭となる。そして侘びとか寂ではなく、乙かそうでないか、そして独自のへうげ(ひょうげ)を作り上げる。このへうげの世界を、ミギャァとかぐにゃぁとか言葉で言い表せない世界を山田芳裕さんは描く。織部の大胆な図柄やへうげたような形の世界が、あぁこういうことねと納得してしまう説得力がこの漫画にはある。
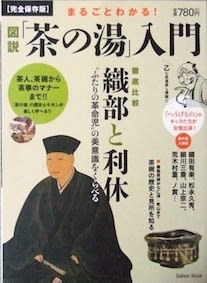
茶や陶器の世界はこだわり始めたらえらいことになるし、すぐ先人達は侘びだの寂だの言葉で説明しにくいことを言い出す。ビートたけしが海外のインタビューで「日本人で侘びとか寂とかいうやつがいたら信用するな」と言ってたが、俺もそう思う。
それは心で感じるもので、表現できるものではないからね。
今、京都や奈良に行っても日本のいにしえの美には出会えない。出会えるけど感じられないと言った方が正しいか。
年間5000万人も観光客が訪れる、どこの名刹に行こうが押し合いへし合い状態。インスタ栄えとかSNSのせいか知らないがカメラやスマホ片手の奴らばっかり。
枯山水の庭園も借景も、数寄屋造の建物も部屋も、落ち着いて見れないし何も感じない。
ちょうど俺が数寄や神社仏閣にハマりだした頃は、ゆっくり見れたし何時間でもそこにぼーっとしてられたんだけどなぁ。
2017年は2800万の人が日本を訪れたらしい。大阪だけでも 1000万人突破した。
まだまだ海外から観光客を呼ぶぞ〜!目標は4000万人だ〜!インバウンド効果だ、クールジャパンを海外になんて言ってるけど、本当にいいのかこれで。
フランスやスペインは観光客だけで8000万人来てるらしい。そのおかげ観光産業は成り立ってるが地元産業が全く伸びなく、そして肝心の歴史建造物がどんどん傷んで言ってるらしい。石畳はボロボロになり、のどかであったはずの景観の良い場所に人があふれ、どこにでも同じようなカフェや土産物屋ができていく。
日本でも神社仏閣に落書きされ、蔵王の雪景色や電車まで落書きされ始めてる。民泊と言いつつ違法で宿泊させて近隣に迷惑をかけ、友人を迎えに来ただけだと言って白タクがはびこる。そして街に英語、中国語、ハングル語が溢れていく。
よく勘違いされるのだが、日本で神社仏閣が一番多い県は京都や奈良ではない。一位は新潟、2位が兵庫、そして福岡、愛知、岐阜だ。
和食がどうたらっていうけど、どこの観光地でもマグロとか海鮮丼ばかりで、訪日客どこにでもあるラーメン屋に列をなしてる。地元に根付いてる食堂とか老舗の料亭など無縁。
もちろん日本人も、ファストフード、インスタント食品、コンビニ弁当やスーパーの惣菜、電子レンジでチンしたら食べれるようなもの食ってたりする。
以前も書いたことがあるが、それでも、お気に入りの使いこんだ茶碗とか、気に入って衝動買いした皿とかに移して食えばいいのに、それさえしない。
別に備前だの有田だの美濃だのって陶器や漆塗りのお椀とか箸とかを使えってのじゃないのよ。ロイヤルコペンハーゲンとかマイセンみたいな磁器じゃなくていいのよ。もっと普段使いで気楽に使えるのでいいのよ。IKEAとかニトリ、100均一で買ったものだっていいのよ。あぁこれに●●乗せたら美味しそうだなって思って買ったお気に入りの食器で食べればさ。

お茶だってペットボトルのお茶でもいいけど、急須でお気に入りの湯呑みで飲むとほっこりさが違うよ。嬉野、八女、掛川って産地にこだわったりしなくていいのよ。すぐ物の本によるとやれお湯の温度は何度がいいとか、時間はこんだけ置けとかグダグダ書いてるけど、そんなの適当でいいのよ。もっと美味しく飲むためにはどうすりゃいいんだ?って思ったら凝ればいいのよ。コーヒーでも紅茶でも「これが美味しい入れ方だ」って雑誌とかにやたら描かれてるけど、そういうのは店やプロがこだわるところで
一般人はもっと気楽に楽しむべきだと思うのよ。料理の世界もやれ出汁の取り方はこうしろとか、下ごしらえはこうしろ調味料のml、対比はこうだってのは無視してね。
そうなのよ、日本人の悪い癖で元々は庶民のものだったものがどんどん「道」の世界に行ってしまって、権威とか流儀とかこれが正しいってのがはびこるのよね。
お茶の世界も茶道、生け花も華道って道になって権威や免状の世界になってしまったし、着付けも何々流、踊りも何々流、三味線や琴も尺八も猫も杓子も。能や狂言なんて無縁。歌舞伎でさえ気楽には観に行けない。最近では相撲までも「品格が」などと言っている。バカじゃないかしら?
所詮は大衆から生まれたもの。権威にしたがるのはわからなくはないけど、それって今後衰退していってしまう前兆だよ。
和食器を見にいって、気に入ったのがあっても「高!」って思ってしまうような値段が平気でついてる。食器として使わずに床の間やサイドボードの上に飾れってか?って思ってしまう。バカラのグラスと伊賀焼きの湯呑みが同じ値段。
海辺の町でご飯を食べようとしたら「地元でとれた魚の海鮮丼」ってやつが1500円。アジフライ定食が1200円、ウニやイクラをのっけたのは2000円くらいする。おいおい、地元の人は毎日これ食べれるのか?どこでもかしこでも同じようなメニューになっていく。
和牛だってA5がどうたらってどんどん高くなる。焼肉なんて2000円くらいで腹一杯食えてたんだけどなぁ。
天然のフグや鰻、ズワイガニなんてもう庶民には手が出ない。
そう考えると寿司はすごいな。
回転ずしと老舗の寿司屋では違いはあるけど、回転ずしのおかげで未だに気楽に寿司がつまめるものね。ちなみに回転ずしが最初に登場したのは大阪万博で元禄ずし初案だ。
そばとかうどんもそうだな。老舗はあるし結構なお値段とるけどそれなりのお味で、かたや相変わらずお安い立ち食いそばとかセルフうどんとかも流行ってる。そう考えるとパスタ屋はどこもかしこもべらぼうに高い値段だな。麺にオリーブオイルと唐辛子絡めたペペロンチーノで1000円って高いよな。うどんにごま油と唐辛子かけただけで1000円って言ったら「誰がそんな値段で食べるねん」って言うだろう。カルボナーラ1500円?うどんに生卵からめて醤油かけて、ちくわ天のっけて500円。どっちが値段相応だ?
話がだいぶそれてしまったが、和を楽しむのは値段や権威ではない。
誰かが決めた価値観や、世間で言われるランキングも関係ない。
自分の気に入ったものをどう見つけて自分がどう楽しむのかだ。
「粋だねぇ」と呼ばれるか「野暮だねぇ」といわれるか。「オッシャレー」と言われるか「ダサい」と言われるか。もっと今風に言えば「インスタ栄えする」と「アップする価値なし」=インスタ萎えか。親指立てた「いいね」とか、リプライとか、言葉とかどうでもいいのよ。
自分が「これが乙だねぇ」「これがいいのよ」「これ気に入ってるのよ」って思えたら、誰が何と言おうとそれがへうげものの世界。
へうげもの最終巻25巻を読んで、俺はこれからもひょうげたものに感動できる人生を送りたいなぁってつくづく思う。

いやぁ、面白かった。いいエンディングだ。思わず一巻から一気読みしてしまった。
へうげものは、2005年からモーニング誌で連載されてた、戦国武将であり茶人の古田織部を山田芳裕さんが独自の解釈で描いた漫画。
この漫画のおかげで(せいで)俺は、それまで興味のなかった日本建築や数寄に興味が出て、和食器に凝りだして骨董市とか陶器市とかに出かけるようになってしまい、お茶とかにもこだわり始めてしまった。ちょうど寺とか仏像に凝り始めた時だったから、シンクロしてやたら和の美と歴史が好きになってしまった。

古田織部は、織田信長、秀吉、家康と仕えた武将でありながら茶や陶器に凝り、千利休に師事して利休亡き後は筆頭茶頭として大名クラスまで出世している。戦国武将は出世するたびに名前変わるから古田重然なんだけど、黒田官兵衛(黒田孝高/如水)とか竹中半兵衛(竹中重治)と同じく、重然より織部の方が一般的だからこのブログでもそう書く。
この漫画は戦国時代ファンが読んでも面白いと思う。
織田信長、明智光秀、羽柴秀吉、徳川家康、細川幽斎・忠興、高山右近、伊達政宗、蒲生氏郷、佐竹義宣、中川清秀、加藤清正、福島政則、石田三成、大谷吉継、柳生宗矩、真田幸村など誰もが知ってる戦国武将がガンガン出てくる。
しかし戦国時代といえばドラマ・小説・漫画でも戦国武将の武の方が重視して描かれるが、このへうげものは茶道・茶器・建築などの美や数奇からこの時代を描く。
土蜘蛛とともに自爆した松永久秀、地下道逃亡の際に茶器を大事に抱えてた荒木村重を始め、上田宗箇、小堀遠州、金森宗和、大久保長安・・・、武家でありながら数寄や茶の世界に入り込んでしまった奴らも描かれてる。
もちろん武将だけでなく、千利休、今井宗久、山上宗二、織田有楽斎、加藤景延、長谷川等伯、岩佐又兵衛、俵屋宗達・・・。のちに日本の美を語る際に出てくる先駆者たちも描かれてる。
大筋は歴史に忠実でありながら、時にフィクションを交え、大胆なレイアウトと大袈裟な描写が真骨頂の山田芳裕さんによって描かれるこの作品は、名作だ。
南蛮の粋と華やかさを武家の世界に取り入れ、茶器や茶会を報酬・恩賞に取り入れた織田信長。奇天烈な鎧兜や服装もこの漫画では、なるほど!って頷いてしまう。
この漫画では本能寺で殺されたのは秀吉の陰謀と描かれ、秀吉に切られた信長は胴体が真っ二つになりながら、そのまま秀吉に茶を振舞ったりする描写があったりする。
その秀吉を動かしたのは独自が極めた侘びの世界を否定し、華美なものを好む信長に反発した千利休。秀吉にはめられ謀反人になってしまった明智光秀もまた独自の美を持った人であったと描かれる。
秀吉の下で侘びの世界を広めた千利休だが、秀吉が豊臣になり箔を欲するようになると対立、切腹させられる。
弟子でもあった古田織部は利休切腹の介錯をし、その後秀吉の筆頭茶頭となる。そして侘びとか寂ではなく、乙かそうでないか、そして独自のへうげ(ひょうげ)を作り上げる。このへうげの世界を、ミギャァとかぐにゃぁとか言葉で言い表せない世界を山田芳裕さんは描く。織部の大胆な図柄やへうげたような形の世界が、あぁこういうことねと納得してしまう説得力がこの漫画にはある。
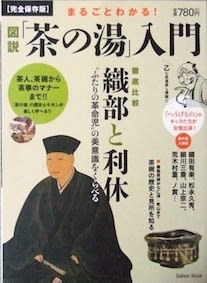
茶や陶器の世界はこだわり始めたらえらいことになるし、すぐ先人達は侘びだの寂だの言葉で説明しにくいことを言い出す。ビートたけしが海外のインタビューで「日本人で侘びとか寂とかいうやつがいたら信用するな」と言ってたが、俺もそう思う。
それは心で感じるもので、表現できるものではないからね。
今、京都や奈良に行っても日本のいにしえの美には出会えない。出会えるけど感じられないと言った方が正しいか。
年間5000万人も観光客が訪れる、どこの名刹に行こうが押し合いへし合い状態。インスタ栄えとかSNSのせいか知らないがカメラやスマホ片手の奴らばっかり。
枯山水の庭園も借景も、数寄屋造の建物も部屋も、落ち着いて見れないし何も感じない。
ちょうど俺が数寄や神社仏閣にハマりだした頃は、ゆっくり見れたし何時間でもそこにぼーっとしてられたんだけどなぁ。
2017年は2800万の人が日本を訪れたらしい。大阪だけでも 1000万人突破した。
まだまだ海外から観光客を呼ぶぞ〜!目標は4000万人だ〜!インバウンド効果だ、クールジャパンを海外になんて言ってるけど、本当にいいのかこれで。
フランスやスペインは観光客だけで8000万人来てるらしい。そのおかげ観光産業は成り立ってるが地元産業が全く伸びなく、そして肝心の歴史建造物がどんどん傷んで言ってるらしい。石畳はボロボロになり、のどかであったはずの景観の良い場所に人があふれ、どこにでも同じようなカフェや土産物屋ができていく。
日本でも神社仏閣に落書きされ、蔵王の雪景色や電車まで落書きされ始めてる。民泊と言いつつ違法で宿泊させて近隣に迷惑をかけ、友人を迎えに来ただけだと言って白タクがはびこる。そして街に英語、中国語、ハングル語が溢れていく。
よく勘違いされるのだが、日本で神社仏閣が一番多い県は京都や奈良ではない。一位は新潟、2位が兵庫、そして福岡、愛知、岐阜だ。
和食がどうたらっていうけど、どこの観光地でもマグロとか海鮮丼ばかりで、訪日客どこにでもあるラーメン屋に列をなしてる。地元に根付いてる食堂とか老舗の料亭など無縁。
もちろん日本人も、ファストフード、インスタント食品、コンビニ弁当やスーパーの惣菜、電子レンジでチンしたら食べれるようなもの食ってたりする。
以前も書いたことがあるが、それでも、お気に入りの使いこんだ茶碗とか、気に入って衝動買いした皿とかに移して食えばいいのに、それさえしない。
別に備前だの有田だの美濃だのって陶器や漆塗りのお椀とか箸とかを使えってのじゃないのよ。ロイヤルコペンハーゲンとかマイセンみたいな磁器じゃなくていいのよ。もっと普段使いで気楽に使えるのでいいのよ。IKEAとかニトリ、100均一で買ったものだっていいのよ。あぁこれに●●乗せたら美味しそうだなって思って買ったお気に入りの食器で食べればさ。

お茶だってペットボトルのお茶でもいいけど、急須でお気に入りの湯呑みで飲むとほっこりさが違うよ。嬉野、八女、掛川って産地にこだわったりしなくていいのよ。すぐ物の本によるとやれお湯の温度は何度がいいとか、時間はこんだけ置けとかグダグダ書いてるけど、そんなの適当でいいのよ。もっと美味しく飲むためにはどうすりゃいいんだ?って思ったら凝ればいいのよ。コーヒーでも紅茶でも「これが美味しい入れ方だ」って雑誌とかにやたら描かれてるけど、そういうのは店やプロがこだわるところで
一般人はもっと気楽に楽しむべきだと思うのよ。料理の世界もやれ出汁の取り方はこうしろとか、下ごしらえはこうしろ調味料のml、対比はこうだってのは無視してね。
そうなのよ、日本人の悪い癖で元々は庶民のものだったものがどんどん「道」の世界に行ってしまって、権威とか流儀とかこれが正しいってのがはびこるのよね。
お茶の世界も茶道、生け花も華道って道になって権威や免状の世界になってしまったし、着付けも何々流、踊りも何々流、三味線や琴も尺八も猫も杓子も。能や狂言なんて無縁。歌舞伎でさえ気楽には観に行けない。最近では相撲までも「品格が」などと言っている。バカじゃないかしら?
所詮は大衆から生まれたもの。権威にしたがるのはわからなくはないけど、それって今後衰退していってしまう前兆だよ。
和食器を見にいって、気に入ったのがあっても「高!」って思ってしまうような値段が平気でついてる。食器として使わずに床の間やサイドボードの上に飾れってか?って思ってしまう。バカラのグラスと伊賀焼きの湯呑みが同じ値段。
海辺の町でご飯を食べようとしたら「地元でとれた魚の海鮮丼」ってやつが1500円。アジフライ定食が1200円、ウニやイクラをのっけたのは2000円くらいする。おいおい、地元の人は毎日これ食べれるのか?どこでもかしこでも同じようなメニューになっていく。
和牛だってA5がどうたらってどんどん高くなる。焼肉なんて2000円くらいで腹一杯食えてたんだけどなぁ。
天然のフグや鰻、ズワイガニなんてもう庶民には手が出ない。
そう考えると寿司はすごいな。
回転ずしと老舗の寿司屋では違いはあるけど、回転ずしのおかげで未だに気楽に寿司がつまめるものね。ちなみに回転ずしが最初に登場したのは大阪万博で元禄ずし初案だ。
そばとかうどんもそうだな。老舗はあるし結構なお値段とるけどそれなりのお味で、かたや相変わらずお安い立ち食いそばとかセルフうどんとかも流行ってる。そう考えるとパスタ屋はどこもかしこもべらぼうに高い値段だな。麺にオリーブオイルと唐辛子絡めたペペロンチーノで1000円って高いよな。うどんにごま油と唐辛子かけただけで1000円って言ったら「誰がそんな値段で食べるねん」って言うだろう。カルボナーラ1500円?うどんに生卵からめて醤油かけて、ちくわ天のっけて500円。どっちが値段相応だ?
話がだいぶそれてしまったが、和を楽しむのは値段や権威ではない。
誰かが決めた価値観や、世間で言われるランキングも関係ない。
自分の気に入ったものをどう見つけて自分がどう楽しむのかだ。
「粋だねぇ」と呼ばれるか「野暮だねぇ」といわれるか。「オッシャレー」と言われるか「ダサい」と言われるか。もっと今風に言えば「インスタ栄えする」と「アップする価値なし」=インスタ萎えか。親指立てた「いいね」とか、リプライとか、言葉とかどうでもいいのよ。
自分が「これが乙だねぇ」「これがいいのよ」「これ気に入ってるのよ」って思えたら、誰が何と言おうとそれがへうげものの世界。
へうげもの最終巻25巻を読んで、俺はこれからもひょうげたものに感動できる人生を送りたいなぁってつくづく思う。











