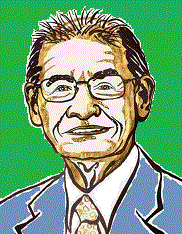きのうの朝日新聞に、神里達博の『専門家によるデータ公開 「科学を装った政治」を防ぐ』というコラムがあった。この小論は、多くの問題を短い行数で論じているので、主張が私にはわかりにくいが、扱っていることは根が深い。
その論点を整理すると次のようになる。
1.《日本の新型コロナウイルス感染症の状況には、よく分からない》《政権自体もこの状況をどう評価すべきか、迷っているようにも見える》
2.《政治家が専門家に重要な判断の責任を押し付けたり、あるいは専門家の側も自分の専門領域以上のところに踏み込んで、社会に対して説明を試みたりしているようにも見える》
3.《よくないのは、政治の側が価値判断をひそかに忍び込ませているのに、あたかも科学的に、自動的に導かれた結論であるかのように、自らの政策を国民に説明することである》《科学的な判断に基づくように装うことで、政治の側は、するりと責任を回避することもできてしまう》
一見、論理が通っているように見えるが、「科学」とは何か、「専門家」とは何か、の理解によっては、問題点が吹き出るだろう。
「新型コロナ対策専門家会議」の名がさすように、彼らは政府お抱えの「専門家」か、「医師会」の幹部である。「科学」とは何の関係もない。神里の小論に、どこにも、「科学者」「学者」「研究者」「医師」「医療従事者」の言葉が出てこないのである。
すなわち、神里の頭には、「政治家」と「専門家」以外の人間が存在しないのである。私は、まず、これに強い違和感を感じる。「政治家」と「専門家」だけで どうして「科学的判断」ができるのだろうか。
第1の論点からいえば、「よくわからない」のはPCR検査を政治的理由で絞ったからである。「科学的」という意味を事実にそって言えば、3月の末、専門家会議の尾身茂が、外人記者団に詫びたように、PCR検査能力が当時の日本になかったのではなく、検査の結果判明する感染者を受け入れる病院がなかったことである。日本医師会は感染者をうけいれたくなかったのである。
人間とは利害で動く動物である。ただ、民主主義社会の政治では、その利害を表に出して、利害の対立するもの同士が妥協することである。残念ながら、それがなされなかった。
若者は、思っているなら、私のような老人に向かって「新型コロナで死ね」と言っても良いのである。私は、その若者に向かって、「おまえも老人になるのだ、老人だからといって死んでも良いのか」と言い返すであろう。
事実を明らかにすることが、科学である。もちろん、事実と妄想との区別はむずかしい。事実とされるものは、つねに、一時的な思い込み、仮説で、新たなできごとで訂正されていかなければならない。
では、今回、政府の決定に「科学者」は参加できたか。排除されている。すなわち、民主主義社会の原則である、利害の調整は、経済団体(大手の経営者)、厚労省の役人、医師会の一部の間だけで利害が調整されたのである。神里は、この点に対して突っ込むべきであったのではないか。多くの人たちは参加できなかったのである。
第2の論点「専門家の側も自分の専門領域以上のところに踏み込んで」と批判の意味がわからない。具体的例をあげてもらうとわかるのだが。
たぶん私が思うに、メディアにいろいろな専門家、研究者、医師がでてきて発言したことを神里が言っているのだろう。まちがったことを言っていると神里が思うなら、それを具体的に批判しないといけない。「専門領域以上」のことを言ってよいのである。それが民主主義というものだ。
第3の論点「科学的な判断に基づく」ように装うというのは、詐欺だから、イケナイことである。
神里は、「科学」とは「数値」でないと言いたいのだろう。それに同意する。緊急事態宣言の解除を政治家が「数値」の問題にすり替えたのは、間違っている。
「科学」が政策の選択を決定できることなんて、そもそも、ありえない。「科学」が仮説を実証によって訂正していくことなら、信頼できる仮説に達するのに、何百年も要する。「政策」は妥協である。
新型コロナ対策も、あくまで、現時点の科学や技術にもとづき、利害を調整しながら行う、政治的施策である。大事な問題であれば、あるほど、議論の過程を公開し、多くの人を巻き込んで、行動していかないといけない。
神里の主張の根底に、「専門家」というものを「権威」として捉えていることがあるのだろう。この考えかたでは、どうしても、「専門家」が「権力」の太鼓たたきになる。科学や技術はむずかしいものではない。頭でこね回してつくりだされた妄想ではない。「科学・技術」は、まともな教育をうければ、多くの人が理解可能なものである。「専門家」以外も、自分の利害を守るため、政策決定にあたって、科学や技術にもとづき、発言して良いのである。それが民主主義社会である。
[補遺]
エンゲルスの著作に『空想から科学へ』(新日本出版社)がある。原題は、 “Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft”がある。しいて訳するなら「ユートピアから科学への社会主義の発展」となるだろう。19世紀のドイツ系知識人のいう「科学(Wissenschaft)」は「神学」に対抗するもので、「合理的思考による学問」という意味である。「知識」と「科学」の区別がついていない。
イギリスの知識人がいう「科学(science)」は、実証によって訂正され蓄積される知識体系である。ノーベル賞受賞者の本庶佑が「教科書に書いてあることに疑問を持たないなら、科学の研究者の資格」がないといった「科学」である。私は、本庶の意見に同意し、日本の科学教育は間違っていると思う。日本の科学の教科書は用語を覚えることに終始しており、科学が現実に適用できるかの実証にも、論理的整合性の検討にも、重きをおかない。まるで、お経を覚えるかのように、「科学」教育をおこなっている。
[補遺]
集団免疫方策を選択したスウェーデンで、老人の死亡例が多いという。これは、自然なことなのか、どうかが気になる。イギリスとかアメリカとかの例では、老人ホームで新型コロナの集団感染が多発しており、死亡はそのなかでも、介護放棄に起因しているように見える。老人の立場から見ると、人為的なものか、施設との相関が高いのか、気になる。西浦博もこの問題を科学的に分析してみたらどうだろうか。