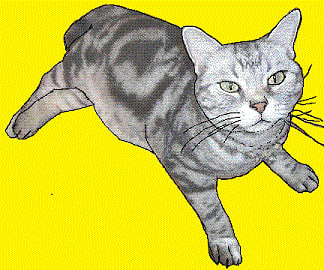きょうの朝日新聞、古川徹のインタビュー記事『学歴分断を超えて』を読んで無性に腹がたった。社会に腹を立てたというより、古川に腹を立てた。社会学者には、ろくでもない人が多すぎる。とくに、1966年生まれの社会学者は。
古川は、社会が学歴で格差をつけるということ自体を分析し批判せず、この学歴を理由とした格差を動かしがたい事実とし、大卒と非大卒との分断、コミュニケーションや連帯の無さを非難する。このような思考法はオカシイではないか。本末転倒ではないか。
確かに現在、大学を社会的序列の上昇のための手段と考えている集団もいるし、大学を高度の職業訓練所と考える財界や高級官僚もいる。
しかも、本当に、大卒であるから、お金儲けができるのか。大卒であるから、成功すると保障できるのか。
私のいとこの息子は、大阪大学を中退して、蕎麦屋をやっている。自分が「あるじ」であるから、社員のように社長にへいこらする必要がない。私のいとこ自身も、高卒の事務員で町中華の中卒の配達員に恋し、ふたりで絨毯の掃除屋を起業した。いとこの親は貸家にすむ工員であったが、掃除屋であてて自分の家をもった。
私が中学のときの校長は、全校生徒を講堂に集めて、「虎のしっぽになるより、鶏のとさかになれ」とよく激を飛ばしていた。どこかに雇われて、へいこらする人生を送るのではなく、起業してトップになれということである。
私は、外資系IT会社にはいって、一時、官庁とも関係をとろうとしたとき、大卒で思った就職もできず、ろくな起業もできない人びとが、行政府の外郭団体にうろちょろして、行政府と企業の間を取り持っている実態にびっくりした。まるでカフカの小説『城(Das Schloss)』のような世界があった。
古川は「でも、学歴差をなくすのは無理です。全員が同じ学歴では労働力を選別できず、産業社会は成立しないからです」という。意味がわからない。どうして古川は選別する側のことを心配するのか。若者も、郵便物のように学歴で選別されるのに身を任さず、能力に自信があるならば、自分でそれを立証すればよい。
私は、IT業界が地殻変動しているときに外資系に参加した。アメリカに行くと、カウボーイハットをかぶり、カウボーイブーツをはいた男が研究所を闊歩していた。そして、「インタネットは無法地帯だ」とうそぶいていた。友達になったシステムエンジニアと話すと、難民出身者が多く、学歴自体が怪しい。しかし、時代の変動に独習で見事についていっている。
古川は「『大きな資産を持てるかどうかは本人の努力次第かどうか』という質問に『そう思う』と答える割合が一番高いのは若年非大卒です」という。私は若年非大卒の考えを健康的だと思う。それなのに、古川は「社会的経済的に不利な状況に置かれているのに、大卒層や社会のせいとは考えず、自分の努力の帰結だと考えている」と上から目線の批判を付け加えている。
古川のいるような大阪大学は解体すべきだ。
現在の学歴社会を変革するには、第1に「資本主義社会をやめる」こと、第2に「能力がないが能力を向上させたい者を大学に入学させ、能力があるものは大学に入学せず、すぐに社会で活動し、そこで足りないものを感じたとき、聴講する」という制度にすればよい。すなわち、いまの受験制度の反対に、成績のよいものには能力保証書を発行し、来なくても良いと言ってやり、成績の悪いものから大学に入学させれば良い。
アメリカの大学の文系は社交の場の意味が強く、社会に出ても同じ大学出身だという閉鎖的社会を作っている。だから、マイケル・サンデルが学歴社会を嘆くのである。解決策は、大阪大学の場合と同じく、アイビー・リーグの大学の文系を閉鎖すればよい。
文系を閉鎖と言うのは、私がいた外資系のアメリカでの研究所にはもはやユーロピアン(白人)が入ってこず、新規の入所者は、アジアンか(インド系や中国系かイスラム系)かアフリカン(黒人)かラテン系(中米か南米出身)しかいないが、文系は人間関係だけで人の上に立とうする不届き者ばかりの管理職を目指す。支配者の手先なんて、まったく、いらないのだ。
私の友だちの京都大学出身の銀行員は、英語の発音、文法に磨きをかけても、パーティーでは同じ大学出身者が集まって話をして、自分がはいっていけなかったという。アメリカの金融業や広告業の人たちは人間のクズである。資本主義社会をなくせば、おのずと事態は改善されるだろう。
[関連ブログ]