会報 ふれんず212号 より
報 告
■ 第22回登校拒否不登校問題「全国のつどいin東京」に参加して
8月26 、27日東京都多摩
「共感した2日間」 代表 江藤圭子
“語りあおう 学びあおう子どもたちをまん中に”をスローガンに、参加者は全国から約650名。
・・・・・省略・・・・・
私は昨年に続き今年も「手をつなぐ輪を広げて」という親の会の経験交流の分科会に参加しました。1日目は14人、2日目17人の参加者で、それぞれの親の会の歴史、特徴、今抱えている問題や思いを交流しました。その中から、少し紹介します。
開催地の東京の方が30年前は近くに親の会がなかった、相談するところがなくて困っていた。そんな中、18年前に知り合いとサークル的に始めた親の会をやっている。集まって話をするだけ。子どもたちは30歳を過ぎている。家族夫婦の事、何でも話せる会になった。新しい人が来た時は情報発信することをしている。緊張した顔の親の方が続けて来てくださり、表情が和らいでいく」と話されました。
また、埼玉の方が「学校は、行けない時は来いこいと言うが、学びたくなった時は何もしてくれない。新潟での全国のつどいのから参加しているが、"つながり"が大事と思う」とも言われました。
そして、昨年フレンズネットワークに義援金を頂いた岩手の親の会からもみえていて、「津波で亡くなった妻の後を引き継いで、不登校の親の会を続けている。7年経った今でも小学校のグランドには仮設住宅がまだある、年長児だった子ども達が今小学校6年生、全国の支援のおかげと作文に書いている。子どもたちも頑張っている」と話されました。
1日目の夜の大交流会は、北海道から九州まで全国から300人近くの参加で、食事をしながらエールの交換が行われました。
2日目の分科会は2月に施行された「教育機会確保法」の中身と問題点について、全国世話人もされている前島康男先生の特別講座が行なわれました。私たちも、その中身について、行政へ出かけ、協議、意見交換をする事が必要だと、よく分かりました。
・・・・・省略・・・・・熊本から1人でしたが、参加して良かったなぁと思いました。・・・・・省略・・・・・
報 告
■ 第22回登校拒否不登校問題「全国のつどいin東京」に参加して
8月26 、27日東京都多摩
「共感した2日間」 代表 江藤圭子
“語りあおう 学びあおう子どもたちをまん中に”をスローガンに、参加者は全国から約650名。
・・・・・省略・・・・・
私は昨年に続き今年も「手をつなぐ輪を広げて」という親の会の経験交流の分科会に参加しました。1日目は14人、2日目17人の参加者で、それぞれの親の会の歴史、特徴、今抱えている問題や思いを交流しました。その中から、少し紹介します。
開催地の東京の方が30年前は近くに親の会がなかった、相談するところがなくて困っていた。そんな中、18年前に知り合いとサークル的に始めた親の会をやっている。集まって話をするだけ。子どもたちは30歳を過ぎている。家族夫婦の事、何でも話せる会になった。新しい人が来た時は情報発信することをしている。緊張した顔の親の方が続けて来てくださり、表情が和らいでいく」と話されました。
また、埼玉の方が「学校は、行けない時は来いこいと言うが、学びたくなった時は何もしてくれない。新潟での全国のつどいのから参加しているが、"つながり"が大事と思う」とも言われました。
そして、昨年フレンズネットワークに義援金を頂いた岩手の親の会からもみえていて、「津波で亡くなった妻の後を引き継いで、不登校の親の会を続けている。7年経った今でも小学校のグランドには仮設住宅がまだある、年長児だった子ども達が今小学校6年生、全国の支援のおかげと作文に書いている。子どもたちも頑張っている」と話されました。
1日目の夜の大交流会は、北海道から九州まで全国から300人近くの参加で、食事をしながらエールの交換が行われました。
2日目の分科会は2月に施行された「教育機会確保法」の中身と問題点について、全国世話人もされている前島康男先生の特別講座が行なわれました。私たちも、その中身について、行政へ出かけ、協議、意見交換をする事が必要だと、よく分かりました。
・・・・・省略・・・・・熊本から1人でしたが、参加して良かったなぁと思いました。・・・・・省略・・・・・














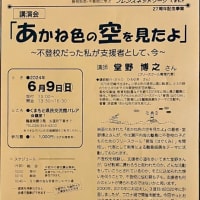
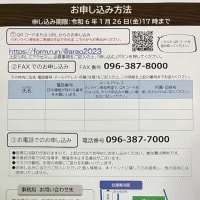
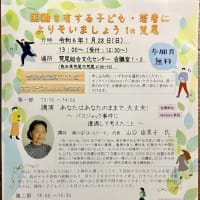

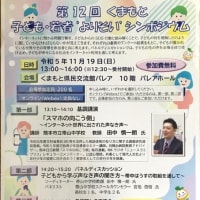

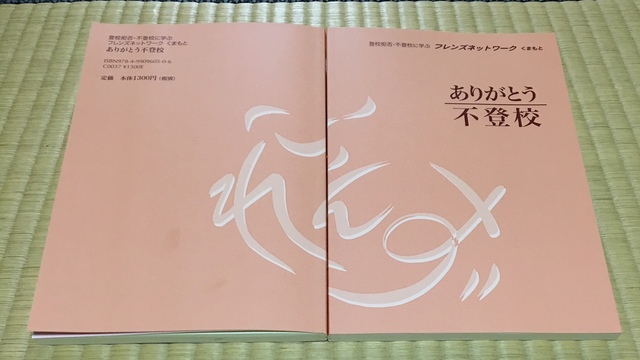





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます