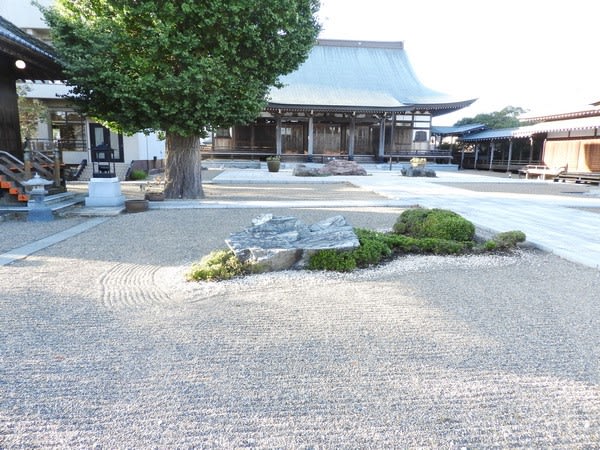イヌツゲが一番多いように感じます。刈り込みにも耐えて、端正な形を見せる樹種のようです。

イヌツゲ(西原)
黄色い花も黒い実もあまり目立たないようですが、気をつけてみるとなかなかきれいな姿です。

オカメザサ(備前町)
オカメザサは、年末の酉の市で、おかめの面をこれに下げたのでついた名前だそうです。ササといいますが、タケの仲間だそうです。

ヒノキ(常盤町)
偕楽園近くの民家で見かけました。大きくなる木なので、じょうずに剪定しなければいけないのでしょう。

ヒノキ(若宮)
すかし剪定をして、奥に光が通るようにして、芽を出させてからその先を剪定して何年かかけて形を整えるのだそうです。そうしないとその枝は枯れてしまうそうです。