司馬遼太郎の文化と文明
このシリーズはメタエンジニアリングで文化の文明化のプロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
書籍名;
「アメリカ素描」読売新聞社[1986] 1986.4.11発行
「韃靼風雲録」中央公論社[1987] 発行日;1987.11.20発行
著者;司馬遼太郎
文化・文明論にはさまざまな説がある。二つを明確に分けない場合も多い。そのような中で、司馬遼太郎のこの二つの書の定義は、メタエンジニアリングにとってまことに都合が良い。特に、優れた文化を文明化するプロセスを論じる際には、この「普遍性と合理性」という必要条件が良い。
先ずは、「アメリカ素描」からの文章を引用する。

P37からの引用;(昭和60年ころの諸事情であることを念頭に)
『アメリカへゆきましょう、と新聞社のひとたちが言ってくれたとき、冗談ではない、私にとってのアメリカは映画と小説で十分だ、とおもった。それにアメリカは日本にもありすぎている。明るくて機能的な建築、現代音楽における陽気すぎるリズム、それに、デトロイトの自動車工場の労働服を材料にみごとに“文明材”に仕立てたジーパン。
ついでながら“文明材”と云うのはこの場かぎりの私製語で、強いて定義めかしていえば、国籍人種をとわず、たれでもこれを身につければ、かすかに“イカシテル”という快感をもちうる材のことである。普遍性(かりに文明)というものは一つに便利と云う要素があり、一つにはイカさなければならない。たとえばターバンはそれを共有する小地域では普遍的だが、他の地域へゆくと、便利でないし、イカしもせず、異様でさえある。
ところが、ジーパンは、ソ連の青年でさえきたがるのである。ソ連政府はこの生地を国産化してやったそうだが、生地の微妙なところがイカさず、人気がでなかったといわれる。
普遍的であってイカすものを生みだすのが文明であるとすれば、いまの地球上にはアメリカ以外にそういうモノやコト、もしくは思想を生みつづける地域はなさそうである。そう考えはじめて、かすかながら出かける気がおこった。』
その後で司馬は、
『ここで、定義を設けておきたい。文明は「たれもが参加できる普遍的なものも・合理的なもの・機能的なもの」をさすのに対し、文化はむしろ不合理なものであり、特定の集団(たとえば民族)においてのみ通用する特殊なもので、他に及ぼしがたい。つまり普遍的でない。』
としている。
次に、彼の最後の小説とも云われている「韃靼風雲録」の完成後に書かれた「女真族来り去るーあとがきにかえて」(昭和62年7月)である。文章を引用する。
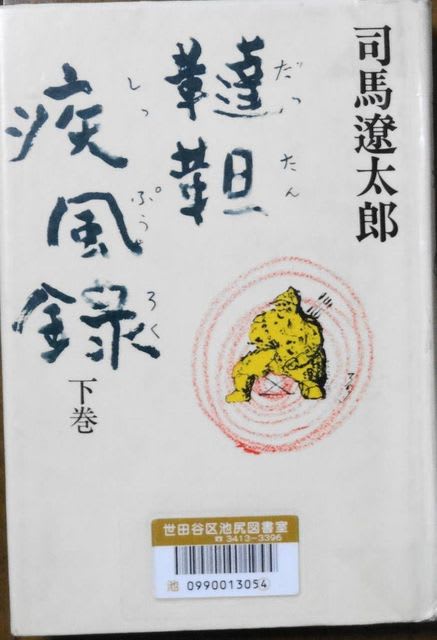
『中国は、漢以後、文明主義(つまり儒教)の国としてやってきた。このため周辺の異民族については、-彼らは華(文明)ではない。と、ひとことで尽くされた。以前は辺境の少数民族の文化をいやしみ、それらの文化を理解しようとしなかった(もともと小さな民族というものは、文化という、文明からみれば不合理なものだけで生きていた。文化こそ小集団が暮らしてゆく上で最善のものと信じていきてきたのである)。
文明というものは、それをどの民族にも押しひろげうるというシステムであるらしい。文化のように込み入ってはいない。また他からみれば理解しがたいほどに神秘的なものではなく、文明は投網のように大雑把なものである。』(pp.491)
『大ざっぱであればこそ、諸文化の上を超えてひろびろとゆきわたることができ、そういう普遍的な機能を以って文明というのである。それだけのもので、それ以上のものではない。
ところが、文明が爛熟すれば文明ボケして、人間が単純になってしまうらしい。文明人というのは“文明”という目の粗い大きな物差しをいつも持っていて、他民族の文化を計ろうとする。くりかえし言うが、文化はかならず特異で他に及ぼせば不合理なものであり、普遍性はない。ないからこそ、文化なのである。それを文明の尺度で文化を計ろうとするのは、体重計で身長を計ろうとするのに似ている。』(pp.491)
この「文明ボケ」という語は、この「韃靼風雲録」の一つのテーマになっていると思う。上下2冊になるこの長編物語は、平戸の武士が女真の公女を助けて、日本と中国を往復する話なのだが、文明が衰退期に達した明国と、文明が及んでいない女真族の攻防を表しており、ついに愛新覚羅による清国が誕生する過程を示している。波乱万丈の末に、二人は明国の元官吏として鎖国中の日本に住み着いて、静かな余生を過ごした。文明国の合理性と普遍性を身につけたように感じさせられる。
下巻の奥付によれば、この小説は「中央公論」で昭和59年1月から始まり、終わりは62年9月とある。二年半以上にわたるまさに長編だった。
この司馬遼太郎の二つの文化・文明論からは、イノベーションを考える過程で、いくつかの興味ある表現がある。イノベーションが文明に相当し、街の発明家の作品や、王様のアイデアの商品が文化であるとの仮定で考えてみたい。文明をイノベーション、文化をアイデア商品という語に置き換えてみよう。
「イノベーションというものは、それをどの民族にも押しひろげうるというシステムであるらしい。アイデア商品のように込み入ってはいない。また他からみれば理解しがたいほどに神秘的なものではなく、イノベーションは投網のように大雑把なものである。」
「もともと小さな民族というものは、アイデア商品という、イノベーションからみみれば不合理なものだけで生きていた。アイデア商品こそ小集団が暮らしてゆく上で最善のものと信じていきてきたのである」となる。
これらの言葉からは、日本におけるガラパコス化ともいわれる新商品競争の激化と、イノベーション不作の現状が見えてくるではないだろうか。
明治維新の文明開化は、江戸文化があってこそだと思う。そこに欧米の文明が侵入して新たな日本文明が出来上がってゆくわけで、強固で優れた文化があってこそ、文明化の可能性があるわけで、イノベーションだけを望んでも、それは無理無体というものであろう。過去のイノベーションを遡れば、膨大な数のアイデア商品があり、それを如何に普遍化・標準化したかによることが明らかになる。航空機の歴史も、そのことを明確に示している。
日本では、イノベーションを実際に目ざす人よりも、イノベーションを語る人の方がずっと多く、その傾向は今も続いている。私は、自身が携わった1980年代からの20年間のジェットエンジンの進化が、空の旅を快適化したイノベーションの一つだったと思っている。最近の低価格化と安心感は、それ以前のエンジンでは実現不可能だった。世界中のどの2地点でも、双発機でノンストップで行くことができるメリットは、全世界の旅行者(ビジネスと観光)のライフスタイルを変えたと思う。
それは、それ以前とは格段に異なる設計と製造の信頼性の上に成り立っているのだが、Boeingと世界のエンジン会社の協力体制で出来上がったものだった。この間の詳細については、拙著の博士論文(勝又[2009])に記した。
これらの後に、メタエンジニアリング的な思考からイノベーションと「現在の文化と次の文明」について考え始めた。つまり、優れた文化を文明化するプロセスと、イノベーションは同じプロセスが必要だということである。
勝又「初期品質安定設計法の提案と評価」東京大学大学院工学系研究科博士論文[2009]
このシリーズはメタエンジニアリングで文化の文明化のプロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
書籍名;
「アメリカ素描」読売新聞社[1986] 1986.4.11発行
「韃靼風雲録」中央公論社[1987] 発行日;1987.11.20発行
著者;司馬遼太郎
文化・文明論にはさまざまな説がある。二つを明確に分けない場合も多い。そのような中で、司馬遼太郎のこの二つの書の定義は、メタエンジニアリングにとってまことに都合が良い。特に、優れた文化を文明化するプロセスを論じる際には、この「普遍性と合理性」という必要条件が良い。
先ずは、「アメリカ素描」からの文章を引用する。

P37からの引用;(昭和60年ころの諸事情であることを念頭に)
『アメリカへゆきましょう、と新聞社のひとたちが言ってくれたとき、冗談ではない、私にとってのアメリカは映画と小説で十分だ、とおもった。それにアメリカは日本にもありすぎている。明るくて機能的な建築、現代音楽における陽気すぎるリズム、それに、デトロイトの自動車工場の労働服を材料にみごとに“文明材”に仕立てたジーパン。
ついでながら“文明材”と云うのはこの場かぎりの私製語で、強いて定義めかしていえば、国籍人種をとわず、たれでもこれを身につければ、かすかに“イカシテル”という快感をもちうる材のことである。普遍性(かりに文明)というものは一つに便利と云う要素があり、一つにはイカさなければならない。たとえばターバンはそれを共有する小地域では普遍的だが、他の地域へゆくと、便利でないし、イカしもせず、異様でさえある。
ところが、ジーパンは、ソ連の青年でさえきたがるのである。ソ連政府はこの生地を国産化してやったそうだが、生地の微妙なところがイカさず、人気がでなかったといわれる。
普遍的であってイカすものを生みだすのが文明であるとすれば、いまの地球上にはアメリカ以外にそういうモノやコト、もしくは思想を生みつづける地域はなさそうである。そう考えはじめて、かすかながら出かける気がおこった。』
その後で司馬は、
『ここで、定義を設けておきたい。文明は「たれもが参加できる普遍的なものも・合理的なもの・機能的なもの」をさすのに対し、文化はむしろ不合理なものであり、特定の集団(たとえば民族)においてのみ通用する特殊なもので、他に及ぼしがたい。つまり普遍的でない。』
としている。
次に、彼の最後の小説とも云われている「韃靼風雲録」の完成後に書かれた「女真族来り去るーあとがきにかえて」(昭和62年7月)である。文章を引用する。
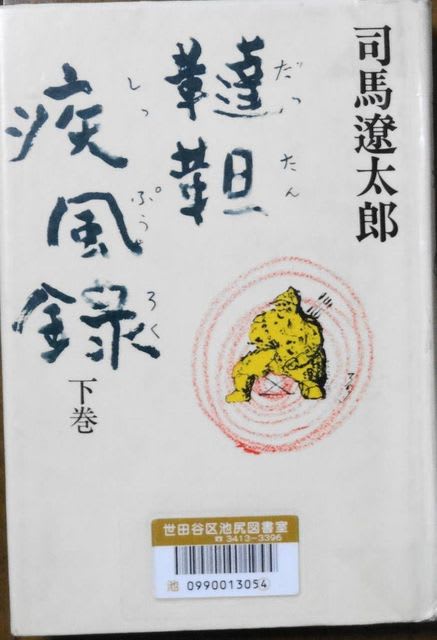
『中国は、漢以後、文明主義(つまり儒教)の国としてやってきた。このため周辺の異民族については、-彼らは華(文明)ではない。と、ひとことで尽くされた。以前は辺境の少数民族の文化をいやしみ、それらの文化を理解しようとしなかった(もともと小さな民族というものは、文化という、文明からみれば不合理なものだけで生きていた。文化こそ小集団が暮らしてゆく上で最善のものと信じていきてきたのである)。
文明というものは、それをどの民族にも押しひろげうるというシステムであるらしい。文化のように込み入ってはいない。また他からみれば理解しがたいほどに神秘的なものではなく、文明は投網のように大雑把なものである。』(pp.491)
『大ざっぱであればこそ、諸文化の上を超えてひろびろとゆきわたることができ、そういう普遍的な機能を以って文明というのである。それだけのもので、それ以上のものではない。
ところが、文明が爛熟すれば文明ボケして、人間が単純になってしまうらしい。文明人というのは“文明”という目の粗い大きな物差しをいつも持っていて、他民族の文化を計ろうとする。くりかえし言うが、文化はかならず特異で他に及ぼせば不合理なものであり、普遍性はない。ないからこそ、文化なのである。それを文明の尺度で文化を計ろうとするのは、体重計で身長を計ろうとするのに似ている。』(pp.491)
この「文明ボケ」という語は、この「韃靼風雲録」の一つのテーマになっていると思う。上下2冊になるこの長編物語は、平戸の武士が女真の公女を助けて、日本と中国を往復する話なのだが、文明が衰退期に達した明国と、文明が及んでいない女真族の攻防を表しており、ついに愛新覚羅による清国が誕生する過程を示している。波乱万丈の末に、二人は明国の元官吏として鎖国中の日本に住み着いて、静かな余生を過ごした。文明国の合理性と普遍性を身につけたように感じさせられる。
下巻の奥付によれば、この小説は「中央公論」で昭和59年1月から始まり、終わりは62年9月とある。二年半以上にわたるまさに長編だった。
この司馬遼太郎の二つの文化・文明論からは、イノベーションを考える過程で、いくつかの興味ある表現がある。イノベーションが文明に相当し、街の発明家の作品や、王様のアイデアの商品が文化であるとの仮定で考えてみたい。文明をイノベーション、文化をアイデア商品という語に置き換えてみよう。
「イノベーションというものは、それをどの民族にも押しひろげうるというシステムであるらしい。アイデア商品のように込み入ってはいない。また他からみれば理解しがたいほどに神秘的なものではなく、イノベーションは投網のように大雑把なものである。」
「もともと小さな民族というものは、アイデア商品という、イノベーションからみみれば不合理なものだけで生きていた。アイデア商品こそ小集団が暮らしてゆく上で最善のものと信じていきてきたのである」となる。
これらの言葉からは、日本におけるガラパコス化ともいわれる新商品競争の激化と、イノベーション不作の現状が見えてくるではないだろうか。
明治維新の文明開化は、江戸文化があってこそだと思う。そこに欧米の文明が侵入して新たな日本文明が出来上がってゆくわけで、強固で優れた文化があってこそ、文明化の可能性があるわけで、イノベーションだけを望んでも、それは無理無体というものであろう。過去のイノベーションを遡れば、膨大な数のアイデア商品があり、それを如何に普遍化・標準化したかによることが明らかになる。航空機の歴史も、そのことを明確に示している。
日本では、イノベーションを実際に目ざす人よりも、イノベーションを語る人の方がずっと多く、その傾向は今も続いている。私は、自身が携わった1980年代からの20年間のジェットエンジンの進化が、空の旅を快適化したイノベーションの一つだったと思っている。最近の低価格化と安心感は、それ以前のエンジンでは実現不可能だった。世界中のどの2地点でも、双発機でノンストップで行くことができるメリットは、全世界の旅行者(ビジネスと観光)のライフスタイルを変えたと思う。
それは、それ以前とは格段に異なる設計と製造の信頼性の上に成り立っているのだが、Boeingと世界のエンジン会社の協力体制で出来上がったものだった。この間の詳細については、拙著の博士論文(勝又[2009])に記した。
これらの後に、メタエンジニアリング的な思考からイノベーションと「現在の文化と次の文明」について考え始めた。つまり、優れた文化を文明化するプロセスと、イノベーションは同じプロセスが必要だということである。
勝又「初期品質安定設計法の提案と評価」東京大学大学院工学系研究科博士論文[2009]









