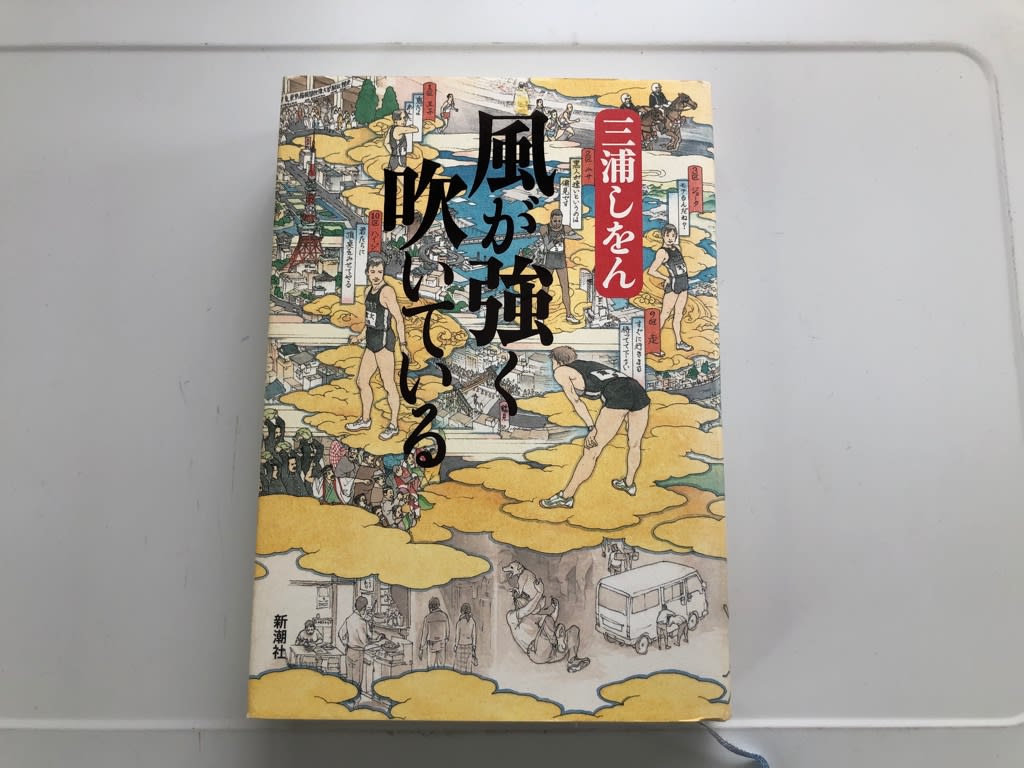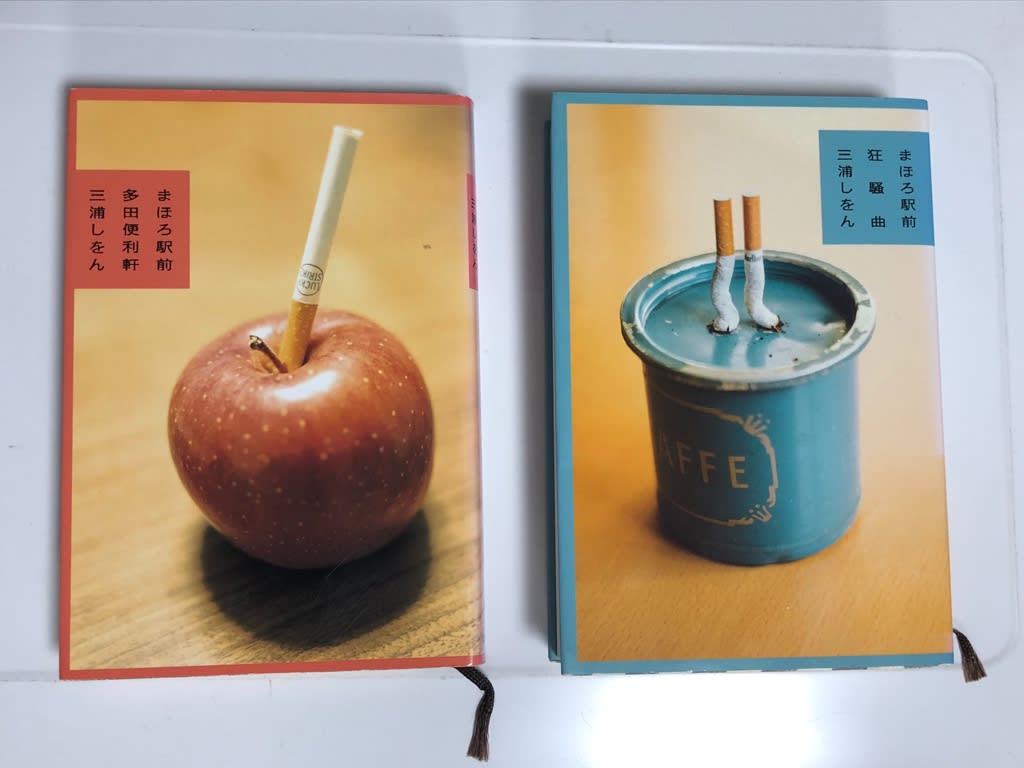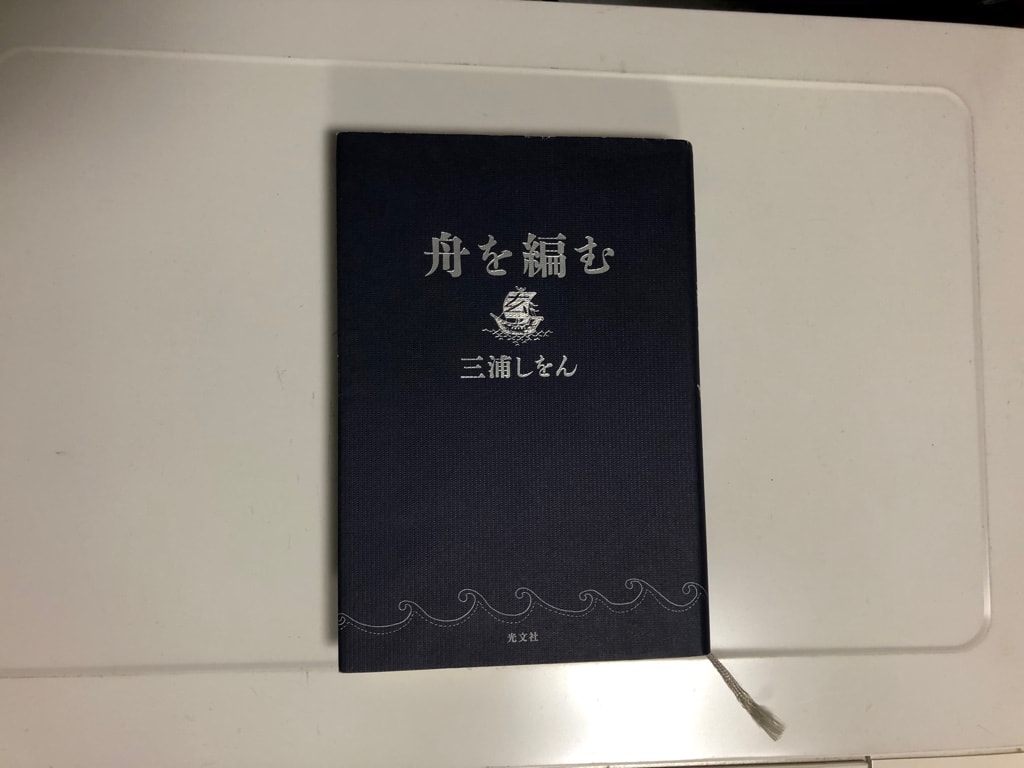7BCの5日目。

表紙デザインは安藤久美子さん。

これ以上の詳細な情報が見たければ、画面を拡大するしかないが、そうすると全体における自分の立ち位置がよく分からなくなる。




なかなか毎日アップする、というのは難しいですな。
だって・・・・
めんどくさいもん。
私の数少ないFB友だちの中にも7BCに参加している人が何人かいるが、皆さん、ちゃんと毎日、更新しておられる。偉いなぁ。
誰が決めたのかも分からない、その目的も趣旨も分からない、それでも
「ルールに従って参加すると承諾した以上、ルールは守る」
というのは、ある意味、日本人が世界に誇るべき美徳なのかもしれぬ。
え、私?
私はスペイン系ですから。たぶん。
いつも午後になるとやたらに眠くなるし。
そろそろ我が事務所でもシエスタを導入しようかと。
で、5日目の今日は昭文社さんの「県別マップル13東京都道路地図」(以下、「MAPPLE」)。

表紙デザインは安藤久美子さん。
私の「東京日帰りツーリング」になくてはならない相棒だ。いや、安藤久美子さんではなくMAPPLEが。
よく、「Google mapの方が便利じゃないですか?」と言われるが、Google mapに限らず、スマホ・パソコン系の地図というのは「特定のポイントを決めて、その近辺の情報を得る」という点には長(た)けているが、「ある地点からある地点までの移動ルートを俯瞰的に把握する」ということには向いていない。
たとえば、「五日市街道を使って日の出山荘(東京日帰りツーリング「日の出町編参照」)に行き、その後、つるつる温泉に抜ける」というルートをGoogle mapで表示するとこうなる。

これ以上の詳細な情報が見たければ、画面を拡大するしかないが、そうすると全体における自分の立ち位置がよく分からなくなる。
Google mapには下の画像のような情報も表示されるが、「全体の中の自分の立ち位置がよく分からない」という点では何も変わらない。「5.2km」とか「1.7km」とかの情報を見て各地点の距離感覚・位置感覚を頭の中に描ける人は国土地理院の職員くらいだろう。

少なくともバイクで走っているときにこの手の情報はほとんど役に立たない。
AI並の記憶力を持っていれば別だが。
最近ではバイクのハンドルバーにスマホを取り付けられるキットが売り出されていて、走りながらスマホを見ているライダーを見かけることが多くなってきたが、危険なことこの上ない。なんでそんなに死に急ぐのか。
赤信号で止まったわずかな時間にスマホの画面を拡大したりスワイプするのも面倒くさいだろう。
危なかったり面倒くさいのは本人の自由だが、「自由を手に入れるためにバイクに乗ってるのに、どこまで行ってもスマホからは自由になれないんだなぁ」と少し気の毒に思ったりする。
で、紙の地図。MAPPLE。
同じ情報がこんな感じ↓

全体のルート、自分が走るべきコースが一目瞭然だ(地図中の赤線は私が書き込んだツーリングコース)。情報量もスマホ画面の比ではない。
昔はこういう地図をバイクのガソリンタンクの上に広げたまま走ることのできるバッグがよく売れたが、そんなものいらん。
これで十分だ↓

自宅でMAPPLEを開き、翌日走るコースをあれこれ思い描いて、コースが決まったら右左折二又など自分だけのキー・ポイントをポストイットに殴り書きして、それをガソリンタンクにセロテープで貼り付けておく。
それでも万一、道に迷った時や、ツーリング途中でいきなり別の場所にも行きたくなったときのために、サドルバッグにはMAPPLEをつっこんでおく。
紙の地図がよくて、スマホの地図は役に立たない、というのではない。
要は使い方と使う場面の問題だ。
スマホは特定の情報に瞬時にアクセスして、それを認識・理解することには向いているが、その情報を中心にしたより大きな視点から全く別の情報までを俯瞰的に把握する「フワッとした」情報把握には向いていない。
この「フワッと全体を俯瞰的に把握して発想を広げていく」という訓練をしたければ、紙の地図(それも1枚地図ではなく広域が本の形式になっているMAPPLEのような地図)を眺めて、自分の立ち位置と向かうべき場所をあれこれ考えてみるとよい。
情報調査能力や整理能力には長けているのに、物事の全体像を思い描いて、自分の立ち位置と向かうべき場所、そこに至るルートの多様性を「フワッと」掴む能力を欠いた人間が増えてきたのは、スマホの普及と無関係ではないかもしれない、と思ったりする。
ちなみに、私のツーリングの相棒はMAPPLEとこいつ↓

てるてるちゃん(私が命名)の幸せそうな顔を見ていると、紙の地図だけを頼りに、どこまでものんびりほーんと走って行きたくなってくる。
5月は、バイク乗りたちの季節である。