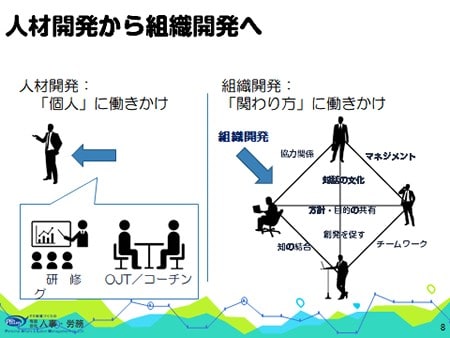こんにちは!有限会社人事・労務の西田です。
最近は、下記のグラフ(総務省HPから抜粋)を見てもわかるように、少子高齢化が急激に進んできています。15歳~64歳の生産年齢人口も減り続ける事が予想される中、労働力の確保のため、中小企業でも多様な働き方がかなり増えてきました。

今までは、社員が同じ働き方、同じ価値観のもとで働いていたので、会社としては皆を同じように見ていればよかったのですが、違う働き方、異なる価値観の中で社員ひとりずつ見ていくことになり、評価の仕方も一元的に見ていくことが難しくなっています。
そのため、以前より評価制度も多様になってきました。
今回は、ある会社の例を紹介したいと思います。
この会社は、都内を中心に展開している小売店ですが、今までは、店で働く社員は、店長が、本社で働く社員は課長が一次評価して、部長の二次評価を経て社長が決定していました。評価の視点は、目標管理を反映する成果評価と日頃の仕事ぶりにおいて必要な能力が発揮できているかを見る能力評価。目標管理は期ごとに目標を立てて、その達成度を評価し、能力評価は、その等級や職種で求められる能力を項目ごとに評価するという一般的な評価の仕方でした。しかし、働き方が多様化して、例え同じ職種でも同じ能力項目で評価することが難しくなってきました。また、二次評価の部長も最終評価の社長も現場ひとりひとりの社員を把握することがしづらくなってきました。
そこで、目標管理はそのままに、能力評価は一番身近で見ている同じ店舗のメンバー同士で評価することにしました。評価項目も今までは、細かい項目を10項目ほど設定していたのですが、それももっとざっくりとした評価に変えました。同じ職場のメンバーであれば、仕事ぶりや能力、貢献度合いがよくお互いに良く分かり、それが公平性にもつながっていきます。メンバー1人1人の働きぶりをメンバー同士が評価をして、最終的には店長が決定し、社長はその評価をほとんど変えず承認を行います。評価というと「評価項目やルールを細かく決めて不満がないように公平、公正に」という考えが強く、「現場で決めるなんて大丈夫か」と思うかもしれませんが、そもそも評価制度を細かく決めるのは、人数が多くなってくると、個人の仕事ぶりや成果が見えづらくなるため、あるいは複数の考課者による評価をある程度統一化できるようにするために、一定のものさしで測り、制度を作るわけです。そのため、個人の仕事ぶりや成果が見えるチームという少人数の範囲であれば、むしろ細かい評価項目を決めて評価するよりも、細かい項目では測れない部分の評価も含め、制度に縛られない方が公正に評価できる部分もあります。
まだ、評価制度を変えたばかりですので、うまくいくかどうかは分かりませんが、最近はこのように、評価をシンプルに、ざっくりとしたいという会社が増えてきています。ただし、ざっくりとした評価は、評価者個人の評価判断に任せることが大きくなり、評価者が会社の文化や価値観を理解して、会社が評価すべき人をしっかりと評価することが求められます。
働き方が多様化してきている今だからこそ、より会社の価値観の浸透が必要となるのです。
最近は、下記のグラフ(総務省HPから抜粋)を見てもわかるように、少子高齢化が急激に進んできています。15歳~64歳の生産年齢人口も減り続ける事が予想される中、労働力の確保のため、中小企業でも多様な働き方がかなり増えてきました。

今までは、社員が同じ働き方、同じ価値観のもとで働いていたので、会社としては皆を同じように見ていればよかったのですが、違う働き方、異なる価値観の中で社員ひとりずつ見ていくことになり、評価の仕方も一元的に見ていくことが難しくなっています。
そのため、以前より評価制度も多様になってきました。
今回は、ある会社の例を紹介したいと思います。
この会社は、都内を中心に展開している小売店ですが、今までは、店で働く社員は、店長が、本社で働く社員は課長が一次評価して、部長の二次評価を経て社長が決定していました。評価の視点は、目標管理を反映する成果評価と日頃の仕事ぶりにおいて必要な能力が発揮できているかを見る能力評価。目標管理は期ごとに目標を立てて、その達成度を評価し、能力評価は、その等級や職種で求められる能力を項目ごとに評価するという一般的な評価の仕方でした。しかし、働き方が多様化して、例え同じ職種でも同じ能力項目で評価することが難しくなってきました。また、二次評価の部長も最終評価の社長も現場ひとりひとりの社員を把握することがしづらくなってきました。
そこで、目標管理はそのままに、能力評価は一番身近で見ている同じ店舗のメンバー同士で評価することにしました。評価項目も今までは、細かい項目を10項目ほど設定していたのですが、それももっとざっくりとした評価に変えました。同じ職場のメンバーであれば、仕事ぶりや能力、貢献度合いがよくお互いに良く分かり、それが公平性にもつながっていきます。メンバー1人1人の働きぶりをメンバー同士が評価をして、最終的には店長が決定し、社長はその評価をほとんど変えず承認を行います。評価というと「評価項目やルールを細かく決めて不満がないように公平、公正に」という考えが強く、「現場で決めるなんて大丈夫か」と思うかもしれませんが、そもそも評価制度を細かく決めるのは、人数が多くなってくると、個人の仕事ぶりや成果が見えづらくなるため、あるいは複数の考課者による評価をある程度統一化できるようにするために、一定のものさしで測り、制度を作るわけです。そのため、個人の仕事ぶりや成果が見えるチームという少人数の範囲であれば、むしろ細かい評価項目を決めて評価するよりも、細かい項目では測れない部分の評価も含め、制度に縛られない方が公正に評価できる部分もあります。
まだ、評価制度を変えたばかりですので、うまくいくかどうかは分かりませんが、最近はこのように、評価をシンプルに、ざっくりとしたいという会社が増えてきています。ただし、ざっくりとした評価は、評価者個人の評価判断に任せることが大きくなり、評価者が会社の文化や価値観を理解して、会社が評価すべき人をしっかりと評価することが求められます。
働き方が多様化してきている今だからこそ、より会社の価値観の浸透が必要となるのです。