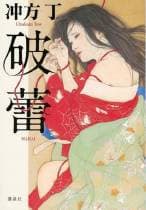江戸時代の著名な浮世絵師たちは、美人画や風景画その他のジャンルでそれぞれが一世を風靡する一方で、春画を今に残している。評判になった歴史時代小説を手掛けてきた冲方も、この浮世絵師たちの例にならったのだろうか、エロティシズムを漂わせる官能小説のジャンルにも創作を広げたようである。著者の作品を幾冊か読み継いできたが、官能小説のジャンルでの作品を読むのはこれが最初である。他にこのジャンルを手掛けているのかどうかも知らない。
本書は3つの作品が収録されている。「咲乱れ引廻しの花道」(69ページもの)、「香華灯明、地獄の道連れ」(87ページもの)、「別式女、追腹始末」(26ページもの)である。奥書によれば前2作品は「小説現代」の2017年11月号、2018年3月号にそれぞれ発表されたもの、最後のものは書き下ろしである。
そのタイトルから推測できると思うが、時代小説として創作されている。多分これらの作品をほぼ忠実に映像作品化することは映倫という枠組みを前提とすれば無理だろう。文字で描かれた世界に読者が想像力で思い描くのは、個々人の自由である。
それでは、個々の作品について読後印象をご紹介する。
[咲乱れ引廻しの花道]
主人公はお咲。南町奉行に一応与力として属し、八丁堀に屋敷を拝領する御家人たる岡田家に嫁いでいる。日常は商家の娘たちに礼儀作法や三味線などを教える内職をして家計を助けている。そのお咲が小伝馬町にある牢屋敷に、叔父と夫に代わって、役人たちに弁当の差し入れに行く。それがお咲の人生を狂わせる。
この夏に江戸で一つの事件が起こっていた。とある裕福な商家の男が、”御家人株”を買い武家となった。晴れて幕臣となったのち、美しいと評判の、身分ある女を妻に娶るのだが、数年後その妻に殺されかけられる。その女はとらえられる。死罪は免れないのだが、その女の出生の秘密の故に、江戸市中の引きまわしには何とかして、身代わりを立てて処置せよと上層部からの指示が出ている。身代わり探しをお咲の夫の叔父が命じられる。そんな身代わりに応じる者が出る筈もない。結局、知らされることなくお咲が身代わりとしての人身御供となる。
このストーリーは、江戸市中の引廻しの身代わりになるお咲の状況を描きあげていく。身代わりなのだが、罪人と同様に後ろ手に縛りあげられた後、僧形の医師・冗賢に身体をくまなく検分され記録に残す手続きをされ、引廻しの途中で気を失わないための処置だと特製の薬剤やりんの玉を措置される羽目になる。そして、ものものしい行列で江戸市中を引き回される。その引廻しの道中模様並びにお咲の身体と心理の変容が克明に描出されていく。引廻しの途中で、お咲が「お情けを・・・・・、どうか・・・・お願いします。お情けをいただけませんか・・・・」と発するが、その意味が引廻しに同行する検視役に誤解されることになる。罪人本人ならば引廻しの後、刑場にそのまま向かうところだが、身代わりのお咲は牢屋敷の蔵に一旦引き戻される。そして・・・・という展開になる。
処刑の一環として江戸市中引廻しという行為は江戸時代に処罰として存在した。しかし、著者がこの引廻しで描き上げたプロセスは多分フィクションではないかと想像する。引廻しという一種の極限状況に、エロティシズムの限りを盛り込んだというところだろうか。事実は小説より奇なりともいうから、果たして実状はどうだったのか、この作品を離れて、知りたい気がする。
[香華灯明、地獄の道連れ]
こちらは上記の連作と言える。おもしろい点は、お咲が身代わりという人身御供になった原因に遡るストーリーという構想になっている。五月晴れの日、南町奉行のお白洲での取り調べから始まる。そして牢屋敷の敷地にある刑場で斬首されることで終わる。その間に、なぜ25歳の「婉然とした、細く嫋やかといってもいい、美貌の女」お芳こと芳乃が夫の殺害を企てるに至ったかの経緯が芳乃の口から語られるという展開が挟み込まれる。
この白洲での取り調べの状況がそもそも異常なやり方で進む。そこでお咲の夫の叔父にあたる岡田鉄心が巻き込まれていく結果、お咲に悲劇が及ぶ経緯が判明する。
岡田鉄心は奉行から独断で、事前にこの女から夫を殺そうと企てた理由を聞き出し、書面にするように命じられる。幕閣の秘事に関わる可能性があることから、岡田は人払いをして、単独でその女に牢の内外で向かい合い尋問する心づもりだった。だが、牢内に入る羽目になる。女は所持品として持ち込んだ3つのさいころをもてあそんでいて、一、一、一のぞろ目が出たのだ。女は岡田に言う。「ぞろ目の一は、わたしをお聞きになる出目です」、「わたしの話を聞きたいのであれば、まず、わたしをお聞きになって下さいませ」と。香道では、香りを嗅ぐことを聞くという。
芳乃は幼い頃から、すごろくに描かれているものが世界そのものという形で育った。母自体が、奥奉公の出世すごろくを絵に描いたようなあがりの人生を過ごしたのである。奥女中から始め、様々な役職をこなし、さる大名のとの間で芳乃を妊るというあがりを拾ったのである。芳乃は己の「あがり」の人生を常に考える思考法をとるようになる。あがりの人生を手に入れるために、母のように奥奉公をする決意をする。そのあがりが何かは徐々に変化していく。あがりを手に入れるために、奥奉公の一環で付き従った寺参りにおいての秘め事を体験させられる。そこで、あがりへの一歩として、寺参りにかこつけた中で行われる色欲がらみの実態で己が主導権をとるように画策していく。なまめかし香遊びの隠微な実態が描き込まれていく。もちろんそれは香遊びという名を借りた邪道の淫欲世界である。芳乃は、己の才覚で、僧、奥奉公先の役職、勘定方、家老などを次々と籠絡していく。芳乃の考える「あがり」は世間の倫理観からでは途轍もない目標だった。その目標に一歩踏み込む。芳乃にとっては、武家となった商家の男に嫁いだのは、目標のあがりを得る手段だったのだ。そして、芳乃は人生すごろくで、別のあがりに導かれる。
このお咲きの引廻し身代わり編に対する発生原因告白編もまた、「聞く」という行為をキーワードとして、アンチ倫理の世界を著者の想像力と妄想で構想するという試みであろう。フィクションの世界で創作されたこの行為。江戸時代に密かに類似のモデルがあったとしても不思議ではないかもしれない。人間の欲望の限りなさを前提とするならば・・・・・。いずれにしても、その顛末のプロセスはおもしろい。
[別式女、追腹始末]
こちらも連作となる。芳乃が奥奉公で仕えたのがある大名の側妾・お初の方だった。そのお初は女剣術指南役という肩書で景を仕えさせていた。お初は芳乃をこの景が性戯に長けていることを見抜き、籠絡の手段として利用する。芳乃を馴致させるためにお初は景を利用する。だがそれはミイラ取りがミイラになる結果となる。
この景が女剣術指南役となるに至ったかの背景話である。そこに景が性戯に長ける始まりがあった。景の父は高名な剣術家であり、二人の弟子がいる。その弟子たちと景の間の物語から話が始まって行く。その景が追腹を切るという結末となる。誰のために? それは本書をお読み願いたい。短編の中にいわばイレギュラーなセクシュアル・シーンの山場を作っていて、最後は殉ずる一念の行動場面を描く。
「別式女(べつしきめ)」という用語を本書で初めて知った。「刀腰婦(とうようふ)、あるいは帯剣女とも呼ばれる。袴姿で佩刀する、侍の姿をした女のことだ。お歯黒もせず、髪もも結わず総髪にし、男装を平常の出で立ちとして江戸の町を闊歩する。特に奥向きの武芸指南を生業とする者のこと」をいうと著者は説明を記している。
先を知りたくなり一気読みさせられる。艶っぽくてある意味異常な次元を描きあげた作品集である。山科理恵作の挿画が入っている。描かれた女の表情が良い。
ご一読ありがとうございます。
この読後印象記を書き始めた以降に著者の作品を読み、書き込んだのは次の作品です。
こちらもお読みいただけるとうれしいかぎりです。
『光圀伝』 角川書店
『はなとゆめ』 冲方丁 角川書店
『決戦! 大坂城』 葉室・木下・富樫・乾・天野・冲方・伊東 講談社
本書は3つの作品が収録されている。「咲乱れ引廻しの花道」(69ページもの)、「香華灯明、地獄の道連れ」(87ページもの)、「別式女、追腹始末」(26ページもの)である。奥書によれば前2作品は「小説現代」の2017年11月号、2018年3月号にそれぞれ発表されたもの、最後のものは書き下ろしである。
そのタイトルから推測できると思うが、時代小説として創作されている。多分これらの作品をほぼ忠実に映像作品化することは映倫という枠組みを前提とすれば無理だろう。文字で描かれた世界に読者が想像力で思い描くのは、個々人の自由である。
それでは、個々の作品について読後印象をご紹介する。
[咲乱れ引廻しの花道]
主人公はお咲。南町奉行に一応与力として属し、八丁堀に屋敷を拝領する御家人たる岡田家に嫁いでいる。日常は商家の娘たちに礼儀作法や三味線などを教える内職をして家計を助けている。そのお咲が小伝馬町にある牢屋敷に、叔父と夫に代わって、役人たちに弁当の差し入れに行く。それがお咲の人生を狂わせる。
この夏に江戸で一つの事件が起こっていた。とある裕福な商家の男が、”御家人株”を買い武家となった。晴れて幕臣となったのち、美しいと評判の、身分ある女を妻に娶るのだが、数年後その妻に殺されかけられる。その女はとらえられる。死罪は免れないのだが、その女の出生の秘密の故に、江戸市中の引きまわしには何とかして、身代わりを立てて処置せよと上層部からの指示が出ている。身代わり探しをお咲の夫の叔父が命じられる。そんな身代わりに応じる者が出る筈もない。結局、知らされることなくお咲が身代わりとしての人身御供となる。
このストーリーは、江戸市中の引廻しの身代わりになるお咲の状況を描きあげていく。身代わりなのだが、罪人と同様に後ろ手に縛りあげられた後、僧形の医師・冗賢に身体をくまなく検分され記録に残す手続きをされ、引廻しの途中で気を失わないための処置だと特製の薬剤やりんの玉を措置される羽目になる。そして、ものものしい行列で江戸市中を引き回される。その引廻しの道中模様並びにお咲の身体と心理の変容が克明に描出されていく。引廻しの途中で、お咲が「お情けを・・・・・、どうか・・・・お願いします。お情けをいただけませんか・・・・」と発するが、その意味が引廻しに同行する検視役に誤解されることになる。罪人本人ならば引廻しの後、刑場にそのまま向かうところだが、身代わりのお咲は牢屋敷の蔵に一旦引き戻される。そして・・・・という展開になる。
処刑の一環として江戸市中引廻しという行為は江戸時代に処罰として存在した。しかし、著者がこの引廻しで描き上げたプロセスは多分フィクションではないかと想像する。引廻しという一種の極限状況に、エロティシズムの限りを盛り込んだというところだろうか。事実は小説より奇なりともいうから、果たして実状はどうだったのか、この作品を離れて、知りたい気がする。
[香華灯明、地獄の道連れ]
こちらは上記の連作と言える。おもしろい点は、お咲が身代わりという人身御供になった原因に遡るストーリーという構想になっている。五月晴れの日、南町奉行のお白洲での取り調べから始まる。そして牢屋敷の敷地にある刑場で斬首されることで終わる。その間に、なぜ25歳の「婉然とした、細く嫋やかといってもいい、美貌の女」お芳こと芳乃が夫の殺害を企てるに至ったかの経緯が芳乃の口から語られるという展開が挟み込まれる。
この白洲での取り調べの状況がそもそも異常なやり方で進む。そこでお咲の夫の叔父にあたる岡田鉄心が巻き込まれていく結果、お咲に悲劇が及ぶ経緯が判明する。
岡田鉄心は奉行から独断で、事前にこの女から夫を殺そうと企てた理由を聞き出し、書面にするように命じられる。幕閣の秘事に関わる可能性があることから、岡田は人払いをして、単独でその女に牢の内外で向かい合い尋問する心づもりだった。だが、牢内に入る羽目になる。女は所持品として持ち込んだ3つのさいころをもてあそんでいて、一、一、一のぞろ目が出たのだ。女は岡田に言う。「ぞろ目の一は、わたしをお聞きになる出目です」、「わたしの話を聞きたいのであれば、まず、わたしをお聞きになって下さいませ」と。香道では、香りを嗅ぐことを聞くという。
芳乃は幼い頃から、すごろくに描かれているものが世界そのものという形で育った。母自体が、奥奉公の出世すごろくを絵に描いたようなあがりの人生を過ごしたのである。奥女中から始め、様々な役職をこなし、さる大名のとの間で芳乃を妊るというあがりを拾ったのである。芳乃は己の「あがり」の人生を常に考える思考法をとるようになる。あがりの人生を手に入れるために、母のように奥奉公をする決意をする。そのあがりが何かは徐々に変化していく。あがりを手に入れるために、奥奉公の一環で付き従った寺参りにおいての秘め事を体験させられる。そこで、あがりへの一歩として、寺参りにかこつけた中で行われる色欲がらみの実態で己が主導権をとるように画策していく。なまめかし香遊びの隠微な実態が描き込まれていく。もちろんそれは香遊びという名を借りた邪道の淫欲世界である。芳乃は、己の才覚で、僧、奥奉公先の役職、勘定方、家老などを次々と籠絡していく。芳乃の考える「あがり」は世間の倫理観からでは途轍もない目標だった。その目標に一歩踏み込む。芳乃にとっては、武家となった商家の男に嫁いだのは、目標のあがりを得る手段だったのだ。そして、芳乃は人生すごろくで、別のあがりに導かれる。
このお咲きの引廻し身代わり編に対する発生原因告白編もまた、「聞く」という行為をキーワードとして、アンチ倫理の世界を著者の想像力と妄想で構想するという試みであろう。フィクションの世界で創作されたこの行為。江戸時代に密かに類似のモデルがあったとしても不思議ではないかもしれない。人間の欲望の限りなさを前提とするならば・・・・・。いずれにしても、その顛末のプロセスはおもしろい。
[別式女、追腹始末]
こちらも連作となる。芳乃が奥奉公で仕えたのがある大名の側妾・お初の方だった。そのお初は女剣術指南役という肩書で景を仕えさせていた。お初は芳乃をこの景が性戯に長けていることを見抜き、籠絡の手段として利用する。芳乃を馴致させるためにお初は景を利用する。だがそれはミイラ取りがミイラになる結果となる。
この景が女剣術指南役となるに至ったかの背景話である。そこに景が性戯に長ける始まりがあった。景の父は高名な剣術家であり、二人の弟子がいる。その弟子たちと景の間の物語から話が始まって行く。その景が追腹を切るという結末となる。誰のために? それは本書をお読み願いたい。短編の中にいわばイレギュラーなセクシュアル・シーンの山場を作っていて、最後は殉ずる一念の行動場面を描く。
「別式女(べつしきめ)」という用語を本書で初めて知った。「刀腰婦(とうようふ)、あるいは帯剣女とも呼ばれる。袴姿で佩刀する、侍の姿をした女のことだ。お歯黒もせず、髪もも結わず総髪にし、男装を平常の出で立ちとして江戸の町を闊歩する。特に奥向きの武芸指南を生業とする者のこと」をいうと著者は説明を記している。
先を知りたくなり一気読みさせられる。艶っぽくてある意味異常な次元を描きあげた作品集である。山科理恵作の挿画が入っている。描かれた女の表情が良い。
ご一読ありがとうございます。
この読後印象記を書き始めた以降に著者の作品を読み、書き込んだのは次の作品です。
こちらもお読みいただけるとうれしいかぎりです。
『光圀伝』 角川書店
『はなとゆめ』 冲方丁 角川書店
『決戦! 大坂城』 葉室・木下・富樫・乾・天野・冲方・伊東 講談社