
本箱に眠っていた本を読んだ。奥書を見れば、2015.5.25付の第7刷である。2015.3.15に第1刷発行とあるので、急激な増刷カーブになる。ウィキペデイアの「又吉直樹」項を読むと、中編小説『火花』は著者にとっては純文学デビューの作品のようだ。単行本発売後、同月内に35万部に達し、単行本の累計発行部数は239万部を突破したという。同年7月に第153回芥川龍之介賞を受賞した。お笑いタレントの純文学作品発表、それが芥川賞を受賞ということとの二重の効果で、爆発的な発売記録冊数を生み出したのだろう。
手許の本は第7刷だが、入手したのは2016年の芥川龍之介賞発表よりも後であり、それからさらに本箱に眠っていた。ひとときのブームとは離れた時点で、遅ればせながら読み始めた。
これには、友人が韓国語の翻訳で読んでおもしろかったという感想を書いているのを読んだことが、本箱での眠りをさまさせるもう一つの動機づけになった。
本書には、お笑い芸人コンビ2組が登場する。一組は「スパークス」という名でコンビを組む僕と山下。僕は徳永という姓である。この徳永の視点からストーリーが綴られていく。もう一組は、「あほんだら」という名でコンビを組む神谷と大林である。だが、山下は、このストーリーでは時折登場するだけ。大林もストーリーの最終コーナーで登場するにとどまる。ストーリーは僕と神谷の関わり方に焦点があたっていく。
このストーリー、熱海湾での花火大会の会場を目指す人々に向けて、スパークスが漫才を披露している-哀しいかな漫才に見向きもされない状況で持ち時間、漫才を披露し続ける-場面描写から始まる。そして、ストーリーの最後は、僕と神谷が花火大会の夜に熱海の旅館に居る場面で終わる。
タイトルの「火花」は、花火の火花、漫才コンビが舞台で生み出す火花、漫才師の内なる情熱、漫才を生み出す火花など、意味合いが重層的だと感じた。直接的には、次の一文が記されている。「今度は巨大な柳のような花火が暗闇に垂れ、細かい無数の火花が捻れながら夜を灯し海に落ちて行くと、一瞬大きな歓声が上がった。・・・・・・そこに人間が生み出した物の中では傑出した壮大さと美しさを持つ花火である。」(p5)の火花だろう。スパークスの僕という存在は、漫才という舞台(花火)の中に咲く無数の火花(コンビ)の一つなのだ。
この花火大会での出演が終わった後、主人公の僕(徳永)は、自分逹「スパークス」より大きな失態を晒す結果となった「あほんだら」の神谷に「取っ払いでギャラ貰ったから呑みに行けへんか?」と誘われた。これが契機となり、この一杯飲みの場で、僕はお笑い芸人として先輩の神谷さんに「弟子にしてください」と頭を下げた。ここに師弟関係が生まれた。ここからストーリーが始まることに。
このストーリーを読み、興味深く、また一方で疑問を持った点がいくつかある。
1.僕と神谷さんは所属する事務所(会社)が異なる。そういう状況で、漫才の世界では師弟関係が実際に成り立つのか? 落語の世界の師弟関係ともまた違うのか?
2.漫才はふつうコンビで成り立つ。ここで描かれる師弟関係は、コンビとしてでなく、個人としての関係性になっている。漫才の世界での師弟関係は、漫才師コンビを師として、漫才コンビで弟子となるという関係ではないのか? 様々な師弟関係がありえるということか。
3.このストーリーでは神谷が大阪弁(たぶん)で語り、僕(徳永)は大阪人であるが標準語で応対するという対話となる。漫才・お笑い芸人の師弟関係で交わされる対話が主体となる。神谷が大阪弁(関西弁)で語り醸し出すニュアンスが、非関西弁の地域の人にどのように、どこまでつたわるのだろうかという興味を抱いた。一方なぜ、大阪人の僕(徳永)は標準語で応対したのかに対する疑問(?)も生まれた。
いわば方言の持つおもしろみと言葉の背景のニュアンスがどれだけ的確に伝達可能性だろうかということへの関心である。大げさかもしれないが、日本語文化圏内のサブ・カルチャ-である方言の異文化コミュニケーションといえるかもしれない。そんな側面に関心を持った。
もし、このストーリーが標準語(?)だけの会話で書かれていたら、賞の対象に入っていただろうか、そんな気さえする。つまり、大阪弁でないと、神谷の存在感とそのおもしろみは表現しづらかったのではないか。
4.序でに、上記3との関わりになるが、大阪弁の会話文の内容をどのように翻訳できるのだろうか。方言が醸し出している雰囲気、方言での表現にまといつく背景がどこまで翻訳に反映できるのだろうか。そんな関心も抱いた。
このストーリー、漫才とは何か? お笑いとは何か? 神谷さんと僕との師弟関係の中で、お笑いの本質論を神谷さんが語り、僕が己の観点で反論したり同意したり・・・・とその経緯を書き止めていく。お笑いの本質とお笑い芸人としての生き様、舞台芸人と実人生の関係、そんな側面に光りが当てられている
。
僕が神谷さんとの最初の出会いで、「俺のことを近くで見てな、俺の言動を書き残して、俺の伝記を作って欲しいねん」(p13)それが師弟関係の契りを結ぶ一つだけの条件となった。このストーリーは、結果的に神谷のお笑い芸人の半生の伝記を描くことになっているという構成である。
面白い会話が出てくる。(p18-19)
「伝記って、その人が死んでから出版するんですよね」
「お前、俺より長生き出来ると思うなよ」
「生前に前編を出版して、死後に中編を出版やな」
「後編気になって、文句出ますよ」
「そんくらいの方が、面白いやんけ」
「お前の言葉で、今日見たことが生きているうちに書けよ」
お笑い芸人としてコンビを組み、舞台に立ち、その浮き沈みの中に身を置いてきた著者の体験・経験・見聞が、ストーリーに色濃く反映されているのだろうという印象を受けた。それ故に、お笑い芸人・漫才師神谷さんが、自分の実人生をも「お笑い」に投げ入れた生き方、その存在をリアルに感じられるのだろうという気がした。
読了後に、ウィキペディアを読み、いくつかの事実を知った。
著者自身、高校時代にサッカー部に属し、インターハイにも出場した経験がある。高校卒業後、1999年にNSC東京校に5期生として入学した。「線香花火」というコンビを組み、M-1グランプリでは準決勝進出まで行ったそうだ、しかし、コンビ解散という経験をしている。その後、綾部祐二に誘われて「ピース」というコンビを組んだ。この作品の発表までに15年ほど、お笑いという世界を経験してきていたのだ。
「お笑い」の世界を観客側から楽しむのではなく、僕(徳永)の視点を仲介にて、演じる側、お笑い芸人そのものの生き様を、読者は垣間見ることになる。興味深くかつ面白かった。
もう一つ加えると、僕と神谷さんが交わすメールのやりとりの文面がおもしろい。それそのものが、芸人センスなのだ。こんなやり取りは例外レベルかと凡人読者としては尋ねたくなる。お笑い芸人さんて、普段でもそんな世界?
本書を読了後なのだが、先日あるテレビ番組を見ていて、最後に神谷さんが、どうせなら面白いやろと思ってやったという姿を、実際に外国人がやってしまっていた!その映像を見て驚いた。発想の原点は全く違うアプローチなのだが、現象面での結果は同じ。小説の中での想像が、既に現実化していた。事実は小説より奇なりを地でいっていた。
神谷さんの発言あるいは姿として記された印象的な文のいくつかをご紹介しておきたい。それが、どんな文脈で語られているかは、148ページというボリュームのこの中編小説をお読みいただきたい。
*漫才師である以上、・・・・あらゆる日常の行動は全て漫才のためにあんねん。・・・・偽りのない純正の人間の姿を晒すもんやねん。つまりは賢い、には出来ひんくて、本物の阿保と自分は真つ当であると信じている阿保によってのみ実現できるもんやねん。 p16
*漫才師はこうあるべきやと語ることと、漫才師を語ることとは、全然違うねん。俺が話しているのは漫才師の話やねん。 p17
(⇒ この後、神谷はボケトとツッコミの具体例を挙げる。)
*一つだけの基準を持って何かを測ろうとすると眼がくらんでまうねん。・・・・創作に携わる人間はどこかで卒業せなあかんやろ。他のもの一切見えへんようになるからな。これは自分に対する戒めやねんけどな。 p32
*だから、唯一の方法は阿保になってな、感覚に正直に面白いかどうかだけで判断したらいいねん。 p34
*だが、一切ぶれずに自分のスタイルを全うする神谷さんを見ていると、随分と自分が軽い人間のように思えてくることがあった。 p79
*せやんな。俺等、そんな器用ちゃうもんな。好きなことやって、面白かったら飯食えて、面白くなかったら淘汰される。それだけのことやろ? p97
*神谷さんが面白いと思うことは、神谷さんが未だ発していない言葉だ。未だ表現していない想像だ。つまりは神谷さんの才能を凌駕したもののみだ。 p114
*俺な、芸人に引退なんてないと思うねん。 p133
僕にとって神谷さんは師と仰ぐ存在だった。だが、僕は己の基軸を揺るがさない。「自分の理想を崩さず、世間の観念とも闘う」(p115)というスタンスである。僕にとっては神谷さんは、師匠であるとともに、己を映し知るための鏡だったのだ。そこから僕(徳永)は己の歩むべき道、一つの方向性を導きだす。
ご一読ありがとうございます。
手許の本は第7刷だが、入手したのは2016年の芥川龍之介賞発表よりも後であり、それからさらに本箱に眠っていた。ひとときのブームとは離れた時点で、遅ればせながら読み始めた。
これには、友人が韓国語の翻訳で読んでおもしろかったという感想を書いているのを読んだことが、本箱での眠りをさまさせるもう一つの動機づけになった。
本書には、お笑い芸人コンビ2組が登場する。一組は「スパークス」という名でコンビを組む僕と山下。僕は徳永という姓である。この徳永の視点からストーリーが綴られていく。もう一組は、「あほんだら」という名でコンビを組む神谷と大林である。だが、山下は、このストーリーでは時折登場するだけ。大林もストーリーの最終コーナーで登場するにとどまる。ストーリーは僕と神谷の関わり方に焦点があたっていく。
このストーリー、熱海湾での花火大会の会場を目指す人々に向けて、スパークスが漫才を披露している-哀しいかな漫才に見向きもされない状況で持ち時間、漫才を披露し続ける-場面描写から始まる。そして、ストーリーの最後は、僕と神谷が花火大会の夜に熱海の旅館に居る場面で終わる。
タイトルの「火花」は、花火の火花、漫才コンビが舞台で生み出す火花、漫才師の内なる情熱、漫才を生み出す火花など、意味合いが重層的だと感じた。直接的には、次の一文が記されている。「今度は巨大な柳のような花火が暗闇に垂れ、細かい無数の火花が捻れながら夜を灯し海に落ちて行くと、一瞬大きな歓声が上がった。・・・・・・そこに人間が生み出した物の中では傑出した壮大さと美しさを持つ花火である。」(p5)の火花だろう。スパークスの僕という存在は、漫才という舞台(花火)の中に咲く無数の火花(コンビ)の一つなのだ。
この花火大会での出演が終わった後、主人公の僕(徳永)は、自分逹「スパークス」より大きな失態を晒す結果となった「あほんだら」の神谷に「取っ払いでギャラ貰ったから呑みに行けへんか?」と誘われた。これが契機となり、この一杯飲みの場で、僕はお笑い芸人として先輩の神谷さんに「弟子にしてください」と頭を下げた。ここに師弟関係が生まれた。ここからストーリーが始まることに。
このストーリーを読み、興味深く、また一方で疑問を持った点がいくつかある。
1.僕と神谷さんは所属する事務所(会社)が異なる。そういう状況で、漫才の世界では師弟関係が実際に成り立つのか? 落語の世界の師弟関係ともまた違うのか?
2.漫才はふつうコンビで成り立つ。ここで描かれる師弟関係は、コンビとしてでなく、個人としての関係性になっている。漫才の世界での師弟関係は、漫才師コンビを師として、漫才コンビで弟子となるという関係ではないのか? 様々な師弟関係がありえるということか。
3.このストーリーでは神谷が大阪弁(たぶん)で語り、僕(徳永)は大阪人であるが標準語で応対するという対話となる。漫才・お笑い芸人の師弟関係で交わされる対話が主体となる。神谷が大阪弁(関西弁)で語り醸し出すニュアンスが、非関西弁の地域の人にどのように、どこまでつたわるのだろうかという興味を抱いた。一方なぜ、大阪人の僕(徳永)は標準語で応対したのかに対する疑問(?)も生まれた。
いわば方言の持つおもしろみと言葉の背景のニュアンスがどれだけ的確に伝達可能性だろうかということへの関心である。大げさかもしれないが、日本語文化圏内のサブ・カルチャ-である方言の異文化コミュニケーションといえるかもしれない。そんな側面に関心を持った。
もし、このストーリーが標準語(?)だけの会話で書かれていたら、賞の対象に入っていただろうか、そんな気さえする。つまり、大阪弁でないと、神谷の存在感とそのおもしろみは表現しづらかったのではないか。
4.序でに、上記3との関わりになるが、大阪弁の会話文の内容をどのように翻訳できるのだろうか。方言が醸し出している雰囲気、方言での表現にまといつく背景がどこまで翻訳に反映できるのだろうか。そんな関心も抱いた。
このストーリー、漫才とは何か? お笑いとは何か? 神谷さんと僕との師弟関係の中で、お笑いの本質論を神谷さんが語り、僕が己の観点で反論したり同意したり・・・・とその経緯を書き止めていく。お笑いの本質とお笑い芸人としての生き様、舞台芸人と実人生の関係、そんな側面に光りが当てられている
。
僕が神谷さんとの最初の出会いで、「俺のことを近くで見てな、俺の言動を書き残して、俺の伝記を作って欲しいねん」(p13)それが師弟関係の契りを結ぶ一つだけの条件となった。このストーリーは、結果的に神谷のお笑い芸人の半生の伝記を描くことになっているという構成である。
面白い会話が出てくる。(p18-19)
「伝記って、その人が死んでから出版するんですよね」
「お前、俺より長生き出来ると思うなよ」
「生前に前編を出版して、死後に中編を出版やな」
「後編気になって、文句出ますよ」
「そんくらいの方が、面白いやんけ」
「お前の言葉で、今日見たことが生きているうちに書けよ」
お笑い芸人としてコンビを組み、舞台に立ち、その浮き沈みの中に身を置いてきた著者の体験・経験・見聞が、ストーリーに色濃く反映されているのだろうという印象を受けた。それ故に、お笑い芸人・漫才師神谷さんが、自分の実人生をも「お笑い」に投げ入れた生き方、その存在をリアルに感じられるのだろうという気がした。
読了後に、ウィキペディアを読み、いくつかの事実を知った。
著者自身、高校時代にサッカー部に属し、インターハイにも出場した経験がある。高校卒業後、1999年にNSC東京校に5期生として入学した。「線香花火」というコンビを組み、M-1グランプリでは準決勝進出まで行ったそうだ、しかし、コンビ解散という経験をしている。その後、綾部祐二に誘われて「ピース」というコンビを組んだ。この作品の発表までに15年ほど、お笑いという世界を経験してきていたのだ。
「お笑い」の世界を観客側から楽しむのではなく、僕(徳永)の視点を仲介にて、演じる側、お笑い芸人そのものの生き様を、読者は垣間見ることになる。興味深くかつ面白かった。
もう一つ加えると、僕と神谷さんが交わすメールのやりとりの文面がおもしろい。それそのものが、芸人センスなのだ。こんなやり取りは例外レベルかと凡人読者としては尋ねたくなる。お笑い芸人さんて、普段でもそんな世界?
本書を読了後なのだが、先日あるテレビ番組を見ていて、最後に神谷さんが、どうせなら面白いやろと思ってやったという姿を、実際に外国人がやってしまっていた!その映像を見て驚いた。発想の原点は全く違うアプローチなのだが、現象面での結果は同じ。小説の中での想像が、既に現実化していた。事実は小説より奇なりを地でいっていた。
神谷さんの発言あるいは姿として記された印象的な文のいくつかをご紹介しておきたい。それが、どんな文脈で語られているかは、148ページというボリュームのこの中編小説をお読みいただきたい。
*漫才師である以上、・・・・あらゆる日常の行動は全て漫才のためにあんねん。・・・・偽りのない純正の人間の姿を晒すもんやねん。つまりは賢い、には出来ひんくて、本物の阿保と自分は真つ当であると信じている阿保によってのみ実現できるもんやねん。 p16
*漫才師はこうあるべきやと語ることと、漫才師を語ることとは、全然違うねん。俺が話しているのは漫才師の話やねん。 p17
(⇒ この後、神谷はボケトとツッコミの具体例を挙げる。)
*一つだけの基準を持って何かを測ろうとすると眼がくらんでまうねん。・・・・創作に携わる人間はどこかで卒業せなあかんやろ。他のもの一切見えへんようになるからな。これは自分に対する戒めやねんけどな。 p32
*だから、唯一の方法は阿保になってな、感覚に正直に面白いかどうかだけで判断したらいいねん。 p34
*だが、一切ぶれずに自分のスタイルを全うする神谷さんを見ていると、随分と自分が軽い人間のように思えてくることがあった。 p79
*せやんな。俺等、そんな器用ちゃうもんな。好きなことやって、面白かったら飯食えて、面白くなかったら淘汰される。それだけのことやろ? p97
*神谷さんが面白いと思うことは、神谷さんが未だ発していない言葉だ。未だ表現していない想像だ。つまりは神谷さんの才能を凌駕したもののみだ。 p114
*俺な、芸人に引退なんてないと思うねん。 p133
僕にとって神谷さんは師と仰ぐ存在だった。だが、僕は己の基軸を揺るがさない。「自分の理想を崩さず、世間の観念とも闘う」(p115)というスタンスである。僕にとっては神谷さんは、師匠であるとともに、己を映し知るための鏡だったのだ。そこから僕(徳永)は己の歩むべき道、一つの方向性を導きだす。
ご一読ありがとうございます。















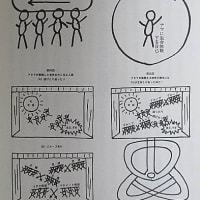




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます