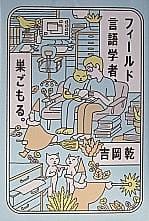
タイトルが面白そうなので手に取った。「フィールド言語学者」というコトバがそもそも初めて目にした語句である。それに「巣ごもる」というコトバがくっつぃている。なんだろう・・・・・という好奇心。面白くなければ、辞めればいいと、そんな軽い気持ちで読み始めた。
「言語学」という研究分野に絡めたエッセイ集だった。重たくなりそうなことが、結構かろやかなタッチで書かれているところがおもしろい。著者がこのエッセイ集について自己説明している。それをまず紹介しておこう。
「フィールド言語学者である僕が、高尚さのかけらもなしに、そんなふうに言語学目線で漫(そぞ)ろに思った日々のアレコレを詰め込んだ一冊となっている」(まえがき、p3)
「ことあらば脱線し、あれよあれよと無駄話をする、微熱に浮かされたようにだらっとした語り口のエッセイで、こっそり言語学についての話をする書籍があっても良いのではないかと思う。心への負担が少ない、魘(うな)されない『隠れ入門書』である。」(まえがき、p5)
「本書は平たいものから小難しいものまで、つらつらと言語に関連して考えたエッセイを集めたものとなっている。・・・・さらっとしたものもあれば、ごてっとしたものもある。」(あとがき、p268)
読み返してみると、ナルホドそうだなと思う。
フィールド研究者が、コロナ禍でフィールドに出られなくなった。テレワークも推奨される中で「巣ごもり」して、そこで書き出したエッセイだという。
「まえがき」「目次」の次に、見開きのページで「ざっくり言語学マップ」が模式図として載っている。左から「他の学問との結び付き」「言語をどう考えるか」「言語の何を考えるか」という大括りの研究領域が横に並び、その右下に「どんな言語データから考えるか」という研究領域を位置づけると言う形で図式化されている。そしてそれぞれの領域に細分化された研究分野の名称が記されている。たとえば、「言語をどう考えるか」という領域の中には、理論言語学・比較言語学・歴史言語学・対照言語学があり、左の領域と跨がるところに認知言語学・計算言語学があり、右の領域と跨がるところに記述言語学・類型論があるという。
「どんな言語データから考えるか」の領域に、コーパス言語学とフィールド言語学という分野があるそうだ。著者はその中のフィールド言語学の研究者だという。なんと2003年から「ブルシャスキー語」の研究を始めて現在に至るとのこと。私には全く初めて知る言語名である。パキスタンの山奥で話されている言語らしい。著者はこれといって日本人による研究はなさそうだというところから研究対象に選んだそうである。これもエッセイの一つのネタになっていて、おもしろい。
このエッセイ集、その内容が、まさに四方八方へと飛んだり脱線しながらも、全体を眺めると上記のマップと大凡対応する形で、読み進める間に言語学の研究分野の入口に誘うアプローチとなっている。その研究分野がどんなことをしているのか垣間見させてくれる。エッセイのネタはごく身近な言語データが取り込まれ、話の風呂敷を広げていく形になっている。そのネタが実にバラエティに富んでいるので、飽きることはない。
本書のカバーには擬人化した猫が描かれているが、「喋る猫のファンタジー」というエッセイがある。古今東西の猫の言語の研究なるものを列挙紹介した上で、猫が人語を話せるかを解剖学的に論じている。ここのアプローチには、実は「音声学・生物学」が絡んでいるという次第。
「日常をフィールド言語学する」というエッセイは、「フィールド言語学・個人語」という視点でのアプローチでありおもしろい。「フィールド言語学というのは、言語使用の現場(フィールド)でネタを見付けて、言語学的に考えるというだけだし、言語学なんてのは単に、科学的に言語を考察するだけなんだから、身構える必要などないのである。」(p78)という軽いのりで始まる。そして、ゲーム実況動画の「『違かった』の字幕」や様々な漫画のコマの吹き出しのコトバ「・・・・なんか 遠くないすかアレ」「あつ 遠くて」「七海先輩のこと すごい好きですよね」「それは 言えないですけど」がネタ(言語データ)として使われて、言語変化の現状を分析し論じている。私はこのエッセイで初めて、この動画や諸漫画のことを知った。そして、「僕は言語学者であって、国語の先生ではないので、こうやってナウいメディアに触れて言語を楽しめる」「我々は、常に言語の現場(フィールド)に生きているのだ。」(p89)という。国語の次元と言語学の次元とは言語に対するスタンスが異なるようだ。興味深い。
「例のあのお方」というエッセイは、ハリー・ポッターをネタに取り上げる。第1巻が諸外国語に翻訳されていて、著者は53言語への翻訳本を蒐集したという。日本語版の「例のあのお方」、元の英語では「You-Know-Who」の箇所が、各言語への翻訳ではどう訳出されているかを紹介し、また、「ハーマイオニー」「ロン」「スネイプ」など個々のキャラ名の翻訳のしかたにも触れていく。このエッセイ、「敬語・借用語・音韻論」という視点での説明事例になっているのだ。
最後から2つめの「日本語はこんなにも特殊だった」(類型論)というエッセイでは、日本語が特殊かどうかを科学的に論じている。おもしろい切り口である点はまちがいない。
このエッセイ集の構成について、著者は「まえがき」で触れている。「読者諸氏の心的負担軽減のために便宜として、各節を(客観性の乏しい)小難しさ度に準じて並べてある。『読みながら慣れていってね』という構成だ」(p5)と。
ページを追う形で読み進めて行った。やはりそれが順当の流れと言えそうである。
各エッセイにはかなり細かくふんだんに註釈が付けられている。これはまあ読者の興味度合いで深入りするか、スルーするか、多分ご自由に・・・ということだろう。単なるエッセイストではなく、フィールド言語学者の立場で註釈しているということとみた。私はスルー気味で拾い読み程度にとどまった。
末尾には、「言語解説」として言語名が7ページに渡って列挙解説されている。アイスランド語から始まり、ワヒー語まで。何と大半が初めて目にする言語名である。地球上には多くの言語があるのだなあ・・・・と思う。
このご紹介の冒頭当たりでお気づきかもしれないが、著者はエッセイ中に意図的にあまり見かけない漢字での表記を織り交ぜているのかな・・・・と感じるところがあった。一般的なエッセイならたぶん漢字表記をしないですますか言い回しを替えるかもしれないなと思うところに、ルビ付きで漢字が使われている。フィールド言語学者の言語データ蒐集の一環なのだろうか。それとも衒学(げんがく)的に使っているのか(この衒学的は「まえがき」に出てくる)、あるいは趣味的な表記なのか・・・・・。いずれにしても私にとっては漢字の使用がおもしろいので、本書の前半部分から上記中のものとは重ならない形で拾い出してみた。勿論、このエッセイの本質とは関係がない。
憖(なまじ)っか/ 然々(しかじか)/ スーパーコンピューター宛(さながら)に
ページを捲(めく)って/ 苟且(かりそめ)にも/ 宥(なだ)め賺(すかし)したり
打(ぶ)ってくれ/ 見付物(みっけもの)/ 夢想に中(あ)てられて/ 齷齪(あくせく)
折角(せっかく)/ 作用を齎(もたら)すもの/ 袖珍(しゅうちん)辞書
躓(つまづ)く/ 門戸は鎖(とざ)され/ 孜々汲々(ししきゅうきゅう)
寧(むし)ろ/ 頓珍漢(とんちんかん)/ 下種(げす)/ 論(あげつら)って
発想を振り翳(かざ)して/ 寧(むし)ろ/ 憚(はばか)らず/ 弥増(いやま)させる
狷介不羈(けんかいふき)/ 侃々諤々喧々囂々(かんかんがくがくけんけんごうごう)/
嘘だって吐(つ)ける/ 転(まろ)び出て/ 嘯(うそぶ)く輩/ 攷究(こうきゅう)
食(は)み出して/ 徐(おもむろ)に/ 迂言(うげん)する/ 打切棒(ぶきらぼう)
これは言語学とは関係なく、単に国語次元で漢字を知らない私の感想・・・・・である。
さらりと読み通したにとどまるが、けっこう投げ出すことなく飽きずに楽しめた。
言語学の入口の香りを少し感じることはできたような・・・・・そんな気がする。
各エッセイには各末尾に執筆時期が記されている。本書は2021年6月に刊行された。
ご一読ありがとうございます。
本書に関連して、関心事項の一端をネット検索した。一覧にしておきたい。
ブルシャスキー語 :ウィキペディア
ブルシャスキー語 :「コトバンク」
言語学 :「コトバンク」
言語学 :ウィキペディア
第1回 フィールドワーカーの苦悩:フィールド言語学とは何か :「Word-Wise Web」
言語学とフィールドワーク 内海敦子 ことばと文化のミニ講座 :「明星大学」
コーパス言語学 :「コトバンク」
理論言語学 :「株式会社 篠研」
社会言語学 :「コトバンク」
ハリー・ポッターシリーズ :ウィキペディア
Harry Potter From Wikipedia, the free encyclopedia
認め難い「違くて」「違かった」 :「毎日ことば」
「違かった」を聞いたことがありますか? :「日本語センター」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
「言語学」という研究分野に絡めたエッセイ集だった。重たくなりそうなことが、結構かろやかなタッチで書かれているところがおもしろい。著者がこのエッセイ集について自己説明している。それをまず紹介しておこう。
「フィールド言語学者である僕が、高尚さのかけらもなしに、そんなふうに言語学目線で漫(そぞ)ろに思った日々のアレコレを詰め込んだ一冊となっている」(まえがき、p3)
「ことあらば脱線し、あれよあれよと無駄話をする、微熱に浮かされたようにだらっとした語り口のエッセイで、こっそり言語学についての話をする書籍があっても良いのではないかと思う。心への負担が少ない、魘(うな)されない『隠れ入門書』である。」(まえがき、p5)
「本書は平たいものから小難しいものまで、つらつらと言語に関連して考えたエッセイを集めたものとなっている。・・・・さらっとしたものもあれば、ごてっとしたものもある。」(あとがき、p268)
読み返してみると、ナルホドそうだなと思う。
フィールド研究者が、コロナ禍でフィールドに出られなくなった。テレワークも推奨される中で「巣ごもり」して、そこで書き出したエッセイだという。
「まえがき」「目次」の次に、見開きのページで「ざっくり言語学マップ」が模式図として載っている。左から「他の学問との結び付き」「言語をどう考えるか」「言語の何を考えるか」という大括りの研究領域が横に並び、その右下に「どんな言語データから考えるか」という研究領域を位置づけると言う形で図式化されている。そしてそれぞれの領域に細分化された研究分野の名称が記されている。たとえば、「言語をどう考えるか」という領域の中には、理論言語学・比較言語学・歴史言語学・対照言語学があり、左の領域と跨がるところに認知言語学・計算言語学があり、右の領域と跨がるところに記述言語学・類型論があるという。
「どんな言語データから考えるか」の領域に、コーパス言語学とフィールド言語学という分野があるそうだ。著者はその中のフィールド言語学の研究者だという。なんと2003年から「ブルシャスキー語」の研究を始めて現在に至るとのこと。私には全く初めて知る言語名である。パキスタンの山奥で話されている言語らしい。著者はこれといって日本人による研究はなさそうだというところから研究対象に選んだそうである。これもエッセイの一つのネタになっていて、おもしろい。
このエッセイ集、その内容が、まさに四方八方へと飛んだり脱線しながらも、全体を眺めると上記のマップと大凡対応する形で、読み進める間に言語学の研究分野の入口に誘うアプローチとなっている。その研究分野がどんなことをしているのか垣間見させてくれる。エッセイのネタはごく身近な言語データが取り込まれ、話の風呂敷を広げていく形になっている。そのネタが実にバラエティに富んでいるので、飽きることはない。
本書のカバーには擬人化した猫が描かれているが、「喋る猫のファンタジー」というエッセイがある。古今東西の猫の言語の研究なるものを列挙紹介した上で、猫が人語を話せるかを解剖学的に論じている。ここのアプローチには、実は「音声学・生物学」が絡んでいるという次第。
「日常をフィールド言語学する」というエッセイは、「フィールド言語学・個人語」という視点でのアプローチでありおもしろい。「フィールド言語学というのは、言語使用の現場(フィールド)でネタを見付けて、言語学的に考えるというだけだし、言語学なんてのは単に、科学的に言語を考察するだけなんだから、身構える必要などないのである。」(p78)という軽いのりで始まる。そして、ゲーム実況動画の「『違かった』の字幕」や様々な漫画のコマの吹き出しのコトバ「・・・・なんか 遠くないすかアレ」「あつ 遠くて」「七海先輩のこと すごい好きですよね」「それは 言えないですけど」がネタ(言語データ)として使われて、言語変化の現状を分析し論じている。私はこのエッセイで初めて、この動画や諸漫画のことを知った。そして、「僕は言語学者であって、国語の先生ではないので、こうやってナウいメディアに触れて言語を楽しめる」「我々は、常に言語の現場(フィールド)に生きているのだ。」(p89)という。国語の次元と言語学の次元とは言語に対するスタンスが異なるようだ。興味深い。
「例のあのお方」というエッセイは、ハリー・ポッターをネタに取り上げる。第1巻が諸外国語に翻訳されていて、著者は53言語への翻訳本を蒐集したという。日本語版の「例のあのお方」、元の英語では「You-Know-Who」の箇所が、各言語への翻訳ではどう訳出されているかを紹介し、また、「ハーマイオニー」「ロン」「スネイプ」など個々のキャラ名の翻訳のしかたにも触れていく。このエッセイ、「敬語・借用語・音韻論」という視点での説明事例になっているのだ。
最後から2つめの「日本語はこんなにも特殊だった」(類型論)というエッセイでは、日本語が特殊かどうかを科学的に論じている。おもしろい切り口である点はまちがいない。
このエッセイ集の構成について、著者は「まえがき」で触れている。「読者諸氏の心的負担軽減のために便宜として、各節を(客観性の乏しい)小難しさ度に準じて並べてある。『読みながら慣れていってね』という構成だ」(p5)と。
ページを追う形で読み進めて行った。やはりそれが順当の流れと言えそうである。
各エッセイにはかなり細かくふんだんに註釈が付けられている。これはまあ読者の興味度合いで深入りするか、スルーするか、多分ご自由に・・・ということだろう。単なるエッセイストではなく、フィールド言語学者の立場で註釈しているということとみた。私はスルー気味で拾い読み程度にとどまった。
末尾には、「言語解説」として言語名が7ページに渡って列挙解説されている。アイスランド語から始まり、ワヒー語まで。何と大半が初めて目にする言語名である。地球上には多くの言語があるのだなあ・・・・と思う。
このご紹介の冒頭当たりでお気づきかもしれないが、著者はエッセイ中に意図的にあまり見かけない漢字での表記を織り交ぜているのかな・・・・と感じるところがあった。一般的なエッセイならたぶん漢字表記をしないですますか言い回しを替えるかもしれないなと思うところに、ルビ付きで漢字が使われている。フィールド言語学者の言語データ蒐集の一環なのだろうか。それとも衒学(げんがく)的に使っているのか(この衒学的は「まえがき」に出てくる)、あるいは趣味的な表記なのか・・・・・。いずれにしても私にとっては漢字の使用がおもしろいので、本書の前半部分から上記中のものとは重ならない形で拾い出してみた。勿論、このエッセイの本質とは関係がない。
憖(なまじ)っか/ 然々(しかじか)/ スーパーコンピューター宛(さながら)に
ページを捲(めく)って/ 苟且(かりそめ)にも/ 宥(なだ)め賺(すかし)したり
打(ぶ)ってくれ/ 見付物(みっけもの)/ 夢想に中(あ)てられて/ 齷齪(あくせく)
折角(せっかく)/ 作用を齎(もたら)すもの/ 袖珍(しゅうちん)辞書
躓(つまづ)く/ 門戸は鎖(とざ)され/ 孜々汲々(ししきゅうきゅう)
寧(むし)ろ/ 頓珍漢(とんちんかん)/ 下種(げす)/ 論(あげつら)って
発想を振り翳(かざ)して/ 寧(むし)ろ/ 憚(はばか)らず/ 弥増(いやま)させる
狷介不羈(けんかいふき)/ 侃々諤々喧々囂々(かんかんがくがくけんけんごうごう)/
嘘だって吐(つ)ける/ 転(まろ)び出て/ 嘯(うそぶ)く輩/ 攷究(こうきゅう)
食(は)み出して/ 徐(おもむろ)に/ 迂言(うげん)する/ 打切棒(ぶきらぼう)
これは言語学とは関係なく、単に国語次元で漢字を知らない私の感想・・・・・である。
さらりと読み通したにとどまるが、けっこう投げ出すことなく飽きずに楽しめた。
言語学の入口の香りを少し感じることはできたような・・・・・そんな気がする。
各エッセイには各末尾に執筆時期が記されている。本書は2021年6月に刊行された。
ご一読ありがとうございます。
本書に関連して、関心事項の一端をネット検索した。一覧にしておきたい。
ブルシャスキー語 :ウィキペディア
ブルシャスキー語 :「コトバンク」
言語学 :「コトバンク」
言語学 :ウィキペディア
第1回 フィールドワーカーの苦悩:フィールド言語学とは何か :「Word-Wise Web」
言語学とフィールドワーク 内海敦子 ことばと文化のミニ講座 :「明星大学」
コーパス言語学 :「コトバンク」
理論言語学 :「株式会社 篠研」
社会言語学 :「コトバンク」
ハリー・ポッターシリーズ :ウィキペディア
Harry Potter From Wikipedia, the free encyclopedia
認め難い「違くて」「違かった」 :「毎日ことば」
「違かった」を聞いたことがありますか? :「日本語センター」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます