
『遊心逍遙記』として読後印象を書き始める少し前に、著者の『臨床真理』と『最後の証人』を読んでいた。そして、『検事の本懐』を未読のままで、この『検事の死命』を読む事になってしまった。
検察官佐方貞人が主人公の本作品、どこかで記憶がある名前だなと振り返ると、『最後の証人』の主人公、あの信念の弁護士佐方その人だった。
『最後の証人』では、「法を犯すのは人間だ。検察官を続けるつもりなら、法よりも人間を見ろ」「どのような理由であれ、罪は罪として償わなければならない。しかし、まっとうに裁くということは、事件の裏側にある悲しみ、苦しみ、葛藤、すべてを把握していなければ出来ないことなのではないか。行動の裏に理由があるように、事件には動機がある。そこにある感情を理解していなければ、本当の意味で罪を裁くことにはならないのではないか。」こんな文章を読後メモとして抜き書きしていた。特に印象深い文章だったからだ。
本書には4つの作品が収められている。それらはヤメ検弁護士佐方貞人が検事の時代だったころの活動を扱った作品群である。『検事の本懐』に続くようだ。私のよくやることだが、今回も順序逆に読み進める結果になった。いずれ『検事の本懐』の読了後にその印象をまとめるとして、まずは本書についての印象をまとめてみたい。
本書は米崎県米崎市に所在する米崎地検に配属された刑事部の担当検察官佐方貞人が主人公であり、彼のサポート役として検察事務官増田陽二が准主人公的な役割で登場する。 本書の4つの短編の主な登場人物が同じである。それぞれが独立した作品であるとともに、その作品のどこかに他作品への連接点が含まれている。それは主な主人公たちを多面的にステージを変えて描くことになる。そのため、特に主人公左方貞人の人物像に奥行きと深みを与えることになる。
収められた4つの作品とは「心を掬う」「業をおろす」「死命を賭ける」「死命を決する」である。最初の2作は全く独立した短編として読める。尚、「業をおろす」には本書の内タイトルページの下に編集者の注記が付されている。後で触れよう。
後の2作はそれぞれ独立した短編であるが、どちらかと言えばこの2作を一つの中編としてとらえる方が私にはスッキリする。まさに「検事の死命」という作品という意味である。それは短編に付された副題でもみることができる。独立した短編とみると、「死命を賭ける」の終わり方がすこし心残りな要素を含んだものにとどまるのだ。それはアメリカ映画において、連作を想定されている時のエンディングの手法に似ている要素が入っているからそう感じるのだろう。
「死命を賭ける」は「死命」と考える事案解決に取り組む刑事部ステージを扱う。副題が「『死命』刑事部編」である。「死命を決する」は同様に「『死命』公判部編」であり、公判部ステージを取り扱う展開となっている。左方検事が刑事部から公判部に横異動して、同じ案件を立場をステップアップして関わって行くという設定である。
検察官左方貞人の信念は「ここで屈したら--たとえ検察にいられたとしても、検事としては死んだも同然です」(p220)という基盤に立ち、検事という職分が生きるか死ぬかという「検事の死命を賭ける」(p220)という意識で法と罪に取り組むことにある。そして、増田が代弁する「わかっています。自分たちの仕事は罪をまっとうに裁くことであり、罪はまっとうに裁かれなければいけない、そう思います」という思いにある。さらに、それは左方の上司・刑事部副部長の筒井が発するつぶやきに通底するのだ。「秋霜烈日の白バッジを与えられている俺たちが、権力に屈したらどうなる。世の中は、いったい何を信じればいい」(p226)
連作作品のそれぞれについて、印象を少しまとめてご紹介してみよう。
《 心を掬う 》
この短編は郵便物紛失事件を取り扱ったもの。酒処ふくろうという飲み屋の親父が、「知り合いの常連客が北海道にいる娘に出した郵便が届かない」ということをふと話題にする。その後、増田と同じ検察事務官が増田に対し、自分が親戚筋から聞いた手紙が届かないという同種の事例を語るのだ。この話を増田が左方検事に伝える。すると、少し考えにふけった後で左方が増田に指示する。「二件の郵便物の宛先、いつ、どこの郵便局またはポストに投函したのかなど、調べてほしいんです」と。 警察から送致されてきた案件ではない。「なにか考えがあるとはいえ、郵便物の紛失話を急いで調べなければいけない理由が、増田にはわからない」。左方検事がトリガーを引いた事案がここから始まる。それが米崎中央郵便局の郵政監察官の懸案事項と思いにリンクしていく。一方左方が増田に出した指示は、手紙に関連した学生時代の思いが底流にあったのだ。
左方は思わぬ手段を密かに実行する。また、そこまで検事が現場に踏み込んで行動するのかと、増田を感動させるシーンに展開していく。この展開への発想に意外性があり、おもしろく、読ませどころである。
やはり、本作品のキーセンテンスは次の言葉である。
「私たちが扱っているのは単なる紙きれではありません。人の気持ち、心です」
こう福村郵政監察官が検事室のソファでつぶやいたのだ。
《 業をおろす 》
本短編は、『検事の本懐』に収録の「本懐を知る」の完結編にあたると内タイトルの下に編集部が付記している。この前作を読んでいなくても、独立した短編として十分に読み応えがあった。この作品だけの世界でも十分に感情移入してしまい涙を誘発させる作品となっている。付記には「『本懐を知る』読了後の方が一段と興趣が増すと考えております」と併記されている。この点はいずれ逆読みすることで、付記通りの順番で読む方がやはり一層よかったのかどうか、確認してみたい。
さて本作品の時期設定は、左方が故郷である広島の県北に位置する次原市山田町に6年ぶりにお盆に帰郷したときである。テーマは亡き父親の選択した行為・道の真実が解明されるということにある。
左方貞人は父・陽世の十三回忌法要のために帰郷する。菩提寺である曹洞宗龍円寺の住職は父陽世のおさな友達でもあった。貞人の父陽世は弁護士であり、顧問先の会社の会長小田嶋隆一朗の遺志で、小田嶋家の遺産を管理していた。しかし、その資産を横領した罪に問われ実刑判決を受け、黙って実刑を受け入れるという行動を選択したのだ。その父が服役中に膵臓癌で死亡する。貞人が高校2年生のときである。
法律の道に進み、検事となった貞人には、横領の発覚時点で金をすべて返済すれば、普通は執行猶予がつき、実刑を受けなくてもよいということを知る。弁護士の父がそれを知らぬはずがないと判断する。父は裁判の判決が出たあとに、現に金を返済しているのだ。
龍円寺の住職(人々から龍円さんと呼ばれている)なら、貞人の父がまるで罰せられることを望んでいたようにも思えるその理由を親友として知っているのではないか・・・・と思い、龍円に尋ねようとする。その場では龍円は答えず話をそらしてしまう。
十三回忌の法要の中で、龍円がもう陽世の業をおろしてもよい時期だろうと語り、ごく最近龍円が知り得た真実を法要の場で明らかにする。こんな流れでストーリーが展開する。弁護士の役割・立場、恩義、己の信念などが複雑に絡まり合っていく。読み応えのある作品に仕上がっている。
龍円は法要の最後に真実を語った後、大愚良寛の残した詩句を語る。
「君看よや 双眼の色 語らざれば 憂いなきに似たり」
この句は「この私の目を見てくれ。何もかたらないからといって、心に何もないわけではないのだ」という意味だと龍円は説いている。そして言う。「・・・・事のすべてを知り陽世の真情を知ったわしとしては、あいつが現世で誤解されたままでいるのが苦しゅうて苦しゅうて、かなわんかったのです」と。(p141)
貞人が龍円に返す言葉もよい。左方貞人らしい。
「父は父のやり方で、自分の仕事をやり遂げました。私は私のやり方で、自分の仕事をするだけです」(p143)
《死命を賭ける [死命」刑事部編》
《死命を決する 「死命」公判部編》
この連作では、検事が抱える幅広い事案件数の重圧下でみれば、一見取るに足りない小さな事案である。極端に言えば、さらりと判断し処理してしまえる案件だ。しかし、その案件をでんと据えて、左方にその案件を真っ向から取り組ませていく。この作品で検事の職分は何かを著者は問いかけている。そこにテーマがあると感じる。
左方に配点されてきた案件の一つは、痴漢行為の案件である。
1.案件内容 満員電車の中で衣服の上から身体を触ったとされる痴漢行為
それはその程度から、迷惑防止条例違反が適用される案件。
強制わいせつ罪レベルに至らない程度のある意味軽いものである。
2.被疑者 武本弘敏、43歳。会社員、地元の大手予備校勤務で経理課長。
武本は職場恋愛の上で、婿入りした男。その結果、県内の名門一族の係累になる。
義母は県内有数の資産家一族本多家の四女。義父は元教育長で地元で有名な教育者
本多家は政財界に様々な伝手と影響力をもつ地元の名家、有力者の一族。
3.被害者 仁藤玲奈、米崎市内の高校生、17歳。母子家庭という家庭環境に育つ。
万引きと恐喝で補導されたという前歴を持つ少女。
4.問題点 武本は左方検事に対し、送致事実に意義を唱える。
「もちろんです。私は少女の身体に触れてなどいない。痴漢なんかしていません!」 「・・・・・・正確には覚えていませんが、もうあんたはおしまいだ、とも言いました。
でも--と、少女はそのあとすぐ、わたしの耳元で囁いたんです。
お金を払えばなかったことにしてやる、と」
主張は真っ向から対立する。どちらかが偽証している。名門の係累に繋がる被疑者を無実にするために、上層部や政治家までがこの事案に圧力をかけてくることになる。
左方はこの案件の送致事実の確認から始め、起訴状を提出する決断を下す。そのプロセスを扱ったのが前半の刑事部編である。罪があれば、その罪を正しく裁く、案件の大小・軽重ではない、勿論、検事としての出世欲や外部からの圧力に屈することがあってはならない。検事社会における赤レンガ族と現場派という2つの潮流の確執の存在もそれとなく巧みに組み込まれていく。だが検事の死命の受け止め方が根本なのだ。左方の本領が発揮される。
検事には送致案件を立件起訴するかどうか決定する役割と、裁判所で刑事罰を告訴し弁護士との対立論争の中で罪の存在を証明する役割との2つのステージに分担されている。前者が刑事部のステージであり、後者が公判部のステージである。
左方は上司の筒井と同時期に刑事部から公判部に米崎地検内で横異動する。そして、刑事部の担当検察官として自分が起訴状を出したこの痴漢行為案件を、公判部の検事として裁判所の法廷の場で、告訴して弁護士と論争し、罪の立証する役割を担っていく。左方の検事人生が、刑事部から公判部へとステージが変わる。
「死命を決める」の読みどころは痴漢行為をどのように立証していくか、その立証のために左方がどういう行動を重ねていくか、そして己の確信を揺るぎない事実として証拠の列挙と論理で構築していくかにある。
武本には、本多家が後ろに控え、その顧問弁護士であり、米澤県下では大物弁護士、やり手と呼ばれる井原である。さらに、本多家が政界との伝手と影響力を行使して、地検や県警などの上層部にさまざまな形で圧力をかけてくる可能性がある。井原弁護士はあらゆる手段を使って、被告人の無罪を勝ち取りに出る。
「井原法令綜合事務所が県下最大の弁護士事務所たり得た理由は、徹底して準備を怠らない用意周到な法廷戦略にある。法に触れない限り、どんな手を使ってでも、依頼人有利の判決に導く。それが井原のポリシーだ。」(p241)
武本は勾留延長が決まったあとの井原弁護士との接見において、井原に頼む。
「もしかしたら、半田という男が裁判の証人になってくれるかもしれません。」
半田は飲み屋で知り合った男であり、事件当日、満員電車に偶然乗り合わせ、自分のすぐそばにいたのだという。その飲み屋があどういう店か井原は武本に尋ねるが、守秘義務のある弁護士の井原に対しても、武本は勘弁してくれと言い、明かさない。半田とコンタクトをとった井原は半田を最後の切り札として使えると判断する。そして、周到な裁判戦略を構築していく。
この半田が意外な裁判闘争の意外な展開の焦点となっていく。実におもしろい。
裁判のプロセスの検事と弁護士の対立論争のプロセスの展開の巧みさがこの種の作品の読ませどころである。どれだけリアルに、論理的に緻密に対立点を明瞭にさせ、立証過程のどこで一転して惨敗するかもしれないという危機感を漂わせるか・・・・その論争プロセスに読者が予期しない展開なり、論理構成の導入があるほど、おもしろい。本書は十分にこの裁判闘争のプロセスを堪能させてくれる。たかが軽い痴漢行為の罪状立証プロセスだが、されど厳しい罪状立証プロセスなのだ。読み応えがある作品にまとまっている。
『検事の本懐』は未読であるが、今後著者はヤメ検弁護士左方貞人シリーズを執筆展開するのか、検事時代の左方貞人の活躍も並行させるのか。いずれにしても、左方シリーズが続くことを期待したい。
ご一読ありがとうございます。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
本書に関連する語句をいくつか調べてみた。一覧にしておきたい。
郵政監察官 ← 郵政監察制度 :ウィキペディア
刑事訴訟法 :「RONの六法全書 on LINE」
60条1,3項を参照ください。
検察官バッジ
検察官の付けているバッジ Q&Aコーナー :「検察庁」
左欄から「Q&Aコーナー」を選び、「その他」の分類に説明あり。
検察事務官バッジで語る役割の重要性 :「釧路地方検察庁」
弁護士のバッジ :「日本弁護士連合会」
違法収集証拠排除原則 ← 違法収集証拠排除法則 :ウィキペディア
令状主義 → 被疑者の権利-令状主義 :「日本国憲法の基礎知識」
横領罪 :ウィキペディア
迷惑防止条例 :ウィキペディア
京都府迷惑行為防止条例 :「京都府」
第3条(卑わいな行為の禁止)
強制わいせつ罪 :「司法試験用 刑事法 対策室」
十王図 10幅 :「奈良国立博物館」
ああ恐ろしや十王図 霊巌寺所蔵
ジャクソン・ポロック :「ヴァーチャル絵画館」
カーゴ・パンツ :ウィキペディア
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
検察官佐方貞人が主人公の本作品、どこかで記憶がある名前だなと振り返ると、『最後の証人』の主人公、あの信念の弁護士佐方その人だった。
『最後の証人』では、「法を犯すのは人間だ。検察官を続けるつもりなら、法よりも人間を見ろ」「どのような理由であれ、罪は罪として償わなければならない。しかし、まっとうに裁くということは、事件の裏側にある悲しみ、苦しみ、葛藤、すべてを把握していなければ出来ないことなのではないか。行動の裏に理由があるように、事件には動機がある。そこにある感情を理解していなければ、本当の意味で罪を裁くことにはならないのではないか。」こんな文章を読後メモとして抜き書きしていた。特に印象深い文章だったからだ。
本書には4つの作品が収められている。それらはヤメ検弁護士佐方貞人が検事の時代だったころの活動を扱った作品群である。『検事の本懐』に続くようだ。私のよくやることだが、今回も順序逆に読み進める結果になった。いずれ『検事の本懐』の読了後にその印象をまとめるとして、まずは本書についての印象をまとめてみたい。
本書は米崎県米崎市に所在する米崎地検に配属された刑事部の担当検察官佐方貞人が主人公であり、彼のサポート役として検察事務官増田陽二が准主人公的な役割で登場する。 本書の4つの短編の主な登場人物が同じである。それぞれが独立した作品であるとともに、その作品のどこかに他作品への連接点が含まれている。それは主な主人公たちを多面的にステージを変えて描くことになる。そのため、特に主人公左方貞人の人物像に奥行きと深みを与えることになる。
収められた4つの作品とは「心を掬う」「業をおろす」「死命を賭ける」「死命を決する」である。最初の2作は全く独立した短編として読める。尚、「業をおろす」には本書の内タイトルページの下に編集者の注記が付されている。後で触れよう。
後の2作はそれぞれ独立した短編であるが、どちらかと言えばこの2作を一つの中編としてとらえる方が私にはスッキリする。まさに「検事の死命」という作品という意味である。それは短編に付された副題でもみることができる。独立した短編とみると、「死命を賭ける」の終わり方がすこし心残りな要素を含んだものにとどまるのだ。それはアメリカ映画において、連作を想定されている時のエンディングの手法に似ている要素が入っているからそう感じるのだろう。
「死命を賭ける」は「死命」と考える事案解決に取り組む刑事部ステージを扱う。副題が「『死命』刑事部編」である。「死命を決する」は同様に「『死命』公判部編」であり、公判部ステージを取り扱う展開となっている。左方検事が刑事部から公判部に横異動して、同じ案件を立場をステップアップして関わって行くという設定である。
検察官左方貞人の信念は「ここで屈したら--たとえ検察にいられたとしても、検事としては死んだも同然です」(p220)という基盤に立ち、検事という職分が生きるか死ぬかという「検事の死命を賭ける」(p220)という意識で法と罪に取り組むことにある。そして、増田が代弁する「わかっています。自分たちの仕事は罪をまっとうに裁くことであり、罪はまっとうに裁かれなければいけない、そう思います」という思いにある。さらに、それは左方の上司・刑事部副部長の筒井が発するつぶやきに通底するのだ。「秋霜烈日の白バッジを与えられている俺たちが、権力に屈したらどうなる。世の中は、いったい何を信じればいい」(p226)
連作作品のそれぞれについて、印象を少しまとめてご紹介してみよう。
《 心を掬う 》
この短編は郵便物紛失事件を取り扱ったもの。酒処ふくろうという飲み屋の親父が、「知り合いの常連客が北海道にいる娘に出した郵便が届かない」ということをふと話題にする。その後、増田と同じ検察事務官が増田に対し、自分が親戚筋から聞いた手紙が届かないという同種の事例を語るのだ。この話を増田が左方検事に伝える。すると、少し考えにふけった後で左方が増田に指示する。「二件の郵便物の宛先、いつ、どこの郵便局またはポストに投函したのかなど、調べてほしいんです」と。 警察から送致されてきた案件ではない。「なにか考えがあるとはいえ、郵便物の紛失話を急いで調べなければいけない理由が、増田にはわからない」。左方検事がトリガーを引いた事案がここから始まる。それが米崎中央郵便局の郵政監察官の懸案事項と思いにリンクしていく。一方左方が増田に出した指示は、手紙に関連した学生時代の思いが底流にあったのだ。
左方は思わぬ手段を密かに実行する。また、そこまで検事が現場に踏み込んで行動するのかと、増田を感動させるシーンに展開していく。この展開への発想に意外性があり、おもしろく、読ませどころである。
やはり、本作品のキーセンテンスは次の言葉である。
「私たちが扱っているのは単なる紙きれではありません。人の気持ち、心です」
こう福村郵政監察官が検事室のソファでつぶやいたのだ。
《 業をおろす 》
本短編は、『検事の本懐』に収録の「本懐を知る」の完結編にあたると内タイトルの下に編集部が付記している。この前作を読んでいなくても、独立した短編として十分に読み応えがあった。この作品だけの世界でも十分に感情移入してしまい涙を誘発させる作品となっている。付記には「『本懐を知る』読了後の方が一段と興趣が増すと考えております」と併記されている。この点はいずれ逆読みすることで、付記通りの順番で読む方がやはり一層よかったのかどうか、確認してみたい。
さて本作品の時期設定は、左方が故郷である広島の県北に位置する次原市山田町に6年ぶりにお盆に帰郷したときである。テーマは亡き父親の選択した行為・道の真実が解明されるということにある。
左方貞人は父・陽世の十三回忌法要のために帰郷する。菩提寺である曹洞宗龍円寺の住職は父陽世のおさな友達でもあった。貞人の父陽世は弁護士であり、顧問先の会社の会長小田嶋隆一朗の遺志で、小田嶋家の遺産を管理していた。しかし、その資産を横領した罪に問われ実刑判決を受け、黙って実刑を受け入れるという行動を選択したのだ。その父が服役中に膵臓癌で死亡する。貞人が高校2年生のときである。
法律の道に進み、検事となった貞人には、横領の発覚時点で金をすべて返済すれば、普通は執行猶予がつき、実刑を受けなくてもよいということを知る。弁護士の父がそれを知らぬはずがないと判断する。父は裁判の判決が出たあとに、現に金を返済しているのだ。
龍円寺の住職(人々から龍円さんと呼ばれている)なら、貞人の父がまるで罰せられることを望んでいたようにも思えるその理由を親友として知っているのではないか・・・・と思い、龍円に尋ねようとする。その場では龍円は答えず話をそらしてしまう。
十三回忌の法要の中で、龍円がもう陽世の業をおろしてもよい時期だろうと語り、ごく最近龍円が知り得た真実を法要の場で明らかにする。こんな流れでストーリーが展開する。弁護士の役割・立場、恩義、己の信念などが複雑に絡まり合っていく。読み応えのある作品に仕上がっている。
龍円は法要の最後に真実を語った後、大愚良寛の残した詩句を語る。
「君看よや 双眼の色 語らざれば 憂いなきに似たり」
この句は「この私の目を見てくれ。何もかたらないからといって、心に何もないわけではないのだ」という意味だと龍円は説いている。そして言う。「・・・・事のすべてを知り陽世の真情を知ったわしとしては、あいつが現世で誤解されたままでいるのが苦しゅうて苦しゅうて、かなわんかったのです」と。(p141)
貞人が龍円に返す言葉もよい。左方貞人らしい。
「父は父のやり方で、自分の仕事をやり遂げました。私は私のやり方で、自分の仕事をするだけです」(p143)
《死命を賭ける [死命」刑事部編》
《死命を決する 「死命」公判部編》
この連作では、検事が抱える幅広い事案件数の重圧下でみれば、一見取るに足りない小さな事案である。極端に言えば、さらりと判断し処理してしまえる案件だ。しかし、その案件をでんと据えて、左方にその案件を真っ向から取り組ませていく。この作品で検事の職分は何かを著者は問いかけている。そこにテーマがあると感じる。
左方に配点されてきた案件の一つは、痴漢行為の案件である。
1.案件内容 満員電車の中で衣服の上から身体を触ったとされる痴漢行為
それはその程度から、迷惑防止条例違反が適用される案件。
強制わいせつ罪レベルに至らない程度のある意味軽いものである。
2.被疑者 武本弘敏、43歳。会社員、地元の大手予備校勤務で経理課長。
武本は職場恋愛の上で、婿入りした男。その結果、県内の名門一族の係累になる。
義母は県内有数の資産家一族本多家の四女。義父は元教育長で地元で有名な教育者
本多家は政財界に様々な伝手と影響力をもつ地元の名家、有力者の一族。
3.被害者 仁藤玲奈、米崎市内の高校生、17歳。母子家庭という家庭環境に育つ。
万引きと恐喝で補導されたという前歴を持つ少女。
4.問題点 武本は左方検事に対し、送致事実に意義を唱える。
「もちろんです。私は少女の身体に触れてなどいない。痴漢なんかしていません!」 「・・・・・・正確には覚えていませんが、もうあんたはおしまいだ、とも言いました。
でも--と、少女はそのあとすぐ、わたしの耳元で囁いたんです。
お金を払えばなかったことにしてやる、と」
主張は真っ向から対立する。どちらかが偽証している。名門の係累に繋がる被疑者を無実にするために、上層部や政治家までがこの事案に圧力をかけてくることになる。
左方はこの案件の送致事実の確認から始め、起訴状を提出する決断を下す。そのプロセスを扱ったのが前半の刑事部編である。罪があれば、その罪を正しく裁く、案件の大小・軽重ではない、勿論、検事としての出世欲や外部からの圧力に屈することがあってはならない。検事社会における赤レンガ族と現場派という2つの潮流の確執の存在もそれとなく巧みに組み込まれていく。だが検事の死命の受け止め方が根本なのだ。左方の本領が発揮される。
検事には送致案件を立件起訴するかどうか決定する役割と、裁判所で刑事罰を告訴し弁護士との対立論争の中で罪の存在を証明する役割との2つのステージに分担されている。前者が刑事部のステージであり、後者が公判部のステージである。
左方は上司の筒井と同時期に刑事部から公判部に米崎地検内で横異動する。そして、刑事部の担当検察官として自分が起訴状を出したこの痴漢行為案件を、公判部の検事として裁判所の法廷の場で、告訴して弁護士と論争し、罪の立証する役割を担っていく。左方の検事人生が、刑事部から公判部へとステージが変わる。
「死命を決める」の読みどころは痴漢行為をどのように立証していくか、その立証のために左方がどういう行動を重ねていくか、そして己の確信を揺るぎない事実として証拠の列挙と論理で構築していくかにある。
武本には、本多家が後ろに控え、その顧問弁護士であり、米澤県下では大物弁護士、やり手と呼ばれる井原である。さらに、本多家が政界との伝手と影響力を行使して、地検や県警などの上層部にさまざまな形で圧力をかけてくる可能性がある。井原弁護士はあらゆる手段を使って、被告人の無罪を勝ち取りに出る。
「井原法令綜合事務所が県下最大の弁護士事務所たり得た理由は、徹底して準備を怠らない用意周到な法廷戦略にある。法に触れない限り、どんな手を使ってでも、依頼人有利の判決に導く。それが井原のポリシーだ。」(p241)
武本は勾留延長が決まったあとの井原弁護士との接見において、井原に頼む。
「もしかしたら、半田という男が裁判の証人になってくれるかもしれません。」
半田は飲み屋で知り合った男であり、事件当日、満員電車に偶然乗り合わせ、自分のすぐそばにいたのだという。その飲み屋があどういう店か井原は武本に尋ねるが、守秘義務のある弁護士の井原に対しても、武本は勘弁してくれと言い、明かさない。半田とコンタクトをとった井原は半田を最後の切り札として使えると判断する。そして、周到な裁判戦略を構築していく。
この半田が意外な裁判闘争の意外な展開の焦点となっていく。実におもしろい。
裁判のプロセスの検事と弁護士の対立論争のプロセスの展開の巧みさがこの種の作品の読ませどころである。どれだけリアルに、論理的に緻密に対立点を明瞭にさせ、立証過程のどこで一転して惨敗するかもしれないという危機感を漂わせるか・・・・その論争プロセスに読者が予期しない展開なり、論理構成の導入があるほど、おもしろい。本書は十分にこの裁判闘争のプロセスを堪能させてくれる。たかが軽い痴漢行為の罪状立証プロセスだが、されど厳しい罪状立証プロセスなのだ。読み応えがある作品にまとまっている。
『検事の本懐』は未読であるが、今後著者はヤメ検弁護士左方貞人シリーズを執筆展開するのか、検事時代の左方貞人の活躍も並行させるのか。いずれにしても、左方シリーズが続くことを期待したい。
ご一読ありがとうございます。
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
本書に関連する語句をいくつか調べてみた。一覧にしておきたい。
郵政監察官 ← 郵政監察制度 :ウィキペディア
刑事訴訟法 :「RONの六法全書 on LINE」
60条1,3項を参照ください。
検察官バッジ
検察官の付けているバッジ Q&Aコーナー :「検察庁」
左欄から「Q&Aコーナー」を選び、「その他」の分類に説明あり。
検察事務官バッジで語る役割の重要性 :「釧路地方検察庁」
弁護士のバッジ :「日本弁護士連合会」
違法収集証拠排除原則 ← 違法収集証拠排除法則 :ウィキペディア
令状主義 → 被疑者の権利-令状主義 :「日本国憲法の基礎知識」
横領罪 :ウィキペディア
迷惑防止条例 :ウィキペディア
京都府迷惑行為防止条例 :「京都府」
第3条(卑わいな行為の禁止)
強制わいせつ罪 :「司法試験用 刑事法 対策室」
十王図 10幅 :「奈良国立博物館」
ああ恐ろしや十王図 霊巌寺所蔵
ジャクソン・ポロック :「ヴァーチャル絵画館」
カーゴ・パンツ :ウィキペディア
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)















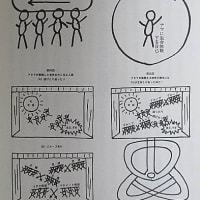




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます