>東洋経済オンライン >日本の職場『縦割り』『分断』全然変わらない4理由 なぜ20年たっても変えることができないのか >遠藤功の意見・ >3日・
>経営コンサルタントとして50社を超える経営に関与し、300を超える現場を訪ね歩いてきた遠藤功氏。
>36刷17万部のロングセラー『現場力を鍛える』は、「現場力」という言葉を日本に定着させ、「現場力こそが、日本企業の競争力の源泉」という考えを広めるきっかけとなった。
>しかし、現在、大企業でも不正・不祥事が相次ぐなど、ほとんどすべての日本企業から「現場力」は消え失せようとしている。
>「なぜ現場力は死んでしまったのか?」「どうすればもう一度、強い組織・チームを作れるのか?」を解説した新刊『新しい現場力 最強の現場力にアップデートする実践的方法論』を、遠藤氏が書き下ろした。
>その遠藤氏が、「日本の職場が今でも『分断』『縦割り』になる根本理由」について解説する。
>日本の職場はいまも「分断」されている
>私は過去30年以上にわたり、日本企業の現場を訪ね歩いてきた。
>その数は300を超える。
>この間、私たちを取り巻く環境も大きく変わった。
>【図1枚でわかる】では、職場の「縦割り」「分断」をなくして「新しい現場力」を生み出す"シンプルな方法"は?
>20年前と比較すると、真っ先に挙げることができるのが「インターネット」「SNS」の普及である。
>時間、空間、国境などあらゆる「境界線」を越えて、さまざまな「人と人」とが「つながる」ことができ、さまざまな「新たな価値」を生み出している。
>では、企業の現場はどうだろうか?
>残念ながら、その答えは「NO」である。
>相変わらず、現場は「分断」され、「孤立」し、サイロ化したままだ。
>さまざまな理由があるが、おもな4つの理由が考えられる。
>【理由①】職場で部署ごとの壁(見えない境界線)がある
>仕事というものは組織や部門をまたがって、「チェーン(鎖)」としてつながることによってはじめて価値を生む。
>しかし、概念としてはそのことを理解しても、実際には「縦割り」の意識が強く、「組織の壁」「部門の壁」で情報の断絶が起きたり、意思疎通がうまくいかなかったりする。
そうですね。日本人の社会は序列社会 (縦社会) ですからね。序列における内外の区別はきびしいですからね。縦割りにならざるをえませんね。
>企業が成長し、関わる従業員が増えてくると、当然のことながら、組織は肥大化し、専門化、機能分化していく。
>部門や個人の仕事はより明確に分けられ、ほかとの「境界線」がはっきり規定される。
>拠点も地理的に分散し、コミュニケーションは形式的になり、人間同士の「触れ合い」はどんどん薄くなる。
そうですね。
日本人は‘なあなあ主義’ で話をする。なあなあ主義には触れ合いが必要ですね。
‘なあなあ主義’ とは、真の意味での検討や意見の交換などをせず、お互いに「なあ、いいだろう」ぐらいの話し合いで全てを済ませること。
>「ひとつの会社」でありながら、一体感は希薄になり、「見えない境界線」が生まれる。
そうですね。厳しい内外の区別が一体感の造成を阻害していますね。
>この「見えない境界線」が「分断」につながるのだ。
馴れ合いには触れ合いが必要ですね。分断は協力の妨げになりますね。
>20年前から「つながる力」は高まっていない
>【理由②】職場で「タコツボ化」が蔓延している
>仕事はつながってこそ価値を生むにもかかわらず、「自分、自部門の業務しか知らない」「他部門の業務は無視し関心がない」といったことが現場に蔓延すると、その現場には「タコツボ」が至るところにできてしまう。
>タコツボ化すると、「自分さえよければいい」ということから、連鎖の視点が欠如する。
>その結果、組織としての全体最適は追求されずに、部分最適の集合体に陥ってしまう。
>タコツボ化は「縦割り」意識が強いので、「前工程は後工程を意識しない」「後工程も前工程の業務品質に問題があっても文句を言わない」といった「分断」が現場を支配してしまう。
>20年前に出版した『現場力を鍛える』でも、「タコツボ」をぶち壊すことの重要性や自律的組織のネットワーク化について言及している。
>しかし、20年後の現実を見れば、現場の「つながる力」は決して高まっているとは言えない。
再教育 (reskilling) が必要ですね。わが国では勉強は子供がするものと決まっているようですね。それが良くない習慣ですね。
>【理由③】職場が「半径5m」に埋没している
>現場は、企業活動における「価値を生み出す主体」である。そのミッションを遂行するためは、わき目も振らずに目の前のことに没頭し、懸命に「いま・ここ」を生きることが求められる。
>放っておけば、現場は目の前のことにしか関心を持たないし、「その日暮らし」に陥る。
>つまり、現場は「半径5m」の中だけで生きているのだ。
>「半径5m」という狭い世界に埋没している現実
>実際の職場では、以下のような話があった。
>「工場内のほかの製造現場を見学したことがない」
>「その工場内にはいくつもの建屋があるが、ほかの建屋に入ることもまれだ」
>「隣に座っている営業マンがいま何をしているのかよく知らない」
>物理的に同じ空間にいるだけで、そこには何の「つながり」も生まれていない。
>それぞれが「半径5m」というきわめて狭い世界に埋没しているのである。
広い職場が良い職場というわけでもないでしょう。
>【理由④】リモートワークで「人の分断」が生じている
>コロナ禍で増えはじめたリモートワークでは「人の分断」を招きやすい。
>たとえば、新入社員などは就職活動の面接から入社後研修に至るまで、ほぼすべてがオンラインで実施。
>配属後の慣れない仕事も最初からリモートワークであり、気軽に上司や先輩に相談できない。
>リクルートキャリアコンサルティングが行ったテレワーク実施前後のモチベーション変化に関する調査によると、テレワーク下でチームでの仕事が減った人に限ると、「モチベーションが低い」とする回答が28.4%だった。
>これは実施前の13.9%と比べると2倍以上になっている。
>便利だからといって、リモートワークやオンライン一辺倒になってしまっては、「人の分断」が生まれやすく、「社員のモチベーション低下」も招いてしまうおそれがある。
>では、「分断」「縦割り」な職場を「つなげる」ことの意味はどこにあるのだろうか。
>それは、現場同士の「交流」(interaction)が生まれることで情報が「交流」し、知恵が「交流」することである。
日本人の交流は肌と肌の触れ合いによるものが多いですね。恣意 (私意・我儘・身勝手) 疎通を意思疎通に切り替えることも必要ですね。
恣意はバラバラな単語で表され文にならないから意味がない。意思は文になっているから意味がある。
>現場力は「実践知」を生み出す活動である。
>それぞれの現場が単独で努力するだけでなく、現場同士がネットワークを組み、みんなで知恵を分かち合うことが、これまで以上に重要となっている。
>組織は「縦社会」のように「縦の力」がきわめて強い。
>しかし、縦糸と横糸が組み合わさってはじめて織物がつくられるように、縦と横が重なり合うことで強い組織はつくられる。
>「横串」「横展開」という「横の意識」を高めることが、いまこそ求められている。
そうですね。日本人は礼儀正しい。日本人の礼儀作法は序列作法で出来ている。ため口をきいてはならない。ため口禁止が横の意識を妨げている。 (ため口: 相手と対等な立場でモノを言うこと)
>「3つのつながり」で現場力はどんどん高まる
>とはいえ、放っておいても現場同士は勝手にはつながらない。
>「交流」を創造するための仕組みや仕掛けを講じる必要がある。
>そのためには、まず「人の交流」を生み出すのが先決である。
>たとえば、現場のリーダークラスがお互いの現場を訪ねるなど、「非日常」を経験させることが大事だ。
>人がつながれば、そこから「情報の交流」「知恵の交流」が生まれてくる。
>現場同士をつなげ、有機的な関係性やネットワークを構築することによって、現場同士が相互に刺激し合い、協力し合い、現場力は間違いなく高まっていく。
>「分断」「縦割り」をなくし、「人」「情報」「知恵」を交流させることが、これからの「新しい現場力」へとつながっていく。
日本人には横社会の精神を加えることが必要ですね。
日本テレビの単独インタビューで「このままでは日本人は滅びる」と日本の将来に危機感をあらわにしていた、ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長。[2024年 10月] 10日の会見でも「日本人同士のなれ合いみたいなことは廃止すべき」と改めて警鐘を鳴らしました。
日本人は‘なあなあ主義’ で話をする。‘なあなあ主義’ とは、真の意味での検討や意見の交換などをせず、お互いに「なあ、いいだろう」ぐらいの話し合いで全てを済ませること。 ‘以心伝心・阿吽の呼吸’といったところか。
司馬遼太郎は、<十六の話>に納められた「なによりも国語」の中で、片言隻句でない文章の重要性を強調しています。
「国語力を養う基本は、いかなる場合でも、『文章にして語れ』ということである。水、といえば水をもってきてもらえるような言語環境 (つまり単語のやりとりだけで意思が通じ合う環境) では、国語力は育たない。、、、、、、ながいセンテンスをきっちり言えるようにならなければ、大人になって、ひとの話もきけず、なにをいっているのかもわからず、そのために生涯のつまずきをすることも多い。」
日本人は学校で受け売り・後追いの練習ばかりをしている。自己の見解 (非現実) を述べる訓練をしていない。すると、知性の欠けた人間の跋扈する奇妙な社会が出来上がる。
イザヤ・ベンダサンは、自著<ユダヤ人と日本人>の中で、我が国の評論家に関して下の段落のように述べています。
評論家といわれる人びとが、日本ほど多い国は、まずあるまい。本職評論家はもとより、大学教授から落語家まで (失礼! 落語家から大学教授までかも知れない) 、いわゆる評論的活動をしている人びとの総数を考えれば、まさに「浜の真砂」である。もちろん英米にも評論家はいる。しかし英語圏という、実に広大で多種多様の文化を包含するさまざまな読者層を対象としていることを考えるとき、日本語圏のみを対象として、これだけ多くの人が、一本のペンで二本の箸を動かすどころか、高級車まで動かしていることは、やはり非常に特異な現象であって、日本を考える場合、見逃しえない一面である。 (引用終り)
我が国の日本人の記事は実況放送・現状報告の内容ばかりで、読者のためになる所が少ない。‘それでどうした、それがどうした’の問いに答を出せる編集者が必要である。我々は自己の見解を述べる教育を受けてこなかった。だが、自己の見解を含まない発言には価値が少ない。我が国には社会の木鐸 (ぼくたく: 世の人を教え導く人) が必要である。そうでなければわが国は迷走に迷走を続けて、いつまでたっても何処にも到達しない。だから、わが国の若者にも夢と希望が無い。
イザヤ・ベンダサンは、自著 <日本人とユダヤ人> の中で ‘自らの立場’ について以下のように述べています。
何処の国の新聞でも、一つの立場がある。立場があるというのは公正な報道をしないということではない。そうではなくて、ある一つの事態を眺めかつ報道している自分の位置を明確にしている、ということである。 読者は、報道された内容と報道者の位置の双方を知って、書かれた記事に各々の判断を下す、ということである。 ・・・・日本の新聞も、自らの立場となると、不偏不党とか公正とかいうだけで、対象を見ている自分の位置を一向に明確に打ち出さない。これは非常に奇妙に見える。 物を見て報道している以上、見ている自分の位置というものが絶対にあるし、第一、その立場が明確でない新聞などが出せるはずもなければ読まれるはずもない。・・・・・ (引用終り)











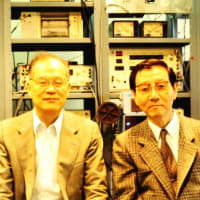
「日本のおかげで、アジアの諸国は全て独立した。日本というお母さんは、難産して母体をそこなったが、生まれた子供はすくすくと育っている。今日東南アジアの諸国民が、米英と対等に話ができるのは、一体誰のおかげであるのか」
と書き記しています。この言葉が、あの戦争が何であったか、そのすべてを表わしているでしょう。