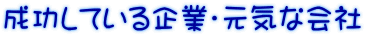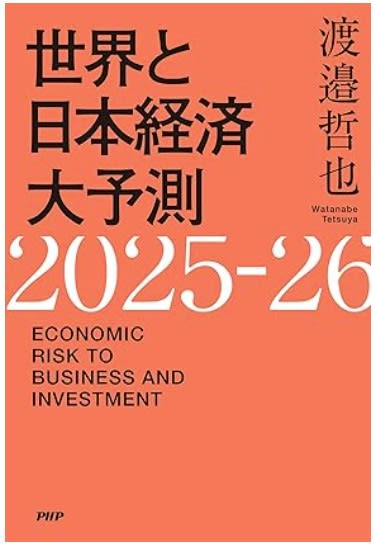『「世界と日本経済大予測2025-26」
Economic risk to business and investment』
(渡邉哲也著 PHP研究所)
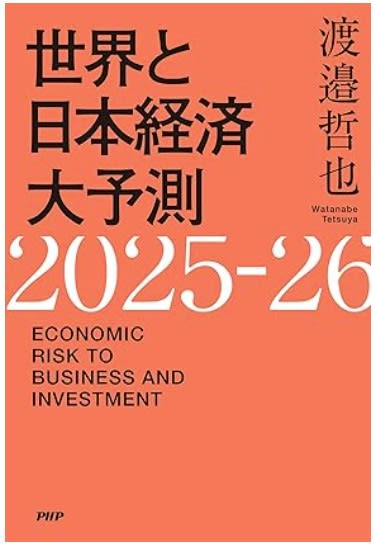

■ 日本経済にインパクトを与える46の国内、国外のリスク(はじめに)
紹介本は、2025-26年に予測される世界・日本の経済のリスクについて、論評しています。著者の経済大予測シリーズは2020年からの6作目です。2023年11月15日に刊行された「大予測2024-25」において予測した、「株価4万越え」は、2024年3月、7月、10月、12月に実現しました。この様に2020年予測本以来、「高い的中率(的中率9割)」が継続中です。Amazon売れ筋ランキングでは、外国・国際法ジャンルで1位です
紹介本の2025-26年本で、著者は、2025-26年のテーマは『政治・ビジネスの新たな潮流』とし、「デフレの頸木(くびき)を外れた日本経済がどこまで登っていくのか」、「トランプ政権のアメリカの政治・経済の行方」、「バブル崩壊の中国経済の行方」などの見逃せない46のリスクについて解き明かします。
それでは、46のリスクから注目記事を、上記テーマの視点からご紹介します。

■ 「政治・ビジネスの新たな潮流」から注目のリスクを見てみよう
【日本経済に関する29リスクからの「注目リスクは?」】
<人手不足-安易な賃上げは命取りになりかねない->
著者は人手不足のリスク対応として、次のチャンスを示します。「人手不足は会社が変わる絶好機」と。その意味するところは、人手不足だからと言って、売上上昇に見合わない賃上げをしても、企業収益を落とすだけで、企業経営の視点からは間違った対応と主張するのです。正しい対応は、人手不足を認め、それを解消するための最適な設備投資をすることです。
その好事例がファミリーレストランのロボット対応です。100席程度の店舗の例です。店に入るとタブレットに人数を打ち込み、空いている席を指定してもらう。注文はすべて各席のタブレットで行い、料理はロボットが運んでくる。会計時にレジで初めて店員と対する仕組みです。これにより4~5名居た店員を、2名に削減出来ます。この結果1日で3万円から4万円、月換算で約100万円のコストを削減出来ます。償却期間を5年とすれば6000万円(ロボット化に十分な金額)の設備を導入できる計算になります。つまり、正しい対応設備を導入することで、賃上げせずとも、人手不足を解消できるのです。
<70歳定年制-終身雇用、年功序列は通用しない->
厚生労働省が発表した「令和5年簡易生命表」によると、2023年の平均寿命は男性81.09年、女性87.14年。90歳までの生存する人の割合は男性26.5%、女性50.1%となっています。
著者は、今や、65歳まで現役バリバリの気持ちでいないと、国が成長していかないと主張します。更には、2021年4月に施行された「改正高年齢者雇用安定法」により「70歳定年制」を進めている時代においては、終身雇用や年功序列は通用せず、あるスポーツ選手が言った「明日の自分は、今日の自分よりも上手くなっているように、と常に思うべき」に含まれる、向上心、自分を磨き続ける努力、それを行おうとする気構えが人生を左右し、社会の活性化に繋がると主張します。
70歳定年制のリスクを変えるチャンスとして、「自分に合った場所、最も輝ける場所を選んで、その場所で全能力を発揮して、見合った報酬を得られる『70歳までのキャリアプラン』を考えるべき」と提示しています。
【「トランプ・トレード」で再び世界が分断する】
<アメリカのウクライナ政策-米露首脳会談が実現する->
ウクライナ戦争は一時的な停止も含め、停戦の可能性は高いでしょう。ここでは、著者の主張する、トランプの戦略に焦点を当ててみましょう。トランプは、露中を再び分断に持ち込み、中国だけを孤立させたいと考えていると言います。
著者は、露中分断の兆候はすでに表れているとして、次の政治的事象を示します。2024年7月、プーチンは、カザフスタンで習近平と会談した際、「両国は史上最良の時期を迎えている」と発言しますが、この時プーチンは、習近平とは対照的に、不愉快そうな顔をしていました。その後プーチンは北朝鮮とベトナムを歴訪します。北朝鮮もベトナムも反中の朝鮮労働党、ベトナム共産党が支配しており、プーチンは習近平に意趣返しをしたのだ、と著者は指摘します。
トランプのウクライナ政策は、アメリカの対欧・ウ・露戦略に加え、対中孤立化戦略の視点から見ることで、より鮮明に見えてくるのではないでしょうか。この流れの中で、北朝鮮との歴史的融和の可能性も見えてきます。
<グローバルサウス-新興国がこのままのスピードで発展することはない->
2025年は、グローバルサウス(インド、ブラジル、南アフリカ、タイなどの南半球にある国や、南半球に近いアジアやアフリカなどの新興国・途上国)のリスクに注目です。これらの国々では、食料・エネルギーの「資源限界(需要に対応する供給が追い付かない現象)」から資源インフレが起きる一方、相対的に先進国の貧困化が進みます。
新興国の経済発展が一定の所まで行くと、政治的におかしくなる状況は世界各国で頻繁に見られます。ミヤンマーの軍事政権化や共産党が支配するベトナムのバブル崩壊などがその例です。新興国では、経済が右肩上がりのうちは国内政治も上手くいきますが、どこかで発展速度が鈍り、停滞すると破綻へと進みます。今、世界の3分の2近くが破綻状態と言われているのはこのためと、著者は指摘します。
この様な状況を反映し、世界は自由主義国の西側と、新興国・グローバルサウスの多くが中国側につく結果、権威主義の東側という二つの体制に分化する流れが進んでいくと著者は指摘します。
アメリカファーストを掲げるトランプ政権と世界の均衡ある発展を願うグローバルサウスの思惑とが一致しないことが及ぼす2025年の世界の政治・経済への動きに注目です。
著者は、「地下資源に恵まれ、経済発展の著しいBRICSの国々を、新興国・途上国のモデルとして考える時代は、そろそろ終わろうとしている」と主張します。
【バブル崩壊の中国に代わり日本がアジアを世界に押し上げる】
<2035年の中国-中国の国際的な影響力は右肩下がりに->
2024年7月15~18日に開催された中国共産党の三中全会(200人の中央委員の会議。5年毎の全国党大会を『一つの「期」』とし、期毎に1から順番に番号が付く)で、「2035年までに高水準の社会主義市場経済体制を完全に確立」が採決されました。
著者の見解は、この採決は21世紀の今においては時代錯誤というしかないとします。今の厳しい中国経済を考えると、中国共産党の採り得る経済政策は、改革開放の社会主義的な部分を取り去って、真に市場経済に門戸を開くか、それとも、共産主義に回帰するかの二者択一であるとします。前者を選択すれば習政権が崩壊してしまうので、後者を選択し共産主義を強化し、配給型の経済体制を作る以外に国家の骨格を維持できないとします。
つまり、習近平としては、八方ふさがり、打つ手がない状況です。この様な混乱の中で、「中国の国際的な影響力は右肩下がり」で落ちていくと指摘します。
<日本企業の中国離れ-「撤退」の負の連鎖が次々起こる->
これまで日本企業は中国から逃げたくても脱出できなかった、その理由は、中国からの資金移動が出来ないことにつきます。黒字が出ている限り、企業経営者としては撤退を進めるわけにいきませんが、しかし、赤字になってしまえば、撤退の正当な理由になります。これが、日本企業(ホンダ、三菱、日産などの自動車関係など)が中国から続々と撤退している背景です。又、地政学リスクからの撤退(パナソニックや日本製鉄など)も増加しています。
ここで注目したいことは、大企業が撤退すると下請けの関連企業も撤退することになります。日本企業の撤退は、中国企業に対する日本メーカー製の高品位な部材の供給が止まることを意味します。結果キーパーツが中国産に変わることとなり、製品の不良率が上昇し、耐久性は低下します。まさに中国国内でのサプライチェーンの瓦解が起きているのです。この瓦解は、同時にほかの日本メーカーの撤退を呼び、負のスパイラルが加速されるだろうと著者は予測します。ここで著者は、この負のスパイラルは「大企業の国内回帰が日本のGDPに寄与する」チャンスになると指摘します。

■ 予測されるリスク・ピンチをチャンスに(むすび)
紹介本では、46のリスク予測の各々の括りとして、「リスク・ピンチをチャンスに切り替えるヒント」が書かれています。ヒントを参考に、ビジネス・チャンスを掴みましょう。

【酒井 闊プロフィール】
10年以上に亘り企業経営者(メガバンク関係会社社長、一部上場企業CFO)としての経験を積む。その後経営コンサルタントとして独立。
企業経営者として培った叡智と豊富な人脈ならびに日本経営士協会の豊かな人脈を資産として、『私だけが出来るコンサルティング』をモットーに、企業経営の革新・強化を得意分野として活躍中。
https://www.jmca.or.jp/member_meibo/2091/
http://sakai-gm.jp/index.html
【 注 】
著者からの原稿をそのまま掲載しています。読者の皆様のご判断で、自己責任で行動してください。

© copyrighit N. Imai All rights reserved