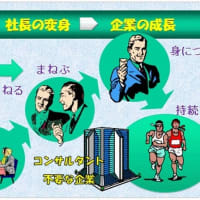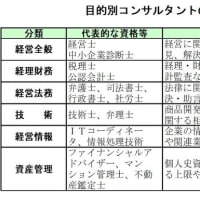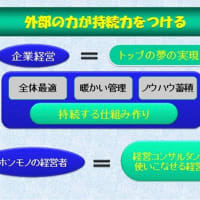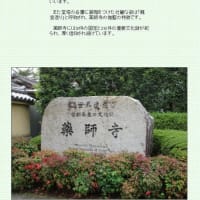【心 de 経営】『書話力』を高める ■7114 〃話のネタ〃の選び方 新規性ある時代の趨勢を題材に

*
私には、「正しい日本語」とはなにか、というようなことを書いていくだけのバックグラウンドがあるわけではありません。一方で、人前でお話をする機会が多々あります。少しでも「美しい日本語ですね」と言われるような言い方をしたいと平素からこころがけています。
経営コンサルタント歴半世紀の経験から体得した『書話力』を皆さんとわかちたいと考え、図々しくここにご紹介します。あまりにも「あたり前」すぎて、笑われてしまうかも知れませんが、「あたり前のことが、あたり前にできる」という心情から、お節介焼き精神でお届けします。
経営コンサルタント歴半世紀の経験から体得した『書話力』を皆さんとわかちたいと考え、図々しくここにご紹介します。あまりにも「あたり前」すぎて、笑われてしまうかも知れませんが、「あたり前のことが、あたり前にできる」という心情から、お節介焼き精神でお届けします。

■【あたりまえ経営のすすめ】3 すべてのビジネスパーソンがめざす一歩上の発想とスキル
時代に即したスキルを磨きながら、業務に活かし、自分の更なる成長に繋げるにはどうしたらよいのでしょうか。その方法は、多岐にわたると思います。
「あたりまえ経営のきょうか書」シリーズの第三章として、経営コンサルタントという仕事を通して、感じてきたことを、ビジネスパーソンに共通する面を中心にお話しています。

■3-710 〃話のタネ〃 テーマ・話材の選び方
*
「日本人は、議論に弱い」「日本人は、論理的な話し方ができない」などとしばしば言われます。かくいう私も、そう言われる人間のひとりです。
しかし、経営コンサルタントという仕事を半世紀も続けているうちに、それでは通じず、次第に、私なりの話し方やビジネスの仕方が、不充分ながら身についてきたように思えます。話すだけではなく、書くことにも共通する「表現力」というスキルがビジネスパーソンには不可欠です。「書く力」「話す力」をあわせて『書話の力』といい、表現力というスキルの一翼を担わせています。
この体験は、当ブログ「【小説】竹根好助の経営コンサルタント起業」としてもお届けしています。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/c39d85bcbaef8d346f607cef1ecfe950

*
「日本人は、議論に弱い」「日本人は、論理的な話し方ができない」などとしばしば言われます。かくいう私も、そう言われる人間のひとりです。
しかし、経営コンサルタントという仕事を半世紀も続けているうちに、それでは通じず、次第に、私なりの話し方やビジネスの仕方が、不充分ながら身についてきたように思えます。話すだけではなく、書くことにも共通する「表現力」というスキルがビジネスパーソンには不可欠です。「書く力」「話す力」をあわせて『書話の力』といい、表現力というスキルの一翼を担わせています。
この体験は、当ブログ「【小説】竹根好助の経営コンサルタント起業」としてもお届けしています。
https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/c39d85bcbaef8d346f607cef1ecfe950

■7114 〃話のネタ〃の選び方 新規性ある時代の趨勢を題材に
〃話のネタ〃、すなわち話材を選ぶという観点で、私の経験から「時宜に即したテーマ」を選定することをご紹介しました。
ここからは、「視点を変えるとテーマが決まる」という観点で、代表的なテーマジャンルについてお話してまいります。
*
私たちには、大なり小なり新規性のあること、めったにおこらないような珍事といえることなどには、興味をそそられます。「野次馬根性」のようなものを持っているように思えます。
この性癖を逆手にとって、〃話のネタ〃として利用しますと、注目度が高まります。たとえば、1970年代後半というのは、まだPCが「マイコン」といわれる時代で、それが経営ツールになるなどとは誰も思っていませんでした。
そのような時代に、これからはビジネスパーソンが皆、「My Computor」、「マイコン」を使う時代が来るのではないかと推察しました。1980年代に入ると、DOSをもとにアプリケーション開発が進み、「パソコン=Personal Computor」、すなわち昨今のPCに相当する機器が量産され始めました。はじめは、漢字が使えず、だれもが「おもちゃはビジネスには使い物にならない」と一部のマニアックな人達以外には見向きもされませんでした。それが「単漢」と言われる、音読みによる漢字変換ができるようになり、やがて今日のような日本語変換ができるようになってきました。一方で、処理速度も遅いという欠点がありました。
このような状況であるにもかかわらず、私は「それでも、PCは使われる」とガリレオ的な態度を改めず、講演会などで話をするようにしてきました。それを聞きつけた某社が私にPC関連の原稿を書籍にしたり、PC雑誌に掲載してくれたりしてくれるようになりました。結果的に、PCの専門家でもない私が、書籍を数十冊になるほどまでもの書籍を上梓(じょうし:出版)するようになりました。「パソコンコンサルタント」と紛われるほどになり、処々から講演やセミナー、出版・雑誌原稿寄稿等の依頼を受けるようになりました。
*
時代の先見性を持つことは、コンサルタント・士業にとっては不可欠なことですが、時代の趨勢を見ていますと、「新規性」「創造性」などから、発想が発展します。
1970年代に私がアメリカに駐在員として派遣されていた頃、クリティカル・シンキングという考え方・スキルが教育分野で話題となりました。日本では、教育分野では多少の関心が持たれたものの、ほとんど注目されませんでした。
私は、リチャード・ポール、リンダ・エルダー共著のクリティカル・シンキングに間する分厚い原語の本を購入して読み始めました。専門用語が多く、難解な本であるとともに、論理思考が苦手な私にとっては、なかなか理解をすることができませんでした。
私の弱点である、論理思考が逆によい方に反応し、日本人には、クリティカル・シンキングの前提となる論理思考が、スキルとして必要であると確信しました。論理思考を身につけるにはどうしたら良いのだろうかと考え込む日が続きました。論理思考について学んでいるうちに、上述のクリティカル・シンキングの本の理解もできるようになってきました。
やがて、日本に帰国し、上述のようにPCとの関係から、ICTメーカーとの関連もでき、その人達を対象として論理思考の研修を実施するようになりました。それと並行して、「ロジカル・シンキング」という言葉が日本でも見られるようになり、私も「論理思考」を「ロジカル・シンキング」と改めて、研修向けに体系化を始めました。その結果、ICTメーカーだけではなく、多くの企業から研修やセミナーなどの依頼が来るようになりました。関連書籍の出版や雑誌寄稿依頼も多数いただけました。文科省関連の外郭団体からはロジカル・シンキングのe-Learning教材制作依頼も受けました。
*
私の経営コンサルタントとしての体験を中心にご紹介して、鼻持ちならないと感じられた方もいらっしゃるかも知れません。経営コンサルタントという「見えないものを売る」には、このような「新規性ある商品」を持たないと、他の先生方と互して行くことはできません。それだけに、〃話のネタ〃を選ぶときの大切さを身をもって体験してきていますので、あえて、そのようにさせていただきました。ご容赦いただき、その大切さをご理解くださり、ご利用していただけると幸いです。
〃話のネタ〃、すなわち話材を選ぶという観点で、私の経験から「時宜に即したテーマ」を選定することをご紹介しました。
ここからは、「視点を変えるとテーマが決まる」という観点で、代表的なテーマジャンルについてお話してまいります。
*
私たちには、大なり小なり新規性のあること、めったにおこらないような珍事といえることなどには、興味をそそられます。「野次馬根性」のようなものを持っているように思えます。
この性癖を逆手にとって、〃話のネタ〃として利用しますと、注目度が高まります。たとえば、1970年代後半というのは、まだPCが「マイコン」といわれる時代で、それが経営ツールになるなどとは誰も思っていませんでした。
そのような時代に、これからはビジネスパーソンが皆、「My Computor」、「マイコン」を使う時代が来るのではないかと推察しました。1980年代に入ると、DOSをもとにアプリケーション開発が進み、「パソコン=Personal Computor」、すなわち昨今のPCに相当する機器が量産され始めました。はじめは、漢字が使えず、だれもが「おもちゃはビジネスには使い物にならない」と一部のマニアックな人達以外には見向きもされませんでした。それが「単漢」と言われる、音読みによる漢字変換ができるようになり、やがて今日のような日本語変換ができるようになってきました。一方で、処理速度も遅いという欠点がありました。
このような状況であるにもかかわらず、私は「それでも、PCは使われる」とガリレオ的な態度を改めず、講演会などで話をするようにしてきました。それを聞きつけた某社が私にPC関連の原稿を書籍にしたり、PC雑誌に掲載してくれたりしてくれるようになりました。結果的に、PCの専門家でもない私が、書籍を数十冊になるほどまでもの書籍を上梓(じょうし:出版)するようになりました。「パソコンコンサルタント」と紛われるほどになり、処々から講演やセミナー、出版・雑誌原稿寄稿等の依頼を受けるようになりました。
*
時代の先見性を持つことは、コンサルタント・士業にとっては不可欠なことですが、時代の趨勢を見ていますと、「新規性」「創造性」などから、発想が発展します。
1970年代に私がアメリカに駐在員として派遣されていた頃、クリティカル・シンキングという考え方・スキルが教育分野で話題となりました。日本では、教育分野では多少の関心が持たれたものの、ほとんど注目されませんでした。
私は、リチャード・ポール、リンダ・エルダー共著のクリティカル・シンキングに間する分厚い原語の本を購入して読み始めました。専門用語が多く、難解な本であるとともに、論理思考が苦手な私にとっては、なかなか理解をすることができませんでした。
私の弱点である、論理思考が逆によい方に反応し、日本人には、クリティカル・シンキングの前提となる論理思考が、スキルとして必要であると確信しました。論理思考を身につけるにはどうしたら良いのだろうかと考え込む日が続きました。論理思考について学んでいるうちに、上述のクリティカル・シンキングの本の理解もできるようになってきました。
やがて、日本に帰国し、上述のようにPCとの関係から、ICTメーカーとの関連もでき、その人達を対象として論理思考の研修を実施するようになりました。それと並行して、「ロジカル・シンキング」という言葉が日本でも見られるようになり、私も「論理思考」を「ロジカル・シンキング」と改めて、研修向けに体系化を始めました。その結果、ICTメーカーだけではなく、多くの企業から研修やセミナーなどの依頼が来るようになりました。関連書籍の出版や雑誌寄稿依頼も多数いただけました。文科省関連の外郭団体からはロジカル・シンキングのe-Learning教材制作依頼も受けました。
*
私の経営コンサルタントとしての体験を中心にご紹介して、鼻持ちならないと感じられた方もいらっしゃるかも知れません。経営コンサルタントという「見えないものを売る」には、このような「新規性ある商品」を持たないと、他の先生方と互して行くことはできません。それだけに、〃話のネタ〃を選ぶときの大切さを身をもって体験してきていますので、あえて、そのようにさせていただきました。ご容赦いただき、その大切さをご理解くださり、ご利用していただけると幸いです。

■ バックナンバー