i行人の恨み節はまだまだ続きます。故郷へ残してきた家族への思いを込めて、その憂慮する声を「五言形式」に替えて強調するが如くに、歌っています。
“長者雖有問” <長者 問ふ有りと雖<イヘ>ども>
例え、里正、村の長が、我々出征兵士に「御勤めはどうですか、何かお困りな事はありますか」と聞いたとしても、
“役夫敢伸恨” <役夫 敢へて 恨を伸べんや>
どうして、兵士は、正直に、その胸の内の苦しみやその恨み事を云うことがありましょうや。言っても何にもなりません。決して救ってはくれはしません。
“且如今年冬” <且つ 今年の冬の如きは>
「且ツ}です。この言い難いほどの我々国民の苦しみを「その上にまだ」。恨み節はより一層高まります。これら兵士の声も、また、“哭声直上干雲霄”
“未休關西卒” <未だ關西の卒を 休めざるに>
前に「山東二百州」があり、それを受けての「関西」です。全土に、あまねく、兵を派遣している事を高らかに歌いあげておるのです。だから、戦いはやめよう と思ってもっても止められないことを強調しているのです。「卒」とは兵を派遣することです
“縣官急索租” <縣官 急に 租を索<モト>む>
”租税從何出” <租税 何(いづこ)より出でん>
「且」は、まだ続きます。役人たちは、その上に、今度は、留守をする家族にも、税を厳しく取り立てて、負担を強いります。残った家族は、その税をどこからひねり出せば良いというのか???。出所って、いったい、どこにあると云うのか
「五言」で六行も続けております。前部の「七言」から受けて、行人の嘆きを強調して大きく訴える効果てきめんの表現方法です。その響きは、中国語で聞くと、更に、その重厚さがより強く感じられるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。
なお、昨日、此処までが、起承転結の「転」に当たる部分だと書いたのですが、よく読んでいたらどうもそれでは文章の構成から考えても間違えているのではないかということに気がつきました。そこら辺りの言い訳を含めて、また、明日にでも此の続きは書いて見たいと思います。ご批判を賜りますよう。
















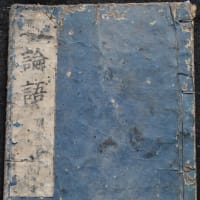

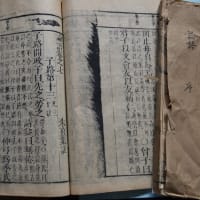
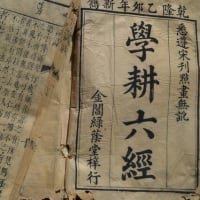
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます