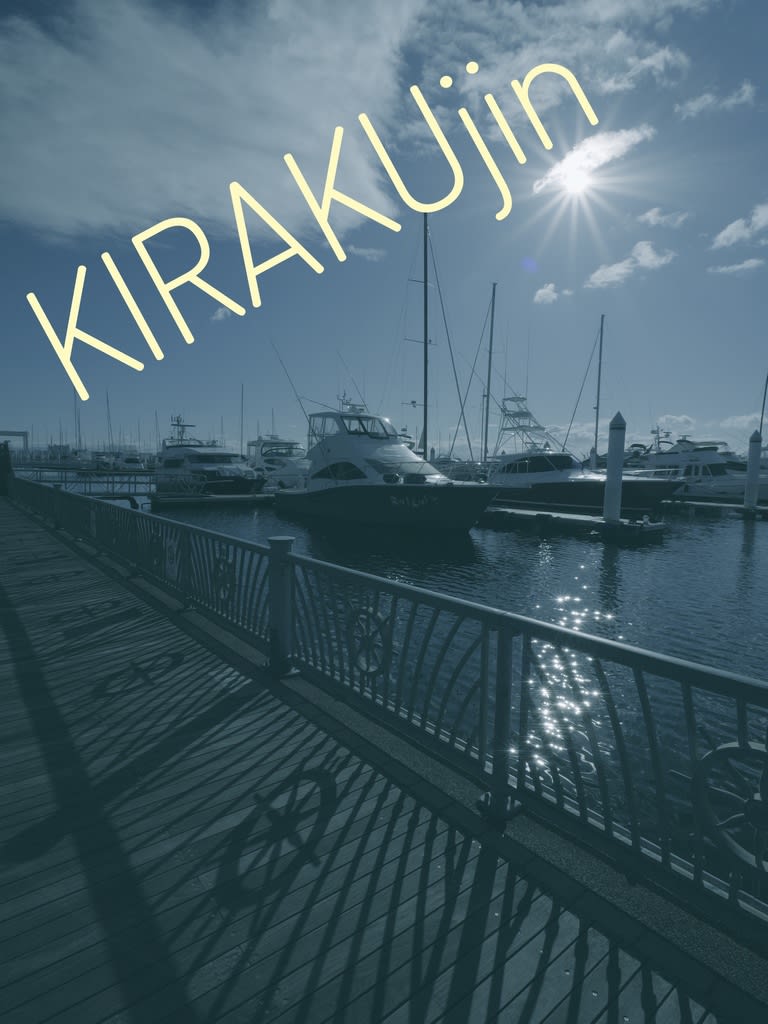いや、きっとそうに違いない。
カメラといえばフィルムが当たり前で、デジタルなど微塵も感じさせなかった頃。
モノクロで撮影し、暗室で現像することが、楽しくて仕方なかったものだ。
今もデジタル世代で生まれた方たちが、古い機械式カメラを提げていらっしゃるのを見る。
レコードやカセットテープで曲を聴くように、アナログの面白さを認識して頂けるのは、嬉しいことだ。
モノクロフィルムで、特に好みだったのは、コダックのTRI-Xだった。
トーンの出方や、適度な粒状感が心地良かった。
デジタルの時代になってもう、久しい。
フィルムが主流ではなくなり、写真の主体はデジタルになり、さらに普段の撮影の主役はスマートフォンになった。
一般的なデジカメですら、かなりシェアを下げている。
しかしそんな時代でも、往年の写真家たちの作品に触れていると、モノクロームの魅力は何ら変わらない。
いやむしろ、モノクロフィルム時代の方が、魅力的に見えることも少なくないのだ。
もし彼らや彼女らがいま、デジタルでモノクロームを撮るとしたら、どのように撮るのだろうか。
おそらくACROSが、大きな選択肢のひとつになることは、間違いない。
毎日気にしていたと問われたら それも嘘になるが
気になって綴ってみても ここ数年はまた 年単位の時が流れていた
写真を撮らなかった訳ではない むしろその逆である
しかし何かに追われれば追われるほど 他のツールへ流れていった
昨日から使ってみたタブレットが ノートパソコンより使い勝手が良いのもあるだろう
しかし今になって再度 ブログの緩さを 懐かしく感じたのかも知れない
最初の投稿に 海が見えない場所で育った私は 海に憧れている
そんな風に綴った と記憶している
自分で紐とけば良いのだか それも億劫だと言える緩さが また良いのかも
時節柄 巨大なアウトレットモールは ゴーストタウンと化し
発着の多かった海上の巨大な国際空港の光もどこか 寂しげだ
写真は光と影 それに少しの心象がエッセンスとして加わるのだとすれば
またこの場所にいずれ立ち 違った心象で撮りたいと願う
本日もお読みいただき ありがとうございました
また近いうちに お会いしましょう
by KIRAKUjin
10年以上前にブログを始めた頃は、毎日ノートパソコンを開け、フィルムからデジタルへの変遷を綴った。
楽しくて夢中になったものだが、ネット環境はブログ以外にも、さまざまな写真関連のサイトが増えていった。
各種SNSは、現在まさに、時代の寵児と言えようか。
最近のネットへの投稿は最新情報が多く、趣味や世の中の事など非常に多岐にわたり、私も恩恵を十二分に受けている。
ただ少し、慌し過ぎるのではないだろうか。
世の中のスピードは早く、また予想だにしなかった事態に、世界中が巻き込まれることもある事を知った。
久しぶりの投稿になる。
この場所だけはそんな、世の趨勢から乖離して、のんびりとしたものにしたい。
かつてのようなノートパソコンではなく、今回からタブレットにしてみた。
ますます、気楽なものにできるだろうか。
(写真について)
例によって、カメラ一台に単焦点レンズ一本である。
写真を撮るための外出ではなく、仕事の延長線のようなもの。
よく知る河口の堤防の夕暮れに、何とか間に合った光である。
"すでに何度か述べたかも知れません いまは最初に一眼レフを購入するとき 標準レンズとしては それは単焦点レンズではなく いわゆる標準ズームなのだと思います
よほど理由がない限り 最初から単焦点レンズを選ぶことは まずないのでしょう しかしまだズームレンズが一般的はなかった遥か昔 とくに1970年代の後半は 一眼レフのカタログには 50mm f1.4 が装置されていたものでした
35mmフィルムカメラ全盛期 スナップカメラの頂点はライカであり それを選ぶカメラマンのタイプによって 選ぶ標準レンズには好みがあり 50mmか35mmが 二つの大きな選択肢だったようです
ゆえにM型ライカの元祖は 究極のレンジファインダーを持つM3であり 50mm枠がメインてあり その後35mm枠も採用したM2が追加されたのです
例えば決定的瞬間という撮影用語の代表格(諸説異論はありますが)である アンリ・カルティエ・ブレッソンは ズミクロン 50mmが代名詞のように語られています
ところで ズミクロンと言えば通常 f2を意味します 現在通常 似たスペックのレンズとしては f1.8になるのでしょうか
もし私が最初に一眼レフを選んだ頃に戻って カメラとレンズを選ぶとしたら シルバーのオリンパスOM-1かブラックのニコンFM そしてレンズは 50mm f1.8かもしれません
当時最も普及していた 50mm f1.4よりも若干暗いとはいえ ズミクロンより明るいわけですし f1.4よりf1.8は 廉価で薄型で 傾向性に優れていました
今回私が使用したレンズはニコンの Ai Af Nikkor 50mm f1.8Dです
1980年に発売されたニコンEMは 当時ブロ仕様とされていたニコンが初めて発売した リトルニコンの代名詞を持つ超小型の一眼レフ
それに合わせて設計された 50mm f1.8 シリーズEはいわゆるパンケーキタイプでしたが 当時NIKKORの銘すら与えられない廉価版でした
このレンズは時代を経て何世代もの変遷を遂げました そしてその基本設計はそのままに 今回の Ai Af Nikkor 50mm f1.8Dに受け継がれており 平成最後も2019年でも 新品で入手することができます しかもニコンで最も廉価なレンズとして
現在の最新設計の優秀な50mmレンズたちとは ちょっと写りは昔風ですし 私のZ7に純正アダプターを介して装着できますが AFは使用できません 最も AFは私にとって必須ではないので この小型軽量のレンズはとても頼りになる相棒です
f1.8開放での神戸旧居留地の撮影ですが 空気感のある しっとりとしたモノクロームを表現できていると思えるのですが いかがなものでしょうか"
そのせいもあろうが、今年の秋はとくに、じっくりと写真に向き合いたいと願っている。
できれば毎日撮りたいが、なかなか、そうは時間が許さないのだが(笑)。
もう何年も秋は京都に魅せられて、秋を追いかけてきた。偶然に近い状況でふと、立ち寄った南禅寺の境内。見たこともない紅葉に驚き、私の中で何かが弾けた。秋だけでなく様々な季節、様々な場所を訪ねた。それぞれに素晴らしく思い入れも深く、もちろんこれからもずっと、追い求めて撮影していくだろう。
京都の華やかさ、荘厳さ、まさに見事な錦秋の秋・・・
しかし今年はもう少し、仄かな秋を感じたい。緩やかに、気持ちよい風を感じて、追い立てられることなく、のんびりと感じたい。
久しぶりのブログアップである。そんな気持ちの写真を、まずはアップしたい。
本阿弥光悦の名前を知ったのは、吉川英治氏の「宮本武蔵」を学生時代に読んでから。
それから幾星霜が過ぎ、京都に魅せられた私は偶然に光悦寺の存在を知り、その名前に惹かれ、ある日訪れた。
そしてそこは、星の数ほどある京都のお寺の中でも、私の筆頭のお気に入りになり、各季節に数えきれない程、訪れることになるのだ。
千本通を北に車で走り、千本ゑんま堂からさらに北上、佛教大学を越えた辺りから、さらに坂が急になっていく。
『本阿弥行状記』によれば、当時は「辻斬り追い剥ぎ」の出没する物騒な土地であったという。鷹峰三山(鷹ヶ峰、鷲ヶ峰、天ヶ峰)を望む景勝地である。
本阿弥光悦は、「寛永の三筆」の一人に位置づけられる書家として、また、陶芸、漆芸、出版、茶の湯などにも携わった。
現代でいうならば、マルチアーティストであり、芸術のプロデューサーでもあったのだろう。徳川家康に与えられたこの地に、芸術村を創ることになる。
光悦が没したのちに、この地は寺となり、現在の日蓮宗・光悦寺になっていったとのことである。
京都の有名寺院と言えば、清水寺や金閣寺や龍安寺など。大きな建物・広大な敷地・禅の枯山水など。あちこちで記念写真を撮り、土産物を買い求める。
いかにも一般的に喜ばれる、「京都らしさ」を楽しめる場所が多い。
光悦寺は縦に細長い敷地で(それはそれで京都らしいともいえるが)、間口が狭くて入口がわかりにくい。
しかしまず魅せられるのがその入口から。もみじのトンネルに包まれるように、石畳の細い道を進んでいく。
大徳寺の高桐院にも同じように直線的な入口からの参道があるが、私は光悦寺の方が、遥かに好みだ。
私のここでの撮影回数・枚数は、枚挙に暇がない。どれほど魅せられてシャッターを切ったかわからない。
ここから小さいが良い佇まいの鐘楼を越え、いつも丁寧な応対の入口を通ると、右手に本堂があり光悦翁の座像がある。
ここから右に池を臨みながら木立の中を歩く、季節により、蛙の鳴き声が楽しめる。
直線を抜けると正面に、光悦垣が見え始める。
光悦垣とは光悦翁の考案で、菱目に編んだ垣と、矢来風に菱に組んだ組子の天端を割竹で巻き、玉縁としている。
一般的なものは垣が平面的で、天端の片端が円弧を描いて終わっていますが、光悦寺のものはスケールが違う。
垣自体が非常に大きくて長く、入口から見て、天端は目の高さ位から、徐々に低くなっていくのだ。
さらに根本的に異なるのは、湾曲を描いているということ。
つまり、湾曲を描きながら、徐々に低くなって行く・・・ このバランスが絶妙なのである。
どこまでも続くような錯覚を覚える程に、実際より遥かに長く長く感じられるのだ。
これを設計した光悦翁は、独特の宇宙観すら、持っていたのだと推察する。当時はもちろん、写真とういメディアは無い。
しかしどこからともなく、この空間を写真で表現してみなさいと、問われているような気がしてならない。
ゆえに訪れる度に、さまざまな試行錯誤と写真表現を行うわけだが、これが楽しくて仕方ないのだ。
茶室をいくつも過ぎて、奥まで到着し、せせらぎを聴きながら腰かける。そして鷹峯を間近に臨む。
決して広くは無いが、私にとっては撮影スポットの宝庫であるし、その場に居るだけで、高揚したり落ち着いたり。
せっかく訪れても、何もないじゃないかと、すぐに帰ってしまう方も散見する。それはそれで、いいのだと思う。
でも私にとって光悦寺は、何度訪れようとも決して飽きない、大切な場所なのである。
光悦寺への感謝と思いから、ついつい綴ってしまった。
ここらで、写真の話をしておかなくては(笑)。
でも詳しくは、次回にしたいと思う。
今回の写真は、光悦垣に向かって右脇に、いつも茂って咲く萩のこと。初夏になり、まだ軟らかで可愛い萩が生え始めたのだ。
その優しい佇まいを、光悦垣とともに撮ってみた。
機材は前回同様。X-Pro2 + XF 18mm F2である。