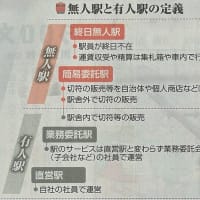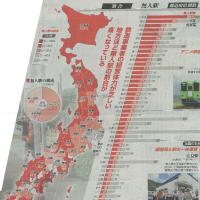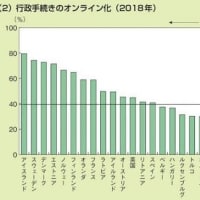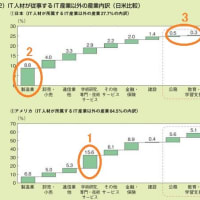「英語と他の言語(1)」から続く。
(3)英語の世界
学校を出てから今日まで50年、最初の仕事は船乗り、三等航海士だった。あの頃から英語の世界を歩き始めた。そこで、今回は、英語に対する自分なりの考えを紹介する。
まず、50年も付き合った自分の英語力を自分なりに評価する。
1.発音は典型的なジャパニーズイングリッシュ、単語を日本語流にはっきりと発音している。
しかし、ハワイのバス停などで見知らぬおばさんに行先を尋ねると、分かり易い英語と褒
められる。
2.専門分野の生産管理とコンピューターでは、自分の英語に自信がある。
3.日本語より英語の文法は合理的だと思っている。特に、英語の関係代名詞は便利だと思う。
4.内容によるが、TVやラジオのイギリス英語は30~60%、アメリカ英語は60~100%聞き取れる。
なお、エリザベス女王や英国首相のスピーチなどはスムーズに90%以上聞き取れる。
5.自分は英語に堪能な人とは思わない。会議などで分らないときは、分からないと聞き返す。
あるとき、あなたは内容をよく理解しているので「分らない」といえるといわれた。さらに、その
カナダ人社長は、(会議などで)日本人は笑って(答えを)曖昧にするのでやり難いとも言った。
このような英語力であるが、ここで自分の英語歴を振り返る。
1)船乗りの英語
外航船の操船命令とその復唱は英語、また、航海日誌と機関日誌は公文書(事故などの証拠物件)、昔から英語だった。日本人のパイロット(水先案内人)は日本語、イタリア人はイタリア語、ドイツ人はドイツ語で操船命令を出すと乗組員は混乱する。そのため、世界各地でよく使われる英語が使用言語(working language)になったようだ。【補足説明参照】
【補足説明】
HP「われら海族」の「航海日誌の書き方」からサンプルを引用する。ただし、サンプル英文の括弧()内の単語および各行の日本文は筆者が付加した。
・・・こんな感じ
0820 Stationed for leaving port.
8時20分、出港のため総員部署に付いた。
0840 Pilot Capt. Tanaka (came) on board.
パイロットのキャプテン田中乗船
0850 Took tugs “Kirishima maru” & “Ajikawa maru” on her port bow & port quarter.
タグボート(曳船)霧島丸と安治川丸を左舷船首と左舷船尾に配置した。
0855 S/B eng.
スタンバイエンジン(機関は待機状態になった)。
0900 Let go all shore lines & left Osaka for Tokyo.
すべての係留ラインを解き放し、東京に向け大阪を出港した。
0902 Dead slow ast'n eng. & used it var’ly.
機関後進極微速、以後エンジンを適宜使用した。機関後進極微速(キカンコウシンキョクビソク)は旧日本
海軍の操船用語、商船では“dead slow astern”(デッド・スロー・アスターン:世界共通語)という。
0910 Cast off all tug.
すべてのタグボートを切り離した。
0920 Cleared out the B.W.E. & Pilot left her.
防波堤出入口を通過、パイロットは退船した。(BWE=Breakwater Entrance)
0930 Full ah’d eng.
機関前進全速、商船では“full ahead”(フル・アヘッド)という。
0936 R/up eng. & Dismissed the station.
機関は平常運転に入り、総員部署を解散した。(R/up=Rung upは「仕事を終えた」の意味)
・・・以上で「航海日誌の書き方」からの引用は終り。
今も昔も変わらないが、航海日誌の1行は長くても20語程度の短文である。港に着けば外国人作業者が荷役を始める。その荷役の指示も英語、4年間も世界を航海していると英語が当たり前になる。しかし、その発音や言い回しには港みなとの違いがあっておもしろい。
たとえば、英語の“Folks(人々)”をドイツ人は“Volks(独語)”というがこの違いにドイツらしさを感じる。また、“Very“や“Fantastic”の発音でも、時には“V”が“F”、“F”が“V”に聞こえるが“訛り”の違いである。さらに、カーゴ(Cargo=積荷)をカルゴと発音すのはインドやイスラム系である。筆者は、この発音にさまざまな香辛料の味とその味にまつわる懐かしい光景を思い出す。もちろんあり得ない話だが、もし世界中の英語が標準的な発音に統一されると、自動翻訳やロボットには好都合だが、世界各地の特色が消滅するおそれがある。
訛りは別として、船乗りの英語はだれにでも伝わる英語でなければならない。あいまいな発音やブロークン・イングリッシュは事故につながる。ちょっとした命令の誤解でも、海の事故はダメージが大きい。
2)アメリカで学んだ英語
4年間の船乗り生活で、感じるところがあってアメリカの工学部大学院に留学した。専門教科の宿題、小論文(Term Paper)、発表(Presentation)、作文教室(Composition)などでは、
1.「Straightforward(率直、簡単な)な文章」
2.「32語以下の短文」
この2点を指導された。両義にとれる(Ambiguous)言葉と表現はNGだった。32語の論拠は忘れたが、この数字は今も頭に焼き付いている。誰にでも分かる英語が最上だと、工学部の先生たちからも叩き込まれた。これには、多民族国家の教育を感じとった。
ちなみに、コンピュータープログラミングでもAmbiguousな表現はNG、yesかno、1か0、二進数(binary digit:バイナリー・デジット→デジタル)の世界である(ambiguousという単語はコンピューター解説書で学んだ)。
なお、当時の留学必須アイテムは、ポータブルタイプライターと無地のビジネススーツだとアメリカ文化センターの資料で知った。タイプライターは宿題や論文で使用、ビジネススーツは論文などの発表で使用するとのことだった。なお、柄物スーツはNGと但し書きがあった。
ヒューストン大学でも作文教室以外では、手書き文章の提出はダメだった。タイピストに頼めばレターサイズ1枚45セント、数式などが入れば手間が掛かるので1枚1ドル、1ドル360円時代だったので、すべての宿題や論文は自分でタイプした。タイプした誤字を消しゴムで消せる紙を利用したが、丁寧にタイプすることで英文に強くなった。なお、数式や図などは手書きOKだった。
作文教室では、書きたい内容を頭に描き、文脈をパラグラフ(段落)のフローチャートにして先生に説明する。1つのキーワード(=話題:トピック)を1パラグラフと考えて、キーワードのフローチャート(流れ図)を試作する。話題を変える時はひし形(分岐マーク)で分岐する。この時、分岐先の位置を流れに沿って分かりやすくする。もちろん、分岐先は新しいパラグラフや既存のパラグラフである。
参考だが、卒業後に日本の民間研究所で共同研究をしたとき、チームで報告書を作成する方法も同じだった。まず、全員でキーワードのフローチャートを作成、その後に各自の担当部分を文章化した。もちろん、文章スタイル、用語と表現などの標準(ひな形/例文)もあった。
キーワードのフローチャートができた時、先生は個々のパラグラフの内容と全体の流れにアドバイスをする。フローチャートを完成し、パラグラフを主題文と支持文で順次文章化すれば作文は完成する。この方法は、コンピューター・プログラムの制作と全く同じだった。
ここで補足になるが、キーワード(=話題:トピック)がそのパラグラフの話題になる。その話題を説明する1行の文章をTopic Sentence主題文という。さらに、その主題文を説明する文章をSupporting Sentence支持文という。したがって、1つのパラグラフは1つの主題文と複数の支持文から成り立つが、支持文なしで主題文だけのパラグラフもOKである。以上を要約すると、1つのパラグラフ=1つの主題文+0~複数の支持文となる。【参考:英語と他の言語(8):文章の形式(Form)(2013-02-25)】
1960年代中頃の日本の大学では、このような指導はなかった。しかし、アメリカの高校・大学がコンピューター教育を重視する理由が分かった。その理由は、まず頭の中の考えをキーワードのフローチャートに展開、次にフローチャートの流れを整理統廃合する:このプロセスはしっかりとした論理展開の涵養に役立つ。日本でも文系・理系に関係なく、コンピューター教育は必要だと思った。
一方、読解力については専門書を多読し、知らない単語は読み飛ばす。何回も同じ単語に出会ううちに、前後の関係から自然にその単語の意味を覚えてしまう。どうしても分らないときは英英辞典で調べる。経験では、専門語は普通の英和辞典に載っていないことが多い。そのため、いつの間にか英英辞典だけを使うようになる。多読が決め手であり、図書館の開館時間は週100時間以上、卒業間際の学生は、24時間利用できる自分の個室を確保できた。当時、160万冊の蔵書と250万巻のマイクロフィルムがあった。
このような大学生活、その間に出会った次の3つのエピソードは今も覚えている。
【エピソード1】
大学では、主な試験や小論文の成績を学部ロビーの壁に貼り出す決りがあった。この成績の公開をめぐって「日本人(筆者)の英語は、われわれ(英語が日常語になっているインドの留学生)の英語より劣っているのになぜ成績が(A)なのか?」と先生に質問があったという。これに対する先生の答えは「君たちの英語は耳から入った英語で文章が話し言葉になっている。しかし、彼(筆者)の文章は文法とスタイル共に論文として立派に通用する」とのことだった・・・この話は、後日、台湾からの留学生に聞かされた。
これを知ったとき、日本の中学・高校の英語教育に感謝した。中学・高校で英文法をシッカリ教わったので読み書きの基礎が身に付いた。“話す“と“聞く”は教室でなく実社会で身に付けるもの、場数を踏めば自然に上達する。もちろん、コンピューター言語でも文法の知識が必須、後は年齢に関係なく場数の問題である。
10年以上も接するタイ語は耳から入った外国語、日常生活に不便はないが、基礎知識がないので「読めない」「書けない」の正真正銘の文盲である。幸い、英語(文学&会話各3年間)の他にラテン語系のフランス語(文学&会話)はそれぞれ3年間、スペイン語(貿易実務)は1年間の教育を神戸商船大学で受けたのでタイ語ほど酷くはない。
また、日米で活躍するある著名な日本人経営者の「日本人の英語は、スタイルは論文調だが、文法は正しく、ビジネスでは十分に通用する」という言葉を思い出した。事実、世界には口が達者でもまともな文章/e-mailを書けない人は意外に多い。
【エピソード2】
「ほのるる丸」の航海日誌(Logbook)は英語だった。したがって、英語の講義には問題なし、もともと自然科学系の理論や数式は世界共通のため違和感はなかった。ついでだが、航海日誌は外国でも通用する公文書(e.g.事故の証拠物件)、書き直し(改ざん)は不可だった。このため、筆者に限らず船乗りにはインクで文字を丁寧に書く習慣があり、その文章は読み易かった。
ある時、子供の発熱で授業を休んだという級友(アメリカ女性)に頼まれてノートを貸した。その結果、筆者のノートは読み易いと評判となり他にも借りに来る人がいた。やがてこの話は“統計学”から“コンピューター”に飛び火、授業中に筆者が取る“ノートが分かり易い”という理由で、コンピューター関係教科(Advanced Numerical Analysis)の助手にもなり、研究室と給料を与えられた。もちろん、学費減免と学内で購入する書籍の教職員割引はありがたかった。
【エピソード3】
専門教科の「ネットワーク論」で、面白いテーマを見つけて小論文に打ち込んだ。しかし、この教科の宿題、クイズ(突然の簡単な試験)、中間試験はおろそかになったので、成績は振るわなかった。
「コロンブスの卵」のような小さな発見を小論文にまとめ、先生から高く評価された。期末試験の1週間前、先生は学生たちに向かって「筆者の小論文から(5問中)1問だけ出題しようと思うが、どう思うか?」と皆の賛否をはかった。約20名のクラスメイトは、賛同の拍手で答えた。そこで直ちに、筆者の小論文を各自がコピーするようにと指示がでた。
さらに先生は、「宿題や中間試験の成績は芳しくないが、彼は小論文に打ち込んだ。出席点には問題がないので、彼に(A)を与えようと思うが、皆はどう思うか?」と続けた。これに対して、また賛同の拍手があった。あの拍手は今も耳に残っている。
日本人の小論文を修士課程の学生たちが期末試験(Final Exam)の問題として学んでくれる・・・このことが嬉しかった。このとき、英語は上手くないが、やればできるという“Can Do精神”を学んだ。アメリカには、日本にない感動がある。
やがて修士号(MS:Master of Science)を得て、国連専門職を目指して歩き始めた。
次回の「3)日本と英語圏での仕事」に続く。