





以前このブログで、「大岡 信 編訳の『小倉百人一首』はすごい」というタイトルの記事を載せました。
http://blog.goo.ne.jp/kohamaitsuo/e/2507469c96bd504ccae3a9c6d1e533c8
これをきっかけとして、親しい仲間六人で、「それぞれのメンバーが百人一首から感銘を受けた歌十首を選び、それを発表しながら口頭または文章で感想と批評を述べ、みんなで自由に語り合う」という趣旨の会を開きました。文学研究者はいますが、短歌に関しては素人ばかりです。
メンバーは三十代男性のHさん、Kさん、五十代男性のUさん、Gさん、六十代女性のMさん、それに私。
四十年近く世代の幅がありながら、話は妙に噛み合い、事前に一切相談しなかったにもかかわらず、選んだ歌が重なる場合もけっこうありました。
しかしまた、それぞれの趣味嗜好、どこにアングルを定めるか、接触体験の深浅などによって、顕著な違いもあらわとなり、それはそれで、メンバー一人一人の個性、人柄を改めて相互に知る結果となりました。
百人一首は定家が編集しただけあって、わずかな例外を除いて、いずれ劣らぬ秀歌がそろっています。しかも恋歌、美しい叙景歌、羇旅の歌、孤独の境涯を自ら偲ぶ歌、技巧の面白さを極めた歌など、多様さに溢れていますから、このような結果になるのは、考えてみれば当然だったとも言えるでしょう。
Hさんは直感派。音声CDを聴きながら、その場でピンとくるのを選んだだけでしたが、けっこういいセンスを示しました。自分にとって縁の深い地名に反応するところに、ナマの現場を尊重する精神が感じられたのと、やはり若い世代にふさわしく、i-phoneなどで絶えず「音」を聴いている日常経験も関係しているのでしょう。
Kさんは歳に似合わず、出家遁世の境地を歌った歌が多く、老成ぶりを示しました。作者を見ると、やはり僧侶が多い。心労の多いお仕事に就いているので、日ごろのストレスも関係しているかと邪推。しかし、そのよくできた円満な人柄からして、むべなるかなと感じたことも事実です。
Uさんは、文学に造詣が深く、慎重に吟味した形跡が感じられました。数多い恋歌はなるべく避け、あえて叙景歌を中心に選んだとのこと。誰でもなじんでいる歌がいくつか含まれていましたが、その感想、批評を聞いていると、あまりに有名なので何気なく通り過ぎていた歌にもずいぶん奥深い歌心が込められていることを教えられました。
Gさんも文学研究者ですが、温和な人柄にふさわしく、清冽な叙景歌や孤独で静謐な心境を歌ったものが多く、あまりに技巧に凝った歌や激しい感情を歌い上げたものは一つも選びませんでした。しかも総じて素直でわかりやすい歌が多い印象がありました。彼は今回の趣向とは別に、詩歌の批評についての発表も自発的に担当しました。持統天皇の「春過ぎて~」の歌における万葉集と新古今集との異同の問題を、昔日流行した「新批評」の旗手が論じた論考を素材とした発表だったので、これをきっかけに大いに議論に花が咲きました。
Mさんは、いかにも女性らしく、ほとんどが恋歌でした。しかも女性歌人の繊細複雑な、また時には激しく乱れる心模様を歌ったものが多く、どれも秀歌と言わざるを得ないものばかりでした。一位から十位までランクをつけて発表した点、自ら選んだほとんどの歌に、日ごろ傾倒しているシャンソンの曲を対応させ、恋の悩み苦しみは古今東西共通したものである点を印象づけたことなど、新鮮でユニークな視点を提供してくれました。
最後に私ですが、あらかじめ文章の形でレポートを用意していったので、それにやや修正を加えて以下に分載します。元のレポートは、「概説」と「各歌感想」の二部仕立てになっていましたが、ここでは、「概説」の冒頭部分をまず掲げ、次に「各歌感想」、最後に「概説」の残りの部分を載せることにします。
会が終わるころ、流れはしだいに、やはり万葉集をやらなければなあ、というところに落ち着いていきました。次の機会には、古典に造詣の深いよき導き手の書いたものを参考にしつつ、ぜひ万葉集に踏み込もうと約束を交わしたのでした。
【概説その1】
私は今回、あえて恋の歌ばかりを選びました。もちろん百人一首には、美しい叙景歌、人の世をはかなむ歌、羇旅の歌、ウィットと技巧のかぎりをつくした歌など、捨てがたい作品がたくさんあります。けれども、それらを捨てて恋歌に絞ったのは、一つには、私自身が最も関心を寄せることがらが、人間と人間との交流のあり方、ことに男女のそれであるために、その領域に限定したいと思ったからです。
もう一つは、百の歌の中で恋歌の占める割合が飛び抜けて多いという事実のうちに、やはりこの時代の関心もそこに集中しているなという確信を得たからです。
加えて、数ある恋歌が、どれも人の心の機微と奥深さ、人生の哀歓全体を表現して余りある秀歌ばかりだという感触を得ました。やるせない恋心を詠っていても、この時代の恋情には、寿命の短さからくる人生観が反映しているのか、必ずと言ってよいほど、人の世の無常、遠からずやってくる死への思いが、影のように付きまとっています。
しかし一口に恋歌といっても、その歌心には、じつに複雑で微妙な綾が詠いこまれています。特に平安時代の貴族階級では、一夫多妻と妻問い婚が一般的でしたから、位の高い男性の多くは艶聞華やかなプレイボーイ、女性は孤閨を守りながら、たまさか訪れてくる男を待ち焦がれたり、いつの間にか忘れられたりといったパターンが多かったようです。
だからこそ、女性の歌には、激しい情熱のほむらの燃え上がりや、胸をちりちりさせる片思い、夜明けまでわびしく空閨をかこつ哀しさ、噂に上ってしまうことを極度に恐れる秘めたる思い、そして時には、相手の言葉のうちに軽薄さを嗅ぎつけたうえでの当てこすりといった繊細な表現が実を結んだのでしょう。












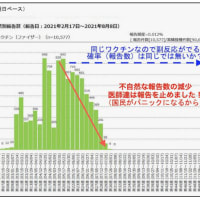

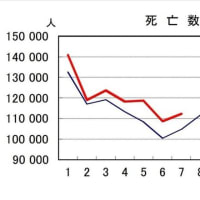
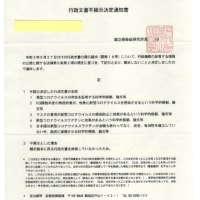
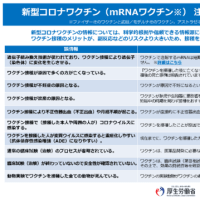

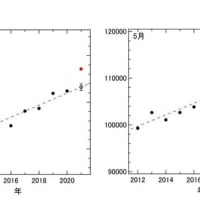

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます