・本日(2月15日(土))午前10時より

・潮音院本堂にて「常楽会(涅槃会)」がお勤めされました
・お忙しい中、たくさんのお参りありがとうございました
・お釈迦さまの遺徳を偲ぶ「佛遺教経」をお唱えし、お参りの方々にはお焼香して頂きました
・法要の後には「仏教の始まり」と言う題で、法話兼勉強会を行いました
・お釈迦さま在世時の時代背景、当時の社会通念に異を唱えた沙門の登場、そしてお釈迦さまの登場…と、仏教の周辺を取り巻いていた常識をかいつまんでお話ししました
・お話しの中盤では今でもお釈迦さまの時代の暮らし方を続けているタイやスリランカの映像を見て、実感を持って当時の仏教を肌で感じて頂きました
・最後に、時代が変わっても仏教が仏教であり続ける理由の一つとして「七佛通誡偈」のお話しをしました
・「諸の悪をなすことなく」…直訳では戒律の遵守が説かれます
・戒律を守ることは後悔なき人生を歩むことと同義であり(清浄道論)、悔いなく暮らすと、自然に戒律は守られています
・「諸の善を行い」…善とは布施のことです
・布施とは現代的に言えば貢献することであり、自分の行いで人が笑顔になることは何よりも徳の高い修行です
・直訳では善を行うとは「clever(巧みである、賢い)」であることで、巧みに生きるには、実のところ貢献にいきることが直路であります
・自分の心のために、他者への思いやりが行われることを忘れてはいけません
・「自らその心を浄くす」…禅定、智慧のことで、いわゆる瞑想しましょう、と言うことです
・戒律によって後悔少なく暮らし、巧みに貢献することによって心を充足させた人は、穏やかに「静けさ」を楽しむことが出来ます
・逆に、後悔多く、心が飢えている人は心が荒れて静かに座ることができません
・静けさを楽しむ瞑想に励むことが出来るのは、前述の持戒と布施が円満である物差しになります
・自分の心に、自分の行いの妥当性をお尋ねする機会が瞑想とも言えます
・これが2500年間、形を変えつつも紡がれてきた仏教の信念です
・一人でも多くの方の前途を、法の輝きが照らして頂けることを祈るばかりです
・バレンタインデー翌日に、お寺からは法のプレゼントでした















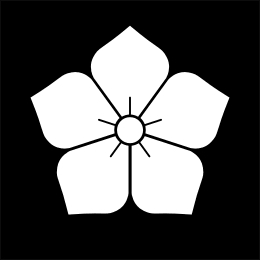

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます