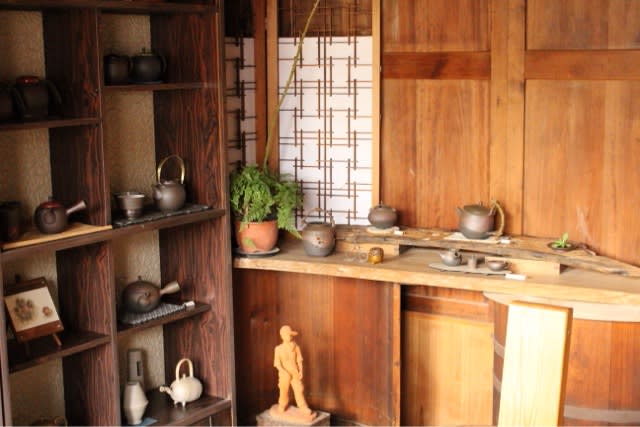今年手元に最初届いた緑茶は、碧螺春(bi4 luo2 chun1)。
清の康煕帝(こうきてい)が江南に訪れた時、色が緑で形が螺旋で春の風物という意味を込め、命名し直したと言われる緑茶。
中国語的には、意味合いも響きも、とても素敵なネーミング。
産地である洞庭山(dong4 ting2 shan1)は、江蘇省にある太湖(たいこ)の一つの島。
中国にいる家族は、清明節に、近くにある親族の墓参りの後、よく洞庭山へ碧螺春を買い求めていた。
一畝(mu3)の茶畑に、わずか二斤(jin1)しか採れない、と今年の明前洞庭碧螺春を譲ってくれた友人Bさんが言う。
ちなみに、中国大陸では、一畝は、約六六七平方メートル。二斤は、一キロになる。

碧螺春は、「先湯後茶(先にお湯を注いでから茶葉を投げ込む)」という意味の「上投法(じょうとうほう)」で淹れる。
その淹れ方について最初記載されたのは、中国明代の張源が書き残した『茶録』。
低温の湯にくねくねした細い碧螺春の茶葉を放り込むと、やがて一面の産毛が光りに変わる。
残された茶則の表面に、薄鶯色のうぶげが、薄らと残る。

舌の上に載せる淡白な茶湯を、口に軽くころがるよう、中国緑茶の繊細な滋味を探しあてる。
私の中国茶飲みの原点でもある。
ふと記憶にある子どもの頃の味覚が蘇る。
茶友に分けてあげたら、桜の満開よりも早く届いた今年の碧螺春、と喜んでくれたから良かった。