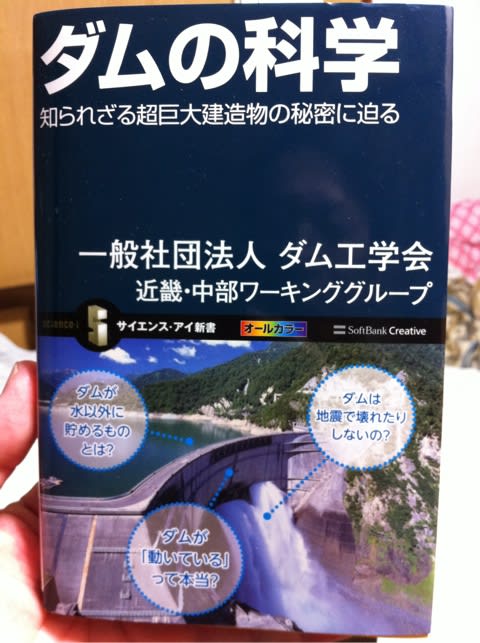『チョコレートの世界史 近代ヨーロッパが磨き上げた褐色の宝石』武田尚子著、中央公論新社(中公新書)、2010年
昨日、2月14日にはたくさんの人から人へと手渡されたのであろうチョコレート。それがどのように生み出され、普及していったのかを、近代ヨーロッパ社会の歴史を軸にして叙述した一冊です。
チョコレートの原料となるカカオ豆の原産地は中米。その歴史は古く、既に紀元前にはカカオが利用されていたことが遺跡から見出されています。
マヤ・アステカ文明の社会においては、カカオ豆は神々へ捧げられる供物であり、貨幣でもあり、健康増進のために飲まれる飲料でもありました。しかし、それは薬用として飲まれる苦いもので、主に特権階級の嗜好品でした。
それが変わっていくのは、1521年にアステカ王国が滅び、スペインにより植民地化されて以降のこと。スペイン人は、苦味ばかりだったカカオ飲料に砂糖で甘みを加え、それが多くの人々へと受け入れられていくのです。「チョコレート」の語が生み出されるのもこの頃です。
その後、ヨーロッパ諸国は中米・アフリカ・アジアに植民地を獲得。カカオは砂糖とともにそれら植民地のプランテーションにより栽培され、「大西洋三角貿易」により販路を広げ、普及していくのです。そこには、黒人奴隷を酷使しての搾取といった負の側面もあったわけですが•••。
ヨーロッパにおいて、カカオはまずココアとして普及していきました。はじめは貴族層の贅沢品だったココアでしたが、機械設備や輸送手段の近代化と歩調を合わせて大量生産が可能となり、次第に庶民にも手の届くものとなっていきました。そして1847年、イギリスにおいて固形チョコレートが誕生するのです。
本書で特に興味深かったのは後半。日本でもおなじみの「キットカット」を生み出した、イギリスのロウントリー社(1988年にネスレが買収)をめぐる記述でした。
クエーカー教徒による実業家ネットワークの一角を占めていたロウントリー社は、ビジネスはもちろんのこと社会改良にも熱心だったといいます。
中でも貧困問題への取り組みは刮目すべきものが。工場のあったヨーク市のワーキング・クラス1万1560世帯を戸別訪問して生活状態を克明に調査、その結果を研究書として出版までしました。それらは、20世紀のイギリスの福祉制度にも反映されていった、といいます。
また、労働者には良好な住環境の「田園ヴィレッジ」を提供したほか、週休二日制、女性従業員への教育プログラムやクラブ活動の整備、さらには労働者が「自主的」かつ「人間的」に働ける職場づくりのために産業心理学を導入するなど、労働者の待遇改善にも熱心に取り組みました。
さらに、ロウントリー社は菓子製造業としてはいち早く、大規模なマーケット・リサーチを行ったり、テレビCMを始めたりもしたとか。いろんな意味で先進的な企業だったんですね。
キットカットの誕生からヒットに至る歴史も興味を引きました。チョコにくるまれた層状のウエハースや、割って食べやすくするための「みぞ」についてのエピソードも面白いのですが、特に印象に残ったのは、戦時下で発売された「青いラッピング・ペーパーのキットカット」の話でした。材料調達がままならない中、「平和な時代」のような商品が作れないことへの苦渋が滲む、ラッピングに記された文面には胸打たれるものがありました。
チョコレートの中にも、歴史と社会のありようが凝縮されているんだなあ、ということを教えてくれる、興味深い一冊でありました。
2月14日の喧騒とは無縁のわたくしでしたが、前もって知人の女性からは、お気遣いのチョコレートを頂くことができました。それをつまみつつ、本書を読みました。

チョコレートの歩みを辿りながらのその味は、より一層深みがあったように思えました。
【関連オススメ本】

『砂糖の世界史』川北稔著、岩波書店(岩波ジュニア新書)、1996年
チョコレートが普及するのに大きく寄与したのが、甘さをもたらした砂糖。『チョコレートの世界史』にも参考文献として挙げられていたこの本は、その砂糖がいかにして「世界商品」になっていったのかを辿りながら、近代世界の歴史を概観していきます。ジュニア新書とはいえ、大人が読んでも面白く興味深い本です。