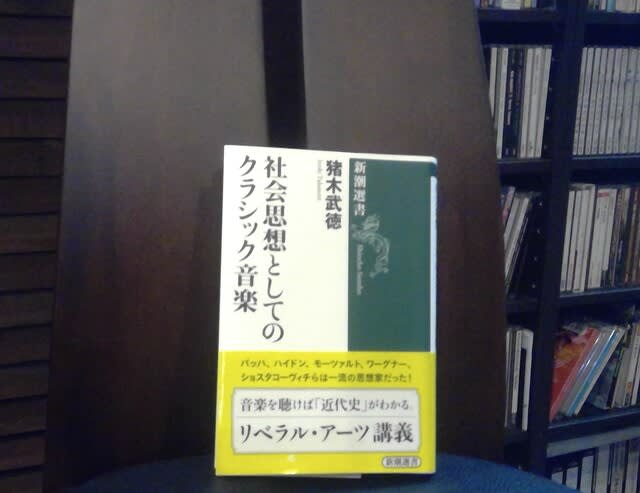
猪木武徳氏は、大阪大学名誉教授、日本経済学会会長も務めた経済学者。
経済学というと、ひょっとすると最近は、すべてを金銭という数量に還元して小難しい方程式を駆使する専門家、などというイメージが流布してしまっているかもしれない。しかし、そんなことはないわけである。この本を読んでいくと、氏は、むしろそういう経済学に対して異議を唱える立場であるのかもしれない。むしろ経済思想、政治経済学がご専門というべきか。人間の社会の成り立ち、歴史、文化を含む社会思想全般について、深い識見をお持ちの方というべきであろう。
【音楽と社会】
まえがきにこうある。
「本書は、音楽が人間の生命と精神、すなわちわれわれの生の根幹と深く結びついていることを、社会思想の視点から探求するひとつの試みである。」(3ページ)
なるほど。
私たちにとって、音楽を聞くことは大きな悦びである。このことは疑うべくもない。レコード、CDで聞き、テレビ、ラジオで聞く。そしてそれ以上に、コンサートで直接に生の音楽に触れること、その悦び。音楽は人間の精神になにか大きなものを与えてくれる。人間の生命の躍動に結びついている。
これは、社会的な公の出来事というよりは、私的領域における個人的な楽しみというべきだろうか。コンサートで大人数が集まってというのは、もちろん、孤独な営みではないわけであるが、あくまで私的な領域の楽しみでしかない、というふうに言われることも多いだろう。
ところが、猪木氏は、音楽を社会思想の観点から探究するのだという。音楽と政治は、密接な関わりを持っていたのだと。
「音楽という極めて抽象的な芸術は、社会風土や政治体制から影響を受けているだけでなく、歴史的にも政治に対して影響力を持ったことがあった。」(3ページ)
たとえば、ロック・ミュージックは、社会から影響を受け、社会に影響を及ぼすという相関関係が、多少は分かりやすいかもしれない。(しかし、あの1969年のウッドストック・フェスティバル以後、われわれは現在どんな世界に生きているのか、という問いは、私にとって巨大な問題であり続けている、今に至っても。われわれは、問題だらけの旧社会を変革しえたのか、変革できなかったのか、あるいは、改悪したのか。若い読者にとっては、ここは注釈が必要なところだろうが、ここでは省く。)
ところで、上記の「極めて抽象的な芸術」というのは、ちょっと考えてみると、ロックやポップや民謡には相応しいとはいえない表現である。それらはなにかもっと泥臭く具象的であろう。
ここで著者が「極めて抽象的な芸術」といって対象とする音楽は「一八世紀から二〇世紀半ばまでの西洋の音楽」、つまり、いわゆる「クラシック音楽」である。
クラシック音楽となると、確かに純粋で抽象的で、社会との相関関係など、とたんに分かりにくくなる。社会から超然とした純粋音楽、のようなイメージをいだいてしまう。クラシック音楽の世界では、確かにそんなふうにも語られてきたはずである。そう主張する音楽家もいたはずだ。(もちろん、たかが歌い手、政治など語るな、という最近の偏見に満ちた物言いは問題外である。)
分かりづらいというのは、単に時間、空間の距離の遠さの影響でもあるだろう。現在でも活発に演奏活動は行われているわけであるが、創作の時点というと、まずは200年以上も前の話であり、場所は地球の反対側のヨーロッパの話である。政治、経済、歴史にさほどの関心を持たない一般人にはその社会的背景など思いも及ばない事柄に相違ない。
著者にとって、この書物は、一般的には結びつきそうもないと思われる事柄の結びつきを解明しようとする「ドンキホーテ的」試みなのだという。しかし、当時の社会体制と、当時の音楽と、双方に造詣の深い著者であってみれば、この書物をものすることは、むしろ、当然の使命というべきかもしれない。
「社会思想や政治経済体制の視点から音楽の形式や内容、その歴史的な変遷を見直してみたいというのが本書の出発点となった。」(4ページ)
「西洋社会の変化と「クラシック音楽」の歴史的流れの間にどのような相関的な現象が見られるのか、これらの問いに向きあうことによって生まれたのが本書である。」(4ページ)
こういう問題意識の書物は、確かにこれまで読んだことがなかったかもしれない。
ところで、この時代のクラシック音楽を取り上げるというのは、ただ単に、著者の個人的な趣味だからと片づけられることではない。日本の社会、国家の現時点において、実は大きな意義を持つものである。バリのガムラン音楽とか、アンデス山脈の民俗音楽とか、そういうものの研究は、それぞれ、人類の人間性の探求や社会のあり方の考察に大きなヒントを与えるものには違いないが、18~20世紀前半のヨーロッパの音楽は、日本の現代社会の成立に、けた違いの直接的な影響を及ぼしたものである。明治期以降の私たちは、積極的にあからさまにそれを学び取り入れることに没頭してきた。もちろん音楽だけということでなく、さまざまな先進的技術、知識、学術の一環として。
ただ、著者は、日本の社会にたいする影響を、直接に語るわけではなく、まずは、ヨーロッパの枠内で、音楽と社会との相関を語るのであるが、それは同時に、読み取る側にとって、現在の日本への影響の話に通じてしまうというわけである。
「こうした試みから、現代の産業社会におけるデモクラシーの抱え持つ難問を考えるためのヒントが得られるのではないか、という欲張りな期待もある。」(6ページ)
言うまでもなく、「現代の産業社会」とは日本を含むグローバルな現代社会である。金融資本が荒らし廻り、市場が席巻する地球、世界、国際社会である。
【リベラル・アーツとしての音楽と社会思想】
著者によれば、社会と音楽という異質なものを結び付けて考察するところに、「リベラル・アーツ」ということばが浮かび上がってくる。
「人間について思いを巡らす茫洋とした知の世界には、隣接分野から、あるいは専門分野以外のものが立ち入る余地が残されているように思える。こう考えると、…「教養」、「リベラル・アーツ」という言葉が浮かび上がってくる。…実利や実践を目的とする知的探求だけの社会は遠からず貧血状態に陥ってしまうのではなかろうか。」(6ページ)
実利のみを追い求める、窮屈な、合目的的な活動のみでは、人間の社会は行き詰るのだ。
「目的のない知的活動から生み出されたものが、後で、思いがけない力と実用性を発揮するということも珍しくない。「発明は必要の母」でもある。トーマス・エジソンが音を再生する器械の制作に没頭していた時、彼の念頭に、ベートーヴェンの『交響曲第九番』をレコードで聴くという考えなど全く無かったはずだ。「目的のないことには意味がない」という強迫観念から自由になることが必要なのだ。友人との目的のない付き合いの中に幸福を感じるときがあるように、目的を持たないで、自由に知識を求める精神にこそリベラル・アーツの根本が存在するのである。」(7ページ)
ここには、現代の合理性、効率性のみ追い求める経済社会体制への批判があることは確かである。同時に、数理のみを追求する現今の主流の経済学派に対する批判でもあるだろう。
「ドストエフスキーやトーマス・マンの小説のあらすじを要約したところで、そこに新たな発見があるわけではない。…言い換えれば、一八世紀以降の近代科学が前提とする数学的「合理性」や「数少ない要素でできるだけ多くの現象を説明する」という理論の効率性の原則に固執する限り、人間と人間感情の謎に迫るのは難しいということになる。」(26ページ)
現代社会のデモクラシーと市場経済、民主主義と自由主義の問題であるが、その行き過ぎた形態、ポピュリズムと新自由主義の問題といった方がイメージしやすいだろうか。
「では現在のあわただしい産業社会に生きるわれわれは、いかなる政治経済体制のもとで生活しているのであろうか。それはデモクラシーと市場経済と要約することができよう。政治も経済も「数」が、そして「数」だけが、物事の最終的な決定原理となっている。…「多数者の支配」という事実を軽視できない。」(29ページ)
生活の「質」を問わない「数量」のみに囚われた政治経済。
しかし、言うまでもなく著者は、社会主義の計画経済を是とするわけではない。
「経済体制としての市場システムは、結局は多数の好むものを選び抜く。経済合理的な力を発揮できる市場制度が社会主義計画経済よりはるかに優れていることを、われわれは二〇世紀の歴史的「大実験」を通して学んだ。しかし市場メカニズムが完璧なシステムであるとは言い難い。」(30ページ)
「市場とデモクラシー…の長所と欠陥を正確に理解しつつ、さらに善き社会の生成に結び付くように修正を加える必要がある。」(30ページ)
と、極めて穏当で妥当な結論が提示される。
【登場する音楽家と思想家。政治家たち】
という総論を踏まえて、この書物でとりあげられる音楽家は、目次から拾っていくと、下記の通りである。
ハイドン、モーツァルト、バッハ、シューベルト、ショパン、ドヴォルザーク、チャイコフスキー、ロシア五人組、ヤナーチェク、マーラー、グールド、ワーグナー、フルトヴェングラー、ショスタコーヴィッチ、プロコフィエフ。
ドイツ、ロシアとその間の東欧が大部を占めている。
クラシック音楽においては、父なるバッハ、天才児モーツァルト、楽聖ベートーベンのドイツの作曲家がなんといっても巨大なピークを形作っている。ロシアは帝政期から社会主義革命にかけての政治、社会の動向と音楽の連環のひとつのモデルケースではあるのだろう。そして、その間をつなぐ、谷間のような不安定な東欧である。
音楽家以外の思想家、政治家(音楽愛好家)、文学者は以下の通りである。
マックス・ブロート、アドルノ、ルートヴィッヒ二世、スターリン、ゴーリキー、幸田露伴。
これらは、露伴以外は、音楽家と同じエリアの人々である。
【この書物の意義】
このあたりの国家、社会と音楽の関係性は、全くその通り、通読して、的確に叙述されている。私がこれまでどこかで読んできた音楽のこと、社会経済政治体制のことと齟齬無く、的確に叙述されている。違和感なく読書を楽しませていただいた。
別の言い方をすれば、既存の常識を並べて述べたにとどまるとも言えそうだ。新たな理路が提示されるわけではない。どこかで読んだことのあることばかり、ではある。しかし、だから良くない、ということにはならない。ここを並べて論じたことは、氏の優れた着想に他ならない。
つまり、大学の教養課程の教科書として、あるいは高校生が楽しみながら課外に読む本として、申し分のない仕上がりであると言える。ここから音楽なり、政治経済なり、いや、その他の分野であっても、専門の課程へ、興味を持って進級していく導入に最適の素材ともなりそうである。
何よりも、私は、興味深く、楽しく読ませていただいた。こういう読書の時間は至福の時である。コーヒーを淹れて、手持ちのCDからこの書物に取り上げられた楽曲を選んで聴きながら、となればなおのことである。
末尾の、以下のところは、ここで取り上げられた以降の現代音楽、調性を排除した一二音音階だとか、コンサートホールでピアノの蓋を開けたままの無音を音楽だと称するなどという、二〇世紀以降の音楽を念頭に書いたものと思う。理屈の行き過ぎた、聞きづらい、分かりにくい、相当に勉強しなければ面白さにたどり着けない現代音楽である。
「自由と平等は、人々の中に隠れていた様々な感情と多様な価値観を社会の表舞台へと引き出した。その結果、…音楽世界をバラバラに解体したように見える。」(288ページ)
「政治体制との類比で考えれば、徹底した平等を謳うデモクラシーは、一二音の音高の均等性によって中心を失った音楽のように、「多数の専制」がもたらす無秩序か、政治権力によって強いられた見せかけの秩序という、自由の精神とは全くかけ離れた世界とみることができよう。」(288ページ)
全くその通りのことと思う。
この書物は、実は経済学批判の書なのだろう。実験室的な前提を設定して、その範囲内の演繹から結論を導きだそうとする数理経済学への厳しい批判なのではないか?仮説から導き出された結論を、前提が仮説であることを忘れたふりをしてすべてに妥当する解答だと喧伝するような(あるいはそう誤解されることを放置しているような)最近の経済学のあり方への警鐘なのではないか。
今、実は、同じく新潮選書の佐伯啓思「経済成長主義への決別」を読んでいるが、そこで語られる「人間の条件」、つまり「生命」、「自然」、「世界」、「精神」の尊重と相通ずる主張を、猪木氏も語られているのではないか、と思わされたところである。
人間の音楽の至福を蔑ろにするような経済学は、不要だということである。
(最後のところは、ちょっと強引な読みに過ぎただろうか?)



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます