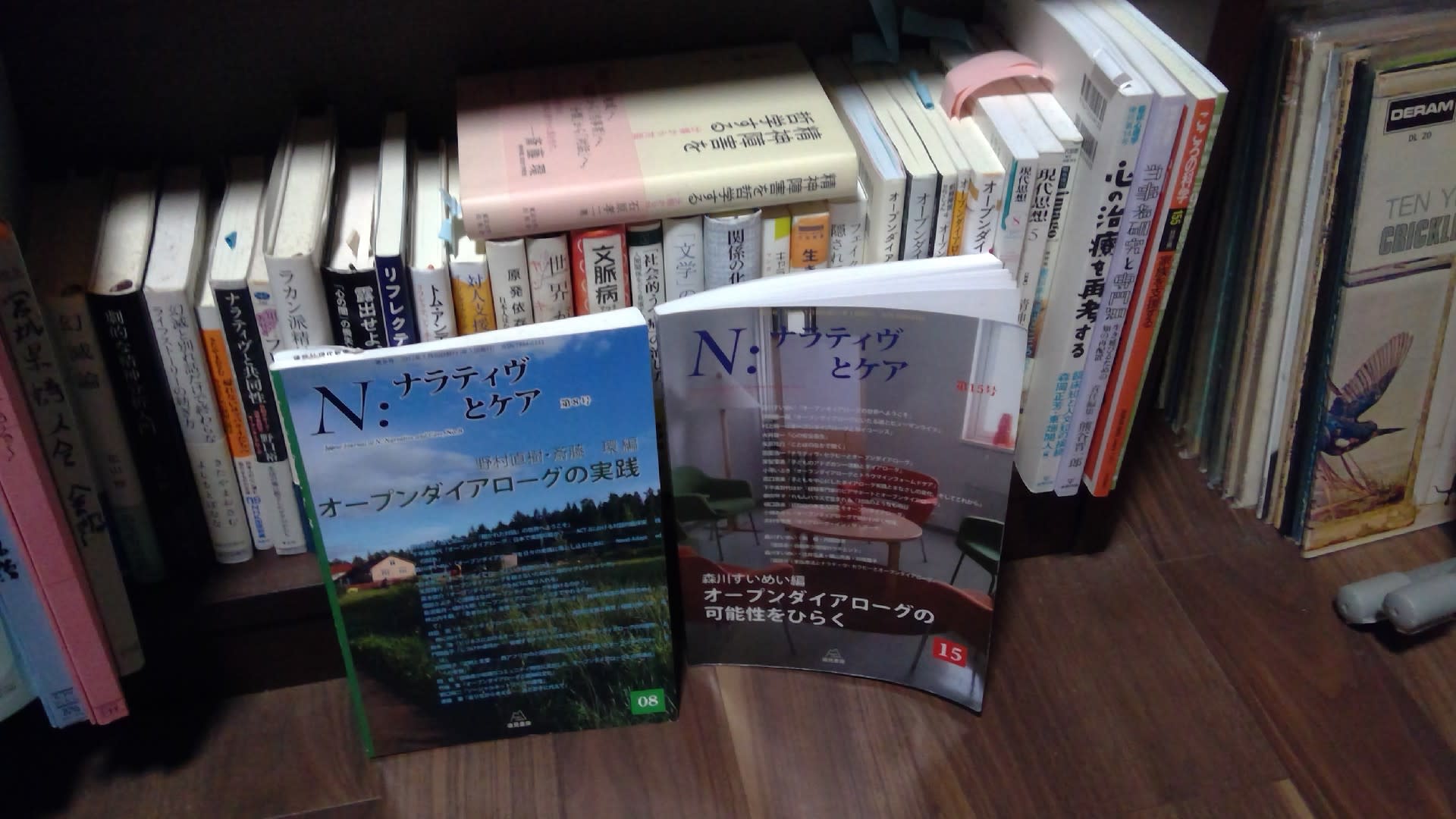
この年1回刊の雑誌は、これで二冊目。第8号の、野村直樹・斎藤環編『オープンダイアローグの実践』以来である。なぜ、ナラティブについての雑誌がオープンダイアローグについての特集を組むのか。それは似たようなものだからである、と私は大雑把に言ってしまいたい。あんまり大雑把にすぎるけれども、あながち的を外してはいないはずだ。
たとえば、国重浩一氏が、この号所収の「ナラティブ・セラピーとオープンダイアローグ」という文章を書いていらっしゃる。それを読んでも、その近さは明らかである。
さて、森川すいめい氏は、冒頭、この特集の趣旨を述べる。
「オープンダイアローグ(開かれた対話)…の世界観に触れながら、日本での多様な実践現場とその活動を、できるだけ開かれた対話的に紹介していきます。」(p.2)
多様な実践を担う人々に声をかけ、報告をしてもらい座談をしてもらった。
「どの分野であっても私より優秀な人たちがいる…。私より現場にいて、葛藤し、不確かな世界で留まり続けながら、何かの答えを探そうとしつづけている人たちが何人もいる。…仲間たちの声が集まったならば、それはオープンダイアローグをこれまでの存在しなかった表現にすることができる可能性がある。」(p.5 なお、「の」はママ)
それらの人々とは、次のような人々である。
「オープンダイアローグの誕生の経緯を知る人、歴史の証人、しかも日本から見たそれを詳しくかける人…(伊藤順一郎さん)。そのあとで、オープンダイアローグの日本のトレーナーたちが各々の実践の現場で見え、それぞれが最も大切に思っていること…(大井雄一さん、辻井弘美さん、村上純一さん)。…日本では水平な関係をつくるのがフィンランドより格段に難しい、上下関係を軽減し対話活動をしている人…(栄留里美さん、高口恵美さん、下平美智代さんと仲間の皆さま、樋口直美さん、矢原隆行さん)
日本では「本人の責任、自己責任」「権利のためには義務を果たすべき」という面がフィンランドよりとても強く、その人を助けるために環境や制度、組織が変わるとか整えるという動きがとても弱い。その弊害として人が負う「トラウマ」というものへの知識も意識も弱く、それは対話実践の妨げになっている。トラウマインフォームドコンセントと対話を行う人…(小澤いぶきさん)。
さらには医療という現場以外で…活動をしている人…(藤田琴子さん、小畑あきらさん、志村季世恵さん)。
ナラティブ…の世界にいる人(国重浩一さん、白坂葉子さん、横山克貴さん)。
そして、その到達点は、人が、自ら命を絶つほどまでに追い込まれない世界、その世界はきっと対話的で、その世界の人たちの声を招きたい(内田加奈さん、岡檀さん)。」(p.6)
最後の「到達点」たる世界とは、いわゆる自殺希少地帯のことである。
上記の執筆者紹介を、森川氏の語り口を、省略しながらそのまま抜き出してみた。各々の人名をご存じでない方は分かりづらいかかもしれないが、森川氏の問題意識は伝わるかと思う。
しかし、森川氏の語り口は優しい。むしろ、弱いというべきか。この弱さは、精神科医森川氏の、とてつもなく優れた長所だと、私は思う。
紹介は、ここまででもいいかもしれないが、以下、私として、より興味あるところを何箇所か取り上げて紹介してみたい(いや、すべてが興味深いのではある)。
【琵琶湖病院の医師、村上純一氏、バフチンとレヴィナス】
琵琶湖病院の医師、村上純一氏は、『オープンダイアローグとサイコーシス』で、レヴィナス、バフチンを取り上げている。
「哲学者レヴィナスは自らユダヤ人として戦争捕虜となり、命は助かったものの身内の多くを殺された。「私」を取り巻く世界が脅威であり、壮絶な経験を経ても世界の有り様は変わらないという不気味さを経験すれば、そこから出発することはむしろ自然だと感じる。」(p.17)
バフチンといえばポリフォニー。その「思想はオープンダイアローグの理論の根幹の1つである」。(p.18)
レヴィナスは、ユダヤ人、バフチンはロシア人である。(現時点の世界においてみると、なんということだろうか、と言わざるをえない。)
【国重浩一氏、脱中心化共有】
国重浩一氏は、「ナラティブ・セラピーとオープンダイアローグ」で、「脱中心化共有」という聞き慣れぬ言葉を記す。
「それは、その場にいる当事者のことを優先し、その人の人生を豊かに記述することに貢献するということである。つまりその場は、あくまでも、そこにいる当事者が中心化されているということであり、私たち治療者は脱中心化されなければならないのである。」(p.39)
「あくまでも舞台の中心にいるのは、相談を求めてきた人なのである。」(p.40)
このところ、オープンダイアローグ関係の書物を読みながら、専門家の専門性とは何かを考えさせられてきた。権力関係をフラットにするとすれば、何をもって専門家は専門家たり得るのか。何をもって対価を得るのか。
それは、「焦点」をどこに置くのか、なのだろうなとあたりをつけてきた。専門家は、自らに焦点を置かない。その場では、あくまでクライアントを中心に置き、焦点をあてる。他の人に焦点を置き、ケアする姿勢で関わるからこそ、対価をもらえる。
国重氏のおっしゃることは、同じことだろうと、勇気づけられる。
【スクールソーシャルワーカー高口恵美氏、社会学者矢原隆行氏と、計画の限界、というよりは無計画の可能性】
福岡県スクールソーシャルワーカースーパーバイザーの高口恵美氏は、「子どもを中心にしたダイアローグ実践とまなざしの変化、そしてこれから」において、学校という閉鎖的な場所で、オープンダイアローグという新しい手法を持ち込む困難さを語る。
「学校教育のなかである意味異物であった福祉と教育が交ざることを目指すため、多様な場面にダイアローグの場を発生させることを意識して教員との協働を試みた。」(p.56)
教育委員会方面は、外からの介入、とまでは行かないにしても、関わりを嫌うきらいがある。私自身の行政における経験から言っても。ご苦労なさったものと思う。しかし、そこで気づいたことがあるとおっしゃる。
「自身の姿勢が「伝える」ことに意識が向きすぎていて「聴く」ことが不足していたことに気が付き、対話を通して学校という組織やシステム、そこにいる人を「知る」ことから始めようと考えるようになった。」(p.59)
学校の先生方も、苦労が多い。(ここでは、余談となるが、教員の確保のためには、金銭的な待遇改善はほとんど意味が無いはずである。子どもの人数に対する教員数の配置をもっと増やして、業務量の軽減を図る、あとは、世の妙な責任追求の姿勢が改まることが必要なはずである。つまり、世の中を変える必要がある。)
高口氏は、矢原隆行氏(熊本大学の社会学の教授)の著書『リフレクティング-会話についての会話という方法』(2016)から、
「一瞬一瞬において、意識とコミュニケーションが時に交差し、時に離れていくような状況のなかで、セラピストに求められるのは、何らかの確定的なプランを保持してそれを実行するような技術ではなく、一瞬にして消えてしまうような『絶好の機会』を待つ技術」
であるという。始めから出口を計画して臨まない方がいいのだと。これも、オープンダイアローグ的には重要なポイントになる。
矢原氏も、紹介は省くが、ここで「少年院のリフレクティングプロセス」(p.27)を記されている。前に、このブログでもその著書、訳書を紹介している。
【レビー小体病当事者・樋口直美氏】
レビー小体病当事者で文筆家の樋口直美氏も「認知症のある人にこそオープンダイアローグ」を担当されている。(p.73)
【ナラティブ実践協働研究センター・横山克貴氏、社会という視点】
ナラティブ実践協働研究センターの横山克貴氏は、座談会②「家族療法とナラティブ・セラピーとオープンダイアローグ」で、次のように述べる。
「ナラティブ・セラピーをやっていて…それまで学んできた心理学では教えてもらわなかったこととして、社会という視点がすごい大切なんだということを考えています。心理学で学ぶのは。個人の心理的な状態の話だったけれど、でも僕たちはこの社会の中で、自分が置かれてしまった位置がある。…それがすごい影響しているんだと思うんです。」(p.109)
これこそ、私が、今になって、臨床心理士ではなく、精神保健福祉士を目指すことにした理由そのものである。
さて、編集後記で、森川氏は次のように記される。
「オープンダイアローグというものをどのようにしたら表現できるか。計画は立てず創造されるものに委ねるという選択。私にとっては想像を超えた出会いになりました。」
この本も、刺激的な書物でした。
野村直樹・斎藤環編 オープンダイアローグの実践 N:ナラティブとケア第8号 遠見書房 - 湾 (goo.ne.jp)
矢原隆行 リフレクティング―会話についての会話という方法 ナカニシヤ出版 - 湾 (goo.ne.jp)
樋口直美・内門大丈 レビー小体型認知症とは何か ちくま新書2023 - 湾 (goo.ne.jp)


















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます