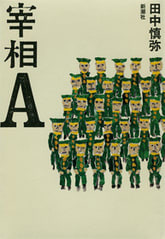「詩」を書くジプシー女の物語
ーーヨアンナ・コス=クラウゼ、クシシュトフ・クラウゼ監督 『パプーシャの黒い瞳』
越川芳明
黒い服を着た身重の女性が、店のウィンドーに飾られた白いドレスの人形をじっと見つめている。窓ガラスに映る女性の顔は少女のように驚くほどあどけない。彼女は「パプーシャ」こと、ブロニフワヴァ・ヴァイスを産んだ母親である。「パプーシャ」とは、ロマ語で人形という意味らしい。
パプーシャは、長い行列をなして森から森へと移動するジプシーの一家に生まれる。生まれて間もなく、パプーシャは厄払いを受ける。祈祷師は「羽根のように軽やかに大地を歩けますように」と祈るが、「この子は恥さらしな人間になるかもしれない」と、不吉な予言をする。
映画は、単純な時系列的展開をしない。パプーシャの誕生(1910年)と晩年の政府による表彰(1971年)という、彼女の人生の外枠をまず設定したうえで、時間軸を行ったり来たりしながら、重要な瞬間を切り取っていく。
パプーシャの物語の中にポーランドの20世紀がかいま見える。中でも、注目すべき時代は次の三つだ。 まず1925年。パプーシャは十五歳のときに、父親によって結婚を強制される。夫になるのはディオニズィという名の、ジプシー楽団のリーダー。親子ほどの年の差だ。それもそのはず、ディオニズィはパプーシャの父の兄だから。二つの大戦のあいだの、一二〇年以上ぶりに三大国から「独立」したポーランドで、ジプシーの楽団は貴族の邸宅に呼ばれて金を稼ぐ。政府の出した「ジプシー追放令」にもかかわらず、貴族たちがそれを無視している姿が映し出される。
次に、1949年~52年。第二次大戦後、パプーシャの人生は大きな転機を迎える。子供の頃から好奇心旺盛で、ジプシーの掟にさからって、商店を営むユダヤ人女性に読み書きを教わってきた彼女。1949年にイェジ・フィツォフスキという名の男がパプーシャたちの野営地にやってきて、二年ほど寝食を共にする。男は首都ワルシャワで、ナチスドイツに対するレジスタンス運動に加わり、戦後は、社会主義国の秘密警察に抵抗して、追われているのだという。皆からは「ガジョ」と呼ばれている。ジプシーたちの言葉で「よそ者」という意味だ。この男は詩人であり、ときたまパプーシャのつぶやく言葉の中に詩を発見して、ロマ語で詩を書くことを勧める。パプーシャが紙入れに書きなぐる詩は、歌の歌詞のように素朴なものだ。
すべてのジプシーよ わたしのもとへおいで 走っておいで 大きな焚き火が輝く森へ
ガジョは、パプーシャの言葉をポーランド語に翻訳して発表する。そして、パプーシャたちと一緒に暮らした経験をもとに、『ポーランドのジプシー』という本を出版する。活字をもたないジプシーの歴史や文化を、彼らに成り代わって書くという行為は、両刃の剣だ。パプーシャはポーランド中で有名になるが、ジプシーの秘密を売ったとして、夫と共に共同体から追放される憂き目に遭う。1952年、社会主義国のポーランドは、ジプシーの定住化政策を進める。住居を提供し、職業を斡旋し、子供の就学機会を与える。それと引き換えに彼らの移動の自由を奪う。
最後に、1971年。刑務所に鶏泥棒で収監されているパプーシャを女性官僚が引き取りにくる。パプーシャはコンサートホールに連れていかれて、「パプーシャのハープ」というオペラの演奏に立ち会わされる。気の進まない彼女に暴君的な大臣が列席を強要する。ジプシー詩人としてのパプーシャを顕彰することで、少数民族にも平等に機会を与えていることを宣伝し、体制内に取り込もうという「同化政策」が透けて見える。
運命に翻弄されるジプシー女性を扱っているとはいえ、悲しい出来事ばかりではなく、笑えるエピソードもある。ワルシャワの新聞がパプーシャを大々的に取りあげたとき、パプーシャの息子が通う校長が子供にその新聞を家に持ち帰らせる。字の読めない男たちに向かって息子がそれを読んできかせると、パプーシャの夫は、とんでもない自慢話を始める。自分たちは才能ある一家だ、と。「昔、俺はレーニンの前で演奏した。革命で疲れ果てたレーニンが演奏を聴いて小躍りして喜んだ。翌朝には執事がシャンペンを注ぎにきた。クレムリン宮殿での話だ。レーニンが言った。『貴君なしには革命はなし得ない。私の右腕としてここにいてくれ。我が偉大なる宮廷楽師よ』」と、大ぼらを吹く。仲間が「なぜ断った」と問いつめると、夫は「ピウスツキ元帥と先約があったからさ。元帥はジプシー音楽を愛したんだ」と、自慢話を締めくくる。
いうまでもなくレーニンは、市民革命によってロシア帝国を打倒し、社会主義国家ソ連を樹立した指導者だし、ピウスツキ元帥と言えば、第一次世界大戦をへてようやく復活した「第二次ポーランド共和国」の初代元首であり、「建国の父」と見なされる男である。だから、このほら話には、自分たちジプシーは、各地で厄介者扱いされながらも、ポーランドにもソ連にも帰属しない誇り高い遊牧民なのだ、という自覚がうかがえる。
ジプシーの物語は、過去のものだろうか。シリアをはじめ、中東の国境地帯でテント暮らしを余儀なくされている戦争難民や、祖国を離れて他国で暮らす経済難民など、世界にはかつてのジプシーと同様、国籍(国軍)によって守られない「見えない人々」が大勢いる。そういう意味で、もっとも現代的なグローバルな問題を提起しているのだ。(『すばる』2015年4月号、340-341ページ)