
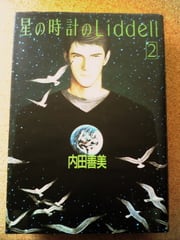

内田善美(集英社)
《あらすじ》
ウラジーミルの友人ヒューは、何度も同じ夢を見る。それはヴィクトリアン・ハウスの屋根裏で目覚める夢で、彼はその夢に何かがひそんでいるというのだが…。
《この一文》
“ 俺はね 何者でもない そのことがね けっこう気に入ってる
詩人でもない 画家でもない 音楽家でもない
たとえばさ そういうことがけっこう気に入っている ”
私は偶然を信じない。いや、私には偶然を知覚できない。というのも、それが起こったり、それと出会った時には、それらはもはや偶然ではなく、なるべくしてそうなったという必然であるから。それらは偶然ではなく運命や宿命と呼ばれるものだと、私にはそのようにしか感じられないからだ。つまり私は「偶然の出会い」を信じない。
そうして運命が時々私を呼ぶ。そんなことが、ついこのあいだも起こった。
ある晴れた土曜日の朝、私は一通のメッセージを受けとった。旧友からで、近くまで来るつもりだから会おうという内容だった。その朝は特別な朝で、ちょうど私は10年近く探し求めていた1冊の古書が私の手に届くような値段で売られているのをようやく初めて見つけて、慌てて注文したところだった。それだけでも十分に幸運だったのだが、この日の幸運はさらに続いた。
なるべく手短に述べると、土曜日に会った友人から内田善美の『星の時計のLiddell』という全3巻の漫画の話を聞いたのだが、それはまさに私がかつて熱心に探したものの手に入れられないままでいた本だったのだ。彼女の口から語られるその物語の内容は、やはり期待していたとおりに魅力的なもので、聞いているだけで心が躍った。彼女は、彼女にとってとても特別なものとなったというそれを、二組持っているから片方を私に譲ってくれるという。信じられないような話だったが、本当になった。
私は驚いたままで後日彼女からその本を受けとったのだが、宿命がやってきたということは既に分かっていた。
宿命の物語とは、その物語のなかに自分ごとすっかり入り込んでしまえる物語、物語が自分の一部になるのではなくて自分がその一部となってしまえる物語、はじめから自分がそこに含まれていたとわかる物語であると私は考えている。以前私は、私にとっての宿命の物語である『類推の山』を彼女にすすめたことがある。彼女はそのことを今でも覚えていてくれて、彼女にとって特別な物語となった『星の時計のLiddell』を「お返しに」と私にくれた。そしてそれが、私がひそかにずっと探していたものであったとしたら、これを運命と言わずに何と言おう。こうして私の歩いてきた道筋に、この本は必然としてやってきたのであった。夢と現実とが結びつくこの美しい瞬間のことを、私は宿命と呼ぶことにする。私に美しいものをもたらしてくれた、彼女に心からの感謝を。
『星の時計のLiddell』、結論から言うと、これはたやすく私の新しい宿命の物語となった。あまりにも望んでいた通りで、あまりにも望んでいた以上で、私はこの物語の前に語る言葉を持たない。私はこの物語によって凌駕され、ただすべてを忘れ、すべてを失ってそこに立っていた。私はそこで何も持たなくてよかった。
夢と、現実と、かなしみと、うつくしさと。
夢の、現実の、かなしみの、うつくしさの、………が。
この物語について私はこれ以上に説明するための言葉を持ち得ないし、それで構わないと思う。私が生きている限り、私はこの物語の一部であり、このさき私から語られる言葉の端々にこの物語の姿がちらちらと見えるようになるだろう。語ろうとして語り切れないでいた言葉が、目を開けたままで見られる夢、目を開けるために見る夢が、より完全に近い形でここにあらわれているのを知るために、私はここへ呼ばれたのだ。
いま、どうにか一言だけ思うことを言えるとすれば、そうだな。この目にも心にも溢れるほどに美しい物語が、もしも本当に私を呼んでくれたのだとしたら、私はせめてそのために少しでも美しいものになりたい。ほんの少しだけでも美しいものでありたい。
そしてこの美しい物語の中にいた間、すべてを忘れすべてを失っていたあの間、私はたしかにほんの少しだけ美しかった。と、確信している。最後の頁を閉じたあとも、たくさんの輝きが私の目に焼き付いていた。焼き付いた分だけ、私は物語の部分となり、それがそうであるように美しくあったはずだ。
いつも見上げている星々の、ひとつの名前が分かった。
『星の時計のLiddell』。予感と希望の夢の物語。




