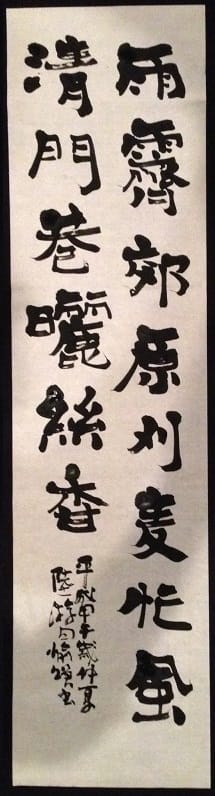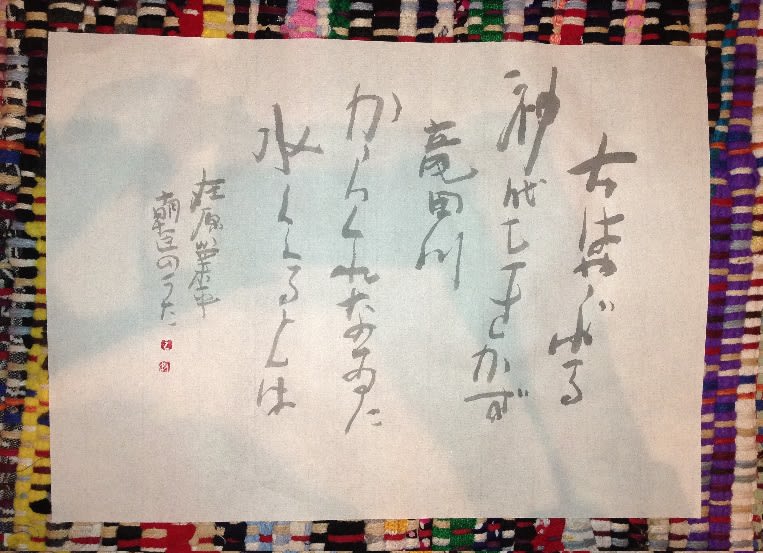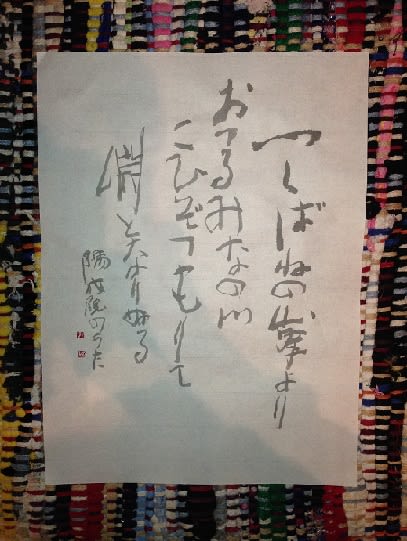母の日はいつも、いもうとと連盟で花をあげることにしている。
それは、今までけいこにあげたいくつかの贈り物で花しか喜んでいる様子がないからだ。
カップが好きだからとロイヤルコペンハーゲンのマグカップをあげても戸棚の中にしまい込んでしまうし、剥げた箸を使っているので高級そうな箸をあげても未だ使っているのを見たことはない。
食べ物も、それがたとえ桐箱に入った霜降り和牛肉であろうと、洗練されたハイソな包装のバームクーヘンであろうと、宝石みたいにきらびやかでお行儀の良く並んだ佐藤錦であろうと、全然欲しくなさそうなのは容易に想像がつく。
アクセサリーやバッグは、さっぱり趣味がわからないのであげる気にもならない。
しかし花というか植物ならなんでも喜ぶ。
事実、何年も前にあげたアジサイやブルーベリーの鉢植えは未だ健在だし、どこかに出かけるときには「アジサイが心配だから長く家は空けられない」などとも言う。
花を飾るのは、好きでなければ面倒以外の何物でもない行為だ。
しかしけいこの家には季節の花が小さな仏壇にも、トイレにも飾ってある。
ただし乱雑に。
私の花好き、植物好きはけいこから来ている。
今年はなんの花にしようかといもうとと話していたら、彼女はミニ盆栽を育てているのでそれがいいのではと言う。
花が咲いて、実がなって、葉っぱが紅葉して、落葉して、芽吹く、その過程を一年を通して見られるからとてもかわいいらしい。
ちなみにいもうとは私よりも花や植物が好きではないが、そのミニ盆栽が海外旅行中に枯れてしまうといけないからとわざわざ宅急便で私に送りつけてきて、水やりを頼むと言われたことがある。
気に入るものがあったら私も買おうかとインターネットを見ていたけれど、盆栽は基本的に日光を好むらしいので、直射日光はあまり当たらない私の部屋は適さないようだ。
ついでに今家にあるパキラがどうにも元気がなく、編まれている5本の木のうち1本以外は枯れているように思ったので色々と調べてみる。
やはり復活は厳しいほどに枯れていると思われたので思い切って編まれている木をほどくように解体していく。
幹もぐらぐらしているので、土から引っこ抜くと小さな虫が動いているのが見えた。
幸い、私の嫌いなうようよ動くものではなく、羽アリのような虫が何匹もいた。
とは言えそういう虫も別に好きなわけではないので、ビニール手袋をして鉢ごとビニール袋に入れて、粗大ごみの予約を入れる。
すると土ごと粗大ごみにはできないらしいので、虫入りの土を分けなければいけないのだが、恐ろしくてまだやっていない。
生きている木の上部だけは挿し木しようと、その方法も調べてとりあえず花瓶に水を入れて避難させる。
新芽が芽吹いている苗木、根付いてくれるといい。
そのパキラが置いてあった場所が空いて、ぽかんと空間ができた。
ついでにその辺りにあった布団乾燥機をしまって、冬用の敷き毛布を洗って、水が溜まった除湿剤を捨てて。
そうしていたら、模様替えがしたくなった。
今のところに引っ越して9か月。
最初に作ったインテリアの感じに飽きてきて、布団カバーやカーテンを変えたかったりもしている。
しかし今の収入では余分なものを買っている余裕はあまりない。
フジロックの費用にプラスしてもう少し稼ごうかなと思う。
ついでついでと色んなことをやっていたら母の日の贈り物を選べずにいる。

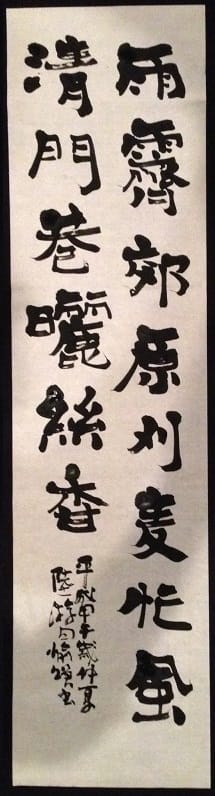
それは、今までけいこにあげたいくつかの贈り物で花しか喜んでいる様子がないからだ。
カップが好きだからとロイヤルコペンハーゲンのマグカップをあげても戸棚の中にしまい込んでしまうし、剥げた箸を使っているので高級そうな箸をあげても未だ使っているのを見たことはない。
食べ物も、それがたとえ桐箱に入った霜降り和牛肉であろうと、洗練されたハイソな包装のバームクーヘンであろうと、宝石みたいにきらびやかでお行儀の良く並んだ佐藤錦であろうと、全然欲しくなさそうなのは容易に想像がつく。
アクセサリーやバッグは、さっぱり趣味がわからないのであげる気にもならない。
しかし花というか植物ならなんでも喜ぶ。
事実、何年も前にあげたアジサイやブルーベリーの鉢植えは未だ健在だし、どこかに出かけるときには「アジサイが心配だから長く家は空けられない」などとも言う。
花を飾るのは、好きでなければ面倒以外の何物でもない行為だ。
しかしけいこの家には季節の花が小さな仏壇にも、トイレにも飾ってある。
ただし乱雑に。
私の花好き、植物好きはけいこから来ている。
今年はなんの花にしようかといもうとと話していたら、彼女はミニ盆栽を育てているのでそれがいいのではと言う。
花が咲いて、実がなって、葉っぱが紅葉して、落葉して、芽吹く、その過程を一年を通して見られるからとてもかわいいらしい。
ちなみにいもうとは私よりも花や植物が好きではないが、そのミニ盆栽が海外旅行中に枯れてしまうといけないからとわざわざ宅急便で私に送りつけてきて、水やりを頼むと言われたことがある。
気に入るものがあったら私も買おうかとインターネットを見ていたけれど、盆栽は基本的に日光を好むらしいので、直射日光はあまり当たらない私の部屋は適さないようだ。
ついでに今家にあるパキラがどうにも元気がなく、編まれている5本の木のうち1本以外は枯れているように思ったので色々と調べてみる。
やはり復活は厳しいほどに枯れていると思われたので思い切って編まれている木をほどくように解体していく。
幹もぐらぐらしているので、土から引っこ抜くと小さな虫が動いているのが見えた。
幸い、私の嫌いなうようよ動くものではなく、羽アリのような虫が何匹もいた。
とは言えそういう虫も別に好きなわけではないので、ビニール手袋をして鉢ごとビニール袋に入れて、粗大ごみの予約を入れる。
すると土ごと粗大ごみにはできないらしいので、虫入りの土を分けなければいけないのだが、恐ろしくてまだやっていない。
生きている木の上部だけは挿し木しようと、その方法も調べてとりあえず花瓶に水を入れて避難させる。
新芽が芽吹いている苗木、根付いてくれるといい。
そのパキラが置いてあった場所が空いて、ぽかんと空間ができた。
ついでにその辺りにあった布団乾燥機をしまって、冬用の敷き毛布を洗って、水が溜まった除湿剤を捨てて。
そうしていたら、模様替えがしたくなった。
今のところに引っ越して9か月。
最初に作ったインテリアの感じに飽きてきて、布団カバーやカーテンを変えたかったりもしている。
しかし今の収入では余分なものを買っている余裕はあまりない。
フジロックの費用にプラスしてもう少し稼ごうかなと思う。
ついでついでと色んなことをやっていたら母の日の贈り物を選べずにいる。