
いくら調べてみてもよくわからないのがアイヌ民族の霊や神の概念だが、11あるうちの約半分が、日本民族と共通のしているそうだ。(「アイヌの霊の世界」より)
それは「カムイ」「ピト」「イノッ」「タマ」等と、古代日本語と共通の「ラマッ」である。
そしてそれらは、約一万年間この列島で栄えた縄文文明・文化の基層的な内容を継承しているのではないだろうか。古代日本と同様と共通するものは、現在先祖霊崇拝とひと言で要約可能だが、それはシャーマニズムとアニミズムとの合体なのではと思う。さらなる特徴は、内地以南の日本列島で、神の使いにへと貶められた動物たちが、その家系の先祖神になっている点かもしれない。この4っつに分類可能な世界を支配している動物霊も、山林は熊神で、コタン(村落)の神はシマフクロウで、地下は蛇神で、海を支配しているのはシャチ神。
アイヌの霊や神を機能面で分類するとー①性別を決定するだけの能力しかない個々の霊 ②憑き神のなかでも2種類の先天的な霊 ③同じく後天的な4種類の神 ④人間集団に憑く5種類の神(先天的な神が2種類と後天的な神が3種類)
次にアイヌ民族の先天的な神である祖先神について考えることにしたい。祖先神の正体は、植物神や自然神よりも動物神が多くて(狩猟民族だったためだろう)、それぞれの家系ごとに祖先神の極秘の物語が伝承されているそうだ。祖先神の具体的な表現は、男女双系のうちの男子系では、木幣や矢などに見られる家紋であり、女子系では貞操帯の女性の出身家系の家紋だ。
ざっと見たところでは、熊・狼・シャチ・鳥類・病気の順に多いような印象がある。アイヌ民族のアイデンティティは、この家系を伝えるという事にかなりの比重が置かれているのではないかと思われる。
この点では、お盆くらいにしか祖先を意識しない日本人や、古代以来のシャーマンであるユタ(東北恐山のイタコや中世の流れ巫女もその末裔)の主要な仕事が家系探しであるらしい沖縄に比べてみても、アイヌ人の方がより基層的な縄文人の信仰形態を、現在まで残しているのではないかと思える。
この列島の信仰の変遷を顧みるならー
①約一万年間という縄文時代のシャーマンと蛇神信仰の次に、この列島に入ってきたのは、②華南とも共通する南九州の隼人の犬神(狐神・狐つきはそのバリエーション)信仰
③古代朝鮮半島とも共通する鳥信仰(高句麗等の古代朝鮮国家の「朱雀」の重視で、沖縄の神女や伊勢神宮の天皇即位式でも朱雀紋の衣服を重視)
④最後にはこの列島に入ってきたのが弥生農耕民がもたらした「サの神」(遮るというサイの神がその原義なのかも・・早乙女、皐月、酒、桜、刺身、薩摩・土佐(青森の十三湊も)・讃岐・佐渡等の地名)信仰であり、鳥居(神の使いという鳥信仰)や、注連縄(蛇信仰)では彼岸・此岸との結界を作って、お盆・正月にはその結界を解いて先祖霊と交流(送り火や節分)をなし、また結界の向こうの山(先祖霊が天から降臨)へと送り返すというこの列島の古代信仰がごっちゃになった風習だと思う。
⑤伊勢神宮で特徴的な・・古代中国の風水&星信仰(伊勢神宮内宮での最高神は「太一」=北極星で、その霊を次の天皇が、添い寝して受け継ぐという儀式が最大の天皇霊継承儀式)で、元々の皇族の家紋も月星紋であり、菊紋や平安時代になんとか上皇が作った紋で・・古代日本で最後の支配者となった天武天皇時代には、極めて道教・儒教的内容が強かったのではと思われる。
それは「カムイ」「ピト」「イノッ」「タマ」等と、古代日本語と共通の「ラマッ」である。
そしてそれらは、約一万年間この列島で栄えた縄文文明・文化の基層的な内容を継承しているのではないだろうか。古代日本と同様と共通するものは、現在先祖霊崇拝とひと言で要約可能だが、それはシャーマニズムとアニミズムとの合体なのではと思う。さらなる特徴は、内地以南の日本列島で、神の使いにへと貶められた動物たちが、その家系の先祖神になっている点かもしれない。この4っつに分類可能な世界を支配している動物霊も、山林は熊神で、コタン(村落)の神はシマフクロウで、地下は蛇神で、海を支配しているのはシャチ神。
アイヌの霊や神を機能面で分類するとー①性別を決定するだけの能力しかない個々の霊 ②憑き神のなかでも2種類の先天的な霊 ③同じく後天的な4種類の神 ④人間集団に憑く5種類の神(先天的な神が2種類と後天的な神が3種類)
次にアイヌ民族の先天的な神である祖先神について考えることにしたい。祖先神の正体は、植物神や自然神よりも動物神が多くて(狩猟民族だったためだろう)、それぞれの家系ごとに祖先神の極秘の物語が伝承されているそうだ。祖先神の具体的な表現は、男女双系のうちの男子系では、木幣や矢などに見られる家紋であり、女子系では貞操帯の女性の出身家系の家紋だ。
ざっと見たところでは、熊・狼・シャチ・鳥類・病気の順に多いような印象がある。アイヌ民族のアイデンティティは、この家系を伝えるという事にかなりの比重が置かれているのではないかと思われる。
この点では、お盆くらいにしか祖先を意識しない日本人や、古代以来のシャーマンであるユタ(東北恐山のイタコや中世の流れ巫女もその末裔)の主要な仕事が家系探しであるらしい沖縄に比べてみても、アイヌ人の方がより基層的な縄文人の信仰形態を、現在まで残しているのではないかと思える。
この列島の信仰の変遷を顧みるならー
①約一万年間という縄文時代のシャーマンと蛇神信仰の次に、この列島に入ってきたのは、②華南とも共通する南九州の隼人の犬神(狐神・狐つきはそのバリエーション)信仰
③古代朝鮮半島とも共通する鳥信仰(高句麗等の古代朝鮮国家の「朱雀」の重視で、沖縄の神女や伊勢神宮の天皇即位式でも朱雀紋の衣服を重視)
④最後にはこの列島に入ってきたのが弥生農耕民がもたらした「サの神」(遮るというサイの神がその原義なのかも・・早乙女、皐月、酒、桜、刺身、薩摩・土佐(青森の十三湊も)・讃岐・佐渡等の地名)信仰であり、鳥居(神の使いという鳥信仰)や、注連縄(蛇信仰)では彼岸・此岸との結界を作って、お盆・正月にはその結界を解いて先祖霊と交流(送り火や節分)をなし、また結界の向こうの山(先祖霊が天から降臨)へと送り返すというこの列島の古代信仰がごっちゃになった風習だと思う。
⑤伊勢神宮で特徴的な・・古代中国の風水&星信仰(伊勢神宮内宮での最高神は「太一」=北極星で、その霊を次の天皇が、添い寝して受け継ぐという儀式が最大の天皇霊継承儀式)で、元々の皇族の家紋も月星紋であり、菊紋や平安時代になんとか上皇が作った紋で・・古代日本で最後の支配者となった天武天皇時代には、極めて道教・儒教的内容が強かったのではと思われる。










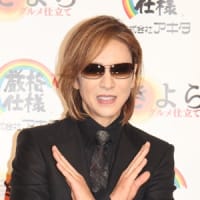


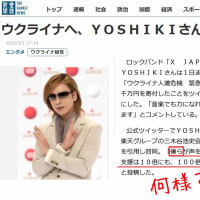


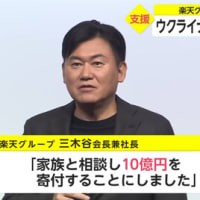
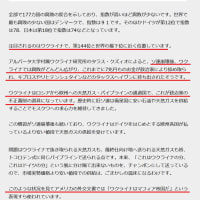



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます