8日(金)9時から昼近くまで、全議員10名出席の元、議員協議会が開かれました。
まず議長から「議会の在り方を検討して行く」と言うことで、臨時議会における
町側説明員の招集の仕方について話し合われました。
町長から臨時議会において職員全員ではなく、関係者のみ出席してはどうか
という提案があり、議会で検討することになりました。
かつて遠藤町長、菊地町長の時は、臨時議会では職員全員ではなく、議案に関係
ある説明員が出席して開かれていたとのことです。しかし逢坂町長の時から全員
<情報共有>した方が良いということで臨時議会においても課長(一部係長クラス)
が全員出席するようになったという経緯があります。
今日の話し合いの結果では臨時会では関係説明員の出席でよいのではないかと
なったようですが、私個人の考えとしてはこれまでもそうでしたが、関係外の説明員が
病気や所用で欠席していたこともありました。ですからどうしてもやむを得ない理由が
ある場合は臨時会を欠席するのは仕方ないことだと思います。しかし逢坂町長と同様に
情報共有と言う意味で説明員は出席した方が良いのではないかと思います。
所管事務調査の実施時期や内容については資料を1週間から10日位前に提出してもらい
確り勉強し、質問出来る形で臨みたいという意見・希望があり、行政側に伝えて
検討してもらうことになりました。これは大切なことと思います。
現在常任委員会は総務常任委員会と産業建設委員会の二つあります。
所管事務調査の資料を双方とももらってはどうかということになりました。
これまでだと所属する委員会が違うと互いに何をしているのか全く分から状態でしたが、
互いに情報共有ができると思います。また開かれる時期が違うので、希望すれば
もう一方の所管事務調査にも出席可能になると思います。
また定例会での日程を現在の4日程度から7~10日取ってその中に日程を組み込み、
議員同士のコミュニケーション活性化を図ることも話合われました。
今日の資料の中にニセコ町・栗山町・芽室町の各議会の会議規則・委員会条例等の比較があり、
その中で議会活動の差についてはニセコ町議会と比較して常任委員会の開催される回数が
栗山町議会で4倍、芽室町議会で7倍も開かれていました。
私は芽室町議会改革の様子を見に過去2回芽室町を訪れたことがあります。
また北海道大学公共政策大学院でも芽室町議会の議会・議員活動と議員報酬の関係に
ついて調査した結果の発表があり参加したことがあります。大変興味深い結果でした。
芽室町議会は北海道大学公共政策大学院と連携して指導教官や院生たちの助けを借りて
議会の在り方について研究やアドバイスを長年に渡って受けてきました。
また道外からも大学教授を顧問に迎え、他にも先進的な議会活動を行なってきた議会議長等
を招いて発表してもらう等様々な活動を行ってきました。
この様子についてニセコ町の議員協議会で少し話しをしようとしたことがありましたが、
残念なことに当時は<馬の耳に念仏、猫に小判、豚に真珠>のことわざ通り、100%否定され
(それよりも)大学とか専門の研究者の意見を聞くことへの反発の強さを感じました。
全面拒否され、受け入れようとしない姿勢でした。
しかしいつまでも現状維持のままではいかないと思います。
また今後「全員協議会」を「政策会議」という名称に変えることになりました。
ニセコ町議会は今新たな議会活動のスタートを切ろうとしています。
5年、10年先にその結果が現れることを目指して切磋琢磨が求められています。
まず議長から「議会の在り方を検討して行く」と言うことで、臨時議会における
町側説明員の招集の仕方について話し合われました。
町長から臨時議会において職員全員ではなく、関係者のみ出席してはどうか
という提案があり、議会で検討することになりました。
かつて遠藤町長、菊地町長の時は、臨時議会では職員全員ではなく、議案に関係
ある説明員が出席して開かれていたとのことです。しかし逢坂町長の時から全員
<情報共有>した方が良いということで臨時議会においても課長(一部係長クラス)
が全員出席するようになったという経緯があります。
今日の話し合いの結果では臨時会では関係説明員の出席でよいのではないかと
なったようですが、私個人の考えとしてはこれまでもそうでしたが、関係外の説明員が
病気や所用で欠席していたこともありました。ですからどうしてもやむを得ない理由が
ある場合は臨時会を欠席するのは仕方ないことだと思います。しかし逢坂町長と同様に
情報共有と言う意味で説明員は出席した方が良いのではないかと思います。
所管事務調査の実施時期や内容については資料を1週間から10日位前に提出してもらい
確り勉強し、質問出来る形で臨みたいという意見・希望があり、行政側に伝えて
検討してもらうことになりました。これは大切なことと思います。
現在常任委員会は総務常任委員会と産業建設委員会の二つあります。
所管事務調査の資料を双方とももらってはどうかということになりました。
これまでだと所属する委員会が違うと互いに何をしているのか全く分から状態でしたが、
互いに情報共有ができると思います。また開かれる時期が違うので、希望すれば
もう一方の所管事務調査にも出席可能になると思います。
また定例会での日程を現在の4日程度から7~10日取ってその中に日程を組み込み、
議員同士のコミュニケーション活性化を図ることも話合われました。
今日の資料の中にニセコ町・栗山町・芽室町の各議会の会議規則・委員会条例等の比較があり、
その中で議会活動の差についてはニセコ町議会と比較して常任委員会の開催される回数が
栗山町議会で4倍、芽室町議会で7倍も開かれていました。
私は芽室町議会改革の様子を見に過去2回芽室町を訪れたことがあります。
また北海道大学公共政策大学院でも芽室町議会の議会・議員活動と議員報酬の関係に
ついて調査した結果の発表があり参加したことがあります。大変興味深い結果でした。
芽室町議会は北海道大学公共政策大学院と連携して指導教官や院生たちの助けを借りて
議会の在り方について研究やアドバイスを長年に渡って受けてきました。
また道外からも大学教授を顧問に迎え、他にも先進的な議会活動を行なってきた議会議長等
を招いて発表してもらう等様々な活動を行ってきました。
この様子についてニセコ町の議員協議会で少し話しをしようとしたことがありましたが、
残念なことに当時は<馬の耳に念仏、猫に小判、豚に真珠>のことわざ通り、100%否定され
(それよりも)大学とか専門の研究者の意見を聞くことへの反発の強さを感じました。
全面拒否され、受け入れようとしない姿勢でした。
しかしいつまでも現状維持のままではいかないと思います。
また今後「全員協議会」を「政策会議」という名称に変えることになりました。
ニセコ町議会は今新たな議会活動のスタートを切ろうとしています。
5年、10年先にその結果が現れることを目指して切磋琢磨が求められています。











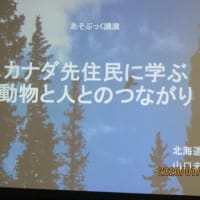


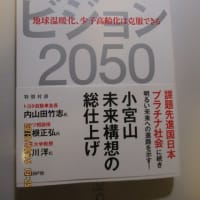



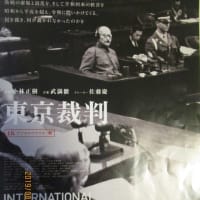
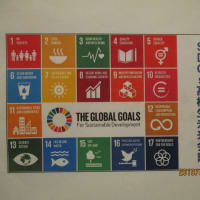
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます