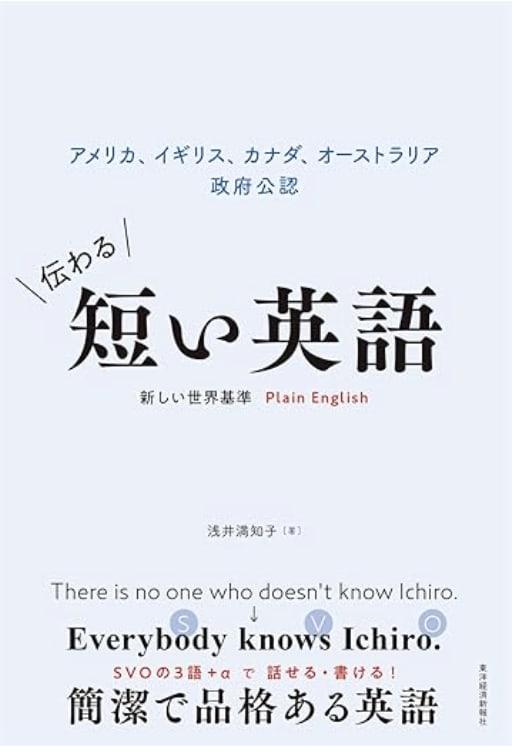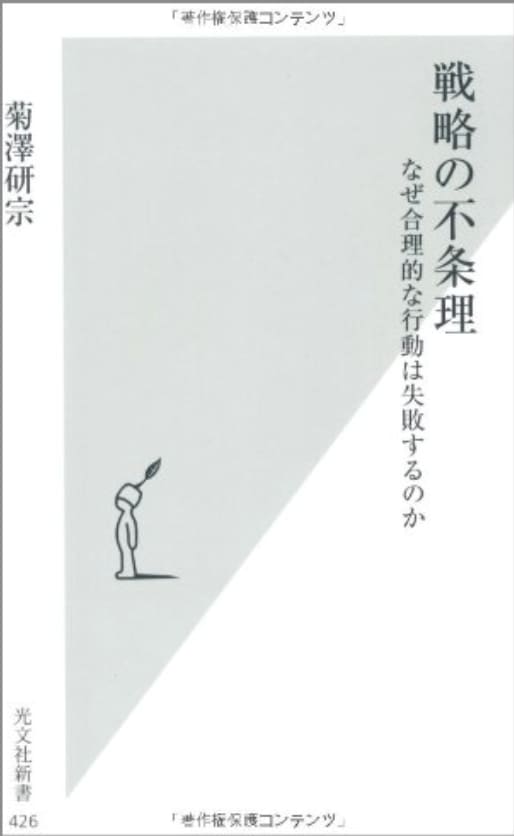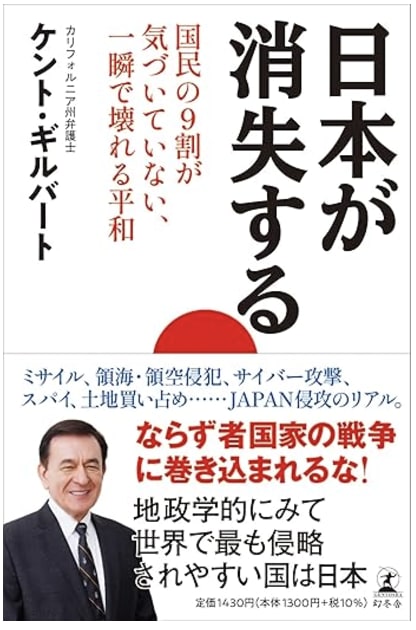@翻訳ビジネスでのエピソード:日本語の文章は主語が抜けて記述することも多々あり、それをそのまま生成AIなどの翻訳にすると意味を間違えて翻訳すると言う。実際その後、翻訳された英語から日本語にする事でその主語がない事での間違いがあることが理解できる、と言う。間違って理解されないようにするには、日本文には的確に主語を入れておく事である。最近富に「速く」「効率的で」「理解しやすく」「簡潔な言葉で」と言うことから急いで間違った文章作成は禁物である。
ここにある、「言葉とは読者、聞き手に効果的に情報を伝達し、『次のアクションに繋げてもらう』と言うニーズに応えるものだ」と言うことだ。英語では特に結論を先に述べ、後に補足するスタイルなので注意したい。今ここに「プレインランゲージ」と言う協会団体が世界標準化に向けて活動しており、日本にもその波が来ている(一般社団法人日本プレインランゲージ協会:https://japl9.org)
『伝わる短い英語』浅井満知子
「概要」書ける!話せる!伝わる!プレイン・イングリッシュをていねいに解説 アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア政府が認める「短い英語」プレイン・イングリッシュ。欧米の官公庁はもちろん、ジャーナリズムやビジネスの現場で使われているスタイルです。「速く」「効率的で」「理解しやすい」を特徴とする簡潔な英語伝達法です。本書は10のガイドラインに基づいて、プレイン・イングリッシュを「書く」「話す」ための方法を解説。強い動詞とシンプルな単語で、クリアでストレートに伝わる英語が使えるようになります。短く言い換える事例、単語の書き換えリストも豊富に掲載。非ネイティブが学びやすい英語の決定版です。
ー法律用語をきっかけに世界中の言語の平易化・標準化が進行中(世界50カ国650人の団体)
一般が分かりにくい文章は、結局理解できなく手間も暇もかかる(時間とコストの浪費)
歴代の米国大統領の演説は「中学校2年生レベル」だという
トランプ大統領の演説は小学校4~5年生レベルであり、誰もが理解できる言葉を採用
日本での日本IR協会(インベスターリレーションズ)での簡易日本語化が普及
(米国、カナダ、オーストラリアではISO(世界標準化規格)を採用、法的化した)
ープレインジャパニーズのガイドライン(日本語化標準)
・情報の整理(効果的に伝えるために:読者にとって大切なことを理解)
・対象読者を想定する(読みやすさ)
・重要な情報は文章の先頭に置く(まず結論を述べる)
・長文より短文を用いる(17~20ワードの長さ)
・短く、シンプルな単語を使う(抽象的よりも直接的な単語を用いる)
・専門用語は必要最低限に抑える(相手の行動を促す分かり易い単語を用いる)
・能動態を使う(受動態を避ける)
・強い動詞を使う(動詞の名詞化は使用しない)
・否定・二重否定を避ける(肯定形に変換する)
・主語・動詞・目的は近づける(何がどうする)
・読みやすいデザインにする(箇条書き・図形挿入)
ー「If you can not explain it simply, you do not understand it well enough」アルバート・アインシュタイン