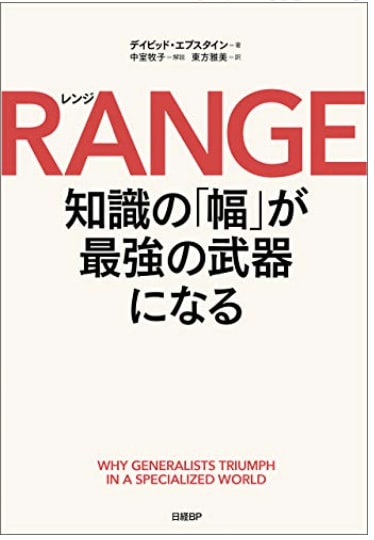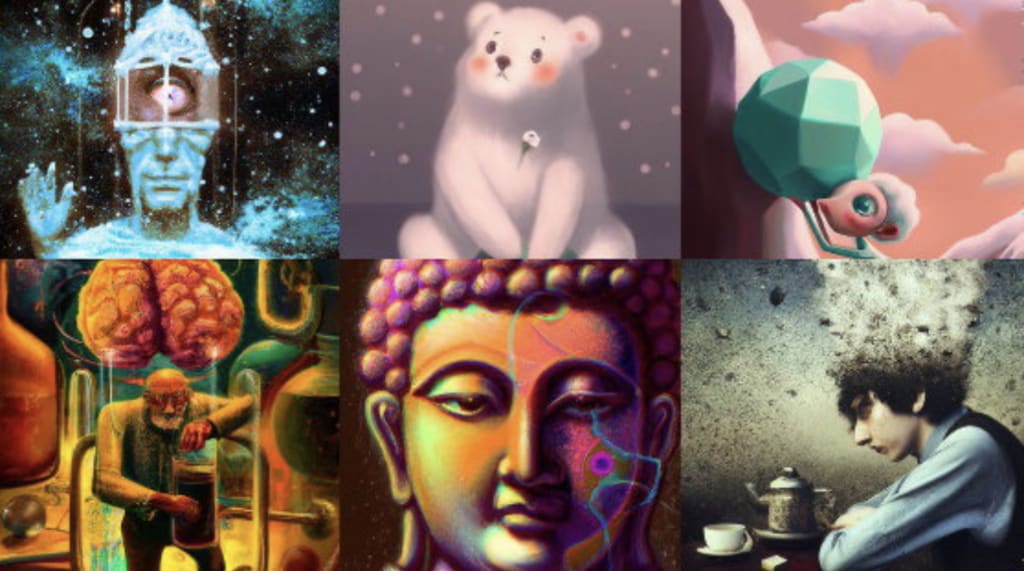@徳川幕府3代将軍までの潤沢な財源もその後は備蓄が瞬く間に減り財政難に、それ以降幕府は再建の見通しがなかったことが明確だ。特に幕末における外国と借款までするという事実は、大政奉還(幕府返上)がもはややもう得ない状況であったことが頷ける。「歴史の繰り返し」は、質素倹約等せず財政難を逃れるとたちまち資金難になる様は現代の政治家等の思考と変わらないのではないかと思える。新たな経済収入構造を構築をできない、しない。しかも政治家は一才国家予算の削減はせず浪費を増やし、収入源は簡単に新税を設け続ける構造は国民にとってもう限界だ。よって財務大臣、日銀総裁は国民が賛同する政策を早々に発信することだ。
『徳川幕府の資金繰り』安藤優一郎
「概要」豊かな財政を誇った徳川幕府も、資金繰りには悩まされていた。将軍の浪費、インフラ整備、相次ぐ災害、鉱山経営の停滞……。財政難を背景に幕府が資金繰りに奔走した歴史を、五つの時代に分けて解明。
ー徳川家康の富(家康から三代将軍家光まで財政は豊かだった)
前:所領250万石(直轄領100万石)vs 秀吉1850万石(直轄220万石)
後:250万石+780万石(直轄400万石)+金銀銅山(鋳造権の独占)
>>収入
年貢+鉱山(勘定所が管轄:大久保長安)
1602年には銀山産出量1万貫(3万7500kg)を超えたがそれ以降減産
鋳造権で中国からの粗悪な銭を排除(銭貨の統一)
貿易は必要なものだけの供給で財源は期待されなかった
大規模年貢米システムで江戸に備蓄、保管された(常に40~50万石)
江戸には蓮池御金蔵、奥御金蔵と巨万の富を蓄えた
ー財政難の始まり(4代将軍家綱から7代将軍家継)
原因:江戸城の大火(明暦の大火)と年貢量の限界・鉱山の減産・富士山の大噴火
収入源として:大火復興費用を大名名義(天下普請:御手伝名目で徴収)
江戸改造(百万都市計画)環境整備費用・寺復興事業(奈良大仏修繕)
貨幣改鋳(荻原重秀による金貨銀貨含有量を減量)
元禄小判:金の含有率を86.8%から57.4%
ー財政再建に取り組む(8代将軍吉宗から10代将軍家治)
対策:新田開発や年貢率のアップ・大名への上米令・商業活動への運上金・冥加金
豪商や豪農の資金(御用金)・幕府による公債割当(低利での貸付)
8代吉宗:質素倹約(1日2食で1汁1菜・衣服は木綿)人員整理
新田開発には奨励金・公募し資産を拡大させた(140万石から156万石に)
年貢率をアップ(30%から50%)させたが定額量「定免法」とした
幕府としての金融業公金貸付開始(低金利で貸付 原資は運上金・冥加金)
1842年貸付額259万両(拝借金91万両、取替金16万両)
富裕層からの御用金で借金し、利息付きでも返済できなかった
豪商・豪農から借金(御用金)を踏み倒す結果になった
125万両のうち55万両が元金で返済不可となり利子38万両も未返済
河川の普請費用は大名が負担・各藩の負担とした(朝鮮通信使の費用も地元負担)
1730年の幕府財政収支の内訳
>>収入の部
年貢63.7%、貿易利潤6.9%、御用金3.6%、小普請3.4% その他18%
>>支出の部
切米・役料40.7%、役所経費20.4%、米買上げ14.2%、奥費用8.3%
ー財政負担を押し付ける(11代諸軍家斉から12代将軍家慶)
11代将軍家斉の50人の養育費と将軍家としての格の経費
大名等からの御用金の上納を繰り返し京都御所、江戸城の再建をさせた
天明の大飢饉、米騒動などから町民からの飢饉備蓄の7分積金が成立
蝦夷地の開拓経費の負担
鋳造で再び含有量を減らす
松平定信:大奥へのメスは(年間20万両:200億円相当)3分の1まで縮小
江戸の豪商からの資金(御用金)
1843年の幕府財政収支の内訳
>>収入の部
年貢39.1%、貨幣鋳造25.6%、御用金10.2%、その他19.3%
>>支出の部
切米・役料23.3%、役所経費23.3%、参詣7%、米買上6.7%、奥費用6.4%
ー外圧が招いた財政破綻(13代将軍家定から15代慶喜)
開国・通商における海防経費及び長州藩再征(軍事費:300万両)
相次ぐ事件での賠償金負担増
生麦事件(10万ポンド)
下関戦争補償(300万ドル)
参勤交代の緩和で軍事費捻出(3年に1度・江戸滞在100日など)
藩札発行するが大政奉還で消滅、各地の藩が勢力を持ち始める(薩摩・長州など)
兵庫開港での100万両はフランスからの借款(小栗忠順)