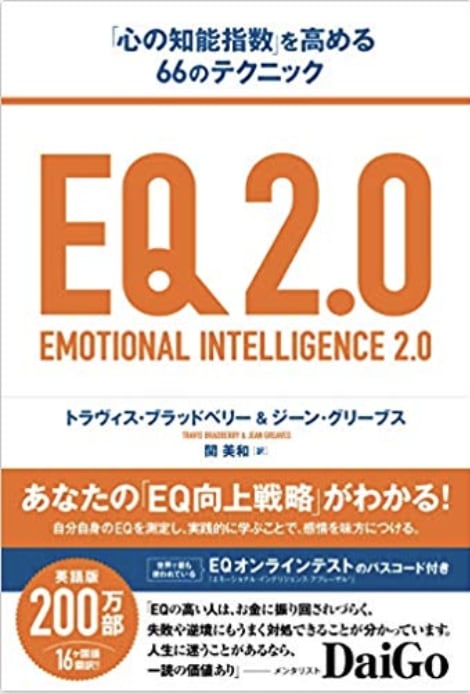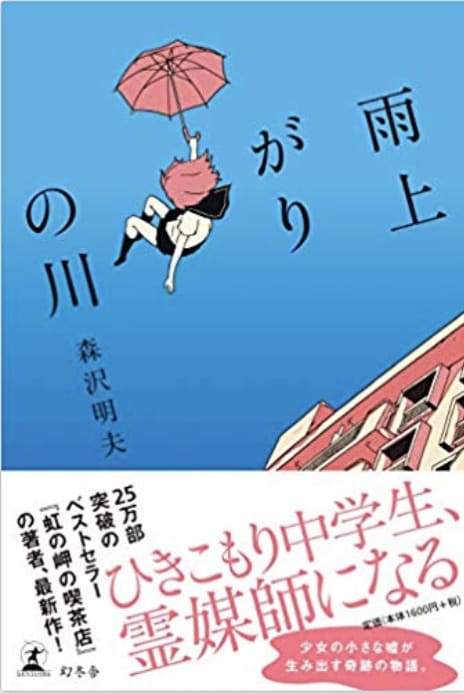@IQ(知能指数)・EQ(心の知能指数)。 今後「心・感情のコントロール」がより重要で役に立つことになる、とこの書は言う。リーダーシップの傾向としてアメリカでは体裁を繕うのはうまいが、行動が伴っていない。リップサービスに精一杯力を注ぎ、フィードバックを求めたり、チームプレーを尊ぶと言ったり、仲間を理解しようと勧めたり、公約を果たすことを誓ったりするだけだ、と言う。 だから感情(マインド)を如何にコントロールできるか、それによってより良い判断・行動を取れるようになる、と言うことだ。
『EQ2.0』トラビス・ブラッドベリー&ジーン・グリーブス
「EQ(エモーショナル・インテリジェンス)」とは、あらゆる重要なスキルの土台になる「心の知能指数」のこと。「EI」「感情的知性」とも呼ばれます。これは、自分自身と他者の心の動きに気づき、それを理解する力。そして、その気づきを使って自分の行動や人間関係を上手にマネジメントする力です。本書の目的は、あなたのEQを向上させること。心の働きを理解して、感情を味方につけるテクニックを身につけます。
- 人間関係を強め、意思決定の質をあげ、リーダーシップ力を高め、組織を成功に導くのがEQスキル、知識・経験・知能を高めること、それにはEQの実践が必要だ
- IQが低い人でもEQが高い人ほど成功率が高い結果がある(70%)
- 心と感情を如何にコントロールできるかが鍵、集中力、時間管理、意思決定、コミュニケーション等
- EQ4つのスキル
「自己認識力」自分の心の動きを正しく把握し、傾向を理解する力
自分の感情を「いい」か「悪い」かで見ない (感情は場合によって武器になる)
居心地の悪さに慣れる(自分の傲慢さを知る)
鷹の目で自分をみる(全体から見渡す)
日誌をつける(自分の傾向を見出す)
振り返り自問する、なぜそうするのか(反省し、見直す)
ストレスのかかった時の自分を知る(要因を発見する)
「自己管理力」心の動きと行動を起こす時の動きを知ること
正しい呼吸をする(深呼吸で落ち着かせる)
10まで数える(落ち着きを取り戻す)
笑顔や笑い声を増やす(気分転換をする)
出会うすべての人から学ぶ(学ぶから心が開かれる)
充電時間を入れる(心の余裕が持てる)
「社会的認識力」他者の感情を性格に読み取り相手を理解すること(聞くこと、観察すること)
挨拶には相手の名前を呼ぶ(名前を呼ぶことで雰囲気が変わる)
ボディー・ランゲージを観察する(体の動きで読み取る)
会う前に事前準備をする(タイミング・質問)
ピープル・ウオッチングに出かける(周囲を観察、感情のヒントを見つける)
他人の立場に立つ(他人の立場で物事を考える工夫)
「人間関係管理力」他者との絆を築くこと
好奇心を持つ(心を開く=打ち明ける心で会話す流)
ちょっとした思いやりを示す言葉を使う(言葉のマナー)
オープンドアー(門戸開放)政策を取り入れる(無理をしない程度に開放)
素直に建設的なフィードバックを与える(タイミングを見計らいアドバイス)
チグハグな会話を修復する(他人を責めないで和解的方法を選択)