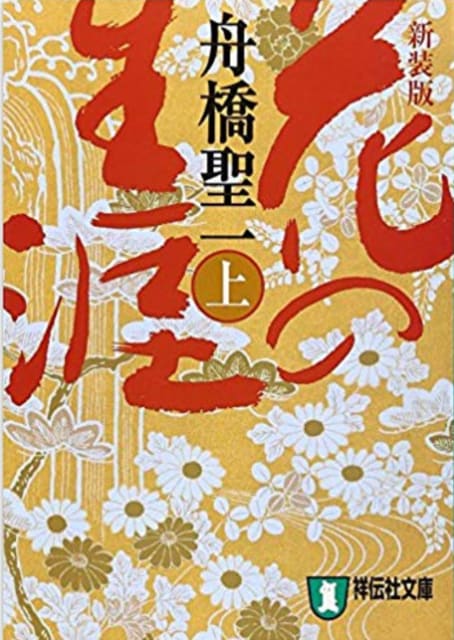@岐阜の歴史・江戸時代・美濃国郡上藩に起きた「郡上一揆」。 山村に住む農民が新税(年貢)に苦しみ一揆を起すが、藩主が弾圧。この一揆の特徴的なところは、直訴した農民の処罰のみならず、藩主の金森、江戸幕府の老中、若年寄なども失脚したと言う歴史始まって以来の大事件・波乱となった。この「郡上一揆」に対し、藩は何度となく繰り返えす一揆を弾圧し、農民の多くを処罰・処刑した。だが藩は改めず、農民も諦めず農民は幕府に直訴する。だがこれも幕府要人からもみ消され、潰され、それでも幕府に直訴し続け、最後に将軍自らが裁断した大事件なのだ。それは、郡上郡代から幕府勘定奉行等、幕府の要人が関与して未解決のまま長期化し、他の地方へも波及し多くの農民が犠牲を払った事で、将軍家重自らが采配を下した一件にある。百姓の一揆で、しかも幕府評定所で将軍自らが裁判をしたのは前代未聞、この一件だけだったとある。 それ程、政治を司る人物が上から下までグルとなってねじり潰そうと威圧をかけた事、だが多くの農民が犠牲を払い続けながらも訴え続けた勝利だという事である。 現代社会では国民の政治に対する不満の先は選挙だけだが、独裁的な政治(経済・賃金が実質の伸びていないのに続々と新税が発表され、ついには今年10月から10%消費税交付)こういった直接の反対行為行動は必要かもしれない。読むところ「車」(取得・保有だけで)について米国と比較すると、いつの間にか32倍の税を自動車保有者は支払っていることになっており、50年前の高度成長期の道路補正・整備にからむ税が今だに継続していると言う。現代版「一揆」は野党、国民が一致団結して改めて行かなければ日本は超過酷な税金課税大国となり、貧富の格差が若者から老人までさらに広がるところか、日本の住民が大挙して外国に移住することにもなりかねない。
『人づくり風土記』岐阜版
- 戦乱の歴史が刻まれた美濃ー飛騨山河。東西を結ぶ中山道を、芭蕉も広重も皇女和宮も旅した。高山祭には飛騨匠の技が輝き、治水に命を捧げた薩摩藩士の鎮魂碑は今も崇敬の的。大河に臨む輪中の村から奥深い山里まで、訪ね歩いて歩んだ岐阜県の人づくり読本。
• 輪中の村 木曽川、長良川、揖斐川3河川は伊勢湾に注ぐ。この辺の土地は知勢的には東高西低の低湿地で、200からの河川が3川に流入している。洪水は、乱流し氾濫を繰り返した。洪水は、肥沃な土砂を堆積させ濃尾平野を形成。輪中の歴史は、水との戦いの歴史だと言われている。宝暦治水工事までの145年間に、約150回の洪水に遭遇した。幕府は薩摩藩にお手伝い不信を命じ、平田鞍負を総奉行に薩摩藩は莫大な出費と犠牲を払って工事を完成させた。総工費は約4990両で、幕府が負担したのは約730両だった。
• 郡上藩の宝暦騒動 農民一揆 藩主金森頼錦は幕府の奏者番となって出費がかさんだ為、赤字財政は一層ひどくなり農民への税を高くした。農民は傘連判状をもとに江戸に直訴した。この騒動は幕府で裁判にかけられ、藩主から農民まで関係者全てが処分されると言う類のない大事件となった。藩主は改易となりましたが当然の要求をした農民にも容赦ない処罰が降り、後世まで多くの人々の胸に義憤の思いを残す結果となった。農民の死刑は14人、そのうち4人は獄門だった。このほかに裁判中に拷問と寒さで死んだのは19人、追放等の処分を受けた農民も100人近くになった。
• 宝暦騒動から200年余り経った昭和39年岐阜の劇団「はぐるま」がこの戦いを描いた小林宏の作品「郡上一揆」を上演。これが翌年訪中新劇団により「郡上の立百姓」として中国各地で講演された。
• 郡上郡白鳥町の白山長滝神社 比叡山延暦寺の別院である白山中宮長滝寺がおそらく延暦寺からの延年、芸能を催す貴族社会の寿命を延ばすという、現在奥州平泉と2箇所にのみになった。

@今海外での暮らしを求める若者が増えていると言う。特に東南アジア諸国への移住、現地で就職・起業する人が増えている状況は何を物語っているのか。その多くは国内の仕事への不満とアジア諸国......













 @「運」はいつでも、どこでも、だれにでもある、だたそれは自分が幸運だったのか、不幸だったのかの「悟り」次第だとある。運を引き寄せるにはやはり「人脈の多さ」と「好奇心」であると思う。......
@「運」はいつでも、どこでも、だれにでもある、だたそれは自分が幸運だったのか、不幸だったのかの「悟り」次第だとある。運を引き寄せるにはやはり「人脈の多さ」と「好奇心」であると思う。...... @現代では老後の孤独より、若者の孤独が増えていると言う。ネット社会の犠牲者なのか、いやそうではない。今の孤独な人々は「孤独の時間」で楽しむことを心得ている。ネット社会だから生まれた......
@現代では老後の孤独より、若者の孤独が増えていると言う。ネット社会の犠牲者なのか、いやそうではない。今の孤独な人々は「孤独の時間」で楽しむことを心得ている。ネット社会だから生まれた......